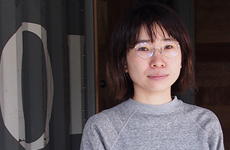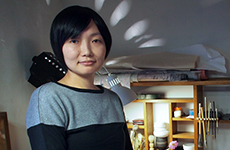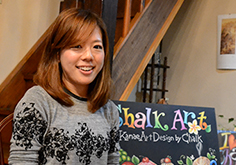HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
![]() 松岡 幸貴さん(刺繍作家/日々輪)
松岡 幸貴さん(刺繍作家/日々輪) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
松岡 幸貴さん(刺繍作家/日々輪)

気持ちそのまま、気の向くままを表現することが心地よい
松岡 幸貴さん
刺繍作家/日々輪
刺繍作家/日々輪
ぐるぐると渦を巻いたような、打ち寄せる小さな波のような、光差す水面のような、海深くに暮らす生き物のような、独特な存在感を放つ刺繍作品をつくる「日々輪」松岡幸貴さん。
高校時代に絵本作家になる夢を諦めてから10年ほどの歳月を経て、創作活動を再開。針と糸で布に絵を描くように刺繍されています。作家活動を始めて16年、松岡さんの世界観が表れる「なみ縫い」の刺繍にたどり着いたのは、まだこの2年ほどのことと言います。
今の表現にたどり着いてから「自分そのものでいいんだと、ラクになれた」と松岡さん。「ラクになれた」という言葉が意味することとは? 「やっと自分らしさを出せた」と思えるものにたどり着くまでに、どんな過程があったのでしょうか。
高校時代に絵本作家になる夢を諦めてから10年ほどの歳月を経て、創作活動を再開。針と糸で布に絵を描くように刺繍されています。作家活動を始めて16年、松岡さんの世界観が表れる「なみ縫い」の刺繍にたどり着いたのは、まだこの2年ほどのことと言います。
今の表現にたどり着いてから「自分そのものでいいんだと、ラクになれた」と松岡さん。「ラクになれた」という言葉が意味することとは? 「やっと自分らしさを出せた」と思えるものにたどり着くまでに、どんな過程があったのでしょうか。
10年前に諦めた「夢」を取り戻して
専門学校を卒業してから6年ほどソーシャルワーカーとして病院などでお勤めだったとのこと。創作活動を始めるきっかけは何だったのですか?
作家活動を始めたのは27歳の時ですが、原点は子どもの頃にあります。
祖父も父も絵を描く人で、生まれた頃から日常に「描くこと」がありました。家で遊んでいたら、そばにあった油絵にばーんとぶつかって、洋服が汚れるなんてことは日常茶飯事。日曜日には、近所の川に出かけて、父が絵を描くそばで川遊びをしていました。
いつしか、私も草花のスケッチや漫画の模写など描くことを楽しむようになり、絵本が大好きだったから、中学時代には絵本作家になることを夢見て、女の子とおじいちゃんが紅茶を通して再会するという絵本を自作して、コンクールに応募したこともありました。
高校生になっても夢は変わらず。「美術関係の学校に進学して絵本作家になる」と心に決めていたのに、両親から猛反対されてしまったんです。
両親の世代は「好きなことを仕事にする」時代ではなく、祖父も父も会社勤めをしながら絵は趣味として続けていたので、私の幸せを願う親心からの反対でしたが、当時の私にはわかるはずもなく。
何もかもがゼロになってしまって、ほかにしたいことがなかったので、まわりからすすめられるままに福祉の道に進みました。
ソーシャルワーカーとして「その人がその人らしく生きるための支援」をしていたのですが、「私は私らしく生きられていないのに」との思いがあり、ずっと苦しかったんです。絵も描かなくなり、遠いものになってしまいました。
祖父も父も絵を描く人で、生まれた頃から日常に「描くこと」がありました。家で遊んでいたら、そばにあった油絵にばーんとぶつかって、洋服が汚れるなんてことは日常茶飯事。日曜日には、近所の川に出かけて、父が絵を描くそばで川遊びをしていました。
いつしか、私も草花のスケッチや漫画の模写など描くことを楽しむようになり、絵本が大好きだったから、中学時代には絵本作家になることを夢見て、女の子とおじいちゃんが紅茶を通して再会するという絵本を自作して、コンクールに応募したこともありました。
高校生になっても夢は変わらず。「美術関係の学校に進学して絵本作家になる」と心に決めていたのに、両親から猛反対されてしまったんです。
両親の世代は「好きなことを仕事にする」時代ではなく、祖父も父も会社勤めをしながら絵は趣味として続けていたので、私の幸せを願う親心からの反対でしたが、当時の私にはわかるはずもなく。
何もかもがゼロになってしまって、ほかにしたいことがなかったので、まわりからすすめられるままに福祉の道に進みました。
ソーシャルワーカーとして「その人がその人らしく生きるための支援」をしていたのですが、「私は私らしく生きられていないのに」との思いがあり、ずっと苦しかったんです。絵も描かなくなり、遠いものになってしまいました。

創作活動を再開するきっかけは?
出産のために27歳で仕事を辞め、赤ちゃんのスタイなどを手づくりしようとミシンを買ったことがきっかけでした。つくり始めると、つくること自体が楽しすぎて、手が止まらない。
子どものものをつくっていたはずが、好きなリネン生地を組み合わせて、ふきんや鍋敷き、かばんをつくるようになり、つくればつくるほどに胸の高鳴りがおさまりません。
子どもを寝かせてから夜中じゅう布小物をつくり続け、あっという間に家庭では使いきれない枚数になっていました。すると、今度は「販売してみたいなあ」という気持ちがむくむくっと芽生えて、手づくり市に出店するようになったんです。
出店すると、ものづくりを仕事にしている人たちと出会え、「自分が好きなことを仕事にしているんだ」と衝撃的で、お話を聞いているだけでも心が満たされたから、「また次も出店しよう」という気持ちにつながっていきました。
京都・知恩寺の手づくり市では、糸を編む、布を染めるなど、1つのことにぎゅっと絞って創作している人たちがかっこよく見えて、ふんわりとものづくりをしている自分がすごく薄っぺらく感じました。私もいろんなことをやるのではなく、何か1つに絞りたいと考えた時、ぱあぁんと思い浮かんだのが刺繍です。
当時、まわりで刺繍をされている作家さんが少なかったので、刺繍のブローチや小さいものをつくったら楽しいんじゃないかとイメージが膨らみ、最初はお花や蝶々などかわいらしい柄を刺繍していました。
今のような「なみ縫い」の刺繍を始めたのは、2年ほど前、2017年からなんです。
子どものものをつくっていたはずが、好きなリネン生地を組み合わせて、ふきんや鍋敷き、かばんをつくるようになり、つくればつくるほどに胸の高鳴りがおさまりません。
子どもを寝かせてから夜中じゅう布小物をつくり続け、あっという間に家庭では使いきれない枚数になっていました。すると、今度は「販売してみたいなあ」という気持ちがむくむくっと芽生えて、手づくり市に出店するようになったんです。
出店すると、ものづくりを仕事にしている人たちと出会え、「自分が好きなことを仕事にしているんだ」と衝撃的で、お話を聞いているだけでも心が満たされたから、「また次も出店しよう」という気持ちにつながっていきました。
京都・知恩寺の手づくり市では、糸を編む、布を染めるなど、1つのことにぎゅっと絞って創作している人たちがかっこよく見えて、ふんわりとものづくりをしている自分がすごく薄っぺらく感じました。私もいろんなことをやるのではなく、何か1つに絞りたいと考えた時、ぱあぁんと思い浮かんだのが刺繍です。
当時、まわりで刺繍をされている作家さんが少なかったので、刺繍のブローチや小さいものをつくったら楽しいんじゃないかとイメージが膨らみ、最初はお花や蝶々などかわいらしい柄を刺繍していました。
今のような「なみ縫い」の刺繍を始めたのは、2年ほど前、2017年からなんです。

家族との何気ない日々が、創作の源
今の「なみ縫いの刺繍」は松岡さんらしい世界観を感じます。その表現にたどり着いた経緯は?
カンタ刺繍の研究家であり、刺繍家でもある望月真理さんの記事を、雑誌で読んだことが始まりです。「なんだろう、これは?」と、もう心臓が止まりそうになるくらいびっくりしました。
「カンタ刺繍」は、インドの女性が家族のためにする手仕事です。なみ縫いなのに、なみ縫いに見えないくらい、すごい世界観を持っているのに素朴。
それに望月先生の「失敗はない」「自由に縫ったらいい」といった想いや考え方に共感することばかりで、見よう見まねでカンタ刺繍を縫い始めました。
まもなく、カンタ刺繍の実物を見ることのできる展覧会が東京で開催されると知り、居ても立っても居られず、思いきって日帰りで見に行ったんです。それはそれはとても素晴らしくて、一針一針に宿る家族への想いが伝わってきて、涙が出そうになりました。
カンタ刺繍をしてみたい気持ちと、自分には恐れ多い気持ちとが入り交じる中、帰りの飛行機で、航空会社発行のフリーマガジンを読んでいたら「潮待ち交差点」の記事に目がとまりました。
2つの潮が行き交う町。その日その日の潮の満ち引きを見て漁に出る時を待つという、自然の流れに委ねて、のんびりゆっくりと暮らしている様子が、心にじーんと響いてきたんです。
子どもの名前にも「潮」という一文字を入れていて、私も海のそばにある町で暮らしているので、潮の流れとリンクさせたなみ縫いの刺繍をしてみようと思いました。
「カンタ刺繍」は、インドの女性が家族のためにする手仕事です。なみ縫いなのに、なみ縫いに見えないくらい、すごい世界観を持っているのに素朴。
それに望月先生の「失敗はない」「自由に縫ったらいい」といった想いや考え方に共感することばかりで、見よう見まねでカンタ刺繍を縫い始めました。
まもなく、カンタ刺繍の実物を見ることのできる展覧会が東京で開催されると知り、居ても立っても居られず、思いきって日帰りで見に行ったんです。それはそれはとても素晴らしくて、一針一針に宿る家族への想いが伝わってきて、涙が出そうになりました。
カンタ刺繍をしてみたい気持ちと、自分には恐れ多い気持ちとが入り交じる中、帰りの飛行機で、航空会社発行のフリーマガジンを読んでいたら「潮待ち交差点」の記事に目がとまりました。
2つの潮が行き交う町。その日その日の潮の満ち引きを見て漁に出る時を待つという、自然の流れに委ねて、のんびりゆっくりと暮らしている様子が、心にじーんと響いてきたんです。
子どもの名前にも「潮」という一文字を入れていて、私も海のそばにある町で暮らしているので、潮の流れとリンクさせたなみ縫いの刺繍をしてみようと思いました。

それが今の刺繍なんですね。
糸の流れは気持ちの流れとして、その時々の気持ちの流れに任せてつくっています。まっすぐ縫っているものもあれば、入り組んでいるもの、ぼこぼこしたものなど、さまざまな作品が出来上がっています。
つくる時も「新たに布や糸を用意してつくる」ではなく、昨日からの続き、机の上にある布と糸から縫い始め、色をどうしても変えたい気持ちになった時以外は、針に一度通した糸は使い切ります。
それをルールにしているわけではなく、なぜだかそうしたい自分がいるから、そうしているだけです。
なみ縫いの作品をつくるようになってから、心が満たされる感じがしました。やっと自分らしさを出せたような、一針一針縫いながら「あー、そうそう。そういうことだ」と納得するような、高揚するような感覚があります。
つくる時も「新たに布や糸を用意してつくる」ではなく、昨日からの続き、机の上にある布と糸から縫い始め、色をどうしても変えたい気持ちになった時以外は、針に一度通した糸は使い切ります。
それをルールにしているわけではなく、なぜだかそうしたい自分がいるから、そうしているだけです。
なみ縫いの作品をつくるようになってから、心が満たされる感じがしました。やっと自分らしさを出せたような、一針一針縫いながら「あー、そうそう。そういうことだ」と納得するような、高揚するような感覚があります。

刺繍をしながら、どんなことを思ったり考えたりしているのですか?
刺繍しながらよく思い出すのは、子どもの頃のことです。
昔暮らしていた家のまわりにあった畑と田んぼの土や草のにおい、母と買い物帰りに手をつないで歩いた時に見えた夕焼け、絵を描く父のそばで川遊びしたこと、晩ごはん前なのにおなかが空いた時に母が握ってくれたおにぎり、家族だんらんの夜のお茶の時間・・・
子どもの頃から、特別な日ではなく、そんな日常が大好きでした。すごく、愛情をもらっていたんだと思います。
屋号の「日々輪」は「昨日も、今日も、明日も全部つながっている」という意味で、「日々」「いつもそこにある」「なんでもないこと」といったことを表現したくて、そう名付けました。
私の創作の源は家族や日常。母であること、子どもたちの心のバランス、日々の暮らしが満たされてはじめて、いい手仕事ができると感じています。
ものづくりを始めたばかりの頃は、つくることに傾き過ぎて、家族とわあぁーんと泣いた日もありますが、今はバランスを大事に。暮らしを整えることも心がけています。
昔暮らしていた家のまわりにあった畑と田んぼの土や草のにおい、母と買い物帰りに手をつないで歩いた時に見えた夕焼け、絵を描く父のそばで川遊びしたこと、晩ごはん前なのにおなかが空いた時に母が握ってくれたおにぎり、家族だんらんの夜のお茶の時間・・・
子どもの頃から、特別な日ではなく、そんな日常が大好きでした。すごく、愛情をもらっていたんだと思います。
屋号の「日々輪」は「昨日も、今日も、明日も全部つながっている」という意味で、「日々」「いつもそこにある」「なんでもないこと」といったことを表現したくて、そう名付けました。
私の創作の源は家族や日常。母であること、子どもたちの心のバランス、日々の暮らしが満たされてはじめて、いい手仕事ができると感じています。
ものづくりを始めたばかりの頃は、つくることに傾き過ぎて、家族とわあぁーんと泣いた日もありますが、今はバランスを大事に。暮らしを整えることも心がけています。

立派にならなくても、「自分そのもの」でいい
最近、絵を再び描かれるようになったそうですね。
陶芸教室の先生が企画した展覧会に参加した時、本職とは違うものを展示することになったんです。先生から絵を描くことをすすめられ、いい機会をいただけたと思いました。
子どもの頃から水彩が好きなんですが、下絵までは自分が思うように描けても、色を入れた瞬間に違うものになってしまうという、ちぐはぐしたものがありました。そこで、学生時代は色鉛筆やアクリル絵の具で描いていたんです。
その展覧会でも最初は水彩で描いてみたものの、やっぱりイメージ通りにはならず。イメージに近いものが描けるクレヨンの作品も見てもらったら「クレヨンの絵はおもしろくない。水彩画は下手だけど、おもしろいね」と言ってもらえて、「うまく見せよう」とする気持ちを見抜かれていました。
うまく見せようなんてしなくていい、描きたいように描けばいい。今は楽しい気持ちで、絵を描くことと向き合えるように、色遊びみたいな感じで描いています。
水をたっぷり使って、ぼとぼとに描いて、6時間ほど経って、水がひいてから作品が出来上がります。なみ縫いの刺繍と同じで、出来上がってみないと、どんな作品になるかはわかりません。
なみ縫いの刺繍も、絵も、つながっていると思います。私にとって刺繍は「縫う」というより「描く」。絵を描くことが好きだったから、刺繍にたどり着いたのだと思っています。
なみ縫いの作品をつくるようになってから、自分の中で滞っていたものが流れ始めて、ラクになれました。自分そのものでいられること、気持ちそのまま、気の向くままを素直に表現していけることがとても心地いいんです。
自分の好きなことをしてもいいんだって、この1年ほどでようやく思えるようになりました。
子どもの頃から水彩が好きなんですが、下絵までは自分が思うように描けても、色を入れた瞬間に違うものになってしまうという、ちぐはぐしたものがありました。そこで、学生時代は色鉛筆やアクリル絵の具で描いていたんです。
その展覧会でも最初は水彩で描いてみたものの、やっぱりイメージ通りにはならず。イメージに近いものが描けるクレヨンの作品も見てもらったら「クレヨンの絵はおもしろくない。水彩画は下手だけど、おもしろいね」と言ってもらえて、「うまく見せよう」とする気持ちを見抜かれていました。
うまく見せようなんてしなくていい、描きたいように描けばいい。今は楽しい気持ちで、絵を描くことと向き合えるように、色遊びみたいな感じで描いています。
水をたっぷり使って、ぼとぼとに描いて、6時間ほど経って、水がひいてから作品が出来上がります。なみ縫いの刺繍と同じで、出来上がってみないと、どんな作品になるかはわかりません。
なみ縫いの刺繍も、絵も、つながっていると思います。私にとって刺繍は「縫う」というより「描く」。絵を描くことが好きだったから、刺繍にたどり着いたのだと思っています。
なみ縫いの作品をつくるようになってから、自分の中で滞っていたものが流れ始めて、ラクになれました。自分そのものでいられること、気持ちそのまま、気の向くままを素直に表現していけることがとても心地いいんです。
自分の好きなことをしてもいいんだって、この1年ほどでようやく思えるようになりました。

高校時代に夢を諦めてから長年、「自分の好きなことをしてはいけない」という思いに囚われてこられたとのこと。何がきっかけで、解き放たれたのでしょうか?
実は手づくり市への出店を決める直前、仕事復帰に向けて動いていました。
「立派な人にならなくてはいけない」「せっかく専門学校まで出させてもらったのだから復帰しなければならない」との思いがあり、就職先も決めていたのですが、子どもの預け先の都合がつかず、断念するしかありませんでした。
自分にはどうにもできない理由で、断念できてよかったです。その後「自分に嘘をついて、やりたいことをやらないままで人生が終わってもいいのか」と自問自答し、「やっぱり自分のやりたいことをやりたい」と思ったから、手づくり市に出店することを決めました。
でも、いつも後ろめたさがあったように思います。
刺繍を始めてから「刺繍を仕事にしたい」という気持ちがありながらも、「好きなことは趣味にしないといけない」「人の役に立つこと以外は仕事ではない」などの思いに襲われ、「刺繍は趣味なんだ」と思い込もうとしていました。
そんなふうに「こうしなければならない」「こうでなければならない」など恐れていたのは、誰かにそう言われたからではなく、自分がそう思い込んでいただけだったことに、最近気づいたんです。
「立派な人にならなくてはいけない」「せっかく専門学校まで出させてもらったのだから復帰しなければならない」との思いがあり、就職先も決めていたのですが、子どもの預け先の都合がつかず、断念するしかありませんでした。
自分にはどうにもできない理由で、断念できてよかったです。その後「自分に嘘をついて、やりたいことをやらないままで人生が終わってもいいのか」と自問自答し、「やっぱり自分のやりたいことをやりたい」と思ったから、手づくり市に出店することを決めました。
でも、いつも後ろめたさがあったように思います。
刺繍を始めてから「刺繍を仕事にしたい」という気持ちがありながらも、「好きなことは趣味にしないといけない」「人の役に立つこと以外は仕事ではない」などの思いに襲われ、「刺繍は趣味なんだ」と思い込もうとしていました。
そんなふうに「こうしなければならない」「こうでなければならない」など恐れていたのは、誰かにそう言われたからではなく、自分がそう思い込んでいただけだったことに、最近気づいたんです。

そう気づけた出来事とは?
今年2月の2人展で、じゃがいもの絵を展示したところ、購入してくださる方がいて、額を用意することになりました。規格外のサイズだったから、木工作品もつくる父に頼むしかないとお願いしたら、絵も見たいと言われ、見せたら「こんな絵を描くんやね」「今度、お父さんにも描いて」とほめてもらえたんです。
また、4月の個展では「日輪」というタイトルで「お母さん」をテーマにしたのですが、フェイスブックで個展を知った母が見に来てくれました。「もっともっと立派になってからでないと見てもらえないと思ってきた」と吐露したら、「そんなん待っていたら、お母さん何歳になるの(笑)。そのまんまでいいやん」と言ってもらえました。
私が好きなことを仕事にしている姿を見て、「そうできているんやね」とびっくりしていました。
「両親にはまだまだ認めてもらえない」「立派な人になってからでないとだめだ」と思ってきたのに、そう思っていたのは自分だけだったんだって、いろんなものがわあぁっと溶けていったんです。
胸の奥にしまい込んでいた「やってみたいこと、してみたいこと」を、勇気を出してやってみてよかったと思っています。やりたいことがある人生の楽しさ、素晴らしさ、「生きているんだ!」という実感で今、満たされています。
また、4月の個展では「日輪」というタイトルで「お母さん」をテーマにしたのですが、フェイスブックで個展を知った母が見に来てくれました。「もっともっと立派になってからでないと見てもらえないと思ってきた」と吐露したら、「そんなん待っていたら、お母さん何歳になるの(笑)。そのまんまでいいやん」と言ってもらえました。
私が好きなことを仕事にしている姿を見て、「そうできているんやね」とびっくりしていました。
「両親にはまだまだ認めてもらえない」「立派な人になってからでないとだめだ」と思ってきたのに、そう思っていたのは自分だけだったんだって、いろんなものがわあぁっと溶けていったんです。
胸の奥にしまい込んでいた「やってみたいこと、してみたいこと」を、勇気を出してやってみてよかったと思っています。やりたいことがある人生の楽しさ、素晴らしさ、「生きているんだ!」という実感で今、満たされています。

近い将来、実現したいことは?
娘が母に編み物を教えてもらっている姿を見て、私も母のようなおばあちゃんになりたいと思いました。そんなことをぐるぐると頭の中で考えていたら、「カンタ刺繍がやりたい」と心ががっしり固まったんです。
私には恐れ多くてできないと思ってしまったカンタ刺繍を自然と求めるようになり、今年の夏に望月先生に習うことにしました。
子どもたちが小さい頃に描いた絵、子どもたちのランドセルや靴、毎日見ている夫の制服、庭に咲く花など、家族とその日常にあふれるものを、カンタ刺繍で描いていきたいと思っています。
私には恐れ多くてできないと思ってしまったカンタ刺繍を自然と求めるようになり、今年の夏に望月先生に習うことにしました。
子どもたちが小さい頃に描いた絵、子どもたちのランドセルや靴、毎日見ている夫の制服、庭に咲く花など、家族とその日常にあふれるものを、カンタ刺繍で描いていきたいと思っています。
松岡 幸貴さん
専門学校を卒業後、ソーシャルワーカーとして病院などで6年ほど勤務。2003年に出産のため退職し、手仕事をスタートする。神戸市内の手づくり市に出店したことを機に、関西各地で出店や展覧会、ワークショップなど活動を広げる。2012年に布小物作家から刺繍作家に転身し、「日々輪」を屋号とした。2017年から「カンタ刺繍」と「潮待ち交差点」から着想を得た「なみ縫いの刺繍」による作品づくりを始める。
HP: https://hiviwa.shopinfo.jp/
BLOG: https://hiviwa.exblog.jp/
FB: hiviwa
(取材:2019年6月)
「なみ縫いの刺繍」による作品をつくり始めてから、「気持ちそのまま、気の向くまま」に素直に表現できるようになり、どんどんどんどん心軽やかに、「そのままの自分でいいんだ」というところにつながっておられる様子が伝わってきました。
だから、作品も「自分そのもの」と思えるくらい、松岡さんご自身を表現するものになっているのだと思います。
松岡さんがおっしゃられていたように、好きなことを仕事にできるようになってきたのは近年のことで、親世代には受け入れられにくいのだと思います。
そんな空気感を、子世代である世代も感じ取り、知らず知らずのうちに内面化しているため、「立派にならなくてはいけない」「仕事とはこういうものだ」といった価値観ができていて、生きづらさの原因になっていることもあるのではないでしょうか。
でも、時代は変わってきていますし、人の考え方や価値観もまた流動的です。「こう思われている」「こう思われるかもしれない」と不安になっていることの中には、自分が思うほどそうではなかったり、相手の考え方や価値観も変化したりしていることもあるかもしれません。
松岡さんが「両親はこう思っている」と思っていたことも、実際は松岡さんが思うほどではありませんでした。もちろん、松岡さんが自分の「やってみたい」「してみたい」という気持ちを大事にして貫かれてこられたからこそ、現実やご両親の気持ちを突き動かしたのだとも思います。
HP: 『えんを描く』
だから、作品も「自分そのもの」と思えるくらい、松岡さんご自身を表現するものになっているのだと思います。
松岡さんがおっしゃられていたように、好きなことを仕事にできるようになってきたのは近年のことで、親世代には受け入れられにくいのだと思います。
そんな空気感を、子世代である世代も感じ取り、知らず知らずのうちに内面化しているため、「立派にならなくてはいけない」「仕事とはこういうものだ」といった価値観ができていて、生きづらさの原因になっていることもあるのではないでしょうか。
でも、時代は変わってきていますし、人の考え方や価値観もまた流動的です。「こう思われている」「こう思われるかもしれない」と不安になっていることの中には、自分が思うほどそうではなかったり、相手の考え方や価値観も変化したりしていることもあるかもしれません。
松岡さんが「両親はこう思っている」と思っていたことも、実際は松岡さんが思うほどではありませんでした。もちろん、松岡さんが自分の「やってみたい」「してみたい」という気持ちを大事にして貫かれてこられたからこそ、現実やご両親の気持ちを突き動かしたのだとも思います。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧
-
「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん
-
「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん
-
「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。
-
「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん
-
「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん
-
「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん
-
「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り
-
「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?
-
「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん
-
「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん
-
「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん
-
「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん
-
「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん
-
「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん
-
「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん
-
「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん
-
「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん
-
「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん
-
「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人
-
「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。
-
「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘
-
「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん
-
「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。
-
「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん
-
「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん
-
「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。
-
「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん
-
「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に
-
「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん
-
「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に
-
「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。
-
「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。
-
「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」