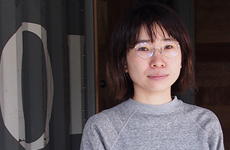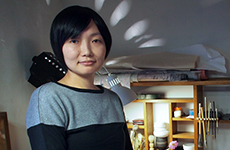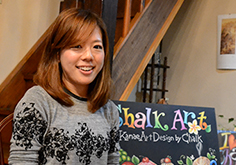HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
![]() 三品由賀里さん(フラワーコーディネーター)
三品由賀里さん(フラワーコーディネーター) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
三品由賀里さん(フラワーコーディネーター)

一家に一輪あれば、平和の素になる
三品 由賀里さん
フラワーコーディネーター/Pelangi
フラワーコーディネーター/Pelangi
「じんわりと幸せになれる」をコンセプトに、生花や枝もの、ツル、木の実、ドライフラワーといったさまざまな種類の植物を用いて、会場装花や生け込み、ブーケ、リースなどをつくり上げる「Pelangi(ペランギ)」の三品由賀里さん。
フラワーコーディネーターの道に進んで32年。一流ホテルでのウェディングや有名デザイナーのショー、パリのブライダルフェア、内モンゴルで開催された日中交流イベントのステージなど、国内外で大きな舞台を手掛けてこられました。
一見すると、順風満帆そうですが、「32年のうち、後半10年ほどは思うように仕事ができない時期もありました。でも、お花が私に役割を残してくれていたんです」と三品さん。
5年、10年、20年、30年と、社会も周囲も自分もめまぐるしく変化する中、どのようにして同じ仕事を長年続けてこられたのでしょうか。長年続けてきたからこそ、見えたこと、わかることとは?
フラワーコーディネーターの道に進んで32年。一流ホテルでのウェディングや有名デザイナーのショー、パリのブライダルフェア、内モンゴルで開催された日中交流イベントのステージなど、国内外で大きな舞台を手掛けてこられました。
一見すると、順風満帆そうですが、「32年のうち、後半10年ほどは思うように仕事ができない時期もありました。でも、お花が私に役割を残してくれていたんです」と三品さん。
5年、10年、20年、30年と、社会も周囲も自分もめまぐるしく変化する中、どのようにして同じ仕事を長年続けてこられたのでしょうか。長年続けてきたからこそ、見えたこと、わかることとは?
子どもの頃から「当たり前」にあった花や緑
短大卒業後、設計事務所で事務職をされていたそうですが、お花の道に進むきっかけは?
お茶屋さんをしていた祖母がお花を仕入れては室内を飾っていたので、母もお花を飾る習慣があり、家はいつもたくさんのお花や緑で溢れていたんです。
私も、家族の誕生日やクリスマスにはお花屋さんに行って選んで、自分でラッピングをして贈るということを10代の頃から楽しんできました。
そんなふうに、お花の存在があまりにも身近で当たり前だったから、最初は仕事にしようとは思い付きもしなかったんです。
設計事務所に就職したのは、その頃に興味があった「ヨットに乗ってみたい」という気持ちから(笑)。友人がその事務所でアルバイトをしていて、社長がヨットを所有していると聞いて決めたのでした。
でも、働くうち、事務所にある洋書を見て、インテリアとしてのお花や緑が素敵だなあと思うようになり、映画を観ていても各場面に登場するお花や緑が気になるように。
「ああいうお花や緑を生ける人になりたい」とお花を習い始め、しばらくして教室の先生から「アシスタントにならない?」と声をかけられたのをきっかけに、この道に進みました。
それから32年が経ちます。
私も、家族の誕生日やクリスマスにはお花屋さんに行って選んで、自分でラッピングをして贈るということを10代の頃から楽しんできました。
そんなふうに、お花の存在があまりにも身近で当たり前だったから、最初は仕事にしようとは思い付きもしなかったんです。
設計事務所に就職したのは、その頃に興味があった「ヨットに乗ってみたい」という気持ちから(笑)。友人がその事務所でアルバイトをしていて、社長がヨットを所有していると聞いて決めたのでした。
でも、働くうち、事務所にある洋書を見て、インテリアとしてのお花や緑が素敵だなあと思うようになり、映画を観ていても各場面に登場するお花や緑が気になるように。
「ああいうお花や緑を生ける人になりたい」とお花を習い始め、しばらくして教室の先生から「アシスタントにならない?」と声をかけられたのをきっかけに、この道に進みました。
それから32年が経ちます。

20代から一流ホテルでのウェディングや海外の舞台も経験されていますね。
20代後半から30代はさまざまな経験をさせてもらいました。
お花の教室でアシスタントを3年ほど勤めた後に就職したお花屋さんは、お店を経営するとともに、姫路市内のほとんどの結婚式場の装花を手掛けていたので、毎週何十組ものウェディングを担当でき、実践の中で技術を磨くことができました。
最新のトレンドを取り入れる職場だったから、東京の一流ホテルでも使用されている什器を使わせてもらったり、第一線で活躍する講師を招いたレッスンを受けさせてもらったり。
この時に東京でスクールを主宰する「恩師」とも出会います。
恩師のおかげで、アメリカのフラワーデザイナー協会のレッスン参加、「アメリカン フローラル アート スクール」でのディプロマ修得、クリスマスデコレーションやさまざまなショー見物など、海外で学ぶチャンスにも恵まれたんです。
職場で磨いた技術力と海外で学んだ表現方法があったおかげで、どんな依頼に対してもやってみようと思えました。
30代では、ゴルフクラブのウェディング専属となるために独立、お花のレッスンをスタート、有名デザイナーのショーで装花を担当、パリのブライダルフェアに参加、内モンゴルで開催された日中交流イベントのステージ装花など、立て続けにさまざまなことにチャレンジしてきました。
それが40代に突入すると、状況が一変します。
お花の教室でアシスタントを3年ほど勤めた後に就職したお花屋さんは、お店を経営するとともに、姫路市内のほとんどの結婚式場の装花を手掛けていたので、毎週何十組ものウェディングを担当でき、実践の中で技術を磨くことができました。
最新のトレンドを取り入れる職場だったから、東京の一流ホテルでも使用されている什器を使わせてもらったり、第一線で活躍する講師を招いたレッスンを受けさせてもらったり。
この時に東京でスクールを主宰する「恩師」とも出会います。
恩師のおかげで、アメリカのフラワーデザイナー協会のレッスン参加、「アメリカン フローラル アート スクール」でのディプロマ修得、クリスマスデコレーションやさまざまなショー見物など、海外で学ぶチャンスにも恵まれたんです。
職場で磨いた技術力と海外で学んだ表現方法があったおかげで、どんな依頼に対してもやってみようと思えました。
30代では、ゴルフクラブのウェディング専属となるために独立、お花のレッスンをスタート、有名デザイナーのショーで装花を担当、パリのブライダルフェアに参加、内モンゴルで開催された日中交流イベントのステージ装花など、立て続けにさまざまなことにチャレンジしてきました。
それが40代に突入すると、状況が一変します。

仕事歴32年の中にある「空白の数年間」
「状況が一変」とは?
2008年にリーマンショックが起き、ウェディング業界は「駅チカ」「簡素化」がトレンドになったため、私の仕事の主軸だったゴルフクラブのガーデンウェディングの依頼は月8~9件から0になる月が出てきました。
さらには2006年に母、2010年に父と、数年のうちに両親を亡くしてしまった喪失感は計り知れないものでした。私のお花の根本には、家族との記憶や思い出がありますから、仕事が手につかなくなってしまったことも。
心と体のバランスをとれなくなって、仕事でも信じられないミスをするなど、さまざまな出来事が重なり、自分でもどうやって生きてこられたのだろうと思うくらい、何も思い出せない空白の数年間があるんです。
さらには2006年に母、2010年に父と、数年のうちに両親を亡くしてしまった喪失感は計り知れないものでした。私のお花の根本には、家族との記憶や思い出がありますから、仕事が手につかなくなってしまったことも。
心と体のバランスをとれなくなって、仕事でも信じられないミスをするなど、さまざまな出来事が重なり、自分でもどうやって生きてこられたのだろうと思うくらい、何も思い出せない空白の数年間があるんです。
その状況をどのように乗り越えたのですか?
目の前に仕事があったことで、「やらなきゃ」「しなきゃ」という気持ちを持てたから、生きてこられたのだと思います。精神的に仕事が手につかなくなって「もう無理かもしれない」と思う時に限って依頼が入りました。
依頼をくださったのは、これまで出会ったさまざまな人たちです。 人が喜ぶ姿を見るのは楽しいし、私を必要としてくれるのならばと「来る者は拒まず」でどんな仕事も引き受けてきました。
その中で、単発で終わる仕事もあれば、長続きする仕事もあって、つながり続けた人たちが生け込みやお祝いのブーケづくり、宴会やイベントの装花、教室の再開、陶芸作家さんとのコラボレーションなどさまざまな仕事に声をかけてくれたんです。
それに、植物にかかわる仕事だったのもよかったんだと思います。
たとえば、ミモザは陽だまりのにおいがして、心が温かくなります。知らず知らずのうちに、植物に癒され、パワーをもらっていました。
さまざまな人や植物から、たくさん与えてもらったから。与えてもらった分、恩返しをすることが私の使命だと、今は奮い立っています。
依頼をくださったのは、これまで出会ったさまざまな人たちです。 人が喜ぶ姿を見るのは楽しいし、私を必要としてくれるのならばと「来る者は拒まず」でどんな仕事も引き受けてきました。
その中で、単発で終わる仕事もあれば、長続きする仕事もあって、つながり続けた人たちが生け込みやお祝いのブーケづくり、宴会やイベントの装花、教室の再開、陶芸作家さんとのコラボレーションなどさまざまな仕事に声をかけてくれたんです。
それに、植物にかかわる仕事だったのもよかったんだと思います。
たとえば、ミモザは陽だまりのにおいがして、心が温かくなります。知らず知らずのうちに、植物に癒され、パワーをもらっていました。
さまざまな人や植物から、たくさん与えてもらったから。与えてもらった分、恩返しをすることが私の使命だと、今は奮い立っています。

日常の中で「じんわりと幸せ」になってもらえるように
お声がかかるのも、三品さんのお人柄はもちろん、装花など表現されたものが魅力的だからだと思います。装花や生け込み、ブーケづくりなどをされる時に大事にされていることは何ですか?
相手の希望が99%、残り1%で自分の色を出すことでしょうか。相手とその贈った相手が喜んでくれることが、一番嬉しいんです。
開店祝いであれば、開店するきっかけや店主さんのことなど、誕生日祝いであれば、相手の人柄や贈り主との関係など。
「どんな想いを持っているのか」「お花を通して伝えたいことは何か」などのお話をうかがい、テーマを決めて形にしています。具体的なイメージがあれば、それに合わせてつくることもあります。
そんなふうに相手の希望に合わせて、普通のも、おしゃれなのも、奇をてらったのも、経験と技術でつくることができてしまうので、「何でもできる」は結局「何もできない」ということ。
「自分らしさって、なんだろう?」ということは、ずっと考えてきました。
開店祝いであれば、開店するきっかけや店主さんのことなど、誕生日祝いであれば、相手の人柄や贈り主との関係など。
「どんな想いを持っているのか」「お花を通して伝えたいことは何か」などのお話をうかがい、テーマを決めて形にしています。具体的なイメージがあれば、それに合わせてつくることもあります。
そんなふうに相手の希望に合わせて、普通のも、おしゃれなのも、奇をてらったのも、経験と技術でつくることができてしまうので、「何でもできる」は結局「何もできない」ということ。
「自分らしさって、なんだろう?」ということは、ずっと考えてきました。

お花を見ていると、三品さんらしい世界観を感じますが・・・
自分の個性はわかりませんが、「したいこと」はあります。
さりげなくその場に存在できるもの、見る人がじんわりと幸せになれるようなものをつくることです。
「じんわりと幸せになれる」とは、もらった瞬間はもちろん、家に持って帰った後も、その人の暮らしの中でなじむということ。帰るまでのこと、帰ってからのことも考えてつくっています。
そう思うようになったのも、ここ数年のことかもしれません。
20~30代の頃、特にウェディングを主軸にしていた時は、いろんな本を見て「こんなふうにしたい」「あんなふうにしたい」と模倣から始めましたし、一流アーティストの講習会にも参加していました。
一流アーティストのように、奇をてらったかっこいいものをつくろうとしていたと思いますし、「華やかなものをつくっている私」が好きというのもあったと思います。
でも、私は一流アーティストのような天才ではありませんし、届けたい相手は身近にいる人たち。日常に寄り添うお花にかかわる仕事をする者として、日常の中でじんわりと幸せになってもらえるものをつくりたいと思うようになりました。
さりげなくその場に存在できるもの、見る人がじんわりと幸せになれるようなものをつくることです。
「じんわりと幸せになれる」とは、もらった瞬間はもちろん、家に持って帰った後も、その人の暮らしの中でなじむということ。帰るまでのこと、帰ってからのことも考えてつくっています。
そう思うようになったのも、ここ数年のことかもしれません。
20~30代の頃、特にウェディングを主軸にしていた時は、いろんな本を見て「こんなふうにしたい」「あんなふうにしたい」と模倣から始めましたし、一流アーティストの講習会にも参加していました。
一流アーティストのように、奇をてらったかっこいいものをつくろうとしていたと思いますし、「華やかなものをつくっている私」が好きというのもあったと思います。
でも、私は一流アーティストのような天才ではありませんし、届けたい相手は身近にいる人たち。日常に寄り添うお花にかかわる仕事をする者として、日常の中でじんわりと幸せになってもらえるものをつくりたいと思うようになりました。

向き合えば向き合うほどに、研ぎ澄まされていく
「じんわりと幸せになれるお花をつくりたい」と思えるようになったのは、ここ数年のことと言いますが、そう気持ちが変化したきっかけは?
ウェディングの仕事が減ったことにより、一つひとつの仕事に注げる時間が増えたおかげで、1本1本の植物と向き合えるようになった気がします。
ウェディングの仕事は2~3時間だけ、その空間を装花するものですから、その一瞬が美しければいいと思っていましたし、たくさんのブーケをつくるので切り刻むように茎をバシバシ短く切るなど、どこか消耗品のように扱っていたように思います。
でも、季節のお花を生け込む機会が増えたことで、切り刻むことに違和感を覚え、枝ものを使う時は造園業の知人に頼んで根っこのあるものを借りるようになりました。
また、会場装花の役割を終えた植物を捨てられずに持ち帰ってアトリエに飾るうち、枝から根っこが生えるなど変化する姿を見て「生きているんだ」と改めて感じたり、以前は咲く一瞬こそが美しいとドライフラワーに興味がありませんでしたが、お花の「その後」を見守る中で「これがお花の最後の形かなあ」と愛おしくなったり。
だんだんと気持ちが変化していったんです。
今は、植物はすでに完成されているのだから、私が何か手を加えるのではなく、あるがままに生けるのが一番いいと思っています。束ねるだけ、差すだけなど、シンプルな生け方に変わりました。
ウェディングの仕事は2~3時間だけ、その空間を装花するものですから、その一瞬が美しければいいと思っていましたし、たくさんのブーケをつくるので切り刻むように茎をバシバシ短く切るなど、どこか消耗品のように扱っていたように思います。
でも、季節のお花を生け込む機会が増えたことで、切り刻むことに違和感を覚え、枝ものを使う時は造園業の知人に頼んで根っこのあるものを借りるようになりました。
また、会場装花の役割を終えた植物を捨てられずに持ち帰ってアトリエに飾るうち、枝から根っこが生えるなど変化する姿を見て「生きているんだ」と改めて感じたり、以前は咲く一瞬こそが美しいとドライフラワーに興味がありませんでしたが、お花の「その後」を見守る中で「これがお花の最後の形かなあ」と愛おしくなったり。
だんだんと気持ちが変化していったんです。
今は、植物はすでに完成されているのだから、私が何か手を加えるのではなく、あるがままに生けるのが一番いいと思っています。束ねるだけ、差すだけなど、シンプルな生け方に変わりました。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
教室の生徒さんが、お花を飾らない友人に「どうして飾らないの?」とたずねたら、「花瓶の水が濁って臭いがしたり、花が傷んで床に落ちたりして、片づけるのが面倒くさい」と言われたそうです。
造花やプリザーブドフラワーなどが流行る背景にはそういった理由があるのだと思いますが、やっぱり生きている植物は違う。たんぽぽでも、れんげ草でもいいから、一家に一輪あれば、平和の素になると、私は信じています。
ただ単純に、お花を見て、腹立たないと思うんです。
さらに言うと、二十四節気という季節を表現するお花を通して、「『当たり前』に思っていることを、もう一度見つめ直してみませんか?」ということを問いかけたい。
ハロウィンやクリスマス、節分、ひなまつりなどの行事に、お花を生け込む機会があるのですが、行事のいわれなどは忘れ去られ、表層だけが独り歩きしてしまっているなあと感じます。
本質が忘れ去られていることによって、たとえば節分の恵方巻きが大量廃棄されていることが問題視されていますが、そのほかにもさまざまなところで問題が生じているのではないでしょうか。
季節のお花を生けることを通して、見る人が行事のいわれについて知ったり考えたりするきっかけをつくり、今「当たり前」と思っている暮らしを見つめ直すことにつなげ、それがひいては平和にもつながっていくのではないかなあと思っているんです。
造花やプリザーブドフラワーなどが流行る背景にはそういった理由があるのだと思いますが、やっぱり生きている植物は違う。たんぽぽでも、れんげ草でもいいから、一家に一輪あれば、平和の素になると、私は信じています。
ただ単純に、お花を見て、腹立たないと思うんです。
さらに言うと、二十四節気という季節を表現するお花を通して、「『当たり前』に思っていることを、もう一度見つめ直してみませんか?」ということを問いかけたい。
ハロウィンやクリスマス、節分、ひなまつりなどの行事に、お花を生け込む機会があるのですが、行事のいわれなどは忘れ去られ、表層だけが独り歩きしてしまっているなあと感じます。
本質が忘れ去られていることによって、たとえば節分の恵方巻きが大量廃棄されていることが問題視されていますが、そのほかにもさまざまなところで問題が生じているのではないでしょうか。
季節のお花を生けることを通して、見る人が行事のいわれについて知ったり考えたりするきっかけをつくり、今「当たり前」と思っている暮らしを見つめ直すことにつなげ、それがひいては平和にもつながっていくのではないかなあと思っているんです。

三品 由賀里さん
服飾デザイン系の短期大学を卒業後、1983年に建築設計事務所に就職。1987年にフラワーアレンジメントスクールのアシスタントになったことを機に、花と緑にかかわる仕事を始める。1989年にフラワーショップに転職。1995年に独立し、「Pelangi」を立ち上げる。現在は企業・店舗・クリニック・個人宅の生け込み、お花のレッスン、ウェディング・パーティーなどの会場装花、お祝いのブーケづくり、ドライフラワー制作・販売などを行う。月に数日「アトリエ開放日」を設けて、ドライフラワーマーケットなどイベントを開催している。
Pelangi
兵庫県姫路市青山1464
HP: https://mishinayukari.jimdofree.com/
(取材:2019年2月)
私から見ると、三品さんがおつくりになるものには「三品さんらしさ」を感じたのですが、三品さんは「自分の個性とは何か」をずっと考えてこられたそうです。
「自分が思うことをやっていればいい。それがいつしか個性になっていたらいいのかなあと漠然と思うようになりました」ともおっしゃっていました。
そのお話を聞いて、「自分らしさ」「個性」は探さなくても見つけられなくても、よいものなのではないか、むしろ探すものではないのかもしれないと思ったんです。
ついつい「自分らしさとは?」「個性とは?」と考えてしまいます。考えて、見つけられたらいいのですが、見つけられなくて焦ったり、自分はダメだと思い詰めたり、しんどくなったりしてしまうこともあるのではないでしょうか。
探さなくても、三品さんのように目の前にある仕事に取り組み、「こうしたい」という気持ちを持ってさえいれば、ちゃんと自分らしい仕事ができているのではないかなあと、お話をうかがって思いました。
HP: 『えんを描く』
「自分が思うことをやっていればいい。それがいつしか個性になっていたらいいのかなあと漠然と思うようになりました」ともおっしゃっていました。
そのお話を聞いて、「自分らしさ」「個性」は探さなくても見つけられなくても、よいものなのではないか、むしろ探すものではないのかもしれないと思ったんです。
ついつい「自分らしさとは?」「個性とは?」と考えてしまいます。考えて、見つけられたらいいのですが、見つけられなくて焦ったり、自分はダメだと思い詰めたり、しんどくなったりしてしまうこともあるのではないでしょうか。
探さなくても、三品さんのように目の前にある仕事に取り組み、「こうしたい」という気持ちを持ってさえいれば、ちゃんと自分らしい仕事ができているのではないかなあと、お話をうかがって思いました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧
-
「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん
-
「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん
-
「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。
-
「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん
-
「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん
-
「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん
-
「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り
-
「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?
-
「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん
-
「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん
-
「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん
-
「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん
-
「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん
-
「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん
-
「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん
-
「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん
-
「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん
-
「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん
-
「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人
-
「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。
-
「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘
-
「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん
-
「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。
-
「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん
-
「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん
-
「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。
-
「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん
-
「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に
-
「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん
-
「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に
-
「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。
-
「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。
-
「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」