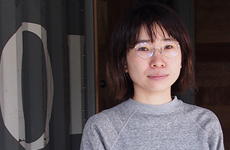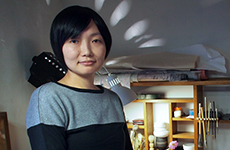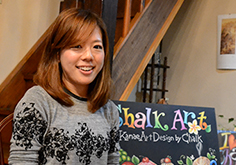HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
![]() 川端 淑恵さん(工作と音楽/いりこ工作舎)
川端 淑恵さん(工作と音楽/いりこ工作舎) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター)
川端 淑恵さん(工作と音楽/いりこ工作舎)

体験をつなぎ合わせたら、自然とこの形に
川端 淑恵さん
工作と音楽/いりこ工作舎
工作と音楽/いりこ工作舎
森に遊びに来たような気持ちになる、木のオブジェ。一見すると、あいらしい双葉がひょこっと顔を出していて、空か湖のような鏡が真ん中にはめ込まれている作品があるのですが、中を覗いてみると、緑色の双葉の上にとまるテントウ虫が。
思わずニコッとなってしまう、そんな作品をつくる「いりこ工作舎」の川端淑恵さん。桐材を主とした木材に異素材を組み合わせるなどして作品をつくるとともに、中南米のトリニダード・トバゴ生まれのドラム缶楽器「スティールパン」奏者として演奏会活動もされています。
もともと設計士だった川端さんが「いりこ工作舎」を立ち上げたきっかけは、さまざまな職人や作家、音楽家の方々と出会い、「自分の体を使って自分の手で何かを生み出したい」と思ったからでした。
「自分も何かを生み出したい」と思っても、実際にやってみること、さらにはお仕事にするのは難しいものですが、川端さんはどのように「やってみたい」という気持ちを形にされてこられたのでしょうか?
思わずニコッとなってしまう、そんな作品をつくる「いりこ工作舎」の川端淑恵さん。桐材を主とした木材に異素材を組み合わせるなどして作品をつくるとともに、中南米のトリニダード・トバゴ生まれのドラム缶楽器「スティールパン」奏者として演奏会活動もされています。
もともと設計士だった川端さんが「いりこ工作舎」を立ち上げたきっかけは、さまざまな職人や作家、音楽家の方々と出会い、「自分の体を使って自分の手で何かを生み出したい」と思ったからでした。
「自分も何かを生み出したい」と思っても、実際にやってみること、さらにはお仕事にするのは難しいものですが、川端さんはどのように「やってみたい」という気持ちを形にされてこられたのでしょうか?
自分で何かを生み出すことへの欲求が芽生えて
短大進学時から「家具職人=木でものづくりをしたい」と思われたそうですが、どうして「木」に関心を持たれたのですか?
父は休日に畑仕事をしたり、家の棚をつくったり、農器具を収納する小屋を建てたり、たいていのものは自分でつくるという人でした。
今でも「すごく嬉しかったなあ」と思い出すのは、私のベッドを丸太からつくってくれたこと。「自分で家具もつくれるんだ。私もつくってみたい」とわくわくしたのを思い出します。
父と一緒に何かをつくることはなかったものの、もくもくと作業する姿を見て、私もノミで木に穴を開けたり、ノコギリで木を切ったりして遊んでいました。この体験が根っこにあるんだと思います。
獣医を諦めて美術系の短大に進学を決めた時は「絵を描くより工作が好き」「陶芸や布ではなくて、木かな」「木だったら、家具をつくれるといいなあ」と子どもの頃の思い出とつながって、「木でものづくり=家具職人」になりたいと思うように。
前の職場は家具工房兼設計事務所であり、ショールーム兼ギャラリーも運営していたので、刺激を受けることがたくさんありました。
職人さんの仕事を見て、「壁紙を貼るんだったら、こういうふうにするんだな」「床材はこう敷くんだな」「ペンキはこう塗るといいんだな」と学んだり、人やモノ、楽しいことが行き交うギャラリーでいろいろな作家や音楽家の方々と出会って「自分で何かをする」おもしろみを感じたり。
そうした日々の中で、自分の体を使って自分の手で何かを生み出すことへの欲求がふつふつと湧いてきて、今につながっています。
今でも「すごく嬉しかったなあ」と思い出すのは、私のベッドを丸太からつくってくれたこと。「自分で家具もつくれるんだ。私もつくってみたい」とわくわくしたのを思い出します。
父と一緒に何かをつくることはなかったものの、もくもくと作業する姿を見て、私もノミで木に穴を開けたり、ノコギリで木を切ったりして遊んでいました。この体験が根っこにあるんだと思います。
獣医を諦めて美術系の短大に進学を決めた時は「絵を描くより工作が好き」「陶芸や布ではなくて、木かな」「木だったら、家具をつくれるといいなあ」と子どもの頃の思い出とつながって、「木でものづくり=家具職人」になりたいと思うように。
前の職場は家具工房兼設計事務所であり、ショールーム兼ギャラリーも運営していたので、刺激を受けることがたくさんありました。
職人さんの仕事を見て、「壁紙を貼るんだったら、こういうふうにするんだな」「床材はこう敷くんだな」「ペンキはこう塗るといいんだな」と学んだり、人やモノ、楽しいことが行き交うギャラリーでいろいろな作家や音楽家の方々と出会って「自分で何かをする」おもしろみを感じたり。
そうした日々の中で、自分の体を使って自分の手で何かを生み出すことへの欲求がふつふつと湧いてきて、今につながっています。

「自分も何かを生み出したい」と思っても、実際にそれを形にするのは難しいと思うのですが、10年前に初めてつくった作品にはすでに川端さんらしい世界観がしっかりと表れていますね。
私の作品においては「桐材」との出会いが大きかったと思います。
当時、近所に桐の木を専門に製材している会社があって、でっかいコンテナに木端がたくさん入れてあったんです。譲ってもらえたので、「この木端を使って何かをつくってみよう」というのが始まりでした。
製材所のおっちゃんから聞いたところによると、昔桐の木は捨てるところがないと言われていて、木端も小さな引き出しといった小間物をつくるのに使われていたそうです。今は海外から製材された木材が輸入されてきますし、小間物をつくる人も少なくなっています。
一本の丸太をひき割って、良質な部分はタンスやお琴になって何年何十年と使われますが、虫食いや木目がきつい部分はお風呂屋さんでお風呂のたきものに使われるか、そのまま処分されるそうです。
同じように何十年と生きてきた一本の丸太なのに選り分けられてしまうなんて、はねられた子らが少々気の毒に思えました。
家具や楽器づくりでは不要とされて捨てられるはずだったものに新たな命を吹き込んで、価値を持つようなものをつくりたい。「不要=捨てられるもん」だからといって、簡単に捨てられるものはつくりたくない。
虫食いや木目のおもしろさを生かして何かできないかなと考えてつくっていたら、自然とこうなっていました。
作品づくりで余った部分も捨て難いと、ピアスやブローチなどちっちゃいアクセサリーもつくるようになったんです。
当時、近所に桐の木を専門に製材している会社があって、でっかいコンテナに木端がたくさん入れてあったんです。譲ってもらえたので、「この木端を使って何かをつくってみよう」というのが始まりでした。
製材所のおっちゃんから聞いたところによると、昔桐の木は捨てるところがないと言われていて、木端も小さな引き出しといった小間物をつくるのに使われていたそうです。今は海外から製材された木材が輸入されてきますし、小間物をつくる人も少なくなっています。
一本の丸太をひき割って、良質な部分はタンスやお琴になって何年何十年と使われますが、虫食いや木目がきつい部分はお風呂屋さんでお風呂のたきものに使われるか、そのまま処分されるそうです。
同じように何十年と生きてきた一本の丸太なのに選り分けられてしまうなんて、はねられた子らが少々気の毒に思えました。
家具や楽器づくりでは不要とされて捨てられるはずだったものに新たな命を吹き込んで、価値を持つようなものをつくりたい。「不要=捨てられるもん」だからといって、簡単に捨てられるものはつくりたくない。
虫食いや木目のおもしろさを生かして何かできないかなと考えてつくっていたら、自然とこうなっていました。
作品づくりで余った部分も捨て難いと、ピアスやブローチなどちっちゃいアクセサリーもつくるようになったんです。

工作と音楽、それらが入り交じって世界観を表現
「工作」ともに、ドラム缶楽器「スティールパン」の演奏活動もされていますね。そのきっかけは?
音楽にはそれほど興味がなかったんですが、前職で、あるスティールパン奏者の演奏とパフォーマンスを観て「音楽ってこんなに素晴らしいんだ。楽しい!」とひき込まれたのがきっかけです。
退職後、その方が教室も兼ねた市民楽団を結成されると聞いて参加。楽器に興味があったのではなく、「音楽の素晴らしさを教えてくださった方とご一緒できるなら」との想いからだったので、まさかスティールパンを使って何かをすることになるなんて想像もしていませんでした。
実際に習い始めたら演奏するのはもちろん、人前で発表するのも楽しい。個人的に「演奏に来てよ」と声をかけられるようになって、「じゃあ!」と引き受けるようになりました。個人で活動を始める前に、スティールパンを教えてくださった方に報告したところ、こんなアドバイスをもらいました。
「その場で見たパフォーマンスがスティールパンの印象になってしまう。『スティールパンって、こんなものか』で終わると、スティールパン奏者全体の次のご縁が切れてしまうかもしれない」
「アマチュアであろうが、プロであろうが、きちんとしたパフォーマンスを見てもらって感動してもらう。『楽しんでやりたい』という気持ちもわかるが、気軽に『アマチュアだから無料でどこでも演奏しに行きますよ』というのは違うよ」って。
技術が伴っていない状態で演奏に行ってもいいのか、やめておいたほうがいいのかもしれないと悩みました。ましてや「出演料をください」なんて言えません。
でも、せっかく声をかけてもらっているので、「稽古をしたり交通費がかかったりするので、演奏活動を続けていくために費用をいただけるとありがたいです」とお願いして、「それでも」と言ってくださるところに行くようにしました。
以降はちょっとずつ、公演料をいただけるようになっていったんです。あのアドバイスがあったから、今も音楽活動を続けることができているのだと思います。
退職後、その方が教室も兼ねた市民楽団を結成されると聞いて参加。楽器に興味があったのではなく、「音楽の素晴らしさを教えてくださった方とご一緒できるなら」との想いからだったので、まさかスティールパンを使って何かをすることになるなんて想像もしていませんでした。
実際に習い始めたら演奏するのはもちろん、人前で発表するのも楽しい。個人的に「演奏に来てよ」と声をかけられるようになって、「じゃあ!」と引き受けるようになりました。個人で活動を始める前に、スティールパンを教えてくださった方に報告したところ、こんなアドバイスをもらいました。
「その場で見たパフォーマンスがスティールパンの印象になってしまう。『スティールパンって、こんなものか』で終わると、スティールパン奏者全体の次のご縁が切れてしまうかもしれない」
「アマチュアであろうが、プロであろうが、きちんとしたパフォーマンスを見てもらって感動してもらう。『楽しんでやりたい』という気持ちもわかるが、気軽に『アマチュアだから無料でどこでも演奏しに行きますよ』というのは違うよ」って。
技術が伴っていない状態で演奏に行ってもいいのか、やめておいたほうがいいのかもしれないと悩みました。ましてや「出演料をください」なんて言えません。
でも、せっかく声をかけてもらっているので、「稽古をしたり交通費がかかったりするので、演奏活動を続けていくために費用をいただけるとありがたいです」とお願いして、「それでも」と言ってくださるところに行くようにしました。
以降はちょっとずつ、公演料をいただけるようになっていったんです。あのアドバイスがあったから、今も音楽活動を続けることができているのだと思います。
「工作」と「音楽」の2本柱でお仕事をされています。それぞれがどう関連しているのですか?
ギャラリーやカフェといった作品の展示もできて音楽も聴けてという場所で、作品展や演奏会を開催することが多いんです。
現在、一緒に音楽活動している相方さんはプロのミュージシャンで、8年前に一緒に何かをしようとなった時、私の作品展で演奏会をしてはどうかという話になりました。
演奏会に来てくれた人が、私のことを知らなくても、その場で作品を見て気に入ってくれるかもしれない。逆に、私の作品展を見に来てくれた人に「今度演奏会をします」と案内したら、音楽に興味を持ってくれるかもしれない。
そういうふうに工作と音楽が入り交じるようなことができたらいいなあと考えました。
今では私の作品展で私が演奏することによって、より世界観を感じてもらえ、イコールでつながっていく感じができています。
現在、一緒に音楽活動している相方さんはプロのミュージシャンで、8年前に一緒に何かをしようとなった時、私の作品展で演奏会をしてはどうかという話になりました。
演奏会に来てくれた人が、私のことを知らなくても、その場で作品を見て気に入ってくれるかもしれない。逆に、私の作品展を見に来てくれた人に「今度演奏会をします」と案内したら、音楽に興味を持ってくれるかもしれない。
そういうふうに工作と音楽が入り交じるようなことができたらいいなあと考えました。
今では私の作品展で私が演奏することによって、より世界観を感じてもらえ、イコールでつながっていく感じができています。

自分が生み出すものが、誰かにとって必要なものに
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか? どう乗り越えられましたか?
壁を乗り越えるというより、工作については壁の上を歩いている感じ、音楽については壁にぶら下がっている感じなんだと思います。
好きで好きでたまらない気持ちが溢れ出して、その溢れ出したものを展示したり販売したり聴いてもらったりする人がうらやましいくらい、私にとっては「好き」「楽しい」気持ちを持ち続けるのは大変なんです。
ものをつくるのは好きだけど、飽き性で面倒くさがりだから、作品づくりにとりかかるまでにだらだらしてしまって、作品展間近になって慌ててつくり始めます。音楽もプレッシャーに押し潰されそうになって、少し前までは本番前に「逃げ出したい」と泣くこともありました。
「苦しい」という気持ちもありながらも続けてこられたのは、矛盾するんですけど、やっぱり楽しいから。
ありがたいことに展示や演奏をさせてもらえる場所があり、行く先々で迎え入れてくださる方々がいて、あたたかい人たちに囲まれていると、私まで楽しくてあたたかな気持ちになれます。演奏直前まで泣いていたのに、終わったら楽しい気持ちになって、その場にいる方々と「ありがとうございました」ときゃっきゃしている(笑)。
「楽しかったよ」「来年、作品展してみいひん?」と楽しさや次の目標を与えてくれる人たちがいるから、10年も続けてくることができたんだと思うんです。
好きで好きでたまらない気持ちが溢れ出して、その溢れ出したものを展示したり販売したり聴いてもらったりする人がうらやましいくらい、私にとっては「好き」「楽しい」気持ちを持ち続けるのは大変なんです。
ものをつくるのは好きだけど、飽き性で面倒くさがりだから、作品づくりにとりかかるまでにだらだらしてしまって、作品展間近になって慌ててつくり始めます。音楽もプレッシャーに押し潰されそうになって、少し前までは本番前に「逃げ出したい」と泣くこともありました。
「苦しい」という気持ちもありながらも続けてこられたのは、矛盾するんですけど、やっぱり楽しいから。
ありがたいことに展示や演奏をさせてもらえる場所があり、行く先々で迎え入れてくださる方々がいて、あたたかい人たちに囲まれていると、私まで楽しくてあたたかな気持ちになれます。演奏直前まで泣いていたのに、終わったら楽しい気持ちになって、その場にいる方々と「ありがとうございました」ときゃっきゃしている(笑)。
「楽しかったよ」「来年、作品展してみいひん?」と楽しさや次の目標を与えてくれる人たちがいるから、10年も続けてくることができたんだと思うんです。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
100円均一ショップでは何でも揃いますし、手づくりされている方もたくさんいて、現代はものがたくさん溢れています。また、年齢を重ねるほどにものを持たない、必要なものだけあればいいという考えに変わってきました。
何かをつくり続けることが本当にいいことなんだろうか、私がつくっているものは生きていくためにどうしても必要なものではないから悩むんです。
そんなことを考えていた時、ブローチづくりのワークショップに小学生が参加してくれたことがありました。桐材はカッターナイフで削れるから簡単でとっつきやすいかなと思ったら、その子が「カッターナイフを使ったことがない」って。音楽の演奏で学校をまわることもあり、工作の提案をするのですが、「学校ではカッターナイフは触らない」というところもありました。
私は子どもの頃からカッターナイフをはじめ、さまざまな工具が家にあって、誰に何を言われることなく使っていたから、自然と身に付いていたのですが、同年代の人でも経験のない人はいます。さらに、今の子どもたちはカッターナイフに触れる機会もないんだと知りました。
私が今こうしてものづくりをしているのも、日々の中で何となく見たり聞いたりといった自分が体験してきたことから自然とできていること。
道具を使ったり材料や素材を組み合わせたりなどいろんな体験があると、たとえば先日の台風の時のように停電した場合に電気が使えないとたちまち困って何もできなくなるのではなく、「あれとこれをこうしたら、こんなことができる」など体験をつなぎ合わせて、アイデアや工夫が思い浮かぶのではないかなって。
そういったアイデアや工夫のもとになる「体験」を一緒に楽しみながら共有できたらいいなあと考えているんです。
「いりこ工作舎」の「いりこ」には「いるこ=必要な子」になれたらいいなあという願いもこめています。自分のつくり出すもの、生み出すものが誰かにとって必要なものであってほしい。これからも、そんなことをしていきたいですね。
何かをつくり続けることが本当にいいことなんだろうか、私がつくっているものは生きていくためにどうしても必要なものではないから悩むんです。
そんなことを考えていた時、ブローチづくりのワークショップに小学生が参加してくれたことがありました。桐材はカッターナイフで削れるから簡単でとっつきやすいかなと思ったら、その子が「カッターナイフを使ったことがない」って。音楽の演奏で学校をまわることもあり、工作の提案をするのですが、「学校ではカッターナイフは触らない」というところもありました。
私は子どもの頃からカッターナイフをはじめ、さまざまな工具が家にあって、誰に何を言われることなく使っていたから、自然と身に付いていたのですが、同年代の人でも経験のない人はいます。さらに、今の子どもたちはカッターナイフに触れる機会もないんだと知りました。
私が今こうしてものづくりをしているのも、日々の中で何となく見たり聞いたりといった自分が体験してきたことから自然とできていること。
道具を使ったり材料や素材を組み合わせたりなどいろんな体験があると、たとえば先日の台風の時のように停電した場合に電気が使えないとたちまち困って何もできなくなるのではなく、「あれとこれをこうしたら、こんなことができる」など体験をつなぎ合わせて、アイデアや工夫が思い浮かぶのではないかなって。
そういったアイデアや工夫のもとになる「体験」を一緒に楽しみながら共有できたらいいなあと考えているんです。
「いりこ工作舎」の「いりこ」には「いるこ=必要な子」になれたらいいなあという願いもこめています。自分のつくり出すもの、生み出すものが誰かにとって必要なものであってほしい。これからも、そんなことをしていきたいですね。
川端 淑恵さん
美術系の短期大学を卒業後、輸入家具を取り扱う会社を経て、家具工房兼設計事務所「ヤマシロファニシング」(現:ブリコラージュ)に入社。設計士として造作家具の設計や空間づくりに伴う内装のコーディネート、現場管理などを担当するほか、同社が運営するショールーム兼ギャラリーでイベントスタッフとしても活躍。2004年に身体の不調により、退職。しばらく休息したのち、前職での経験によって創造することのおもしろさや音楽の素晴らしさを知ったことで、自分自身で何かを生み出すべく動き出す。2007年より活動を開始し、2008年に「いりこ工作舎」と屋号を付けた。現在は関西を中心に、各地で作品展やワークショップ、演奏会を開催するほか、学校等を回っての演奏活動も行う。
いりこ工作舎
FB: irikokousakusya
(取材:2018年9月)
「私が今こうしてものづくりをしているのも、日々の中で何となく見たり聞いたりといった自分が体験してきたことから自然とできていること」と川端さん。
川端さんが「いりこ工作舎」を立ち上げたのは30代前半でした。子どもの頃から「木でものづくり」に興味がありながらも、ご自身の作品をつくることはされていませんでしたが、「自分で何かを生み出したい」と作品をつくった時、すでに川端さんらしい世界観が出来上がっていました。
人それぞれ個性があるので「その人らしさ」は自然と表れると思いますが、川端さんの作品には揺るぎないまなざしを感じます。
そこには、川端さんの感性と、子どもの頃からお父さまをはじめ、職人や作家、音楽家の方々などのそばで、見て聞いて感じて蓄積されてこられた技術や表現方法が根本にあります。川端さんが個人で活動を始められたタイミングはまさに「機が熟する時」だったのだと思いました。
川端さんのお話をうかがいながら、私も見たり聞いたり感じたりといった体験を日常的に行っていますが、一つひとつの体験を大切にできているだろうか、「おぉ!」「なるほど!」と吸収する素直さを持つことができているだろうかと自問しました。
HP: 『えんを描く』
川端さんが「いりこ工作舎」を立ち上げたのは30代前半でした。子どもの頃から「木でものづくり」に興味がありながらも、ご自身の作品をつくることはされていませんでしたが、「自分で何かを生み出したい」と作品をつくった時、すでに川端さんらしい世界観が出来上がっていました。
人それぞれ個性があるので「その人らしさ」は自然と表れると思いますが、川端さんの作品には揺るぎないまなざしを感じます。
そこには、川端さんの感性と、子どもの頃からお父さまをはじめ、職人や作家、音楽家の方々などのそばで、見て聞いて感じて蓄積されてこられた技術や表現方法が根本にあります。川端さんが個人で活動を始められたタイミングはまさに「機が熟する時」だったのだと思いました。
川端さんのお話をうかがいながら、私も見たり聞いたり感じたりといった体験を日常的に行っていますが、一つひとつの体験を大切にできているだろうか、「おぉ!」「なるほど!」と吸収する素直さを持つことができているだろうかと自問しました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(クリエイター) 記事一覧
-
「音楽に関わりたい」がスタートライン職業や肩書きには囚われず、さまざまな肩書きを持つ岡安さん
-
「おもしろい!と思うものには目がない」出会いに感化されてイラストレーターの道を歩む暢さん
-
「自分が好きで動いてきたことは無駄じゃない」眠っていた印刷機を復活させ、活版印刷の味わいを伝える雅子さん。
-
「チャレンジし続けないと現状維持できない」1点1点手描きでマトリョーシカをつくる小林さん
-
「気の向くままを表現することが心地よい」布に絵を描くように独特な存在感の刺繍作品をつくる幸貴さん
-
「あるものを生かして自分らしい表現をしたい」「播州織」と出会い、ブランドを立ち上げた大塚さん
-
「続けるためにはどうしたらいいのかを考え続けて」帽子を作り続けて17年。秘訣は仕事の仕組み作り
-
「一家に一輪あれば平和の素になる」花を仕事にして32年の三品さん。長年続けてきたからこそ、見えたこととは?
-
「何者にもならなくていい」自身の表現に悩みながらイラストレーターから転身した青木さん
-
「体験をつなぎ合わせたら自然とこの形に」木工と音楽の2つを組み合わせる川端さん
-
「私が着てみたい服をつくる」自分のイメージを形にした洋服が大人気ブランドになった甲斐さん
-
「オーダーメイドはいつも新しいことへの挑戦」好奇心からのはじまりで現在のお仕事に辿り着いたという降矢さん
-
「自分がつくりたいものじゃないと作品が生きてこない」ユニークな形のカバンが人気の革カバン作家、山本さん
-
「人と人が出会うことで起こせる化学反応」アートスペース『ブリコラージュ』を運営する増谷さん
-
「人形劇をしたいというよりその世界に行きたい」人形劇で自分の思い描く世界を表現する亜矢子さん
-
「記憶に刻まれるカバンをつくりたい」自分発信のものづくりをしたいとカバン職人になった前波さん
-
「「私にしか」が自信につながる」ボタンづくりに魅せられ、創作することで素になれたと仰る山田さん
-
「その人の人生と結びつく、奥深いにんぎょうをつくりたい」人生を背負った相棒としてにんぎょうを創る入江さん
-
「個展は「お芝居」、ぬいぐるみと人形は「役者」」結成11年。自分たちが愛着を持てる人形を創り続けるお二人
-
「どこにどんなチャンスがあるかわからない」やわらかな色彩で魔法のような世界観を描く絵本作家の水穂さん。
-
「信頼しているから互いの仕事には口出ししない」オーダーメイドウェディングドレスのブランドを作る森下さん母娘
-
「自分がくじけない限りは失敗とは言わない」てのひらサイズのアコーディオン風楽器ペパニカを考案した岡田さん
-
「プロになるということは目がプロになること」パッケージデザイン界の「さかなクン」を目指す三原さん。
-
「どんな人が作っているか、わざわざ来ていただいけるようになりたい」銀製かんざしアーティスト華枝さん
-
「思い出を載せられるものを作れるのは、たまらない」一生ものの宝物を作れることは幸せという徳永さん
-
「色を重ねていくことは人との繋がりや想いと同じ」クマのイラストに「祈り」を込めて絵本を出版されたツナ子さん。
-
「人の想いを引き出せる写真を撮りたい」単身ニューヨーク等世界中を旅するカメラマン後藤みゆきさん
-
「元気になれるこの世界観が好き。と言われることが一番嬉しい」編み物が大好きだった女の子が全国にファンを持つニット帽作家に
-
「自分で作りたい」手芸が好きで手芸業界に就職。幼い頃からの想いを叶えるため作家に転身されたこのみさん
-
「一つ一つがニューヨークの香りがする」初めて訪れたニューヨーク。古い小さな雑貨との出会いからスーベニール創作作家に
-
「壁画に恋した作家」日本全国のみならず海外でも活躍中の「おえかきさきえ」こと今川さん。彼女の絵には数え切れないほどの幸せが隠れています。
-
「何もないまま帰国したら中身のない30代になってしまう」27歳の時オーストラリアのワーキングホリデー留学中に偶然出会ったチョークアート。
-
「趣味ではなくプロになろうと一大決心」一冊の本の表紙デザインから始まったシュールでお洒落な「山本佳世ワールド」