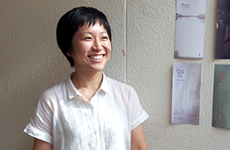HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() 関谷 友加里さん(音楽家)
関谷 友加里さん(音楽家) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
関谷 友加里さん(音楽家)

生きることと、音は直結する
関谷 友加里さん
音楽家
音楽家
ジャズピアニストとして演奏活動を行うほか、自作曲の発表、作編曲の提供、即興演奏による舞踏家や画家とのコラボレーションなど、音楽家として幅広く活躍する関谷友加里さん。
ミュージシャンとしてこれからという24歳で結婚し、「同世代に負けたくない」という焦りと向上心ゆえの理想像により、「家庭の中での自分」と「ミュージシャンの私」を切り分けようとしたことで、そのジレンマに思い悩んだと言います。
「生きることと、音は直結する」。一度は切り分けようとしたものを再び結びつけ、どちらも自分自身、自分の人生として大事にできるようになったきっかけとは?
ミュージシャンとしてこれからという24歳で結婚し、「同世代に負けたくない」という焦りと向上心ゆえの理想像により、「家庭の中での自分」と「ミュージシャンの私」を切り分けようとしたことで、そのジレンマに思い悩んだと言います。
「生きることと、音は直結する」。一度は切り分けようとしたものを再び結びつけ、どちらも自分自身、自分の人生として大事にできるようになったきっかけとは?
音を合わせる中で、ひゅぃっと混ざり合える
4歳の時からピアノを習い、もともとはクラシック音楽をされていたそうですが、ジャズに転向するきっかけは?
私はまったく覚えていないのですが、ピアノを習い始めたのは、私から「習いたい」と言ったみたいです。ピアノ教室ではクラシック音楽だけではなく、好きなアニメやJ-POPの曲も弾かせてもらえたので、高校生になっても機嫌良く通っていました。
ジャズに興味を持ったのは高校1年生の時。中学時代からバンド活動をしていた2歳上の兄から「キーボードを演奏して」と頼まれて、バンドに参加したことがきっかけでした。
それまで1人で演奏して完結していた私にとって、ベーシストやギタリスト、ドラマーと演奏するのは初めて。誰かと一緒に演奏するのって、なんて気持ちがいいんだろうと、快感になってしまったんです(笑)。
その時に演奏した曲のジャンルが、ジャズと、ロックやラテン音楽などさまざまな音楽が融合した「フュージョン」だったから「ジャズをやろう」と、高校2年生の時からジャズのピアノレッスンに通い始めました。
ジャズの即興性にも魅かれ、ますますのめり込んでいったんです。
ジャズに興味を持ったのは高校1年生の時。中学時代からバンド活動をしていた2歳上の兄から「キーボードを演奏して」と頼まれて、バンドに参加したことがきっかけでした。
それまで1人で演奏して完結していた私にとって、ベーシストやギタリスト、ドラマーと演奏するのは初めて。誰かと一緒に演奏するのって、なんて気持ちがいいんだろうと、快感になってしまったんです(笑)。
その時に演奏した曲のジャンルが、ジャズと、ロックやラテン音楽などさまざまな音楽が融合した「フュージョン」だったから「ジャズをやろう」と、高校2年生の時からジャズのピアノレッスンに通い始めました。
ジャズの即興性にも魅かれ、ますますのめり込んでいったんです。

短大のジャズコースを卒業後、どのようにご自分のお仕事をつくってこられたのですか?
在学中から始めたカフェでBGMを演奏するアルバイトを続けながら、オリジナル曲をつくって兄と兄の音楽仲間と一緒にライブ開催やアルバム制作をしていたほか、アマからプロまでさまざまなミュージシャンが集うジャズのライブハウスに通い始めました。
ライブハウスのマスターから音楽活動のアドバイスをもらったり、歌の伴奏などピアニストとして経験を積めるチャンスをもらったり、その場に集ったミュージシャンと即興演奏する「セッション」を通して出会いがあり、「一緒にライブをやろう」と声をかけてもらったりして、経験を積みながら、ふわふわふわっと活動の機会も増やしていきました。
フリーのミュージシャンって、結びつき方がおもしろいんです。
「今日はここ」「明日はあそこ」とライブハウスを転々としながら、日々違うミュージシャンとセッションします。お互いに「合う」と思えば、ライブを一緒にしたりバンドを組んだりすることがありますし、どちらか一方でも「合わない」と思えば、1度限りということもあります。
バンドも1グループだけではなく、自分がリーダーのグループを持ちつつ、ほかのグループにも所属することもあるんです。
私がリーダーとして率いる「関谷友加里トリオと由中小唄」は、私が憧れのピアニストのライブに行った時、コントラバス奏者の森定道広さんを紹介してもらい、初対面かつセッションをしたことがないのに、森定さんから「じゃあ、一緒にやろか」「セッションしなくても、だいたいわかるやん」と言われて(笑)。
音を合わせてみたら合ったから、そのままバンドを結成し、2018年で10周年を迎えました。
ライブハウスのマスターから音楽活動のアドバイスをもらったり、歌の伴奏などピアニストとして経験を積めるチャンスをもらったり、その場に集ったミュージシャンと即興演奏する「セッション」を通して出会いがあり、「一緒にライブをやろう」と声をかけてもらったりして、経験を積みながら、ふわふわふわっと活動の機会も増やしていきました。
フリーのミュージシャンって、結びつき方がおもしろいんです。
「今日はここ」「明日はあそこ」とライブハウスを転々としながら、日々違うミュージシャンとセッションします。お互いに「合う」と思えば、ライブを一緒にしたりバンドを組んだりすることがありますし、どちらか一方でも「合わない」と思えば、1度限りということもあります。
バンドも1グループだけではなく、自分がリーダーのグループを持ちつつ、ほかのグループにも所属することもあるんです。
私がリーダーとして率いる「関谷友加里トリオと由中小唄」は、私が憧れのピアニストのライブに行った時、コントラバス奏者の森定道広さんを紹介してもらい、初対面かつセッションをしたことがないのに、森定さんから「じゃあ、一緒にやろか」「セッションしなくても、だいたいわかるやん」と言われて(笑)。
音を合わせてみたら合ったから、そのままバンドを結成し、2018年で10周年を迎えました。

関谷さんがおっしゃる通り、結びつき方がおもしろいですね。「合う、合わない」とは、どんな感覚なのですか?
「ジャズ」と一言で言っても、その中でジャンルが多岐に分かれています。
「ジャズといえば」とのイメージが多く持たれる定番のものがあれば、ピアノのソロ演奏のしっとりとしたもの、「ビッグ・バンド」と呼ばれるオーケストラタイプのもの、キーもコードもリズムも自由な「フリー・ジャズ」と呼ばれるものなど。
また、即興音楽ですが、演奏スタイルがあります。
「1、2」と行進するみたいに合わせるもの、「これをしたら、こうするか、ああするか」「それをしたら、こうするか、ああするか」といくつかの選択肢から選んでパリッと決めるもの、道筋を決めず、演奏する中で音を追いかけたり離れたり反応し合ったりする自由なスタイルのものなど。
私の場合は、フリー・ジャズで、フリーな演奏スタイルが好きなんです。
即興で音楽をつくり上げていく中で、そういった音楽の方向性はもちろん、「どのタイミングで入るか」「どんなポジションを担うか」「どんな動きをするか」といったことから、性格や価値観までもが見えてきます。
言葉を交わさなくても、音を合わせるだけで、お互いをわかり合い、親密になっていくような感覚があって、気が合う人となら、ひゅぃっと混ざり合える。まるで一心同体になるような感覚があるんです。色で例えるなら、赤と白を混ぜてピンクになるみたいな感じ。
「関谷友加里トリオと由中小唄」で演奏している時は、わああっと1つのところに集まってきたと思ったら、1人がふわっと離れたり、その1人を3人で追いかけてまた4人で集まったり、全員がばらばらになってみたり、また「集合!」となって1つになったりというイメージが、演奏中ずっと広がっています。
違う人間同士、違う音同士が、音と音を重ねた時に混ざり合って1つになる感覚を体験できて、なんてラッキーなんだって、いつも思うんです。ライブであれば、お客さんのエネルギーやその場が持つ空気も混ざり合うから、より濃厚なイメージが広がります。
私がライブ主体で活動しているのは、その快感がたまらないからかもしれません。
「ジャズといえば」とのイメージが多く持たれる定番のものがあれば、ピアノのソロ演奏のしっとりとしたもの、「ビッグ・バンド」と呼ばれるオーケストラタイプのもの、キーもコードもリズムも自由な「フリー・ジャズ」と呼ばれるものなど。
また、即興音楽ですが、演奏スタイルがあります。
「1、2」と行進するみたいに合わせるもの、「これをしたら、こうするか、ああするか」「それをしたら、こうするか、ああするか」といくつかの選択肢から選んでパリッと決めるもの、道筋を決めず、演奏する中で音を追いかけたり離れたり反応し合ったりする自由なスタイルのものなど。
私の場合は、フリー・ジャズで、フリーな演奏スタイルが好きなんです。
即興で音楽をつくり上げていく中で、そういった音楽の方向性はもちろん、「どのタイミングで入るか」「どんなポジションを担うか」「どんな動きをするか」といったことから、性格や価値観までもが見えてきます。
言葉を交わさなくても、音を合わせるだけで、お互いをわかり合い、親密になっていくような感覚があって、気が合う人となら、ひゅぃっと混ざり合える。まるで一心同体になるような感覚があるんです。色で例えるなら、赤と白を混ぜてピンクになるみたいな感じ。
「関谷友加里トリオと由中小唄」で演奏している時は、わああっと1つのところに集まってきたと思ったら、1人がふわっと離れたり、その1人を3人で追いかけてまた4人で集まったり、全員がばらばらになってみたり、また「集合!」となって1つになったりというイメージが、演奏中ずっと広がっています。
違う人間同士、違う音同士が、音と音を重ねた時に混ざり合って1つになる感覚を体験できて、なんてラッキーなんだって、いつも思うんです。ライブであれば、お客さんのエネルギーやその場が持つ空気も混ざり合うから、より濃厚なイメージが広がります。
私がライブ主体で活動しているのは、その快感がたまらないからかもしれません。

生活と音楽を切り分けたゆえに、生まれたギャップ
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
結婚や子育てとの両立について悩んだり葛藤したりすることが多々ありました。
ミュージシャンとしてこれからという24歳で結婚。夫もミュージシャンとしてライブ活動しているので理解はあったものの、夫は当時会社員として働いていたので、遠慮する気持ちもあって、「妻」と「ミュージシャン」という2つの立ち位置のバランスが難しかったんです。
ライブは夜が中心で、バンドの練習も夜が多いので、出産後はますます音楽活動がしにくくなっていきました。
まわりの同世代は独身でバリバリ活躍していたから、「負けたくない」という意地がありましたし、音楽仲間から声をかけられることが減るかもしれないという焦りもありましたから、「私は変わらず、向上し続けます」「これまで通り、夜でも変わりなくライブができます」とアピール。
独身時代に比べると、ペースは落ちたものの、無理に無理を重ねてきた気がします。
そんな状況の中、ライブなどに行くと「人妻になったんやろ?」「夫に養ってもらってるん?」「お子さんはどうしているの?」「ママなのに偉いね」、さらにはアドバイスのつもりで「ミュージシャンはお母さん感を出すもんじゃない」と言われることもあって、悪意はないことはわかるのですが、気持ちがもやもや。
言われれば言われるほどに、生活感を出さないようにと頑なになっていきました。
ミュージシャンとしてこれからという24歳で結婚。夫もミュージシャンとしてライブ活動しているので理解はあったものの、夫は当時会社員として働いていたので、遠慮する気持ちもあって、「妻」と「ミュージシャン」という2つの立ち位置のバランスが難しかったんです。
ライブは夜が中心で、バンドの練習も夜が多いので、出産後はますます音楽活動がしにくくなっていきました。
まわりの同世代は独身でバリバリ活躍していたから、「負けたくない」という意地がありましたし、音楽仲間から声をかけられることが減るかもしれないという焦りもありましたから、「私は変わらず、向上し続けます」「これまで通り、夜でも変わりなくライブができます」とアピール。
独身時代に比べると、ペースは落ちたものの、無理に無理を重ねてきた気がします。
そんな状況の中、ライブなどに行くと「人妻になったんやろ?」「夫に養ってもらってるん?」「お子さんはどうしているの?」「ママなのに偉いね」、さらにはアドバイスのつもりで「ミュージシャンはお母さん感を出すもんじゃない」と言われることもあって、悪意はないことはわかるのですが、気持ちがもやもや。
言われれば言われるほどに、生活感を出さないようにと頑なになっていきました。

その「壁」または「悩み」をどのように乗り越えられ、どんなことを学ばれましたか?
現実を受け入れて、今のベストを尽くす、したいことをすることに焦点を当てると、ひらきなおれるようになっていきました。そうなれたのは、自分が何かをして乗り越えたというより、歳月の積み重ねとともに、自分も、状況も、少しずつ変化してきたからだと思います。
たとえば、上の子は知的障害なのですが、3歳の時に診断されるまで、「もしかしたら」「いや、違うかもしれない」と思い悩み、周囲の「こうでは」「ああでは」という意見にも心が揺れ、ライブに向かう途中もスマホで調べるなど、気持ちの切り替えが難しくて、ライブ活動を続けていけないかもしれないと思った時期がありました。
同じ頃、第2子を授かりたいとも考えていたのですが、そのことについて、相手の立場で考えれば仕方のないことかもしれませんが、ものすごく理不尽なことを言われて、「もう我慢している必要はない」とプチンと切れるものがありました。
下の子が生まれて2人の子育てとなると、できることがさらに限られてきます。上の子の障害について診断が出ると、悩みはあるけれども、悩みの質が変わって、目の前がぱあぁっとクリアになっていったんです。
私は、私にできることしかできない。そう、すとんと落ちてきました。
今振り返れば、「結婚しても、出産しても、私は変わらない。バリバリ活動して、強くてかっこいいミュージシャンをめざすんだ」って、ずっと理想の自分になろうとしていたのだと思います。「家庭の中での私」と「ミュージシャンの私」を切り分けようとしていたから、そのギャップがしんどかったんです。
「家庭の中での私」も、「ミュージシャンの私」も、どちらも私。音楽には私そのものが表れるという実感があったから、生活も大切に、丁寧に生きていきたいとリンクし始めました。
たとえば、上の子は知的障害なのですが、3歳の時に診断されるまで、「もしかしたら」「いや、違うかもしれない」と思い悩み、周囲の「こうでは」「ああでは」という意見にも心が揺れ、ライブに向かう途中もスマホで調べるなど、気持ちの切り替えが難しくて、ライブ活動を続けていけないかもしれないと思った時期がありました。
同じ頃、第2子を授かりたいとも考えていたのですが、そのことについて、相手の立場で考えれば仕方のないことかもしれませんが、ものすごく理不尽なことを言われて、「もう我慢している必要はない」とプチンと切れるものがありました。
下の子が生まれて2人の子育てとなると、できることがさらに限られてきます。上の子の障害について診断が出ると、悩みはあるけれども、悩みの質が変わって、目の前がぱあぁっとクリアになっていったんです。
私は、私にできることしかできない。そう、すとんと落ちてきました。
今振り返れば、「結婚しても、出産しても、私は変わらない。バリバリ活動して、強くてかっこいいミュージシャンをめざすんだ」って、ずっと理想の自分になろうとしていたのだと思います。「家庭の中での私」と「ミュージシャンの私」を切り分けようとしていたから、そのギャップがしんどかったんです。
「家庭の中での私」も、「ミュージシャンの私」も、どちらも私。音楽には私そのものが表れるという実感があったから、生活も大切に、丁寧に生きていきたいとリンクし始めました。

音楽には私そのものが表れる
「音楽には私そのものが表れる」。それまで切り分けようとしていた生活と音楽の2つを、どう結びつけていったのですか?
「音楽には私そのものが表れる」と最初に感じたのは、オリジナル曲のほかに、曲がない状態から音を出す「完全即興」にも取り組んでいたからだと思います。
まったくのアドリブ演奏だから、つくり込んだものではない、私そのものが表れてしまうんです。「私は、私にできることしかできない」と思えた根本には、その体感があったのでしょう。
たとえば、家がぐちゃぐちゃで、子どもに対しても「早く、早く」と言っていたら、そんな音しか出てこないと思うんです。
だから、演奏中だけではなく、日常生活から、人との接し方、悩みや問題との向き合い方もうやむやにせず、自分の軸をしっかりと持って生きることで、自分が出せる音も発展させていけるのではないか・・・生きることと、音は直結する。そんなふうに考えるようになったんです。
そう考えていくと、だんだんと音楽は私にとって特別ではなく、寝る、食べる、遊ぶ、料理するという、生きていることの一部になってきました。それくらい当たり前で、欠かせないものになっています。
まったくのアドリブ演奏だから、つくり込んだものではない、私そのものが表れてしまうんです。「私は、私にできることしかできない」と思えた根本には、その体感があったのでしょう。
たとえば、家がぐちゃぐちゃで、子どもに対しても「早く、早く」と言っていたら、そんな音しか出てこないと思うんです。
だから、演奏中だけではなく、日常生活から、人との接し方、悩みや問題との向き合い方もうやむやにせず、自分の軸をしっかりと持って生きることで、自分が出せる音も発展させていけるのではないか・・・生きることと、音は直結する。そんなふうに考えるようになったんです。
そう考えていくと、だんだんと音楽は私にとって特別ではなく、寝る、食べる、遊ぶ、料理するという、生きていることの一部になってきました。それくらい当たり前で、欠かせないものになっています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
上の子のおかげで、障害のある子に興味が湧きすぎて、放課後等デイサービスで週1回働いています。そんな日々の中で、障害のある人を対象にしたライブやワークショップを開催したいと思うようになりました。
一般的なコンサートやライブには行きにくいと感じている障害のある人やご家族がいます。中には「演奏中に大きな声を出したらどうしよう」「くるくる歩きまわったらどうしよう」と考えて遠慮している人たちもいるんです。
私の娘も、暗い場所も、大きな音も恐がってしまうから、会場の中に入れなかったり、途中で帰ろうとなったりします。
昼間に、それぞれがそれぞれのスタイルで音楽を楽しめるように広い会場で、照明も明るく、音も優しくしたライブができたらいいなあと。かつ、子ども向けではない、プロのほんまんの音楽が聞けるという内容で、定期的に開催したいと考えています。
そのほか、以前にライブでOHPという機器の上に乗せた水槽に絵の具やオイルなどで描くという手法で、私たちの音楽を表現してもらったことがあって、この手法なら耳の聞こえない人にも音楽を楽しんでもらえるのではないかなと思い、演奏による音の響きと、ダンサーのダンスなどの視覚的要素を取り入れたライブもしてみたいとも。
上の子のおかげで芽生えた夢です。日々のことと音楽は混ざり合っていきます。
一般的なコンサートやライブには行きにくいと感じている障害のある人やご家族がいます。中には「演奏中に大きな声を出したらどうしよう」「くるくる歩きまわったらどうしよう」と考えて遠慮している人たちもいるんです。
私の娘も、暗い場所も、大きな音も恐がってしまうから、会場の中に入れなかったり、途中で帰ろうとなったりします。
昼間に、それぞれがそれぞれのスタイルで音楽を楽しめるように広い会場で、照明も明るく、音も優しくしたライブができたらいいなあと。かつ、子ども向けではない、プロのほんまんの音楽が聞けるという内容で、定期的に開催したいと考えています。
そのほか、以前にライブでOHPという機器の上に乗せた水槽に絵の具やオイルなどで描くという手法で、私たちの音楽を表現してもらったことがあって、この手法なら耳の聞こえない人にも音楽を楽しんでもらえるのではないかなと思い、演奏による音の響きと、ダンサーのダンスなどの視覚的要素を取り入れたライブもしてみたいとも。
上の子のおかげで芽生えた夢です。日々のことと音楽は混ざり合っていきます。
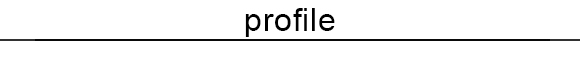
関谷 友加里さん
大阪音楽大学短期大学部音楽専攻ジャズコースを首席で卒業。師である石井彰氏の影響でオリジナル曲をつくるようになり、2004年に第1作目となる『Nobody Is There』を発表、2005年には自作曲を収録したアルバム『a sunset glow』を発表した。2007年に自身がリーダーとして率いる「関谷友加里トリオ」を結成、2010年にボーカルの田中ゆうこ(現、由中小唄)が加入した(のちに「関谷友加里トリオと由中小唄」と改名)。2011年に2枚目のアルバムとなる『ありふれた愛なので・・・』を発表。2013年には同タイトル曲で「石川県加賀温泉郷フェス」のイベントでグランプリを受賞。現在は、ピアニストとして演奏活動を行うほか、自作曲の発表、作編曲の提供、即興演奏による舞踏家や画家とのコラボレーション、「メロンオールスターズ」「SEMODAI」といった他グループ参加、母校の大阪音楽大学短期大学部で講師を務めるなどしている。
BLOG: http://sunset-glow.dreamlog.jp
(取材:2019年7月)
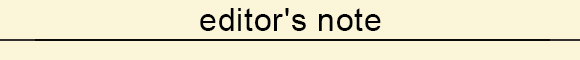
そういった理想や2面性を持ってしまった背景には、「女性だから」「結婚しているから」「子どもがいるから」という視点で見られることをひしひしと感じていたからではないでしょうか。どこか「求められる自分」「必要とされる自分」を演じてしまっていたのではないか、とも。私自身も子育てをしながら、仕事を続けてきた中で、心当たりがありました。
関谷さんは「『こうなりたい』という理想があるから、目標に向かって突き進んでいける場合もありますが、理想もほどほどでないとだめですね」といったこともおっしゃっていて、理想と自分、その現実にかい離があると、自分自身の性格や特性に合わない無理をしてしまい、時に自分自身を追い詰めてしまうこともあるんだと、関谷さんのお話をうかがいながら思いました。
切り分けられるものなどなく、どれも自分であり、自分の人生。そうおっしゃられた時の関谷さんの姿が心に残っています。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。