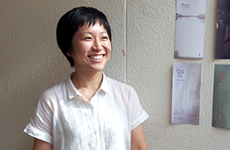HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() 上原 奈未さん(音楽家)
上原 奈未さん(音楽家) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
上原 奈未さん(音楽家)

「なんとなく」ではなく、「好き」と確信できることを
上原 奈未さん
音楽家
音楽家
アイルランドやスコットランドなどケルト地域や、ノルウェーやスウェーデンなど北欧の伝承音楽を演奏するアンサンブルユニット「シャナヒー」、4人の歌手を加えた「シャナヒー&アンニコル」、ケルト・北欧の笛演奏家hataoさんとのデュオ「hatao&nami」を結成し、音楽活動に長く取り組んできた上原奈未さん。
ピアノやハープ、足踏みオルガンを演奏するミュージシャンであり、ご自身で曲のアレンジや作曲をはじめ、絵・デザインも含めたCD制作、WEBページやチラシ制作までを手掛けるアーティストでもあります。
「自分が好きなことをして生きていきたい」「それが私の幸せ」と語る上原さん。その言葉通り、「これが好き」「こういうことをやりたい」という強い想いを持ち、貫き、自分らしい仕事をつくってこられました。
これほどまでに強い想いを持つきっかけとは? その想いを持ち続けてきた背景には、何があるのでしょうか?
ピアノやハープ、足踏みオルガンを演奏するミュージシャンであり、ご自身で曲のアレンジや作曲をはじめ、絵・デザインも含めたCD制作、WEBページやチラシ制作までを手掛けるアーティストでもあります。
「自分が好きなことをして生きていきたい」「それが私の幸せ」と語る上原さん。その言葉通り、「これが好き」「こういうことをやりたい」という強い想いを持ち、貫き、自分らしい仕事をつくってこられました。
これほどまでに強い想いを持つきっかけとは? その想いを持ち続けてきた背景には、何があるのでしょうか?
自分で見つけた「楽しい」が、「好き」になった
幼い頃から大学時代まで、ピアノでクラシック音楽をされてきたそうですね。
ピアニストの夢を志半ばで諦めて音楽教師になった祖父が、私が生まれる少し前に亡くなったこともあって、母は私をピアニストにしようと考えたそうです。
今でこそ、音楽の道に進むきっかけをくれた母に感謝していますが、高校時代までは音楽が好きかどうかより、「上手に弾きたい。弾かなければならない」という想いしかなく、しんどくて逃げ出したくなったこともありました。
同じように、母親の情熱からピアノ人生を歩み始めた友人たちが、途中でピアノをやめたり、親子断絶したりする姿を目の当たりにしてきました。
私の場合は幸い、母が自分のお店をオープンして情熱が移ったので、大学時代にようやく、自分の意思で音楽と向き合えるようになったんです。
今でこそ、音楽の道に進むきっかけをくれた母に感謝していますが、高校時代までは音楽が好きかどうかより、「上手に弾きたい。弾かなければならない」という想いしかなく、しんどくて逃げ出したくなったこともありました。
同じように、母親の情熱からピアノ人生を歩み始めた友人たちが、途中でピアノをやめたり、親子断絶したりする姿を目の当たりにしてきました。
私の場合は幸い、母が自分のお店をオープンして情熱が移ったので、大学時代にようやく、自分の意思で音楽と向き合えるようになったんです。
自分自身で「音楽が好き」と思えたのは、いつ、何がきっかけだったんですか?
「音楽を聴く」楽しさを知ったことだと思います。
幼い頃からクラシック音楽を勉強していましたが、技術向上のための勉強であって、聴くよりも弾くことばかり。聴く楽しみはありませんでした。
大学生になって、洋楽のポップスやロックにはまったり、声楽家の松井智惠さんとの出会いから古楽に親しんだり。
当時、歌手のエンヤやリバーダンス、映画の影響でアイルランド音楽が流行り、日本に押し寄せ一大ジャンルとなっていたケルトや北欧などヨーロッパのワールド音楽をたくさん聴いていました。
幼い頃からクラシック音楽を勉強していましたが、技術向上のための勉強であって、聴くよりも弾くことばかり。聴く楽しみはありませんでした。
大学生になって、洋楽のポップスやロックにはまったり、声楽家の松井智惠さんとの出会いから古楽に親しんだり。
当時、歌手のエンヤやリバーダンス、映画の影響でアイルランド音楽が流行り、日本に押し寄せ一大ジャンルとなっていたケルトや北欧などヨーロッパのワールド音楽をたくさん聴いていました。

さまざまな音楽がある中で、どうしてアイルランド音楽やケルト音楽、北欧の伝承音楽を選ばれたのですか?
日本にもさまざまな音楽がありますが、現代ポップスは恋愛を歌うばかりで、どれも似たように聴こえ、興味を持てませんでした。
一方で、アイルランド音楽やケルト音楽、北欧の伝承音楽は、長い歴史の中で伝えられてきたものだから、その時代に生きた人々のメッセージが込められています。中でも、歌の曲が好きで、聴いていると情景が思い浮かび、心に響いてくるんです。
たとえば、移民による家族との一生の別れを歌ったものや新天地に向けての希望を歌ったもの、戦場に向かう息子の背中を見つめる母の気持ちを歌ったもの、ほかにもグリム童話のように口伝えされてきた物語歌もあります。
詩には日々の出来事や恋愛、戦争の苦しみ、別れ、希望などが綴られ、メロディーには限りない優しさや豊かな詩情に溢れている・・・この美しい曲を演奏したいと思うようになりました。
でも、楽譜通り演奏するクラシック音楽を長年やってきた私にとって、なかなか難しいものでした。というのも、伝承音楽の世界は、その地域で耳伝えされてきた音楽でメロディーしかなく、楽譜がありませんし、アレンジはまるで自由だからです。
クラシックでは暗譜して演奏するというスタイルが一般的ですが、譜面を取っ払って、耳で聴いて奏でるようになると、音楽が自分の中に「自分の音楽」として染み込んでいくのを感じるようになりました。内側から湧き上がってくるものがあって、それを自由に奏でられるようになっていったんです。
「こうあるべき」というものを取っ払って、制約のない世界に飛び込むと、ものすごく楽しい。優れたアーティストの自由な音楽性に刺激を受けて、今では自分で曲をつくるようにもなり、音楽を「つくる楽しさ」を知りました。
一方で、アイルランド音楽やケルト音楽、北欧の伝承音楽は、長い歴史の中で伝えられてきたものだから、その時代に生きた人々のメッセージが込められています。中でも、歌の曲が好きで、聴いていると情景が思い浮かび、心に響いてくるんです。
たとえば、移民による家族との一生の別れを歌ったものや新天地に向けての希望を歌ったもの、戦場に向かう息子の背中を見つめる母の気持ちを歌ったもの、ほかにもグリム童話のように口伝えされてきた物語歌もあります。
詩には日々の出来事や恋愛、戦争の苦しみ、別れ、希望などが綴られ、メロディーには限りない優しさや豊かな詩情に溢れている・・・この美しい曲を演奏したいと思うようになりました。
でも、楽譜通り演奏するクラシック音楽を長年やってきた私にとって、なかなか難しいものでした。というのも、伝承音楽の世界は、その地域で耳伝えされてきた音楽でメロディーしかなく、楽譜がありませんし、アレンジはまるで自由だからです。
クラシックでは暗譜して演奏するというスタイルが一般的ですが、譜面を取っ払って、耳で聴いて奏でるようになると、音楽が自分の中に「自分の音楽」として染み込んでいくのを感じるようになりました。内側から湧き上がってくるものがあって、それを自由に奏でられるようになっていったんです。
「こうあるべき」というものを取っ払って、制約のない世界に飛び込むと、ものすごく楽しい。優れたアーティストの自由な音楽性に刺激を受けて、今では自分で曲をつくるようにもなり、音楽を「つくる楽しさ」を知りました。

つらい時に救ってくれたのは「好きなこと」
「シャナヒー」や「hatao&nami」を結成して、自分が「好き」と思う分野でのお仕事をつくってこられたんですね。
大学卒業後は、自宅や教室でピアノを教えながら、ジャンルを問わず、ホテルや船上での演奏、合唱の伴奏、人権啓発のためのコンサートなど、ご依頼いただいたお仕事を引き受けていました。
自分主体の音楽活動をしたいと、24歳の時にメンバーを集めて「シャナヒー」を結成。こうして自分がやりたい音楽を追求するようになったのが、転機だったのかもしれません。
個人で受けるお仕事の中には、自分がやりたいジャンルではないものもありました。同じ音楽でも、積み重なっていくとストレスを感じるようになっていたんです。自分の好きなことを大切にして生きていきたい。
「好き」を仕事にするのは大変かもしれませんが、多忙であっても充実感があり、ストレスが溜まることもなく、心が元気でいられると思ったからです。自分の音楽以外の依頼をお断りする覚悟を決めました。
結婚して出産すると、さらに時間が限られるので、自分が本当にやりたいことをしなくては、という想いをますます強くしました。在学時から続けてきたピアノ講師を辞めて、演奏活動に注力するようになりました。
その後、新たに「hatao&nami」「シャナヒー&アンニコル」を結成するなど、自分の「好き」「やりたい」ことを、さまざまな形で表現し、それは仕事を超えた仕事・・・人生のライフワークだと感じています。
自分主体の音楽活動をしたいと、24歳の時にメンバーを集めて「シャナヒー」を結成。こうして自分がやりたい音楽を追求するようになったのが、転機だったのかもしれません。
個人で受けるお仕事の中には、自分がやりたいジャンルではないものもありました。同じ音楽でも、積み重なっていくとストレスを感じるようになっていたんです。自分の好きなことを大切にして生きていきたい。
「好き」を仕事にするのは大変かもしれませんが、多忙であっても充実感があり、ストレスが溜まることもなく、心が元気でいられると思ったからです。自分の音楽以外の依頼をお断りする覚悟を決めました。
結婚して出産すると、さらに時間が限られるので、自分が本当にやりたいことをしなくては、という想いをますます強くしました。在学時から続けてきたピアノ講師を辞めて、演奏活動に注力するようになりました。
その後、新たに「hatao&nami」「シャナヒー&アンニコル」を結成するなど、自分の「好き」「やりたい」ことを、さまざまな形で表現し、それは仕事を超えた仕事・・・人生のライフワークだと感じています。

これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
若い頃は「好き」という気持ちで突っ走ることができましたが、年齢を重ねるごとに結婚や妊娠、出産をはじめ、大切な人が病気になる、突然亡くなってしまうなど、いろいろな出来事が起こります。
母が亡くなった時には、「私がやっている音楽はなんて無力なのだろう」と絶望し、音楽なんかやっていても何にもならないという気持ちが大きくなりました。
大きなホールでの大切なコンサートを控えて忙しくする日々の中での母との別れ。
それまでは、良い音楽をすること、音楽家なら何があろうともコンサートを成功させることが一番大事なのだと信じてきましたが、コンサートを終えてみると、永遠の別れという悲しみに比べれば、そんなこと、なんてちっぽけなことだったのだろう・・・コンサートなんてキャンセルすればよかったと激しく後悔していました。
ほどなくして、まるで親子のように仲がよかった祖母も亡くなり、落ち込んでいる時に小学生時代からの親友も亡くなってしまったんです。息をするのもしんどい・・・生きることが、ただただ苦しい時期でした。
そんな私を救ってくれたのも、音楽だったんです。
母が亡くなった時には、「私がやっている音楽はなんて無力なのだろう」と絶望し、音楽なんかやっていても何にもならないという気持ちが大きくなりました。
大きなホールでの大切なコンサートを控えて忙しくする日々の中での母との別れ。
それまでは、良い音楽をすること、音楽家なら何があろうともコンサートを成功させることが一番大事なのだと信じてきましたが、コンサートを終えてみると、永遠の別れという悲しみに比べれば、そんなこと、なんてちっぽけなことだったのだろう・・・コンサートなんてキャンセルすればよかったと激しく後悔していました。
ほどなくして、まるで親子のように仲がよかった祖母も亡くなり、落ち込んでいる時に小学生時代からの親友も亡くなってしまったんです。息をするのもしんどい・・・生きることが、ただただ苦しい時期でした。
そんな私を救ってくれたのも、音楽だったんです。
「音楽が救ってくれた」とは?
「シャナヒー」のセカンドCDをつくっている最中だったので、レコーディングしたり、編集したり、デザインしたりなど制作に没頭すると、その間だけでも、つらさから逃げることができました。そんな日々の積み重ねで、少しずつ少しずつ、気力が湧いていったように思います。
「シャナヒー」のCDジャケットを描いてくださっているテンペラ画家の清嶋素子さんとの出会い、やりとりも大きい。
宗教画を長く描かれてきた清嶋素子さんは、母と同い年であり、母と同時期に癌を患われましたが、絵を描き続けながら克服されました。治療の副作用や手術などいろいろおありになったのですが、やりとりしたお手紙の中に「副作用で手が震えても、 絵を描いている時は震えない。残された生への感性が研ぎ澄まされたし、自分の中で絵を描く喜びが溢れている。病を得てよかったと思うくらいの喜びがあるから、神様に感謝している」というメッセージが。
好きなこと、情熱を注げるものがあるからこそ、すべてを受け入れ、輝いて生きることができるんだと、清嶋さんの生き方や表現を見て感じました。
「シャナヒー」のCDジャケットを描いてくださっているテンペラ画家の清嶋素子さんとの出会い、やりとりも大きい。
宗教画を長く描かれてきた清嶋素子さんは、母と同い年であり、母と同時期に癌を患われましたが、絵を描き続けながら克服されました。治療の副作用や手術などいろいろおありになったのですが、やりとりしたお手紙の中に「副作用で手が震えても、 絵を描いている時は震えない。残された生への感性が研ぎ澄まされたし、自分の中で絵を描く喜びが溢れている。病を得てよかったと思うくらいの喜びがあるから、神様に感謝している」というメッセージが。
好きなこと、情熱を注げるものがあるからこそ、すべてを受け入れ、輝いて生きることができるんだと、清嶋さんの生き方や表現を見て感じました。

「なんとなく」ではなく、信念を持って
「好きなことが生きる支えになる」という実感から、ハープのワークショップを始められたそうですね。
亡くなった親友は、音楽が好きで、亡くなる1カ月前にも私のコンサートに来てくれて、「ハープを弾いてみたい」と話してくれていたんです。
彼女は私と同じ2児の子育て中で、上の子も下の子も同い年くらい。人間関係のトラブルや子育てのしんどさから、うつ病になっていました。
どうして、彼女は亡くなってしまったのかを考える中で、私自身の子育てのしんどさ、つらさも思い出し・・・。でも、私は音楽をしていたから、いろんな人との接点があり、居場所があり、出口もあったから、救われていたのかなと思いました。
自分の人生もしっかりと生きていきたいから音楽の仕事を続ける覚悟はありましたが、日本では女性が仕事をするなら家事も育児もすべてしなければならない現状ですから、とてもしんどくて。
仕事をしているのに「好きなこと=遊び」と思われたり、仕事のためなんだけど、子どもを預ける度に「ごめんね」と子どもにもまわりにも罪悪感を持ってしまったり。
でも、音楽を通して、スウェーデンやノルウェーの精神的に豊かな暮らし、文化、家族や夫婦の在り方を知ると、日本の価値観がすべてではなくて、多様な価値観があるのだと視野が広がりました。
知ったからといって、具体的に何かをしたわけでも、現実が変わるわけでもないのですが、理不尽さに気づけたことで、心持ちが変わったように思うんです。
そういうふうに、好きなことがつらい時に自分を支えてくれる力になるし、人生も豊かにしてくれるから。生きづらい世の中で、すべての人が、好きなことや好きな人を大切にし、幸せに生きていけたらいいなあ、と。
親友のようにハープを弾いてみたい、音楽を楽しみたいという人の力になれればと、ハープのワークショップを始める決心をしたんです。
実は「シャナヒー&アンニコル」という女性ばかりのユニットを結成するきっかけになったのも、いろいろなことを抱えながらがんばっているメンバー一人ひとりが「存分に輝ける場所=舞台」をつくりたいという想いからでした。
彼女は私と同じ2児の子育て中で、上の子も下の子も同い年くらい。人間関係のトラブルや子育てのしんどさから、うつ病になっていました。
どうして、彼女は亡くなってしまったのかを考える中で、私自身の子育てのしんどさ、つらさも思い出し・・・。でも、私は音楽をしていたから、いろんな人との接点があり、居場所があり、出口もあったから、救われていたのかなと思いました。
自分の人生もしっかりと生きていきたいから音楽の仕事を続ける覚悟はありましたが、日本では女性が仕事をするなら家事も育児もすべてしなければならない現状ですから、とてもしんどくて。
仕事をしているのに「好きなこと=遊び」と思われたり、仕事のためなんだけど、子どもを預ける度に「ごめんね」と子どもにもまわりにも罪悪感を持ってしまったり。
でも、音楽を通して、スウェーデンやノルウェーの精神的に豊かな暮らし、文化、家族や夫婦の在り方を知ると、日本の価値観がすべてではなくて、多様な価値観があるのだと視野が広がりました。
知ったからといって、具体的に何かをしたわけでも、現実が変わるわけでもないのですが、理不尽さに気づけたことで、心持ちが変わったように思うんです。
そういうふうに、好きなことがつらい時に自分を支えてくれる力になるし、人生も豊かにしてくれるから。生きづらい世の中で、すべての人が、好きなことや好きな人を大切にし、幸せに生きていけたらいいなあ、と。
親友のようにハープを弾いてみたい、音楽を楽しみたいという人の力になれればと、ハープのワークショップを始める決心をしたんです。
実は「シャナヒー&アンニコル」という女性ばかりのユニットを結成するきっかけになったのも、いろいろなことを抱えながらがんばっているメンバー一人ひとりが「存分に輝ける場所=舞台」をつくりたいという想いからでした。

自分が好きなことを見つけることも、その好きなことを続けるのも、難しいものだと思います。その「好き」を見失わず、大切にできる秘訣は何ですか?
「なんとなく」では行動しないことです。迷っているうちはまだダメで、「これだ!」というものが見つかった時にちゃんと行動するようにしています。
たとえば、買い物をする時でも、「なんとなく、好きだから」では買いません。「こういうものが必要」というイメージを描いて、アンテナをはる・・・。そうすることで、「これだ!」というものと出会え、その必要な物を買います。
仕事においてもそう。「人に言われたから」「仕事として金銭面でいいから」などに左右されることなく、自分が本当にやりたいかどうか・・・。そうした一つひとつの選択の積み重ねが大事です。
たとえば、買い物をする時でも、「なんとなく、好きだから」では買いません。「こういうものが必要」というイメージを描いて、アンテナをはる・・・。そうすることで、「これだ!」というものと出会え、その必要な物を買います。
仕事においてもそう。「人に言われたから」「仕事として金銭面でいいから」などに左右されることなく、自分が本当にやりたいかどうか・・・。そうした一つひとつの選択の積み重ねが大事です。
演奏も、作曲も、プロデュースもされる上原さんが、音楽を通して表現したいこととは何でしょうか?
理想としている音楽があります。
大学時代に古楽に興味を持つきっかけとなった声楽家の松井さんの伴奏を務めていた頃、彼女の音楽を聴いて、「音楽の中に神様がいる」と思う瞬間があったんです。
「神様がいる」というのは、音楽を聴いた瞬間に景色が変わって、自分の過去に閉ざされていたものが開いて、涙がわあぁっと出る、感動する・・・という感じ。
日常の中では劇的なドラマはないかもしれないけれど、音楽を通して非日常的な時間を持つことで、心が浄化されるんだと思いました。
そういう音楽を聴いて私も感動したいし、表現できるようにもなりたいんです。
大学時代に古楽に興味を持つきっかけとなった声楽家の松井さんの伴奏を務めていた頃、彼女の音楽を聴いて、「音楽の中に神様がいる」と思う瞬間があったんです。
「神様がいる」というのは、音楽を聴いた瞬間に景色が変わって、自分の過去に閉ざされていたものが開いて、涙がわあぁっと出る、感動する・・・という感じ。
日常の中では劇的なドラマはないかもしれないけれど、音楽を通して非日常的な時間を持つことで、心が浄化されるんだと思いました。
そういう音楽を聴いて私も感動したいし、表現できるようにもなりたいんです。

上原 奈未さん
5歳からピアノを習い始める。大学までクラシック音楽を学んだ後、古楽やワールド音楽からアイルランドや北欧の伝承音楽に傾倒。神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻を卒業後、ピアノ講師を務めながらフリーの音楽家として活動する。1998年に「シャナヒー」、2011年に 「hatao&nami」、2016年に「シャナヒー&アンニコル」を結成し、各地で演奏活動を行う。担当はピアノやハープ、足踏みオルガン。自身のCDでは、作曲やレコーディング、ジャケットのデザイン、時には絵も描く。そのほか、さまざまなコマーシャルやゲーム、アーティストのCDなどの 音源制作も手掛けている。
HP: http://namiuehara.com
Blog: http://diary.namiuehara.com/
シャナヒー HP: http://shanachie.jp/
シャナヒー&アンニコル HP: http://shanachie.jp/annikor.html
hatao&name HP: http://hataonami.com
(取材:2018年3月)
「好きなこと」を見つけるのも難しいですが、見つけられても、持続することは並大抵ではありません。自分を取り巻く環境や状況は変化し続けますし、そんな中で想いを持ち続けることは難しく、見失ってしまうこともあるのではないでしょうか。
上原さんは、日常の一つひとつから、「なんとなく」ではなくて、「これが好き」「これがやりたいこと」と明確な意志を持ち、それに必要なアクションを起こし続けてこられました。
そのために、断らなければならないことがあったり、ぐっと堪えなければならないことがあったりもされたでしょうが、貫かれたからこそ、どんどん想いを純化されていて、「自分が大切にしたいことを大切にできる」今につながっているのだと感じます。
HP:『えんを描く』
上原さんは、日常の一つひとつから、「なんとなく」ではなくて、「これが好き」「これがやりたいこと」と明確な意志を持ち、それに必要なアクションを起こし続けてこられました。
そのために、断らなければならないことがあったり、ぐっと堪えなければならないことがあったりもされたでしょうが、貫かれたからこそ、どんどん想いを純化されていて、「自分が大切にしたいことを大切にできる」今につながっているのだと感じます。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。