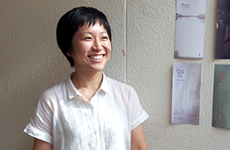HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() イマニシユカさん(シンガーソングライター)
イマニシユカさん(シンガーソングライター) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
イマニシユカさん(シンガーソングライター)

誰しもの中にいる「小さな子ども」が喜ぶ歌を
イマニシユカさん
シンガーソングライター
シンガーソングライター
空想の夜の町で繰り広げられる出来事、風に乗って旅をしている目には見えない「小さいもの」の秘密など自身で作詞・作曲した歌を歌う、シンガーソングライターのイマニシユカさん。聴いていると、まるで絵本を1枚1枚めくって読んでいるような、小さな世界に入り込んだような、ドキドキ、わくわくする気持ちになります。
イマニシさんは活動を始めた当初を「愛情の渇望や死への恐怖、悲しみ、苦しみ、辛さなど、自分の中にいる『小さな子ども』が言いたかったことを吐き出す音楽だった」と振り返りますが、だんだんと「誰しもの中にいる『小さな子ども』がドキドキ、わくわくする音楽をつくりたい」と心境が変化していったそうです。
心境が変化したきっかけとは? そもそも、イマニシさんが言う「誰しもの中にいる『小さな子ども』」とは、どんな存在でしょうか。
イマニシさんは活動を始めた当初を「愛情の渇望や死への恐怖、悲しみ、苦しみ、辛さなど、自分の中にいる『小さな子ども』が言いたかったことを吐き出す音楽だった」と振り返りますが、だんだんと「誰しもの中にいる『小さな子ども』がドキドキ、わくわくする音楽をつくりたい」と心境が変化していったそうです。
心境が変化したきっかけとは? そもそも、イマニシさんが言う「誰しもの中にいる『小さな子ども』」とは、どんな存在でしょうか。
夢が「歌手」から「シンガーソングライター」へ
子どもの頃から「歌手」をめざしていたそうですね。
よく歌う子どもでした。
テレビ番組の「NHK みんなのうた」や音楽のカセットテープに合わせて歌ったり、メロディー調で絵本を読む母を真似て絵本に出てくる言葉に節を付けて歌ったり、小さなおもちゃのピアノでアニメの主題歌をなぞって弾いて歌ったり。
歌っている時、父と母が褒めてくれたことがとても嬉しかった記憶があります。
幼稚園の頃からピアノを習わせてもらい、短大時代にレストランで弾き語りのアルバイトを始めると、ボイストレーニングに通うようになりました。20歳の少し前までは「シンガーソングライター」ではなく、「歌手」をめざしていたんです。
テレビ番組の「NHK みんなのうた」や音楽のカセットテープに合わせて歌ったり、メロディー調で絵本を読む母を真似て絵本に出てくる言葉に節を付けて歌ったり、小さなおもちゃのピアノでアニメの主題歌をなぞって弾いて歌ったり。
歌っている時、父と母が褒めてくれたことがとても嬉しかった記憶があります。
幼稚園の頃からピアノを習わせてもらい、短大時代にレストランで弾き語りのアルバイトを始めると、ボイストレーニングに通うようになりました。20歳の少し前までは「シンガーソングライター」ではなく、「歌手」をめざしていたんです。
「歌手」から「シンガーソングライター」に変わったのは?
短大時代に、他大学との合同の軽音サークルに所属したことがきっかけです。バンドでオリジナル曲をつくってみようという話になり、歌詞を担当することになりました。
歌詞づくりは初めてでしたが、中学校・高校時代に詩を書いていたので、するするっと書くことができました。そのうち、ポツポツと作詞の段階から言葉にメロディーが付いてくるようになって、作曲も手がけるようになったんです。
幼い頃におもちゃのピアノで、自由に弾いて歌っていたことを思い出すような出来事だったかもしれません。子どもの頃からの夢である「歌手」、幼稚園の頃から習っていた「ピアノ」、思春期に衝動的に書き綴っていた「詩」、自分の中でバラバラだった要素が結びついた瞬間でした。
さらには曲をライブで発表すると、聴いてくださった方々が共鳴してくださり、自分で曲をつくって歌うことの素晴らしさを知ったから、自分で作詞・作曲して歌う「シンガーソングライター」になろうと決めたんです。
歌詞づくりは初めてでしたが、中学校・高校時代に詩を書いていたので、するするっと書くことができました。そのうち、ポツポツと作詞の段階から言葉にメロディーが付いてくるようになって、作曲も手がけるようになったんです。
幼い頃におもちゃのピアノで、自由に弾いて歌っていたことを思い出すような出来事だったかもしれません。子どもの頃からの夢である「歌手」、幼稚園の頃から習っていた「ピアノ」、思春期に衝動的に書き綴っていた「詩」、自分の中でバラバラだった要素が結びついた瞬間でした。
さらには曲をライブで発表すると、聴いてくださった方々が共鳴してくださり、自分で曲をつくって歌うことの素晴らしさを知ったから、自分で作詞・作曲して歌う「シンガーソングライター」になろうと決めたんです。

「音楽をやめる」という選択肢はない
当初はバンドとして活動されていたんですね。ソロになるきっかけは何だったのですか?
バンド結成から約4年後、メンバーそれぞれが別々の道で生きていくことになり、2008年に活動休止しました。これが私にとって、大きな転機となります。ここから4年ほどさまようことになり、一番しんどい時期になるからです。
自分1人の力で音楽を届ける自信を持てなかったから、バンドメンバーを募集したものの、「この人だ!」という人に巡り合えない。
「そもそも私は音楽で何を表現したいんだろう」「やりたい音楽も見つからないのに、何をしているんだろうか」と自問するけれど、答えが見つからない。
曲も思い浮かばない。曲がつくれても、自分がつくりたかったものなのか、自信を持てない。発表する機会もない。
どんどん迷宮に入り込んでいくような感じがしました。
自分1人の力で音楽を届ける自信を持てなかったから、バンドメンバーを募集したものの、「この人だ!」という人に巡り合えない。
「そもそも私は音楽で何を表現したいんだろう」「やりたい音楽も見つからないのに、何をしているんだろうか」と自問するけれど、答えが見つからない。
曲も思い浮かばない。曲がつくれても、自分がつくりたかったものなのか、自信を持てない。発表する機会もない。
どんどん迷宮に入り込んでいくような感じがしました。
どのようにして乗り越えられたのですか?
「運を天に任せる」ことにしました。
無理して曲をつくろうとしない、つくりたくなる時を待つ。もちろん、「このまま一生何も思い浮かばないかもしれない」という思いに襲われることもありましたが、そんな時は散歩したり、景色を眺めたり、美術館に行ったりして気分転換して、必要以上に考えないように努めました。
ある種、楽天的にいられたのは、私の中に「音楽をやめる」という選択肢がなかったからかもしれません。
就職、結婚、育児など人生の節目で「音楽をやめる」という選択をされる方もいますが、私にはその「音楽をやめる」という感覚がわからなくて。私は「おばあちゃんになっても歌っていたい」と、生きる中で音楽がずっとあればいいという想いだから、「音楽をやめる」という感覚がない。
いつかきっと曲をつくりたくなる時が来るだろう。もし私の音楽を必要としてくれる人がいたら、発表の機会に恵まれるだろう。「運を天に任せる」気持ちでいながらも、細くてもいいから音楽の世界とはつながり続けました。
作詞・作曲やライブなど積極的な音楽活動はしなくても、友人のライブに行ったり、お誘いがあれば他のバンドに参加したりなど、細い糸でもいいからつながりを断たないようにしていたんです。
そうする中で、さまざまなミュージシャンと出会い、それぞれの音楽に対する想いを聞いたり、人生に触れたり、協力できる関係性が出来たり、「また曲を書きなよ」という励ましの声も受けたりして、「自分の音楽」というものが固まってきたように思います。
2012年頃からソロでの活動を徐々に始め、今では少しずつ自分が望むペースで音楽活動ができるようになってきました。
無理して曲をつくろうとしない、つくりたくなる時を待つ。もちろん、「このまま一生何も思い浮かばないかもしれない」という思いに襲われることもありましたが、そんな時は散歩したり、景色を眺めたり、美術館に行ったりして気分転換して、必要以上に考えないように努めました。
ある種、楽天的にいられたのは、私の中に「音楽をやめる」という選択肢がなかったからかもしれません。
就職、結婚、育児など人生の節目で「音楽をやめる」という選択をされる方もいますが、私にはその「音楽をやめる」という感覚がわからなくて。私は「おばあちゃんになっても歌っていたい」と、生きる中で音楽がずっとあればいいという想いだから、「音楽をやめる」という感覚がない。
いつかきっと曲をつくりたくなる時が来るだろう。もし私の音楽を必要としてくれる人がいたら、発表の機会に恵まれるだろう。「運を天に任せる」気持ちでいながらも、細くてもいいから音楽の世界とはつながり続けました。
作詞・作曲やライブなど積極的な音楽活動はしなくても、友人のライブに行ったり、お誘いがあれば他のバンドに参加したりなど、細い糸でもいいからつながりを断たないようにしていたんです。
そうする中で、さまざまなミュージシャンと出会い、それぞれの音楽に対する想いを聞いたり、人生に触れたり、協力できる関係性が出来たり、「また曲を書きなよ」という励ましの声も受けたりして、「自分の音楽」というものが固まってきたように思います。
2012年頃からソロでの活動を徐々に始め、今では少しずつ自分が望むペースで音楽活動ができるようになってきました。

自分の中にいる「小さな子ども」が喜ぶ歌を
イマニシさんが見つけた「自分の音楽」とは?
バンド時代は「悲しい気持ち」を起源とした暗めのポップスロックでした。
今振り返ると、歌詞も曲も、中学校・高校時代に書いていた詩の延長線上で、思春期ならではの鬱屈したもの、家庭環境から感じ取ったものを源にして、愛情の渇望や死への恐怖、悲しみ、苦しみ、辛さなど、自分の中にいる「小さな子ども」が言いたかったことを吐き出す音楽だったと思います。
共鳴することで癒えていく感情もあります。当時は、その衝動的な感情の放出が自己表現でした。
ただ、続けているうちに、音楽ってまるで波紋みたいに空気の振動で伝わっていくものだから、光みたいなものが、私の音楽にあればいいのにという想いが芽生えていました。私自身が少しずつ、音楽によって心癒されていたからこそ、思えたことかもしれません。
かつて「悲しい」「辛い」と叫んでいた自分の中にいる「小さな子ども」が喜ぶような、そんな曲をつくりたいと思ったんです。
今振り返ると、歌詞も曲も、中学校・高校時代に書いていた詩の延長線上で、思春期ならではの鬱屈したもの、家庭環境から感じ取ったものを源にして、愛情の渇望や死への恐怖、悲しみ、苦しみ、辛さなど、自分の中にいる「小さな子ども」が言いたかったことを吐き出す音楽だったと思います。
共鳴することで癒えていく感情もあります。当時は、その衝動的な感情の放出が自己表現でした。
ただ、続けているうちに、音楽ってまるで波紋みたいに空気の振動で伝わっていくものだから、光みたいなものが、私の音楽にあればいいのにという想いが芽生えていました。私自身が少しずつ、音楽によって心癒されていたからこそ、思えたことかもしれません。
かつて「悲しい」「辛い」と叫んでいた自分の中にいる「小さな子ども」が喜ぶような、そんな曲をつくりたいと思ったんです。
具体的にどんな曲をつくっていますか?
夜に空を眺めたり、自然に触れたり、自転車を漕いだり、美術館で絵を見たりする中で広がった空想の世界だったり、見えないものの世界だったり。自分の中にいる「小さな子ども」が「うわぁ」とドキドキ、わくわくしたことを曲にしています。
たとえば、「夜の町」シリーズは、画家のパウル・クレーの「魔法劇場」という絵を見て広がった世界を描いています。
化け物のような異形の者たちが楽器を持って佇んでいるその絵を見た瞬間、「これ、好き」とドキンとして、私の中で世界がわあぁっと広がっていきました。気づいたら、その町に立っていたんです。
その町で私は、住人たちにとってはいないのも同じ存在で、気ままに散歩させてもらっています。町で見かけたものや出来事を歌として描写している感じです。
ある夜、空を眺めていて、ふいに何か白く小さなものがたくさんたくさん連なって、ふわふわと横切っていくのが見えたような気がしました。「彼らはなんなのだろう?」「すごくかわいらしいものだったら楽しいな」という気持ちから生まれた歌が「小さなものたち」です。
彼らはなんの気なしに旅をしていて、あるところでギュッと固まって「名前」という呪文をかけると、私たちの目の前にある物になっているのではないかしら。それはもう、「世界の秘密を見つけてしまった」という気持ちで表現しました。
たとえば、「夜の町」シリーズは、画家のパウル・クレーの「魔法劇場」という絵を見て広がった世界を描いています。
化け物のような異形の者たちが楽器を持って佇んでいるその絵を見た瞬間、「これ、好き」とドキンとして、私の中で世界がわあぁっと広がっていきました。気づいたら、その町に立っていたんです。
その町で私は、住人たちにとってはいないのも同じ存在で、気ままに散歩させてもらっています。町で見かけたものや出来事を歌として描写している感じです。
ある夜、空を眺めていて、ふいに何か白く小さなものがたくさんたくさん連なって、ふわふわと横切っていくのが見えたような気がしました。「彼らはなんなのだろう?」「すごくかわいらしいものだったら楽しいな」という気持ちから生まれた歌が「小さなものたち」です。
彼らはなんの気なしに旅をしていて、あるところでギュッと固まって「名前」という呪文をかけると、私たちの目の前にある物になっているのではないかしら。それはもう、「世界の秘密を見つけてしまった」という気持ちで表現しました。
イマニシさんの曲を聴いていると、「そういえば、私も子どもの頃」と思い出します。その感性を持ち続けられるのはなぜですか?
感性を持ち続けるために意識していることは特にありませんが、自分がドキドキ、わくわくしていないと曲をつくることはできません。だから、自然と自分が好きなことをする時間を持つことを大切にしています。
何より、子どもの頃から想像することが大好きなんです。
魔法使いが魔法をかけたり、お月さまを取っちゃったり、動物がしゃべったり、王様がゾウの大きなたまごを探して旅したりする絵本、「NHK みんなのうた」のような一曲完結型の小さな世界に、ドキドキ、わくわくしていました。
お月さまがあって、星がきらめいて、その上に宇宙が透けて見える気がする「夜」という時間が大好きで、夜空を見上げていると、ベッドはまるで「明日に向かう船」に思えました。
そういうドキドキ、わくわくしたことって、細胞の小さな一粒にでも残っていると思うんです。
大人になるにつれて、その細胞は分裂してどんどん小さくなっていくんですが、自分の中にひとかけらでもあるものだから、自分の心の窓がこちら側にあいている時に風が吹いたら、ふいに蘇るものだと思うんです。
今、私が曲にしていることは、ひらめきと言うよりも、幼い頃にドキドキ、わくわくしたことが、経験の中で形を変えて返ってきているのかなって。
先ほどの「小さなものたち」も、小学校の理科の授業で原子を学んだ時に「目に見えるものは小さな粒々がぎゅっと集まってできている」と聞いて感動したことと、つながったんだと思うんです。
何より、子どもの頃から想像することが大好きなんです。
魔法使いが魔法をかけたり、お月さまを取っちゃったり、動物がしゃべったり、王様がゾウの大きなたまごを探して旅したりする絵本、「NHK みんなのうた」のような一曲完結型の小さな世界に、ドキドキ、わくわくしていました。
お月さまがあって、星がきらめいて、その上に宇宙が透けて見える気がする「夜」という時間が大好きで、夜空を見上げていると、ベッドはまるで「明日に向かう船」に思えました。
そういうドキドキ、わくわくしたことって、細胞の小さな一粒にでも残っていると思うんです。
大人になるにつれて、その細胞は分裂してどんどん小さくなっていくんですが、自分の中にひとかけらでもあるものだから、自分の心の窓がこちら側にあいている時に風が吹いたら、ふいに蘇るものだと思うんです。
今、私が曲にしていることは、ひらめきと言うよりも、幼い頃にドキドキ、わくわくしたことが、経験の中で形を変えて返ってきているのかなって。
先ほどの「小さなものたち」も、小学校の理科の授業で原子を学んだ時に「目に見えるものは小さな粒々がぎゅっと集まってできている」と聞いて感動したことと、つながったんだと思うんです。

音楽を通して、魔法をかける
お話の中で何度か登場する、誰しもの心の中にいる「小さな子ども」。その「小さな子ども」がわくわくすることがなぜ大事だと思うのですか?
「小さな子ども」の声が聴こえると、「本当はこうしたいんだよ」という本当の自分の気持ちが見えてくるのではないかなあと思うんです。それによって心が楽になれる人もいるのではないかなあって、私がそうだったから。
以前、私は「小さな子ども」を大事にできていませんでした。
バンド時代に自分の中にいる「小さな子ども」が言いたかったことを表現の軸にしていたのは、ずっと押さえ込んでいた時期があるからだと思うんです。
「本当はこう思うけど、まわりの人たちはこう言っているから」「本当はこうしたいけど、多数決で多いから」「本当はこうだけど、相手が望むなら自分はこうでないといけない」など、「本当は」という気持ちを知っている「小さな子ども」を「今は静かにしていて」と言い聞かせてきました。
それが音楽と一緒に生きていく中で、いろんな人たちの考え方や生き方に触れたり、「小さな子ども」の叫びを歌ったりするうち、ちょっとずつ変わってきたように思うんです。
「自分がやりたい」と思うことを抑え込むことを、一体誰のためにしているんだろう。自分が我慢してでも、誰かが喜ぶことを優先することがいいんだろうか。
なんか違うなあ、悲しいなあという「小さな子ども」の声に気づいて、「自分の人生。誰がどう言おうと、今の自分の心が正しいと思うこと、やりたいと思うことを正直にやっていこう」とちょっとずつ心を強く持てるようになっていきました。
「これだ」という言葉が並んだ歌詞はまるで呪文みたいで、1曲の間ずっと魔法が効いているような時間になるから。誰しもの中にいる「小さな子ども」をドキドキ、わくわくさせることで、「本当は」ということを思い出し、自分自身と向き合える時間をつくることができたらいいなあと思っています。
以前、私は「小さな子ども」を大事にできていませんでした。
バンド時代に自分の中にいる「小さな子ども」が言いたかったことを表現の軸にしていたのは、ずっと押さえ込んでいた時期があるからだと思うんです。
「本当はこう思うけど、まわりの人たちはこう言っているから」「本当はこうしたいけど、多数決で多いから」「本当はこうだけど、相手が望むなら自分はこうでないといけない」など、「本当は」という気持ちを知っている「小さな子ども」を「今は静かにしていて」と言い聞かせてきました。
それが音楽と一緒に生きていく中で、いろんな人たちの考え方や生き方に触れたり、「小さな子ども」の叫びを歌ったりするうち、ちょっとずつ変わってきたように思うんです。
「自分がやりたい」と思うことを抑え込むことを、一体誰のためにしているんだろう。自分が我慢してでも、誰かが喜ぶことを優先することがいいんだろうか。
なんか違うなあ、悲しいなあという「小さな子ども」の声に気づいて、「自分の人生。誰がどう言おうと、今の自分の心が正しいと思うこと、やりたいと思うことを正直にやっていこう」とちょっとずつ心を強く持てるようになっていきました。
「これだ」という言葉が並んだ歌詞はまるで呪文みたいで、1曲の間ずっと魔法が効いているような時間になるから。誰しもの中にいる「小さな子ども」をドキドキ、わくわくさせることで、「本当は」ということを思い出し、自分自身と向き合える時間をつくることができたらいいなあと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
「ことばの力」を大切にされているフリーアナウンサーの方と出会い、彼女の朗読を聞きました。
「人魚姫」の朗読では、海の中などその情景が思い浮かぶような表現をされていて、話す言葉の一つひとつにエネルギーが宿っているのを感じたんです。詩そのものにも力があるということを再認識する出来事でした。
「ことばの力」というところも掘り下げてみたいとの想いが膨らんで、彼女から学んでいるところです。いずれは、制作した物語の朗読を行うなど、表現の幅をひろげていきたいと考えています。
「人魚姫」の朗読では、海の中などその情景が思い浮かぶような表現をされていて、話す言葉の一つひとつにエネルギーが宿っているのを感じたんです。詩そのものにも力があるということを再認識する出来事でした。
「ことばの力」というところも掘り下げてみたいとの想いが膨らんで、彼女から学んでいるところです。いずれは、制作した物語の朗読を行うなど、表現の幅をひろげていきたいと考えています。
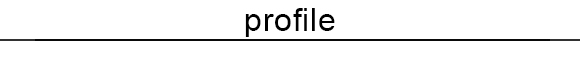
イマニシユカさん
20歳の時に1カ月ほど渡米し、ブロードウェイで活躍していたミュージカル女優に師事。帰国後に結成したバンド「CROSSHOUR」では、ボーカルを務めるとともに作詞・作曲を担当し、2枚のアルバム制作と全国4都市ツアーを行った。バンド解散後、よりシンプルに自らの世界を表現したいとの想いからソロ活動を開始。さまざまなミュージシャンとともに、民族楽器を気まぐれに取り入れたスタイルで、カフェ等を中心にライブを開催。書道家や陶芸家といった他分野のアーティストとのコラボレーションのほか、短編映画や朗読劇、お店のテーマソングを手掛けることもある。2014年にアルバム「ナハトムジーク」発売。受賞歴として「岡山国際芸術祭 エンターテイメントチャレンジ審査員特別賞」(2016年)がある。
HP: http://yukalotusnight.wixsite.com/imanishiyuka
FB: YukaLotusNight
撮影場所協力:カフェ サルンポヮク イマニシさんがライブを開催したり、アルバムを店頭販売したりしているお店。お店のテーマソングをイマニシさんがつくったこともある。
http://www.geocities.jp/salunpowaku/
(取材:2018年12月)
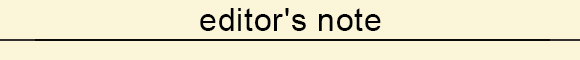
そうやってドキドキ、わくわくしていたことを一つひとつ思い出すうち、「こんなことが好きだったなあ」「こんなことをしたいと思っていたなあ」と自分が好きだったことややりたかったこととつながっていき、日常の中では押さえ込んでいる自分が、ひょこっと顔を出すという体験をしました。
年齢や経験を重ねるとともに、「こうしなければならない」「こんなことをしたら変」「こんな役割が求められている」といった他人の目を気にしたり、世間一般論を意識したりして、いつのまにか自分の気持ちを押さえつけ、がんじがらめになっていることがあります。
「『自分がやりたい』と思うことを抑え込むことを、一体誰のためにしているんだろう」とイマニシさんが思われたように、「なんで?」「どうして?」と自分と向き合うことで、ほぐれていく、自由になっていくものがあると思います。
それが、イマニシさんの言う「自分の中にいる『小さな子ども』」が喜ぶことで、楽になる」ということなんだろうなあと思いました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。