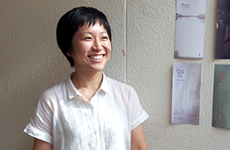HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() 荻山 泊水さん(薩摩琵琶奏者)
荻山 泊水さん(薩摩琵琶奏者) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
荻山 泊水さん(薩摩琵琶奏者)

過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く
荻山 泊水さん
薩摩琵琶奏者
薩摩琵琶奏者
琵琶の伴奏に合わせて物語を節に乗せて歌う、伝統芸能「薩摩琵琶」。プロの奏者として活躍する荻山泊水さんが薩摩琵琶を始めるきっかけは、たまたま観ていたテレビ番組で琵琶を演奏する様子を観て「かっこいい!」と一目惚れしたことでした。
当初は趣味のつもりで習い始めたそうですが、琵琶の奥深さに魅了されるうち、プロの奏者として活動されるように。現在では伝統芸能を受け継ぐ1人として次代につなぐために奮闘されています。
「伝統芸能は先人から受け継いだ芸を次代に渡す役割が求められます。なので、琵琶を『自己表現のツール』としてのみ使いたい場合にはこの仕事は向きません。逆に、過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置いてみたいのなら天職になり得ます」と荻山さん。
その言葉の奥には、どういった想いや覚悟があるのでしょうか。
当初は趣味のつもりで習い始めたそうですが、琵琶の奥深さに魅了されるうち、プロの奏者として活動されるように。現在では伝統芸能を受け継ぐ1人として次代につなぐために奮闘されています。
「伝統芸能は先人から受け継いだ芸を次代に渡す役割が求められます。なので、琵琶を『自己表現のツール』としてのみ使いたい場合にはこの仕事は向きません。逆に、過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置いてみたいのなら天職になり得ます」と荻山さん。
その言葉の奥には、どういった想いや覚悟があるのでしょうか。
「かっこいい!」と一目惚れから、伝統芸能の世界へ
「薩摩琵琶奏者」をめざすきっかけは?
たまたま観たテレビ番組で、樹木希林さんが黒塗りの琵琶を弾いておられる姿に「かっこいい!」と一目惚れ。そして後日、別のテレビ番組で薩摩琵琶奏者が弾き語りする姿を観て、「自分もやってみたい」と思ったんです。
薩摩琵琶は琵琶の伴奏に合わせて物語を節に乗せて歌う、いわゆる「語り芸」。学生時代に演劇をやっていたこともあり、「語り」に興味を持っていましたから、このような語りの世界があるのだと興味が湧きました。
日本の琵琶には楽琵琶、平家琵琶、盲僧琵琶、筑前琵琶、薩摩琵琶と5種類あるのですが、九州・薩摩国で考案され、武士を中心に伝承されてきた「薩摩琵琶」の持つ勇壮でドラマチックな世界観に魅かれたんです。
当時は落語家である夫の個人事務所の事務仕事をしながら学習塾でアルバイトするという2足の草鞋を履いていましたから、あくまで趣味のつもりで習い始めました。
薩摩琵琶は琵琶の伴奏に合わせて物語を節に乗せて歌う、いわゆる「語り芸」。学生時代に演劇をやっていたこともあり、「語り」に興味を持っていましたから、このような語りの世界があるのだと興味が湧きました。
日本の琵琶には楽琵琶、平家琵琶、盲僧琵琶、筑前琵琶、薩摩琵琶と5種類あるのですが、九州・薩摩国で考案され、武士を中心に伝承されてきた「薩摩琵琶」の持つ勇壮でドラマチックな世界観に魅かれたんです。
当時は落語家である夫の個人事務所の事務仕事をしながら学習塾でアルバイトするという2足の草鞋を履いていましたから、あくまで趣味のつもりで習い始めました。
趣味のつもりがプロの奏者へ。どんな心境の変化がありましたか?
全国で琵琶奏者数が1000人を切ったと言われるなど、後継者が減少しています。もしかしたら、私が生きている間にも廃れてしまうのではないか、何とかこの芸能を後世に残したいと考えるようになったんです。
薩摩琵琶は伝統芸能ですから、先人から受け継いだ芸を次代に渡す役割が求められます。自分だけで完結すればいいというものではなく、過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置くということなんだと思うようになりました。
たとえば、私が所属する錦心流は明治の終わり頃に永田錦心という人物が興した流派。永田錦心から受け継いだ人たちが型を守りながらも、それぞれの時代に即して変化させながら次代へとつないできたから現在があり、私が今こうして薩摩琵琶と出会い、受け継ぐことができています。
そんな壮大な流れの中にいる1人として、草の根運動でもいいから、薩摩琵琶を知ってもらう活動をしたいと2013年から自主的な演奏活動を始めました。
学習塾でのアルバイトを辞めて時間を捻出し、雑貨店や喫茶店等でのライブを企画して開催したり、学校や福祉施設などに訪問して演奏したり、所属団体の演奏会以外にも活動の機会を増やしてきたんです。
薩摩琵琶は伝統芸能ですから、先人から受け継いだ芸を次代に渡す役割が求められます。自分だけで完結すればいいというものではなく、過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置くということなんだと思うようになりました。
たとえば、私が所属する錦心流は明治の終わり頃に永田錦心という人物が興した流派。永田錦心から受け継いだ人たちが型を守りながらも、それぞれの時代に即して変化させながら次代へとつないできたから現在があり、私が今こうして薩摩琵琶と出会い、受け継ぐことができています。
そんな壮大な流れの中にいる1人として、草の根運動でもいいから、薩摩琵琶を知ってもらう活動をしたいと2013年から自主的な演奏活動を始めました。
学習塾でのアルバイトを辞めて時間を捻出し、雑貨店や喫茶店等でのライブを企画して開催したり、学校や福祉施設などに訪問して演奏したり、所属団体の演奏会以外にも活動の機会を増やしてきたんです。

自分に「ない」ものではなく、「ある」ものを強みに変えて
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
習い始めたのは30歳の時で、奏者としてはかなり遅いスタートだったことは否めません。幼稚園から大学までエレクトーンを習っていましたが、音楽の世界で通用するほどの腕前には達せず、さらに邦楽の素養はまったくありませんでした。
なので、身体能力や音感、表現技術など、幼少時より伝統芸能や西洋音楽に深く携わってきた同世代の方々との差を痛感させられることが多々ありました。
たとえば、民謡や詩吟をされていた人は声からして全然違います。声が美しいし、節回しも上手。西洋音楽をされていた人は鮮やかな弾法で琵琶の音色を聴かせるのが素晴らしい。「大嵐の中、平家の亡霊が現れる」というシーンを琵琶の音色だけで「本当に嵐が来た」と思わせる表現力には憧れます。
「この人らには一生追いつかれへん」と壁を感じました。
なので、身体能力や音感、表現技術など、幼少時より伝統芸能や西洋音楽に深く携わってきた同世代の方々との差を痛感させられることが多々ありました。
たとえば、民謡や詩吟をされていた人は声からして全然違います。声が美しいし、節回しも上手。西洋音楽をされていた人は鮮やかな弾法で琵琶の音色を聴かせるのが素晴らしい。「大嵐の中、平家の亡霊が現れる」というシーンを琵琶の音色だけで「本当に嵐が来た」と思わせる表現力には憧れます。
「この人らには一生追いつかれへん」と壁を感じました。
その「壁」または「悩み」をどのように乗り越えられましたか?
焦る気持ちはありましたが、子どもの頃に剣道を習っていて、型が身に染み込まないと応用が効かないと知っていたので、まずは基礎を身に付けることに心を注ぎました。
5年ほど経ってもう一段ステップアップしようと思った時、「ほかの人になくて私だからこそのものは何か」を考えました。
そんなふうに考えられたのは「できなくてもできるようになるまで頑張ればいい」と辛抱強く見守ってくれる師匠の存在と、そもそも琵琶の世界は優劣があるのではなく、みんな違ってみんないいの世界。
誰かと比べる必要もないので、「私にも何かちょっとはええところがあるんちゃうん?」と自分の伸びしろを信じてみようと思えたんです。
そこで、学生時代の演劇経験を自分の強みにすることにしました。実際に物語を読み解いて情景や心情を深く掘り下げる方法や滑舌の訓練が役立っています。
ただ演劇は自分の内面や感情を発露する芸術ですが、薩摩琵琶は物語の筋や情景、登場人物の心情を「伝える」もの。基本的に表情を変えたり動作を入れたりしません。声や音色の調子や強弱、速さによってのみ表現し、ただただ一点を見つめて弾き語るものなんです。
抑制された中でどのように物語や人物を表現するのかを考えることは、すごくおもしろいと思いました。
5年ほど経ってもう一段ステップアップしようと思った時、「ほかの人になくて私だからこそのものは何か」を考えました。
そんなふうに考えられたのは「できなくてもできるようになるまで頑張ればいい」と辛抱強く見守ってくれる師匠の存在と、そもそも琵琶の世界は優劣があるのではなく、みんな違ってみんないいの世界。
誰かと比べる必要もないので、「私にも何かちょっとはええところがあるんちゃうん?」と自分の伸びしろを信じてみようと思えたんです。
そこで、学生時代の演劇経験を自分の強みにすることにしました。実際に物語を読み解いて情景や心情を深く掘り下げる方法や滑舌の訓練が役立っています。
ただ演劇は自分の内面や感情を発露する芸術ですが、薩摩琵琶は物語の筋や情景、登場人物の心情を「伝える」もの。基本的に表情を変えたり動作を入れたりしません。声や音色の調子や強弱、速さによってのみ表現し、ただただ一点を見つめて弾き語るものなんです。
抑制された中でどのように物語や人物を表現するのかを考えることは、すごくおもしろいと思いました。

言葉には表れていないものも、理解したい
物語や人物を捉えて伝えるために、どんなことをされていますか?
歌本を読み込んで、さらには元ネタになった一次資料に当たって掘り下げていくというアプローチを試みています。
一次資料からどんな変化を遂げ、この琵琶歌の作者まで行き着いたのかを辿り、「この物語ではここがポイントになる」「こういった背景があったから、この登場人物はこう動いたんだな」と解釈し、どう表現するかを考えるんです。
正直、物語の登場人物の心情って、「なんで、そんなことで切腹するの?」など現代人の私には共感できないことも多いんですが、共感できなくても理解したいという気持ちで、歌詞や資料から想像を膨らませています。
物語の中の時代の考え方もあって、歌詞には直接的な言葉としては表れていない、その時代を生きていた人たちが考えていたことまで掘り下げられたら、と。登場人物が影響を受けているであろう孔子の論語や孫子の兵法など武士の学問書についても勉強したいと思うようになりました。
一次資料からどんな変化を遂げ、この琵琶歌の作者まで行き着いたのかを辿り、「この物語ではここがポイントになる」「こういった背景があったから、この登場人物はこう動いたんだな」と解釈し、どう表現するかを考えるんです。
正直、物語の登場人物の心情って、「なんで、そんなことで切腹するの?」など現代人の私には共感できないことも多いんですが、共感できなくても理解したいという気持ちで、歌詞や資料から想像を膨らませています。
物語の中の時代の考え方もあって、歌詞には直接的な言葉としては表れていない、その時代を生きていた人たちが考えていたことまで掘り下げられたら、と。登場人物が影響を受けているであろう孔子の論語や孫子の兵法など武士の学問書についても勉強したいと思うようになりました。
言葉として表現されているものではなく、その背景にある思想なども理解する・・・果てしない作業ですね。
そうなんです。さらには物語の中だけではなく、その歌詞を書いた作者についても興味を持ち始めました。きっかけは男女共同参画センターでの演奏会で、「女性の立場での琵琶歌はありませんか?」というリクエストを受けたことでした。
薩摩琵琶の物語は男性武士が主人公で、女性は男性に運命を翻弄されるパターンが多いんですが、珍しく女性を主人公にした物語を見つけました。
「巴の前」という物語で、源平合戦の時代、木曽義仲の家臣として戦場で長刀を振るい、数々の武勲を立てた巴御前という女武者が主人公です。
 巴御前が敵の武将と一騎打ちになるのですが、お互いに怪力過ぎて、鎧の掴み合っていたところがブチッと切れて離れてしまう。「おまえ、やるじゃねえか」と笑い合って別れていくという描写がありました。
巴御前が敵の武将と一騎打ちになるのですが、お互いに怪力過ぎて、鎧の掴み合っていたところがブチッと切れて離れてしまう。「おまえ、やるじゃねえか」と笑い合って別れていくという描写がありました。
どうして、この歌詞の作者は巴御前と相手の武将、女性と男性を対等に書いたのだろうとすごく気になったんです。
作者は前坊法外という人で、残っていたのはこの一作だけ。いろいろ調べても奈良の人ということしかわからず、どういう想いでこの詩を書いたのかはわからずじまいでした。
でも、この作品が書かれた明治・大正時代について、ドーンセンターの方からその時代に平塚らいてうらによって女性の地位向上の運動が起きていたから時代の空気を汲んだのではないかとの見解を教えてくださり、「なるほど」と思ったんです。
物語の中の時代と、物語が書かれた時代があります。その両方を理解することで、語りにも表れるのではないか、と。「やらなければならない」というより、自分自身の興味もありますから趣味と実益を兼ねて取り組んでいます。
薩摩琵琶の物語は男性武士が主人公で、女性は男性に運命を翻弄されるパターンが多いんですが、珍しく女性を主人公にした物語を見つけました。
「巴の前」という物語で、源平合戦の時代、木曽義仲の家臣として戦場で長刀を振るい、数々の武勲を立てた巴御前という女武者が主人公です。
 巴御前が敵の武将と一騎打ちになるのですが、お互いに怪力過ぎて、鎧の掴み合っていたところがブチッと切れて離れてしまう。「おまえ、やるじゃねえか」と笑い合って別れていくという描写がありました。
巴御前が敵の武将と一騎打ちになるのですが、お互いに怪力過ぎて、鎧の掴み合っていたところがブチッと切れて離れてしまう。「おまえ、やるじゃねえか」と笑い合って別れていくという描写がありました。どうして、この歌詞の作者は巴御前と相手の武将、女性と男性を対等に書いたのだろうとすごく気になったんです。
作者は前坊法外という人で、残っていたのはこの一作だけ。いろいろ調べても奈良の人ということしかわからず、どういう想いでこの詩を書いたのかはわからずじまいでした。
でも、この作品が書かれた明治・大正時代について、ドーンセンターの方からその時代に平塚らいてうらによって女性の地位向上の運動が起きていたから時代の空気を汲んだのではないかとの見解を教えてくださり、「なるほど」と思ったんです。
物語の中の時代と、物語が書かれた時代があります。その両方を理解することで、語りにも表れるのではないか、と。「やらなければならない」というより、自分自身の興味もありますから趣味と実益を兼ねて取り組んでいます。
過去から現在、現在から未来につなぐ、1人として
お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか?
理想は「物語の依り代になる」ことです。
「敦盛」という物語を例に話しますと、源氏側として百戦錬磨の武将・熊谷、平家側として初戦となる美少年・敦盛が登場し、一騎打ちとなる場面があります。
熊谷は敦盛を組み伏せて首を取ろうとするんですが、兜から自分の息子と同じくらいの年齢の少年の顔が見えたものですから、「助けてあげたい」と思います。でも、味方の援軍がやってきたから逃がすわけにはいかず、泣く泣く敦盛の首を切るという物語です。
熊谷の立場になって心が揺れ動いたり、泣く泣く首を切るしかなかった熊谷の気持ちを思って心が締めつけられたり・・・聴いてくださったお一人おひとりが物語に入り込んでくださった時が一番嬉しい。
でも、まだまだ我が強く、その境地にはほど遠いんです。
「敦盛」という物語を例に話しますと、源氏側として百戦錬磨の武将・熊谷、平家側として初戦となる美少年・敦盛が登場し、一騎打ちとなる場面があります。
熊谷は敦盛を組み伏せて首を取ろうとするんですが、兜から自分の息子と同じくらいの年齢の少年の顔が見えたものですから、「助けてあげたい」と思います。でも、味方の援軍がやってきたから逃がすわけにはいかず、泣く泣く敦盛の首を切るという物語です。
熊谷の立場になって心が揺れ動いたり、泣く泣く首を切るしかなかった熊谷の気持ちを思って心が締めつけられたり・・・聴いてくださったお一人おひとりが物語に入り込んでくださった時が一番嬉しい。
でも、まだまだ我が強く、その境地にはほど遠いんです。
「我が強い」というのは、どういうことですか?
「こう表現したい」「上手いと思ってほしい」という欲が出てしまうんです。
極端な例で言いますと、上手いと思ってほしいという気持ちがちょっときどったバチ打ちに表れてしまうなど、「我」が端々に出てしまいます。また演奏中に「いびきをかいて寝ている人がいる」「後ろのほうの人が動いた」など客席を気にしているうちは、まだまだです。
ふと私の「我」が出てしまうと、聴き手に伝わってしまい、せっかく物語に入り込んでくださっても我に帰らせてしまいます。
こればかりは日々の稽古と場数を踏むしかありません。
この世界は60歳でようやく一人前と言われ、50代でもまだ若手。41歳の私なんてあと20年近くは若手時代が続きますから、その20年の間にきっちりと稽古と経験を積み重ねていきたいと思います。
極端な例で言いますと、上手いと思ってほしいという気持ちがちょっときどったバチ打ちに表れてしまうなど、「我」が端々に出てしまいます。また演奏中に「いびきをかいて寝ている人がいる」「後ろのほうの人が動いた」など客席を気にしているうちは、まだまだです。
ふと私の「我」が出てしまうと、聴き手に伝わってしまい、せっかく物語に入り込んでくださっても我に帰らせてしまいます。
こればかりは日々の稽古と場数を踏むしかありません。
この世界は60歳でようやく一人前と言われ、50代でもまだ若手。41歳の私なんてあと20年近くは若手時代が続きますから、その20年の間にきっちりと稽古と経験を積み重ねていきたいと思います。
近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
「教師」の免状を取得して教室を開くことが大きな目標の一つです。
子どもの頃から伝統芸能に精通していたわけでもない私が今こうして薩摩琵琶に魅了され、奏者をしています。知れば、きっと私と同じように感じてくれる人はいるのではないでしょうか。
ライブや演奏会などを通して知ってもらえる努力を続け、そこから聴いてくれる人が増えれば、習いたい人も増える。さらには、その中から奏者が育ってくれたらいいなあ、と。
薩摩琵琶は次代につなぐもの。受け継いでくれる人を育て、後世に残すことができたらと思っています。
子どもの頃から伝統芸能に精通していたわけでもない私が今こうして薩摩琵琶に魅了され、奏者をしています。知れば、きっと私と同じように感じてくれる人はいるのではないでしょうか。
ライブや演奏会などを通して知ってもらえる努力を続け、そこから聴いてくれる人が増えれば、習いたい人も増える。さらには、その中から奏者が育ってくれたらいいなあ、と。
薩摩琵琶は次代につなぐもの。受け継いでくれる人を育て、後世に残すことができたらと思っています。

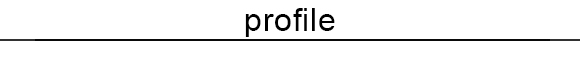
荻山 泊水さん
関西大学文学部卒業後、見学施設の案内係や老人クラブ広報誌の編集、劇場売店の売り子、学習塾での教材作成などさまざまな仕事を経験。2004年に落語家の林家染太と結婚後は夫の個人事務所の事務方として制作や落語会の受付など、裏方の仕事も務める。2007年から錦心流薩摩琵琶弾奏家の中野淀水に師事。2015年に錦心流琵琶全国一水会皆伝取得。武士の伝統を汲む薩摩琵琶の勇壮な演奏と語りを得意とし、自主開催のライブや演奏会ではスケッチブックを用いて物語を図解するなど工夫を凝らす。また、現代の言葉で日本の昔話を語る「おとぎ琵琶」にも取り組み、作詞にも挑戦中。錦心流琵琶全国一水会大阪支部理事を務めている。
HP: https://ogiyamahakusui.jimdo.com
(取材:2018年6月)
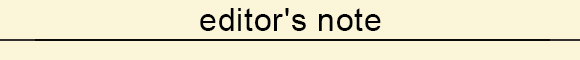
好き・嫌い、得意・不得意、優・劣、勝ち・負け、自己表現といった枠組みを超え、脈々と継承されてきたものを受け継ぎ、型を守りながらも現在を生きる自分の感性や経験などを活かして、次代につないでいくということ。
自分1人だけ、この1時代だけで完結させない。壮大な流れの中に身を置く決心と覚悟が伝わってきました。
荻山さんが薩摩琵琶を観て「かっこいい!」と一目惚れしたと語っておられましたが、私は荻山さんが弾き語る姿を観て、そう感じました。その姿に生き方や決心、覚悟が表れているからこそなんだと思います。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。