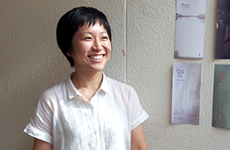HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() 今井 亜紀さん (「ははは劇場」主宰)
今井 亜紀さん (「ははは劇場」主宰) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
今井 亜紀さん (「ははは劇場」主宰)

人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい
今井 亜紀さん
「ははは劇場」主宰
「ははは劇場」主宰
「ふとんの上で正座」「お湯を沸かして番茶を飲む」など毎朝の日課を描いた「あさめがさめたら」、「えー、まずはじめに」を言いたがるおじさんが物語る「まずはじめにおじさん」、知的障害のあるふみちゃんとの思い出から物語が広がった「ふみちゃん」といったオリジナルの紙芝居をつくり、公演している今井亜紀さん。
フリーの俳優として他劇団の舞台に客演するほか、自身で「ははは劇場」を主宰して、保育所や児童養護施設、地域のコミュニティスペース、イベントなどで紙芝居を公演しています。
今井さんにとって紙芝居は、「『~ねばならない』に囚われている自分」から解き放たれ、「もっと自由に表現できることを」と模索する中でたどり着いた1つの表現方法です。
ここにたどり着くまでに壁となったという「『~ねばならない』に囚われている自分」とは? そこからどう解き放たれ、今井さんが「無理なく、自分自身も自然に楽しめている」という表現活動にたどり着けたのでしょうか。
フリーの俳優として他劇団の舞台に客演するほか、自身で「ははは劇場」を主宰して、保育所や児童養護施設、地域のコミュニティスペース、イベントなどで紙芝居を公演しています。
今井さんにとって紙芝居は、「『~ねばならない』に囚われている自分」から解き放たれ、「もっと自由に表現できることを」と模索する中でたどり着いた1つの表現方法です。
ここにたどり着くまでに壁となったという「『~ねばならない』に囚われている自分」とは? そこからどう解き放たれ、今井さんが「無理なく、自分自身も自然に楽しめている」という表現活動にたどり着けたのでしょうか。
演劇を通して、抑え込んできたものを表出できた
演劇を始めるきっかけは?
とにかく「有名になりたい」という、物心ついた頃から抱いている強い思いが出発点です。当時大人気だったアイドルを見て「有名になるには、テレビが1番」と安直に思っていました。
中学1年生の時にはライバル視していた同級生が俳優養成所に入所したと聞きつけ、「抜かされてたまるか」と急いで入所。以降はテレビドラマなどのオーディションを受けまくりますが、ことごとく落選していました。
そんな日々が1年ほど続いたある日、講師が養成所内の劇団を勧めてくれたことが、演劇との最初の接点になります。目立ちたがり屋だから恐れることなく、初舞台を踏み、劇団内で評価されて初舞台では新人賞、2回目の舞台では演技賞と立て続けに受賞しました。
でも、中学3年生になると、ほかにも興味のあることが出てきて、あっさりと退所してしまうんです。高校時代はソフトボール部や生徒会の活動が忙しくて、演劇からは遠ざかっていました。
再開したのは19歳の時。通っていた短大の最寄り駅で、演劇セミナーのチラシをたまたま見つけて、「昔、演劇をしていたなあ」「みんなで1つの舞台をつくり上げる過程がおもしろかったなあ」と懐かしく思い出し、参加してみることに。
演劇セミナーで表現するおもしろさを体感し、さらにはプロの劇団員の方々の「何をしていても注目してしまう」「惹きつけてやまない」演技力に憧れて、俳優を志すようになり、演劇学校を経て劇団に入団したんです。
劇団に3年ほど所属した後、1999年からフリーで演劇活動をしています。
中学1年生の時にはライバル視していた同級生が俳優養成所に入所したと聞きつけ、「抜かされてたまるか」と急いで入所。以降はテレビドラマなどのオーディションを受けまくりますが、ことごとく落選していました。
そんな日々が1年ほど続いたある日、講師が養成所内の劇団を勧めてくれたことが、演劇との最初の接点になります。目立ちたがり屋だから恐れることなく、初舞台を踏み、劇団内で評価されて初舞台では新人賞、2回目の舞台では演技賞と立て続けに受賞しました。
でも、中学3年生になると、ほかにも興味のあることが出てきて、あっさりと退所してしまうんです。高校時代はソフトボール部や生徒会の活動が忙しくて、演劇からは遠ざかっていました。
再開したのは19歳の時。通っていた短大の最寄り駅で、演劇セミナーのチラシをたまたま見つけて、「昔、演劇をしていたなあ」「みんなで1つの舞台をつくり上げる過程がおもしろかったなあ」と懐かしく思い出し、参加してみることに。
演劇セミナーで表現するおもしろさを体感し、さらにはプロの劇団員の方々の「何をしていても注目してしまう」「惹きつけてやまない」演技力に憧れて、俳優を志すようになり、演劇学校を経て劇団に入団したんです。
劇団に3年ほど所属した後、1999年からフリーで演劇活動をしています。

当初は「有名になりたい」という願望から演劇を始められましたが、現在にまで至る強い想いにつながったのはなぜですか?
演劇セミナーで、「劇表現」という「ごっこ遊び」から表現につなげる基礎訓練を受けました。
たとえば、「猛獣狩りへ行こう!」とリーダーが言うのを真似て後をついてまわり、途中で「かいじゅう!」と言われたら、文字数と同じ5人で集まって怪獣に化けて動き回るという、遊びの中で自分の内側にあるものを表現として出す訓練です。
この時、自分の中にずっとあった「言葉にできないモヤモヤとしたもの」をようやく出せた気がしました。
中学生の頃から詩を書くことで、少しずつは出せていたものの、出しきれていないしんどさがあり、いつしか「どうして誰も受け止めてくれないんだ」という宛のない怒りにも変わっていたように思います。
その抑え込んできたものをいいエネルギーに変えて表現として出すことができたんです。
でも、劇団に入団すると、また出せなくなってしまいました。先輩の凄さに圧倒されて、「これが技術なんだ」「自分は全然できていない」と焦りを感じ、「~ねばならない」と技術を追うがあまり、まるでプラスチックケースの中に自分を閉じ込めて動かしているみたいな感覚に陥ったんです。
それでも「石の上にも三年」と踏ん張り、もがき続けました。退団直前に客演した舞台で、ごちゃごちゃ考えず、自分に正直にシンプルに表現してみようと吹っ切れたら、入団前の自由な表現と入団後に得た技術が組み合わさって、自分なりの表現が掴めそうな気が。
一区切りとして劇団は辞めましたが、演劇は続けていこうと心に決めたんです。
たとえば、「猛獣狩りへ行こう!」とリーダーが言うのを真似て後をついてまわり、途中で「かいじゅう!」と言われたら、文字数と同じ5人で集まって怪獣に化けて動き回るという、遊びの中で自分の内側にあるものを表現として出す訓練です。
この時、自分の中にずっとあった「言葉にできないモヤモヤとしたもの」をようやく出せた気がしました。
中学生の頃から詩を書くことで、少しずつは出せていたものの、出しきれていないしんどさがあり、いつしか「どうして誰も受け止めてくれないんだ」という宛のない怒りにも変わっていたように思います。
その抑え込んできたものをいいエネルギーに変えて表現として出すことができたんです。
でも、劇団に入団すると、また出せなくなってしまいました。先輩の凄さに圧倒されて、「これが技術なんだ」「自分は全然できていない」と焦りを感じ、「~ねばならない」と技術を追うがあまり、まるでプラスチックケースの中に自分を閉じ込めて動かしているみたいな感覚に陥ったんです。
それでも「石の上にも三年」と踏ん張り、もがき続けました。退団直前に客演した舞台で、ごちゃごちゃ考えず、自分に正直にシンプルに表現してみようと吹っ切れたら、入団前の自由な表現と入団後に得た技術が組み合わさって、自分なりの表現が掴めそうな気が。
一区切りとして劇団は辞めましたが、演劇は続けていこうと心に決めたんです。

「『~ねばならない』に囚われる自分」から解き放たれて
現在は、さまざまな劇団の舞台に客演するほか、「ははは劇場」として各地で紙芝居をされていますね。
紙芝居にたどり着いたのは、ほんの3年前のことで、それまでの15年、そして今も自分がやりたい演劇は一体何なのかを模索してきました。
退団後まもなくから、友人や知人の舞台に客演するほか、自分自身でも舞台をつくってきました。
最初は演劇学校時代の同期生5人と集まって、それぞれが脚本・演出を手掛ける5人5つのお芝居を行いました。
今、主宰している「ははは劇場」は「芸人ではない役者がやる、笑える劇をつくろう」と、友人と2人で2004年に旗揚げ。1回目の公演後に、友人は家庭の事情で離れてしまい、今は個人で主宰しています。
以降は「ははは劇場」として、演劇仲間と一緒にコントものをつくったり、中学生の頃から書き綴っている詩を演出家3人に演出してもらったり、自分の母をテーマにした物語をつくったりなど、2013年までの8年間で全5回の公演を行いました。
でも、劇団員時代に体験した「~ねばならない」に囚われてしまう自分がいて、その自分が壁になったんです。
退団後まもなくから、友人や知人の舞台に客演するほか、自分自身でも舞台をつくってきました。
最初は演劇学校時代の同期生5人と集まって、それぞれが脚本・演出を手掛ける5人5つのお芝居を行いました。
今、主宰している「ははは劇場」は「芸人ではない役者がやる、笑える劇をつくろう」と、友人と2人で2004年に旗揚げ。1回目の公演後に、友人は家庭の事情で離れてしまい、今は個人で主宰しています。
以降は「ははは劇場」として、演劇仲間と一緒にコントものをつくったり、中学生の頃から書き綴っている詩を演出家3人に演出してもらったり、自分の母をテーマにした物語をつくったりなど、2013年までの8年間で全5回の公演を行いました。
でも、劇団員時代に体験した「~ねばならない」に囚われてしまう自分がいて、その自分が壁になったんです。

「『~ねばならない』に囚われてしまう自分が壁になった」とは?
3回目の公演前、病気になり、手術が必要になりました。手術後、目が覚めるかどうかもわからないのに、当時の私は「一度決めたのだから、しなければならない」と自分を追い込みました。
座長である私がそのような状況だったので、役者や演出家、照明や音響といった舞台技術者、当日運営スタッフなど関係各所とのコミュニケーションや調整が十分に取れず、人間関係がぎくしゃく・・・修復不可能に。その雰囲気は舞台にも表れ、お客さんにも伝わっているのがわかりました。
今でも当時を思い出すのがまだ辛いくらいですから、当時はもっと辛くて、公演後1カ月ほどは外に出られる状態ではありませんでした。心身に不調が生じ、何もやる気が起きず、流れるままに日々を過ごしていたように思います。
もう、限界だったのかもしれません。
稽古場や劇場の使用料なども含めて1回の公演に200万円ほどかかるため、アルバイトを掛け持ちして頑張ってはお金を注ぎ込む。脚本を書き、役者や演出家、舞台技術者に依頼をかけ、調整する。公演が近づけば連日、稽古が続き、当日に向けて会場設営からお弁当の手配をする・・・など。
手伝ってもらうものの、主担当は自分です。アルバイトから帰って、寝る時間を惜しんで、公演に向けて準備を進める日々・・・身体も、心も、悲鳴を上げていたのだと思います。
座長である私がそのような状況だったので、役者や演出家、照明や音響といった舞台技術者、当日運営スタッフなど関係各所とのコミュニケーションや調整が十分に取れず、人間関係がぎくしゃく・・・修復不可能に。その雰囲気は舞台にも表れ、お客さんにも伝わっているのがわかりました。
今でも当時を思い出すのがまだ辛いくらいですから、当時はもっと辛くて、公演後1カ月ほどは外に出られる状態ではありませんでした。心身に不調が生じ、何もやる気が起きず、流れるままに日々を過ごしていたように思います。
もう、限界だったのかもしれません。
稽古場や劇場の使用料なども含めて1回の公演に200万円ほどかかるため、アルバイトを掛け持ちして頑張ってはお金を注ぎ込む。脚本を書き、役者や演出家、舞台技術者に依頼をかけ、調整する。公演が近づけば連日、稽古が続き、当日に向けて会場設営からお弁当の手配をする・・・など。
手伝ってもらうものの、主担当は自分です。アルバイトから帰って、寝る時間を惜しんで、公演に向けて準備を進める日々・・・身体も、心も、悲鳴を上げていたのだと思います。

その状況からどう立ち上がり、今も続けることができているのですか?
そんな私を救ってくれたのは、友人です。「一緒に演劇をしよう」と誘ってくれたのを機に、「また、やってみよう」という気持ちになれ、演劇活動を少しずつ再開させていけました。
その2年後には、再び「ははは劇場」として第4回目の公演を開催できるようにまでなりました。
振り返ると、「自分を見てほしい」「有名になりたい」「演劇で名を残したい」といった欲があって、そのために「~ねばならない」と自分に義務をどんどん課してきたように思います。
「しんどい」と自分が悲鳴を上げていることに気づいているのに、「これくらいで、しんどいと言ってはいけない」「これくらい、自分にできるはず」と押さえつけて、おしりを叩いてきました。
一方で、永く続けていくためには、このままではとても続けられないのではないかという気持ちも。それは、まわりの状況の変化や出会った人たち、自分自身のさまざまな経験によって頑なさが緩んできたおかげだと思います。
その2年後には、再び「ははは劇場」として第4回目の公演を開催できるようにまでなりました。
振り返ると、「自分を見てほしい」「有名になりたい」「演劇で名を残したい」といった欲があって、そのために「~ねばならない」と自分に義務をどんどん課してきたように思います。
「しんどい」と自分が悲鳴を上げていることに気づいているのに、「これくらいで、しんどいと言ってはいけない」「これくらい、自分にできるはず」と押さえつけて、おしりを叩いてきました。
一方で、永く続けていくためには、このままではとても続けられないのではないかという気持ちも。それは、まわりの状況の変化や出会った人たち、自分自身のさまざまな経験によって頑なさが緩んできたおかげだと思います。

どんな変化や出会い、経験が「~ねばならない」から解き放つ力になったのですか?
「これ」というものではなく、日常の一つひとつの出来事や出会い、経験の積み重ねによるものです。
たとえば、劇団時代は約400人規模の劇場で公演するため、見えない、知らない、大勢の誰かに向けて、演じてきました。
自分で演劇活動を始めてからは約30人規模の劇場で公演するため、すぐそばにお客さんがいて、私からお客さんがよく見えるし、お客さんからも私がよく見えます。
そのお客さんも、必死で手売りして来てもらった初めましての方もいましたが、自分の友人や、友人の友人がほとんど。また、当時働いていた知的障害のある人たちが通所する作業所で日々接している利用者さんと職員さんが、わざわざ休日に観に来てくれたこともありました。
その時、素直に嬉しいと思いました。
「よりたくさんの人たちに観てもらわなきゃ」という気持ちが前面に出ていた時は素直に喜べなかったかもしれませんが、この喜びに正直でいいんじゃないかって。特に、作業所の方々は私に「自分に正直であることの素晴らしさ」を教えてくれた人たちだから、そう思えたのだと思います。
この時、「見えない、大勢の誰か」ではなく、「目の前の誰か」に目を向けるようになりました。日常の延長線上で演劇をするほうがおもしろいんじゃないか、そのほうが自分に正直でいられるんじゃないかとも思ったんです。
奇しくも、転機となった5回目の公演では、母をテーマにした物語でした。母を初めて招待していて、芝居中に母が視界に入った途端、感情が高ぶって泣いてしまったんです。「役者、失格やな」となった半面、「それでもいいんちゃう」とそんな自分を許せた自分もいました。
振り返れば、物心ついた頃から抱いている「有名になりたい」という強い思いの根本には、「自分を見てほしい」という欲求があったのかもしれません。母はいつもどこかしんどうそうで不機嫌そうで、ぎゅっと抱きしめられた記憶もなかったから、満たされないものがあったのでしょう。
オリジナルの物語を書きながら、抱えていた想いも少しずつ昇華させることができていたようです。
そのほかにも、演劇をする心身づくりのために始めたヨガやそこから派生して学んだネイチャーゲームなど、さまざまな知恵や体感、体験なども積み重なって、「~ねばならない」を手放し、「ほかの方法を探してみる」という明るい諦めができるようになったのだと思います。
たとえば、劇団時代は約400人規模の劇場で公演するため、見えない、知らない、大勢の誰かに向けて、演じてきました。
自分で演劇活動を始めてからは約30人規模の劇場で公演するため、すぐそばにお客さんがいて、私からお客さんがよく見えるし、お客さんからも私がよく見えます。
そのお客さんも、必死で手売りして来てもらった初めましての方もいましたが、自分の友人や、友人の友人がほとんど。また、当時働いていた知的障害のある人たちが通所する作業所で日々接している利用者さんと職員さんが、わざわざ休日に観に来てくれたこともありました。
その時、素直に嬉しいと思いました。
「よりたくさんの人たちに観てもらわなきゃ」という気持ちが前面に出ていた時は素直に喜べなかったかもしれませんが、この喜びに正直でいいんじゃないかって。特に、作業所の方々は私に「自分に正直であることの素晴らしさ」を教えてくれた人たちだから、そう思えたのだと思います。
この時、「見えない、大勢の誰か」ではなく、「目の前の誰か」に目を向けるようになりました。日常の延長線上で演劇をするほうがおもしろいんじゃないか、そのほうが自分に正直でいられるんじゃないかとも思ったんです。
奇しくも、転機となった5回目の公演では、母をテーマにした物語でした。母を初めて招待していて、芝居中に母が視界に入った途端、感情が高ぶって泣いてしまったんです。「役者、失格やな」となった半面、「それでもいいんちゃう」とそんな自分を許せた自分もいました。
振り返れば、物心ついた頃から抱いている「有名になりたい」という強い思いの根本には、「自分を見てほしい」という欲求があったのかもしれません。母はいつもどこかしんどうそうで不機嫌そうで、ぎゅっと抱きしめられた記憶もなかったから、満たされないものがあったのでしょう。
オリジナルの物語を書きながら、抱えていた想いも少しずつ昇華させることができていたようです。
そのほかにも、演劇をする心身づくりのために始めたヨガやそこから派生して学んだネイチャーゲームなど、さまざまな知恵や体感、体験なども積み重なって、「~ねばならない」を手放し、「ほかの方法を探してみる」という明るい諦めができるようになったのだと思います。

「何気ない日常」こそが、舞台
演劇から紙芝居へ。どうして「紙芝居」にたどり着いたのですか?
紙芝居を始める前に、1人劇、ヨガ、食事を組み合わせた「体感ライブ」というものを2回ほど開催しました。
きっかけは、第5回目の公演の時に、必死に準備してきて迎えた当日「いらっしゃいませ」とお客さんを出迎える中で、「ここに来るまでにもう演劇は始まっているのではないか」「いや、生活そのものが演劇ではないか」とひらめくものがあったからです。
この時、劇団時代に代表から教わった「人生は演劇」という言葉と結びつきました。
演劇とは「play=遊び」、遊びとは「楽しいもの、自由なもの、どんなふうにだって進路変更できるもの」と私は解釈しています。
たとえば、演劇であれば、舞台上で好きなことができます。ここが宇宙だと思えば、宇宙にもなります。人生も、それと同じなんじゃないかって。
何かに縛られたレールの上を歩かなくても、「~ねばならない」に囚われなくてもいい。望めば願えば、どこにでも行けるし、何にでもなれる可能性がある・・・もっともっと自由に生きていいんじゃないかなって。
毎日の生活の場が劇場、生活が演劇になれば、きっと楽しい。そのために、体感・体験してもらえる場をつくりたいと、「体感ライブ」を企画。ヨガで身体を動かしたり、カフェで食事をしたり、参加要素を取り入れた1人劇をしたりなど、工夫しました。
すると、今度は1人ぼっちでの稽古に味気なさを感じてしまいました。これまでは作品に関わる人たちと集まって、「ああでもない、こうでもない」と言い合いながらつくり上げるおもしろさがあったのが、1人ではビデオで撮影しながら、もくもくと進めるだけだからです。
1人でも楽しみながらできる方法はないかなと考えてたどり着いたのが、紙芝居という1人劇です。
最初は図書館で紙芝居を借りていたのですが、もっと気軽にできないだろうかを突き詰めるうち、自分で描くようになりました。「1人稽古=創作の時間」「私と紙芝居があればどこでもいつでも公演できるスタイル」、このほうが自分には合っているようでした。
きっかけは、第5回目の公演の時に、必死に準備してきて迎えた当日「いらっしゃいませ」とお客さんを出迎える中で、「ここに来るまでにもう演劇は始まっているのではないか」「いや、生活そのものが演劇ではないか」とひらめくものがあったからです。
この時、劇団時代に代表から教わった「人生は演劇」という言葉と結びつきました。
演劇とは「play=遊び」、遊びとは「楽しいもの、自由なもの、どんなふうにだって進路変更できるもの」と私は解釈しています。
たとえば、演劇であれば、舞台上で好きなことができます。ここが宇宙だと思えば、宇宙にもなります。人生も、それと同じなんじゃないかって。
何かに縛られたレールの上を歩かなくても、「~ねばならない」に囚われなくてもいい。望めば願えば、どこにでも行けるし、何にでもなれる可能性がある・・・もっともっと自由に生きていいんじゃないかなって。
毎日の生活の場が劇場、生活が演劇になれば、きっと楽しい。そのために、体感・体験してもらえる場をつくりたいと、「体感ライブ」を企画。ヨガで身体を動かしたり、カフェで食事をしたり、参加要素を取り入れた1人劇をしたりなど、工夫しました。
すると、今度は1人ぼっちでの稽古に味気なさを感じてしまいました。これまでは作品に関わる人たちと集まって、「ああでもない、こうでもない」と言い合いながらつくり上げるおもしろさがあったのが、1人ではビデオで撮影しながら、もくもくと進めるだけだからです。
1人でも楽しみながらできる方法はないかなと考えてたどり着いたのが、紙芝居という1人劇です。
最初は図書館で紙芝居を借りていたのですが、もっと気軽にできないだろうかを突き詰めるうち、自分で描くようになりました。「1人稽古=創作の時間」「私と紙芝居があればどこでもいつでも公演できるスタイル」、このほうが自分には合っているようでした。

紙芝居となると、絵で表現する必要も出てきますが、その部分での表現の難しさはありませんでしたか?
子どもの頃に、好きなイラストを真似て描いたり、折り紙で封筒をつくってオリジナル絵封筒をつくったりしていたから、躊躇なく描くことができました。
物語は最初のうち、登場人物の設定や起承転結などもきっちり考えて描いていましたが、「~ねばならない」に囚われたものが仕上がってしまうので、心が動かないんです。
だから、今は描きながら、「この登場人物はこんなことを考えているよなあ」と思ったらその方向に話が転がっていったり、途中で先が見えなくなった時はそこで止めて、見えてきたら続きを描いたり、描きながら心向くままに物語を紡いでいます。
たとえば、おばあちゃんや犬、赤ちゃん、お母さんといった登場人物みんなが歩いていたのは、実は同じ帽子のつばの上やったんやなあというお話の「えっちら、おっちら」。
この紙芝居は、外がよく見えるカフェでぼーっとお茶をしていた時、向こうから歩いてくるおばあちゃんの姿を見て、「えっちら、おっちら歩いてはるわ」「えっちら、おっちら歩いているのは、おばあちゃんだけじゃないよね?」と思ったのが始まり。
その場面を言葉でメモしておいて、頭の中でその場面から広がっていくものがあったら、終わりを決めずに描き始めます。
物語は最初のうち、登場人物の設定や起承転結などもきっちり考えて描いていましたが、「~ねばならない」に囚われたものが仕上がってしまうので、心が動かないんです。
だから、今は描きながら、「この登場人物はこんなことを考えているよなあ」と思ったらその方向に話が転がっていったり、途中で先が見えなくなった時はそこで止めて、見えてきたら続きを描いたり、描きながら心向くままに物語を紡いでいます。
たとえば、おばあちゃんや犬、赤ちゃん、お母さんといった登場人物みんなが歩いていたのは、実は同じ帽子のつばの上やったんやなあというお話の「えっちら、おっちら」。
この紙芝居は、外がよく見えるカフェでぼーっとお茶をしていた時、向こうから歩いてくるおばあちゃんの姿を見て、「えっちら、おっちら歩いてはるわ」「えっちら、おっちら歩いているのは、おばあちゃんだけじゃないよね?」と思ったのが始まり。
その場面を言葉でメモしておいて、頭の中でその場面から広がっていくものがあったら、終わりを決めずに描き始めます。

まずは赤い杖をついているおばあちゃんがいて、次に舌を出している犬、続けて両手を広げて歩く赤ちゃん、おなかに赤ちゃんがいるお母さん、鳥の「ひばり」と描いて、風が吹いてきたらおもしろいなあと思いつきました。
風を表現するために風に舞う葉っぱと、さらには帽子も飛ばそう、と。風ときたから、お日さまも歩いて沈むなあと思い、日が沈んでいく様子を表現して、時間の経過が生まれたから夜の場面も描こう、と。
夜になったら、木にひっかかった帽子の内側がわいわいしている気がしました。その帽子のつばの上をみんなが歩いているんじゃないかってひらめいたんです。
おばあちゃんはゆっくり、犬は「ハア、ハア」と息を切らしながら、おなかに赤ちゃんがいるお母さんはよいしょよいしょと、みんなそれぞれ歩く速度はバラバラでも、違うところを歩いているように思えても、実はみんな同じところを歩いていて、ぐるぐるとまわっている・・・人生もそれと同じじゃないのかなあとつながったんです。
そんなふうに、日常の一点から膨らんだことを物語にしています。
風を表現するために風に舞う葉っぱと、さらには帽子も飛ばそう、と。風ときたから、お日さまも歩いて沈むなあと思い、日が沈んでいく様子を表現して、時間の経過が生まれたから夜の場面も描こう、と。
夜になったら、木にひっかかった帽子の内側がわいわいしている気がしました。その帽子のつばの上をみんなが歩いているんじゃないかってひらめいたんです。
おばあちゃんはゆっくり、犬は「ハア、ハア」と息を切らしながら、おなかに赤ちゃんがいるお母さんはよいしょよいしょと、みんなそれぞれ歩く速度はバラバラでも、違うところを歩いているように思えても、実はみんな同じところを歩いていて、ぐるぐるとまわっている・・・人生もそれと同じじゃないのかなあとつながったんです。
そんなふうに、日常の一点から膨らんだことを物語にしています。

今井さんが表現活動を通して、伝えたいこととは?
舞台作品をつくっている頃から、日常の中で「こんな感じのことをしたいなあ」というものが積もっていって、「じゃあ、やろう!」というものを表現してきました。
でも、舞台作品の時は「舞台は特別でなければならない」と非日常や特別感を追い求めてきましたが、今は「何気ない日常と、その延長線上にあるもの」を表現しています。
何気ない日常なんだけど、日常の風景を見ていて、ふと想像が膨らむことはありませんか?
たとえば、ぶらんこでも、ふぁんふぁんふぁんって漕いでいたら、そのまま空に飛んでいってしまいそうですし、もしかしたら身体が揺れているのではなく眉毛だけが揺れているのかもしれないなあと想像してしまいます。
日常の何気ない物語から、「そういえば、自分も」「自分だったら」と自分自身の何かと結びつけて感じてもらい、一人ひとりの心のずっと奥にある感情と出会うきっかけになれば、嬉しいですね。
でも、舞台作品の時は「舞台は特別でなければならない」と非日常や特別感を追い求めてきましたが、今は「何気ない日常と、その延長線上にあるもの」を表現しています。
何気ない日常なんだけど、日常の風景を見ていて、ふと想像が膨らむことはありませんか?
たとえば、ぶらんこでも、ふぁんふぁんふぁんって漕いでいたら、そのまま空に飛んでいってしまいそうですし、もしかしたら身体が揺れているのではなく眉毛だけが揺れているのかもしれないなあと想像してしまいます。
日常の何気ない物語から、「そういえば、自分も」「自分だったら」と自分自身の何かと結びつけて感じてもらい、一人ひとりの心のずっと奥にある感情と出会うきっかけになれば、嬉しいですね。

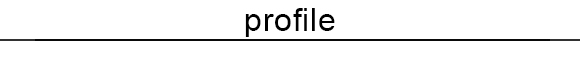
今井 亜紀さん
短期大学在学中に、「兵庫県立ピッコロ劇団」の演劇セミナーを受け、1998年に「ピッコロ演劇学校」に入学。オーディションを受け、1999年から「兵庫県立ピッコロ劇団」に所属する。2002年に退団し、フリーで演劇活動を開始。さまざまな劇団の舞台に客演するほか、2004年に「ははは劇場」を旗揚げ。現在は紙芝居を主として各地を公演で回るほか、演劇する心身づくりのために始めたヨガのインストラクター資格、そこから派生して関心を持ったネイチャーゲームリーダー資格(自然案内人)を活かしたイベントやワークショップも企画。2017年から兵庫県香美町にある祖父母が住んでいた家を利用して、「ははは劇場」として開かれた場づくりも行っている。
ははは劇場
BLOG: http://888gekijou.jugem.jp/
FB: 888gekijou
(取材:2019年6月)
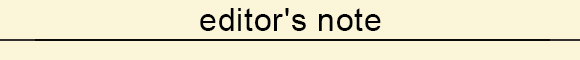
そんな時は「~ねばならない」ではなく、もともとあった「~したい」という気持ちを思い出すことが大切なのかなあと、今井さんのお話をうかがいながら思いました。
「舞台上で好きなことができます。そこが宇宙だと言えば、宇宙にもなります。人生も、それと同じなんじゃないか」「もっともっと自由に生きていいんじゃないかな」という今井さんのメッセージが印象に残っています。
取材時に、最新作の紙芝居「あさめがさめたら」を見せていただきました。
「ふとんの上で正座」「お湯を沸かして番茶を飲む」など今井さんご自身の毎朝の日課がたんたんと描かれているのですが、「朝目覚められることが奇跡的なこと」「私はこんなふうに朝の時間を大切にできているのかなあ」「日常を疎かにしてまで何を生き急いでいるのかなあ」「丁寧に生きていきたい」と、じんわりと響いてきました。
今井さんが紙芝居をされているほんの数分の間に、自分の日常を見つめ直し、「~したい」を思い出せたんです。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。