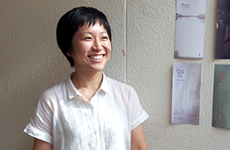HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() 小森 真理子さん(生田流箏曲師範 箏演奏家)
小森 真理子さん(生田流箏曲師範 箏演奏家) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
小森 真理子さん(生田流箏曲師範 箏演奏家)

誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事
小森 真理子さん
生田流箏曲師範 箏演奏家
生田流箏曲師範 箏演奏家
打楽器奏者やピアニスト、ヴァイオリニスト、サックス奏者、フルート奏者、シンガー、フラダンサーなどさまざまなアーティストとコラボレーションして演奏したり、Tシャツライブ、匂い袋づくりワークショップ付き、料亭を会場に舞妓姿で演奏といったユニークな箏の演奏会を企画したりしている箏演奏家の小森真理子さん。
伝統に縛られない自由な演奏活動をするようになったのは、箏人生50年のうち、まだ10年ほどのことと言います。子どもの頃から長年、伝統の世界に身を置き、師匠の教えや流派のしきたりの中で生きてきた小森さんにとって、当初は罪悪感があったそうです。
破門まで覚悟して、現在のような演奏活動を始めるきっかけとは何だったのでしょうか。そこにある想いとは?
伝統に縛られない自由な演奏活動をするようになったのは、箏人生50年のうち、まだ10年ほどのことと言います。子どもの頃から長年、伝統の世界に身を置き、師匠の教えや流派のしきたりの中で生きてきた小森さんにとって、当初は罪悪感があったそうです。
破門まで覚悟して、現在のような演奏活動を始めるきっかけとは何だったのでしょうか。そこにある想いとは?
「残りの人生」を意識したからこそ持てた覚悟と勇気
8歳の時から箏を習っておられるとのこと。習い始めるきっかけは何だったのですか?
母がどうやらお箏が好きだったようで、近所にお教室があったので、習ってみたらとすすめてくれたのがはじまりです。お箏の音色を聞いて、木を伝わって響く音色を心地よく感じ、一気に大好きになりました。
当時、世間では洋ものが流行っていて、一般的に和ものは「地味、ダサイ」というイメージを持たれているようでしたから、学校でお箏を習っていると話したら「地味やなあ」と言われることもあったように思います。
私にしてみたら、こんなにも素敵なお箏の音色が知られていないなんてもったいない、もっとたくさんの人に聞いてもらえたらいいなあと思っていました。いつしか、お箏の先生になって魅力を伝えていくことが夢になっていたんです。
でも、お箏一本で生計を立てられるとは考えもしなかったですし、子どもが好きで教育関係の仕事に就きたいという気持ちもあったので、大学卒業後は学童保育指導員として就職し、お箏は趣味として続けていました。
32歳の時に師範のお免状をいただいた時、ちょうど出産して仕事を辞めていたタイミングだったので、自宅でお箏教室を開いたんです。
当時、世間では洋ものが流行っていて、一般的に和ものは「地味、ダサイ」というイメージを持たれているようでしたから、学校でお箏を習っていると話したら「地味やなあ」と言われることもあったように思います。
私にしてみたら、こんなにも素敵なお箏の音色が知られていないなんてもったいない、もっとたくさんの人に聞いてもらえたらいいなあと思っていました。いつしか、お箏の先生になって魅力を伝えていくことが夢になっていたんです。
でも、お箏一本で生計を立てられるとは考えもしなかったですし、子どもが好きで教育関係の仕事に就きたいという気持ちもあったので、大学卒業後は学童保育指導員として就職し、お箏は趣味として続けていました。
32歳の時に師範のお免状をいただいた時、ちょうど出産して仕事を辞めていたタイミングだったので、自宅でお箏教室を開いたんです。

フルタイムの仕事に復帰され、週末に箏教室を開くという生活を長年続けられてきたそうですね。現在は教室に加え、演奏家としても活躍されています。何かタイミングがあったのですか?
最初のきっかけは、ギターリストの香登みのる先生との出会いです。お箏用に、ポップスやロック、ジャズなどの音楽を編曲され、ギターとお箏のコンサートを開いておられました。
実は、中学時代にフォークソングにはまって以来、ギターを弾いて歌うのを楽しんでいたんです。
お箏ではお箏の曲を弾き、ギターではフォークソングを弾き語り。それぞれまったく別物で交わることがないと思っていたので、お箏でフォークソングを弾けることに衝撃を受けました。
お箏でどのように現代の音楽を演奏するのか、習いたい。ただ、私が所属する流派では先生の教えを守るために他の流派に習いに行くことは禁じられているので、ばれたら破門です。
ですが、習ってみたい衝動を抑えきれず、後ろめたさを感じながらも内緒で習うことにしたんです。
実は、中学時代にフォークソングにはまって以来、ギターを弾いて歌うのを楽しんでいたんです。
お箏ではお箏の曲を弾き、ギターではフォークソングを弾き語り。それぞれまったく別物で交わることがないと思っていたので、お箏でフォークソングを弾けることに衝撃を受けました。
お箏でどのように現代の音楽を演奏するのか、習いたい。ただ、私が所属する流派では先生の教えを守るために他の流派に習いに行くことは禁じられているので、ばれたら破門です。
ですが、習ってみたい衝動を抑えきれず、後ろめたさを感じながらも内緒で習うことにしたんです。

箏で現代音楽を弾くこと、それを習うこと自体が、とても勇気がいることなんですね。
流派それぞれで爪の形や構え方、奏法などに違いがあるので、他流派と交流したり習ったりすると、せっかく先生から教わったことが崩れてしまうかもしれないとの理由から、私が所属する流派では禁じられていたんです。
でも、他流派を習ってみたことで「自分がしたいことはこういうことかもしれない」というものが見えてきて、その後ほどなくして大きな病気を経験したのを機に「自分がしたいことをしていこう」と覚悟が決まりました。
入院していた1カ月ほどの間に、自分の人生、どう生きたいのかについて一生懸命に考えたからです。
このまま死んでしまうかもしれない。手術が成功したとしても、あとどのくらい生きられるのかもわからない。残りの人生、自分は何がしたいんだろう、自分には何ができるんだろう。自分が生きていた証ってなんだろう。
そして、改めて思ったんです。
子どもの頃からお箏を習い始めて、その音色が大好きになりました。この音色をたくさんの人たちに聞いてもらいたい。「お箏っていいなあ」と感動してもらえたら、この楽器をまた次の世代に継いでいけるのではないか。さらには、お箏をきっかけに日本の伝統についても再発見してもらえたらいいなあ。
そんな想いから「琴 感動」という屋号を付けたんです。
本来であれば、琴柱があるものを「箏」、ないものを「琴」と表記し、まったく異なる楽器なのですが、常用漢字である「琴」という字のほうが知られているので、「一般の人たちにもっと知ってほしい」という想いから「琴」という字を使っています。
お箏の先生にも「これからは自分がしたいことをしたいです」と打ち明けました。自分の好き勝手するのだから破門になっても仕方がないと覚悟していましたが、先生も理解してくださり、流派に所属しながらも「小森真理子」としての活動を行えることになったんです。
でも、他流派を習ってみたことで「自分がしたいことはこういうことかもしれない」というものが見えてきて、その後ほどなくして大きな病気を経験したのを機に「自分がしたいことをしていこう」と覚悟が決まりました。
入院していた1カ月ほどの間に、自分の人生、どう生きたいのかについて一生懸命に考えたからです。
このまま死んでしまうかもしれない。手術が成功したとしても、あとどのくらい生きられるのかもわからない。残りの人生、自分は何がしたいんだろう、自分には何ができるんだろう。自分が生きていた証ってなんだろう。
そして、改めて思ったんです。
子どもの頃からお箏を習い始めて、その音色が大好きになりました。この音色をたくさんの人たちに聞いてもらいたい。「お箏っていいなあ」と感動してもらえたら、この楽器をまた次の世代に継いでいけるのではないか。さらには、お箏をきっかけに日本の伝統についても再発見してもらえたらいいなあ。
そんな想いから「琴 感動」という屋号を付けたんです。
本来であれば、琴柱があるものを「箏」、ないものを「琴」と表記し、まったく異なる楽器なのですが、常用漢字である「琴」という字のほうが知られているので、「一般の人たちにもっと知ってほしい」という想いから「琴」という字を使っています。
お箏の先生にも「これからは自分がしたいことをしたいです」と打ち明けました。自分の好き勝手するのだから破門になっても仕方がないと覚悟していましたが、先生も理解してくださり、流派に所属しながらも「小森真理子」としての活動を行えることになったんです。

「こうしたら、どうかなあ」と思っていたことを形に
以来、「箏でタンゴ曲」などさまざまな試みをされていますね。
思うまま、感じるままに、「こうしたら、どうかなあ」と思っていたことに挑戦しています。
たとえば、お箏の発表会の来場者の多くは関係者だったから、もっと一般の人たちにも聞いてもらいたいと思っていました。
そこで、ギターとお箏のコンサートから発想を得て、打楽器奏者、ピアニスト、ヴァイオリニスト、サックス奏者、フルート奏者、シンガー、フラダンサーなど、さまざまなアーティストとコラボしてコンサートを開きました。
そのほかにも、京都の小さな町屋を借りて、お箏のコンサートとわらびもち、匂い袋づくり、レストランで食事などのお楽しみもプラスした企画を考えました。もし私がコンサートに出かけるなら、おいしいものを食べたいし、訪れた周辺も楽しみたいという発想からです。
また、私が所属する流派では「着物で正座」「無表情、体も動かさずに演奏する」スタイルが基本ですが、チャイナドレスやウェディングドレス、気軽に演奏を楽しんでほしいとTシャツライブをしたり、その時々の感情に合わせて振付や手の表現をつけたり、スタンディング用の台をつくって会場の雰囲気に合わせて立って演奏したり、私なりの演奏スタイルをつくってきました。
お教室でも同じです。お免状に合わせて弾ける曲を限定するのではなく、「やってみたい」という気持ちがある人にはどんどん教えていこう。ほかに習いたい楽器、習いたい先生がいたら、自由に習ってもらっていい。
お箏っていいなあ、楽しいなあという気持ちで続けてもらえるようにしました。
たとえば、お箏の発表会の来場者の多くは関係者だったから、もっと一般の人たちにも聞いてもらいたいと思っていました。
そこで、ギターとお箏のコンサートから発想を得て、打楽器奏者、ピアニスト、ヴァイオリニスト、サックス奏者、フルート奏者、シンガー、フラダンサーなど、さまざまなアーティストとコラボしてコンサートを開きました。
そのほかにも、京都の小さな町屋を借りて、お箏のコンサートとわらびもち、匂い袋づくり、レストランで食事などのお楽しみもプラスした企画を考えました。もし私がコンサートに出かけるなら、おいしいものを食べたいし、訪れた周辺も楽しみたいという発想からです。
また、私が所属する流派では「着物で正座」「無表情、体も動かさずに演奏する」スタイルが基本ですが、チャイナドレスやウェディングドレス、気軽に演奏を楽しんでほしいとTシャツライブをしたり、その時々の感情に合わせて振付や手の表現をつけたり、スタンディング用の台をつくって会場の雰囲気に合わせて立って演奏したり、私なりの演奏スタイルをつくってきました。
お教室でも同じです。お免状に合わせて弾ける曲を限定するのではなく、「やってみたい」という気持ちがある人にはどんどん教えていこう。ほかに習いたい楽器、習いたい先生がいたら、自由に習ってもらっていい。
お箏っていいなあ、楽しいなあという気持ちで続けてもらえるようにしました。

演奏会に、演奏スタイル、教室と、次々と改革されてこられたんですね。
箏奏者も箏づくりの職人も減ってきているという状況を感じていたから、脈々と受け継がれてきたことを受け継いでいくことはもちろん大事ですが、今の時代にマッチする新しいスタイルもつくっていかなければ、このまま減少する一方ではないかと思ったんです。
さまざまなジャンルのアーティストとコラボレーションしたおかげで、たとえばジャズが好きな人に「お箏がどう絡むのか」と興味を持ってもらえるなどお箏関係者以外の人たちに聞いてもらえる機会となり、「お箏のイメージが変わった」「古典曲だけではなく、こんなにもいろんなジャンルの音楽を弾ける楽器なんだと再発見した」といった感想をもらえました。
聞いてもらえる人が増えると、今度はお箏を弾いてみたい人が増えるというところにもつながっています。お箏教室に通う生徒さんも、以前だったらもともとお箏や日本文化に関心のある人がほとんどだったのですが、今は新しく興味を持ったという人が多いんです。
先生である私が、独特な演奏活動をしているからでしょうか。通う生徒さんも個性豊かです。
お箏を弾きながらポップス曲を歌う。手づくり市の出店時に演奏もする。自分が好きな曲をお箏で演奏できるように楽譜を自作する。コンパクトサイズのお箏で路上ライブをする。お箏の弾き方を英語で説明した動画をつくって海外に発信する。
一人ひとりが好きなものや得意なことを組み合わせて楽しみ、それぞれがそれぞれの世界でお箏を伝え広げていってくれていると感じます。
さまざまなジャンルのアーティストとコラボレーションしたおかげで、たとえばジャズが好きな人に「お箏がどう絡むのか」と興味を持ってもらえるなどお箏関係者以外の人たちに聞いてもらえる機会となり、「お箏のイメージが変わった」「古典曲だけではなく、こんなにもいろんなジャンルの音楽を弾ける楽器なんだと再発見した」といった感想をもらえました。
聞いてもらえる人が増えると、今度はお箏を弾いてみたい人が増えるというところにもつながっています。お箏教室に通う生徒さんも、以前だったらもともとお箏や日本文化に関心のある人がほとんどだったのですが、今は新しく興味を持ったという人が多いんです。
先生である私が、独特な演奏活動をしているからでしょうか。通う生徒さんも個性豊かです。
お箏を弾きながらポップス曲を歌う。手づくり市の出店時に演奏もする。自分が好きな曲をお箏で演奏できるように楽譜を自作する。コンパクトサイズのお箏で路上ライブをする。お箏の弾き方を英語で説明した動画をつくって海外に発信する。
一人ひとりが好きなものや得意なことを組み合わせて楽しみ、それぞれがそれぞれの世界でお箏を伝え広げていってくれていると感じます。

お箏を通して見えた「私が生きてきた証」
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
40年近くに渡って所属した流派に対して、「もっとこうしたらいいのではないか」「ここはどうなんだろう」と思うことはありましたが、子どもの頃から身を置く世界、そうすることがこの道だと思ってきたので、何かを変えようなんて思ったこともありません。
自分自身でも「こういう世界だ」「こういうものだ」と思い続けてきましたから、それに背くことに対して最初は罪悪感がありました。
先生のお許しをいただいてからも、ルールを破った者としてそれまでの待遇とはがらりと変わりましたし、流派の関係者から「何がしたいの?」「新しいことばかりして、どこに向かおうとしているの?」「お稽古をした成果を聞いてもらうのに、有料でコンサートを開くなんて信じられない」といった辛辣なご意見をいただくこともありました。
また、家族の理解を得ることも課題でした。長年フルタイムの仕事をしながら、週末にお教室を開いていましたから、「お箏=好きなこと=趣味」と思われていたので、活発に活動するほどに「遊んでいる」と思われて活動しづらいところもあったんです。
それでも続けてこられたのは、「残りの人生、自分の好きに生きる」「私が大好きになったお箏の音色を次の世代に残すための活動をしたい」という信念があったから。
実は32歳の時にお教室を立ち上げた時、お箏一本でやっていきたいという希望を持っていました。直後、バブル崩壊で不況となり、子どもが2人いますから、将来のことも考えて家計を支えるために断念。
その後も介護などさまざまなことが重なって、次々と心が折れそうになる出来事が降りかかりましたが、目の前の現実から逃げることなんてできないから、ただただ日々をどう過ごすのかを考えるだけの時期もあって、生活のために自分の好きなことができなくなるつらさも痛いほどわかっています。
だからこそ余計に、病気をして残りの人生を考えた時に思ったんです。もうこれ以上しんどいことはない。次は死ぬ時だから、悔いの残らないように自分の人生を生きようって。
それから11年が経ちました。今では経験や実績、評価がついてきたり、周囲の状況や環境が変わったりして、最初は懐疑的だったり否定的だったりした人たちからも、認めてもらえるようになっています。
誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きること。それこそが大事なんだと思っています。
自分自身でも「こういう世界だ」「こういうものだ」と思い続けてきましたから、それに背くことに対して最初は罪悪感がありました。
先生のお許しをいただいてからも、ルールを破った者としてそれまでの待遇とはがらりと変わりましたし、流派の関係者から「何がしたいの?」「新しいことばかりして、どこに向かおうとしているの?」「お稽古をした成果を聞いてもらうのに、有料でコンサートを開くなんて信じられない」といった辛辣なご意見をいただくこともありました。
また、家族の理解を得ることも課題でした。長年フルタイムの仕事をしながら、週末にお教室を開いていましたから、「お箏=好きなこと=趣味」と思われていたので、活発に活動するほどに「遊んでいる」と思われて活動しづらいところもあったんです。
それでも続けてこられたのは、「残りの人生、自分の好きに生きる」「私が大好きになったお箏の音色を次の世代に残すための活動をしたい」という信念があったから。
実は32歳の時にお教室を立ち上げた時、お箏一本でやっていきたいという希望を持っていました。直後、バブル崩壊で不況となり、子どもが2人いますから、将来のことも考えて家計を支えるために断念。
その後も介護などさまざまなことが重なって、次々と心が折れそうになる出来事が降りかかりましたが、目の前の現実から逃げることなんてできないから、ただただ日々をどう過ごすのかを考えるだけの時期もあって、生活のために自分の好きなことができなくなるつらさも痛いほどわかっています。
だからこそ余計に、病気をして残りの人生を考えた時に思ったんです。もうこれ以上しんどいことはない。次は死ぬ時だから、悔いの残らないように自分の人生を生きようって。
それから11年が経ちました。今では経験や実績、評価がついてきたり、周囲の状況や環境が変わったりして、最初は懐疑的だったり否定的だったりした人たちからも、認めてもらえるようになっています。
誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きること。それこそが大事なんだと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
学校に事務職員として勤めていた時、授業の一環としてお箏を教えさせてもらったり、幼稚園に演奏しにうかがったりしていて、退職後も何カ所か続けさせてもらっています。
途中、「関西山口県同郷会」事務局のスタッフを務めていた時期もあって、その時に山口県の知り合いがたくさんできたので、年1回、山口県内を巡るコンサートツアーを開催しています。
生活のためにお箏とは別の仕事をしなければならなかったのですが、それぞれで親しくなった人たちがコンサートに来てくださったり演奏に呼んでくださったりするなどつながっていて、生計を立てるための仕事とお箏の世界が交わって、これも私が生きてきた証だなあと思っています。
お箏一本でとなれたのは、つい最近のこと。この数年も積極的にさまざまなことに挑戦しながらも、実親が病気で倒れたり私が別の病気になったりと「なんで、こんなにも次々と試練が訪れるんだろう」の連続でしたが、そんな中でも続けてきた今が一番充実しています。
お箏を習い始めて50年、自分らしい活動は11年。まだまだ模索中ですが、自由な感性で歴史伝統とコラボして「琴感動 小森真理子ブランド」を確立させたいですね。
途中、「関西山口県同郷会」事務局のスタッフを務めていた時期もあって、その時に山口県の知り合いがたくさんできたので、年1回、山口県内を巡るコンサートツアーを開催しています。
生活のためにお箏とは別の仕事をしなければならなかったのですが、それぞれで親しくなった人たちがコンサートに来てくださったり演奏に呼んでくださったりするなどつながっていて、生計を立てるための仕事とお箏の世界が交わって、これも私が生きてきた証だなあと思っています。
お箏一本でとなれたのは、つい最近のこと。この数年も積極的にさまざまなことに挑戦しながらも、実親が病気で倒れたり私が別の病気になったりと「なんで、こんなにも次々と試練が訪れるんだろう」の連続でしたが、そんな中でも続けてきた今が一番充実しています。
お箏を習い始めて50年、自分らしい活動は11年。まだまだ模索中ですが、自由な感性で歴史伝統とコラボして「琴感動 小森真理子ブランド」を確立させたいですね。

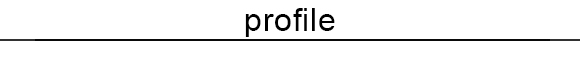
小森 真理子さん
8歳から箏を習い始める。高校時代には箏曲部を設立し、老人会や拘置所などでの演奏会も行っていた。子どもに関わる仕事がしたいと教育学科のある大学に進学し、小学校教諭一種免許状および幼稚園教諭一種免許状を取得。卒業後は高槻市立学童保育指導員として働き始める。1999年に師範となり、自宅で箏教室を開講。平日は小・中学校で事務職員として勤めながら、園児・児童・生徒に箏の指導にもあたるほか、休日は箏教室を開く生活を続けてきた。2007年に病気が発覚し、手術を経験。以降、「残りの人生はお箏を一般の人たちに知っていただく活動をしていきたい」との想いで、オリジナルのコンサート活動をスタート。現在は箏の演奏家として各地で演奏活動を行うほか、高槻市内で箏教室を2カ所開設、幼稚園や小・中学校での箏の指導も続けている。
HP: http://koto-kandou.com/
(取材:2019年1月)
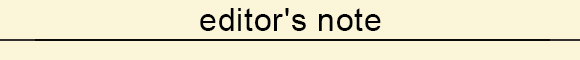
誰しも長年、同じ社会や組織にいると、習慣やしきたりに対して「?」と思うことがあっても、「こういうものだ」「しかたない」と思ってしまうものではないでしょうか。
自分が「こうしたらどうか」「こうだったらいいなあ」と思ったとしても、時に押さえ込んだり、隠したり、いつしか見失ってしまったりしてしまうことがありますが、行動を起こしてみることで、自分が思っていたよりもできることがあったり、世界は広いことがわかったりするのだと、小森さんのお話をうかがって思いました。
その一歩を踏み出すのも、そのまま自分が信じた道を突き進むのも、小森さんが「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」とおっしゃられるように、相当の覚悟と勇気が必要だとも思います。自分が思っていたような結果が必ず出るものでもありませんし、短期間で変わるわけでもありませんから。
その覚悟と勇気を持ち、乗り越えた小森さん。これまで「当たり前」と思っていたことを捉え直すことにもつながっていて、箏の歴史や古典の曲に今一度興味を持たれるなど、また新しい気持ちで箏の世界を楽しんでおられました。そんなご自身を「生まれ変わった」と表現されていたことも印象に残っています。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。