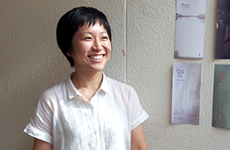HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
![]() 植木 美帆さん(チェリスト)
植木 美帆さん(チェリスト) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト)
植木 美帆さん(チェリスト)

| 植木 美帆さん (チェリスト)
兵庫県出身。チェリスト。大阪音楽大学音楽学部卒業。同大学教育助手を経てドイツ、ミュンヘンに留学。帰国後は演奏活動と共に、大阪音楽大学音楽院の講師として後進の指導にあたっている。「クラシックをより身近に!」との思いより、自らの言葉で語りかけるコンサートは多くの反響を呼んでいる。 チェリスト植木美帆オフィシャルサイト http://www.mihoueki.com/ |
| チェロを始めたのはいつですか? |
| 先にピアノを習っていましたが、中学生の頃、なにか違う楽器をやってみたいと思い、なんとなく母に勧められて。チェロがどんな楽器で、どんな音かも知りませんでしたが、チェロを習っている人が周りにいなかったことも逆に興味を惹いたのでしょうね。自宅近くに大阪音楽大学の講師をされていた先生がおられて、教えていただけることになったのですが、せっかくだから音楽大学を目指しましょうということになりました。 |
| チェロの音に初めて触れたときはどう感じましたか? |
| チェロという楽器は、人間の肉声に一番近いと言われています。高すぎず低すぎず、リラックスできるような「中低音」ですから、心地良いなと感じたと思います。コンサートでも、「すっと入ってきますね」と仰るお客様もおられますから、人間にとって魅力のある楽器なのかもしれませんね。 また、チェロには表板と裏板があって、弾いていると裏板がすごく振動するんです。身体とチェロが共鳴して、自分の声が楽器から出ているような感覚。真正面を向いて演奏するので、お客様と対話するような感じです。 |
| 音楽大学に入学後、音楽留学されました。 |
 音楽大学に入ると、より専門的なことを学びますが、そこに集まってくる人たちは皆、志を持ってこられた人たちばかり。先生方も志を全うされた方々なので、意識の高さに良い刺激を受けました。そしてさらに留学して外国に住むと言うことが良い鍛錬になりました。 音楽大学に入ると、より専門的なことを学びますが、そこに集まってくる人たちは皆、志を持ってこられた人たちばかり。先生方も志を全うされた方々なので、意識の高さに良い刺激を受けました。そしてさらに留学して外国に住むと言うことが良い鍛錬になりました。それまで親元にいましたが、留学となると外国で、全て一人でやっていかなくてはいけない。ドイツに着いたのが2月の寒い時期で、風邪をひいて喉が痛いということすら、言葉が通じない。これは本当に命がかかっていると思いましたね。 およそ2年半の留学でしたが、この期間を実りあるもののするには、まず言葉の勉強をしなくてはと、ものすごく頑張りました。 |
| 留学先にドイツを選ばれたのは? |
| 最初からドイツにこだわっていたわけではありませんが、自分に合う先生を探したくて、いろんな国の講習会でたくさんの先生を見て、その中で「この先生しかいない」と思った方がドイツにいらっしゃったので、行き先が決まりました。 その先生は、クラウス・シュトゥルク氏という著名なチェリストだったのですが、講習会の会場からすぐに家に電話して「ドイツに留学することに決めました」と言うと、「とりあえず一旦日本に帰ってきて」。そのまま帰って来ないんじゃないかと親が思うほどの勢いで、この先生に学びたい!と思ったんです。 |
| シュトゥルク氏に学びたいと思ったのはなぜですか? |
| まず、レッスンでの雰囲気作り、言葉の選び方に感心しました。音楽を学ぶことって、自分に足りないことを教えていただくわけですから、そうすると先生も力が入りすぎたり、その場の空気が重くなることもあります。それが、その先生のマジックというか、レッスンを受けると「ああ、もっと上手くなりたい」「音楽って楽しい」と思う気持ちを引き出してくれる先生だったんです。 この先生に学べば、自分は絶対に上手くなると確信しましたし、将来自分が教える立場になった時、やはり良いレッスンを受けないと、良いレッスンはできないと直感的に思いました。この先生に学び「音楽を生涯の仕事にしたい」と言う気持ちが固まりました。 |
| どういったところがご自身に「合う」と思われましたか? |
| 音楽を楽しむということは根底としてありますが、偉大な作曲家が残してくれた曲、例えばベートーベンなら、ベートーベンがこういう風に演奏して欲しいというところを汲み取ってそれを伝えていく。なんだか「巫女」みたいな感じですが、そこで「自分はこうすれば格好良く聴こえるから」ではなくて、根本的なところを表現しましょうと。そうすることで曲が本当に活きてきて、聞いてくださる方にも伝わり、自分の喜びになるというところです。 |
 |
| 「表現すること」を今、どのように取り入れておられますか? |
| 留学では演奏という表現のしかたを習ってきましたが、帰国後、がむしゃらに仕事をしてきた中で、曲を言葉で考えることが少なかったと思います。 ですが1年ほど前のコンサートで、ソナタを演奏するにあたり「皆さん、ソナタっでご存知ですか?」と聞いてみたんですね。するとほとんどの方が「冬のソナタ」なら知ってると(笑)「では、ソナタって何なのかご存知ですか?」と聞くと、「うーん、ちょっと説明できない」と仰るんです。 ソナタって簡単に言うと3つの柱があって、1つ目は主題を提示する部分、2つ目は先に提示された主題をもとに展開する部分、そして3つ目は、最初の主題を再現するのですが、ここで「これは最初に聞いたな」と思ってくださいねとお話をすると、すごく反響が良かったんです。 といっても、マイクを持って人前で話すことには抵抗があったんですね。演奏するほうがずっと気が楽なんですが、上手に話せなくても、聞いている人はアナウンサーと思って聞いているわけじゃないし、今から演奏する人が、その人の言葉で一生懸命伝えることが大事だから、達者に喋らないといけないと思わなくていいんじゃないと言ってくださった方もいて、すごくラクになりました。それから、コンサートの度にお話する時間をいただいています。 でもお客様にわかりやすく説明しようと思うと、すごく自分の中で考えるんですね。言葉を考えていく上で、自分の考えの根底のところに行き着いたりして、さらに理解が深まっていくこともあります。やはり人間は言語の動物だということがすごく腑に落ちましたね。 |
 |
| どのようなお話をされるのですか? |
| あるコンサートで、2人の作曲家、ドイツのシューマンとノルウェーのグリーグをご紹介したのですが、どちらも何となく聞いたことはあるけど、どこの国の人であるとか、どういう音楽であるかは、皆さんあまりご存知ないですね。 シューマンはトロイメライで有名ですねというと、ああ、なんか聴いたことあるというくらいで。ドイツにはカフェ文化というものがあり、画家や音楽家、哲学者など様々な人が集まっては何時間も過ごしたくらいお喋りが大好きです。なので音楽もすごく哲学的で、対人間として作曲されることが多いのです。 方やノルウェーはフィヨルドもあって圧倒的に自然の国なんですね。聞くところによると、日本と同じくらいの面積なのですが、なんと人口は横浜市と同じくらい。隣の家はものすごく遠くて、1週間も2週間も、家族以外と会わないこともあるそうです。なので音楽も対自然が多い。ということは、この2人の作曲家は根本的に大きく違いますね。 そういう話をコンサートですると、お客様は帰りに「私はグリーグ派でした」とか「私はシューマンが好き」など、それぞれに風景や情景を思い浮かべながら聞くことで、曲に国や作曲家のイメージをくっつけて楽しんでいただける。そうしたことで、楽曲をより深く理解して知識にしていただいて、それが教養ということになれば、私ができる、社会に価値を提供することになるのではないかと思っています。 |
| 大阪音楽大学音楽院でも教えておられますね |
| 教えるということも、ただこの曲を弾けるようにすることだけじゃなくて、より深いところで曲を理解して、自分の腹に落としてから弾けるようになってもらいたいと考えています。 たとえば三拍子と四拍子の拍子間など、ここにはこういう意味があるという知識を知っていると、ああそういうことかと目からうろこのような。自分の教え方というか、自分なりのメソッドを追求していきたいと思います。 |
| 演奏されることと教えること、思いを伝えることは同じですか? |
| 演奏することと教えることは全然違うように思われますが、根底は一緒だと思います。演奏するとき、特に練習しているときは、自分が自分の先生として、ここはこうしたらいいと、自分で考えていますが、教えるということは、それを他人にしていること。生徒には「自分で自分を教えられるようになりなさい」と言っています。 ここをチェックしておこうとか、こういうやり方があるとかを、たくさん引き出しに貯めていってねと。何年も使わなくても、いつか引き出して役立つときもあります。今日聞いてハイ終わり、じゃなくて、どんどん貯めていって引き出しを太らせてねと。 つまり、私は足りないことを教えることはできるけれど、やはり独立して私の元を去ってもらうことが仕事だと思っているので、いつまでも先生に頼らず、自分で考えていけるようになっていって欲しいと思っています。 |
| プロとなると「自分なり」のものを見つけなければいけないですね |
| やはり声色が皆違うように、十人十色なんですね。音楽は何が素晴らしいかというと、ファンタジーをどれだけ膨らませられるかなんです。ドイツで先生の最上級のほめ言葉が「ファンタスティック!」でした。 自分も含めてですが、音楽を学ぶにも、日本人は真面目で一生懸命なんですが、お行儀が良すぎる。そうすると聴いてて創造性が乏しいと言われるんです。指は動くし、達者なんだけど、ファンタジーが乏しいと。それに比べて海外の同世代の子たちを見ていると、すごく自由奔放。それが良いことも悪いこともありますが(笑) |
| 音楽の道を目指す方へメッセージをお願いします |
 完璧に技術を習得しないといけない時期も必要ですし、それがあったからこそ、自分が今こうして演奏できていると思っていますが、どういう表現をするかということは、最終的には自分で考えて結論だして納得することが大切だと思います。 完璧に技術を習得しないといけない時期も必要ですし、それがあったからこそ、自分が今こうして演奏できていると思っていますが、どういう表現をするかということは、最終的には自分で考えて結論だして納得することが大切だと思います。ドイツ留学時代、チェロだけでなくバイオリニストやピアニストなど他の楽器のコンサートにたくさん行きましたが、いろんな音楽を聴くことも必要ですし、一流の方がなぜ上手いのかを考えることも良いと思います。 また私は読書が大好きで、特に「生くる」執行草舟・著(講談社)は、人生の指針にしていますが、そう言った自分の軸になる本であったり、また歴史など生きる上で知恵を授けてくれる本も面白いです。読書は自分が体験できないことを客観的に感じることができますから、本を読むことによって知識や世界が膨らみ、仕事のみならず人生にも良い影響を及ぼすように思います。 |
| 将来の夢は何ですか? |
| 「自分がいなくなっても、世の中に生き続ける価値あるものを作り上げること」 です。生きた証が残り、それが後世の人々を豊かにし、または更に発展できる「基礎」を残したい。人生を燃焼することができたら、夢は叶う!と信じています。そしてその思いが自分を前進させています。 |
| ありがとうございました。 |
| (取材:2014年7月 関西ウーマン編集部) |
■関西ウーマンインタビュー(アーティスト) 記事一覧
-
「誰かに必要とされるかではなく、自分がやりたいかどうか」劇団に入団して24年。実力派女優の中田彩葉さん
-
「生きることと、音は直結する」生活と音楽のギャップに悩み、自分にできる音楽を表現する友加里さん
-
「人生そのものを演劇に。もっともっと自由に生きていい」演劇を通して自分の表現を見つめ続ける亜紀さん
-
「誰に何を言われようとも、自分が信念を持って生きることが大事」新しいお箏の世界を創る小森さん
-
「誰しもの中にいる小さな子どもが喜ぶ歌」を作り歌い続けることが自分の音楽というユカさん
-
「自分の心に100%の嘘は絶対につけない」音楽一家に生まれながらも、自分の音楽を見つけた黒田さん
-
「過去から現在、未来へとつながる流れの中に身を置く」薩摩琵琶に魅了され天職となった荻山 泊水さん
-
「なんとなく」ではなく「好き」と確信できることを 北欧の伝承音楽の演奏活動に取り組む上原さん
-
「フルートは人との出会いをくれる魔法のスティック」幅広いジャンルの音楽を演奏するフルート奏者の大塚さん
-
「歌うように、二胡を演奏する」喉を壊し、声楽家の道を断念するも、二胡奏者の道を選んだ一圓 さん。
-
「魂が響けば、身体は動いてくれる」障がい者にしかできない表現を追究する金滿里さん
-
「続けていれば新展開」音大卒業後、自分らしいスタイルを探して「ひとりおもちゃ楽団」に辿りついたアキさん
-
「自分の殻を破って、自分を解放する」ドラムや音楽を通して、「楽しい自分」を表現することを伝える藤谷さん
-
「誰もがその人自身のダンスを持っている」喜怒哀楽さまざまなダンスで対話を表現する高野さん
-
「自分の気持ちに素直に」出産を機に断念したジャズシンガーの道。子育てしながら再開の道をみつけた臼井さん。
-
「好き嫌いという次元のものではない」迷い悩んだ時期を経て、琵琶奏者として生きることが運命と決めた川村さん
-
手話から創作する「観る音楽」を身体で表現する「サインアーティスト」の三田さん。
-
「これが弾きたいと思ったら、とことんその世界をつきつめる」マリンバと民族音楽に惹かれ演奏家になった山本さん
-
「演奏家は目の前にいる人間を喜ばせること」教職から邦楽界へ。箏・三絃で京地唄を伝承する戸波さん
-
古典は実生活に役立つものでは無い。でも心は確実に豊かになります。源氏物語の語り部として活動する六嶋さん
-
「能管の響きが持つ力を伝えたい」一生を貫くものを探そうと能管に出会った野中さん。ご縁を繋げながら海外でも活躍中
-
「踊れなくなるまでずっと踊りたい」日本人というコンプレックスを超えてブラジルのエネルギーを伝えるみちるさん
-
「私なんて・・・と言わずに済む力を身につけないとプロじゃない」大学院で舞踊の博士号を目指す礼奈さん
-
「踊りたくなるような気分で帰っていただける、そんな舞台人になりたい」バレリーナ&指導者として活躍する有可さん
-
「「こうするもの」を超えて楽しむ」ことをNYで学んだ、パフォーミングアーティストとして活躍するちさとさん。
-
「いつも感受性を豊かにもち、ロマンチストでありたい」フルートに魅せられ数々のコンクールで入賞、現在はアンサンブルが楽しいと話す麻里子さん。
-
「"おおきに"という言葉を広げていきたい」元芸妓&JAZZシンガーの真箏さん。病気を克服し人の幸せを想い活躍中
-
「舞台は世界!」初主演映画がカンヌで絶賛を浴び、女優として活躍。京都でロングラン公演中の『ギア』ドール役として出演中の祐香さん
-
「教えることも歌うことも表現は同じ」シンガーとして数多くのステージに立ち、ボーカル講師でもある西潟さん
-
「クラシックをより身近に」自らの言葉で語りかけるコンサートが評判。国内外で活躍する美人チェリスト。