HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(起業家)
■関西ウーマンインタビュー(起業家)
![]() なかたにみさこさん(ひとまち元気カンパニー 代表)
なかたにみさこさん(ひとまち元気カンパニー 代表) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(起業家)
なかたにみさこさん(ひとまち元気カンパニー 代表)

幸せになれない仕組みがあるなら、それを変えたらいい
なかたにみさこさん
ひとまち元気カンパニー 代表
ひとまち元気カンパニー 代表
「『何屋さんですか?』と聞かれるのが困るんです」と話す、「ひとまち元気カンパニー」のなかたにみさこさん。
地域に貢献する人材育成や市民活動の支援、地域福祉計画策定の推進、休眠預金活用プロジェクト、対話を使ったセミナー、SDGs(持続可能な開発目標)推進のプラットフォームづくりなど、どんな仕事や活動をしているのかを端的に説明することが難しいほど多様な分野に関わっておられます。
これほどまでに多様な分野に関わるきっかけとは? 何が原動力になっているのでしょうか?
地域に貢献する人材育成や市民活動の支援、地域福祉計画策定の推進、休眠預金活用プロジェクト、対話を使ったセミナー、SDGs(持続可能な開発目標)推進のプラットフォームづくりなど、どんな仕事や活動をしているのかを端的に説明することが難しいほど多様な分野に関わっておられます。
これほどまでに多様な分野に関わるきっかけとは? 何が原動力になっているのでしょうか?
目の前にやってくるものに取り組んでいたら
同時進行でいくつもの仕事や活動に関わっておられます。現在に至るまでにもさまざまな仕事や活動に関わってこられたそうですが、その出発点はどこにあるのでしょうか?
止まったら死ぬという「マグロ」みたいやなと言われているんですが(笑)。振り返れば、子どもの頃から、夢や憧れ、興味、関心を持っていることがいくつもあり、それらに関わる活動を同時進行で行っていました。
子どもの頃の夢はアイドル。オーディション番組やイベントに参加してみたいと思う一方、「自分には無理かな」と思っていたところ、行き着いたのが某喜劇団でした。高校時代に劇団員募集を見つけて応募。「君はおもしろくない」と言われて入団こそできなかったものの、「台本作家になったらどうか」と声をかけられて一時期、出入りしていたことがあります。
小学生の時に母に連れられて参加したキャンプではキャンプリーダーに憧れ、大学時代には念願のキャンプリーダーになりました。大学卒業後も30代半ばまで、そのキャンプを主催する社会教育関係団体でボランティア活動を続けます。
私の仕事や活動の大きな軸になっている福祉についても、子どもの頃から関心を持っていたんです。中学時代、教室に畳のスペースがあって、重度障害のある子が一緒に学んでいましたし、キャンプでも障害のある子と一緒に活動していたからかなと思います。
そのほかにも、自分の母校に入学させようとする母のもとで勉強の日々、クリスチャンの母に連れられて教会に通い始める、中高大とバスケットボール部所属、大学時代にはボランティア活動など、いくつものいろんなことに取り組んできました。
子どもの頃の夢はアイドル。オーディション番組やイベントに参加してみたいと思う一方、「自分には無理かな」と思っていたところ、行き着いたのが某喜劇団でした。高校時代に劇団員募集を見つけて応募。「君はおもしろくない」と言われて入団こそできなかったものの、「台本作家になったらどうか」と声をかけられて一時期、出入りしていたことがあります。
小学生の時に母に連れられて参加したキャンプではキャンプリーダーに憧れ、大学時代には念願のキャンプリーダーになりました。大学卒業後も30代半ばまで、そのキャンプを主催する社会教育関係団体でボランティア活動を続けます。
私の仕事や活動の大きな軸になっている福祉についても、子どもの頃から関心を持っていたんです。中学時代、教室に畳のスペースがあって、重度障害のある子が一緒に学んでいましたし、キャンプでも障害のある子と一緒に活動していたからかなと思います。
そのほかにも、自分の母校に入学させようとする母のもとで勉強の日々、クリスチャンの母に連れられて教会に通い始める、中高大とバスケットボール部所属、大学時代にはボランティア活動など、いくつものいろんなことに取り組んできました。

子どもの頃から、さまざまなことに興味や関心を持つだけではなく、それらに関わる活動を同時進行で取り組んでこられたのですね。
大学卒業後はどんなふうに仕事や活動の幅を広げてこられたのでしょうか?
大学卒業後はどんなふうに仕事や活動の幅を広げてこられたのでしょうか?
「目の前にやってくるものに取り組んでいたらこうなっていた」という感じがしているので、自分で選んできたという意識はないんです。
大学卒業後からの大まかな職歴を話しますと、「内定をもらえた1社目のリゾート施設運営会社」「大学時代から手伝っていた母が起業した衣料品販売会社」「大学時代からボランティアを続けてきた社会教育関係団体」。
2008年に拠点を大阪府から、暮らしている奈良県に移した後は、これまでの仕事や活動を地域に活かしていけたらと、「ひとまち元気カンパニー」を立ち上げました。
並行して「社会教育関係団体に勤めていた時代に、広報面で協力関係にあった福祉団体を訪問。その時に見つけたチラシきっかけで、障害のある人がつくった商品のセールス・プロモーションや仕事受注などを担うセンター」「前職のセンターで出会った福祉団体に誘われ、障害者就業・生活支援センター」。
母が亡くなった2010年には、母の会社を経営上の事情で私が引き継がざるを得なくなり、以降は母の会社と「ひとまち元気カンパニー」の2つを軸として、仕事や活動に取り組んでいます。
「大まかな」としたのは、その先々で派生した仕事や活動があるからです。
たとえば、市報で見つけたまちづくりセミナーに参加したら、まちづくり団体と知り合い、一緒に奈良県でSDGsを推進するための協議会を立ち上げたり、参加していたメーリングリストをきっかけに休眠預金活用事業プロジェクトに関わることになり、生きづらさを抱える若者の支援に取り組んだり、友だちや大学の先輩から声をかけられてコミュニティFM放送のパーソナリティを務めたり。
そのほかにも、介護情報誌の制作、大学の非常勤講師、対話を使ったセミナーの講師など、同時進行でいろいろなことに関わってきました。
振り返って思うのは、それぞれの仕事や活動先で出会ったり聞いたり経験したりする中で、「こんな世界があるんだ」とインプットされたことが、次につながるきっかけになっているということです。
まちづくりセミナーに参加したのも、何の脈絡もなく参加したわけではなく、その前の職場で講座を企画した時に、たまたまたどり着いた講師が「まちづくり」に関わっていたので、そのキーワードがインプットされていました。
そんな小さなきっかけからつながってみたら、その先でいろいろな出会いや展開があり、どんどん深まったり広がったりしていったんです。
大学卒業後からの大まかな職歴を話しますと、「内定をもらえた1社目のリゾート施設運営会社」「大学時代から手伝っていた母が起業した衣料品販売会社」「大学時代からボランティアを続けてきた社会教育関係団体」。
2008年に拠点を大阪府から、暮らしている奈良県に移した後は、これまでの仕事や活動を地域に活かしていけたらと、「ひとまち元気カンパニー」を立ち上げました。
並行して「社会教育関係団体に勤めていた時代に、広報面で協力関係にあった福祉団体を訪問。その時に見つけたチラシきっかけで、障害のある人がつくった商品のセールス・プロモーションや仕事受注などを担うセンター」「前職のセンターで出会った福祉団体に誘われ、障害者就業・生活支援センター」。
母が亡くなった2010年には、母の会社を経営上の事情で私が引き継がざるを得なくなり、以降は母の会社と「ひとまち元気カンパニー」の2つを軸として、仕事や活動に取り組んでいます。
「大まかな」としたのは、その先々で派生した仕事や活動があるからです。
たとえば、市報で見つけたまちづくりセミナーに参加したら、まちづくり団体と知り合い、一緒に奈良県でSDGsを推進するための協議会を立ち上げたり、参加していたメーリングリストをきっかけに休眠預金活用事業プロジェクトに関わることになり、生きづらさを抱える若者の支援に取り組んだり、友だちや大学の先輩から声をかけられてコミュニティFM放送のパーソナリティを務めたり。
そのほかにも、介護情報誌の制作、大学の非常勤講師、対話を使ったセミナーの講師など、同時進行でいろいろなことに関わってきました。
振り返って思うのは、それぞれの仕事や活動先で出会ったり聞いたり経験したりする中で、「こんな世界があるんだ」とインプットされたことが、次につながるきっかけになっているということです。
まちづくりセミナーに参加したのも、何の脈絡もなく参加したわけではなく、その前の職場で講座を企画した時に、たまたまたどり着いた講師が「まちづくり」に関わっていたので、そのキーワードがインプットされていました。
そんな小さなきっかけからつながってみたら、その先でいろいろな出会いや展開があり、どんどん深まったり広がったりしていったんです。

「したいことができる」幸せを
さまざまな仕事や活動を広げていく原動力になっているものは何ですか?
「変えてもいい」と思っていることでしょうか。
私には「しょうがない」という言葉がありません。生きていて、「嫌だな」「おかしいな」と思ったら、変えたくなるんです。
私には「しょうがない」という言葉がありません。生きていて、「嫌だな」「おかしいな」と思ったら、変えたくなるんです。
これまでどんなふうに行動を起こしてこられたのでしょうか? その一例を教えてください。
私にとっての大きな軸になっている福祉のことでお話しします。
まず大きな出会いになったのは社会教育関係団体で、知的障害のある人たちを対象とした余暇活動事業を担当した時のことです。
この取り組みが始まった1970~1980年代というと、障害のある人は学校を卒業したら施設に入所するか、家で家事手伝いになるかという選択肢がほとんどでした。その現状を受けて当初、学校卒業後の選択肢を増やすための社会訓練の場として事業を行っていたんです。
その後、福祉施設が整備されていき、卒業後の選択肢が増えるなど社会の状況が変化してくると、社会訓練の場としての役割を終え、個々で遊びに出かけることが難しいという知的障害のある人に向けての、余暇活動の場としての事業に変わりました。
参加者もスタッフも支援する・されるの関係性なしに一緒に余暇を楽しもうと、全員が同額の活動費を支払うことにしていたのですが、その中で1人だけ、活動費を支払わない参加者がいたんです。
参加する以上は支払ってもらわなければ困るので、詳しく話を聞いてみると、給料が月1万円ほど、そこから昼食などの手当てを引かれるという、障害のある人の労働実態を知ることになりました。
その給料から活動費を支払うのはかなりの負担です。まずは稼ぐ支援をしなければ、遊ぶ支援なんてできないのではないか。そんな問題意識が生まれ、その社会教育関係団体で障害のある人の就労を支援したり改善をめざしたりする勉強会や講演会を企画し始めました。
紆余曲折があり、その社会教育関係団体を離れることになってしまいましたが、その後は障害のある人がつくった商品のセールス・プロモーションや仕事受注などを担うセンターに入職。そのセンターで、奈良県にある120カ所ほどの福祉施設の実態調査に関わったことで、障害のある人が稼げるビジネスモデルがないことに気がつきました。
福祉的就労において、障害のある人は自分たちがした仕事で出た利益を配分します。利益が増えなければ、給料が上がることはないわけですが、現場の様子を見ると、利益を増やそうにもなかなか難しい状況があるように感じました。
たとえば、福祉施設の職員は生活支援については学んできていますが、働く支援や商品のつくり方、マーケティング、セールス・プロモーションなどについては学んできていないことがほとんどです。
ビジネスモデルに問題があるということなので、新しいビジネスモデルを考える必要があるのではないか。私自身は、障害のある人たちが集まって働く福祉的就労より、障害のある人も含めて多様な人たちが働く環境をつくったり、一般就労を促進したりするほうがいいのではないかなと思ったんです。
いろいろ考えて提案などしてみるものの、その組織内でできることには限界がありました。
退職後、前職のセンターで知り合った福祉団体から声をかけられて、障害者就業・生活支援センターに入職。そこは障害のある人を対象にしたハローワークのようなところで、就労支援相談員として地域に暮らす障害のある人をどう仕事につなぐかについて知恵を絞っていました。
その矢先、母の会社を引き継がなければならなくなり、途中で辞めることになってしまったんです。
まず大きな出会いになったのは社会教育関係団体で、知的障害のある人たちを対象とした余暇活動事業を担当した時のことです。
この取り組みが始まった1970~1980年代というと、障害のある人は学校を卒業したら施設に入所するか、家で家事手伝いになるかという選択肢がほとんどでした。その現状を受けて当初、学校卒業後の選択肢を増やすための社会訓練の場として事業を行っていたんです。
その後、福祉施設が整備されていき、卒業後の選択肢が増えるなど社会の状況が変化してくると、社会訓練の場としての役割を終え、個々で遊びに出かけることが難しいという知的障害のある人に向けての、余暇活動の場としての事業に変わりました。
参加者もスタッフも支援する・されるの関係性なしに一緒に余暇を楽しもうと、全員が同額の活動費を支払うことにしていたのですが、その中で1人だけ、活動費を支払わない参加者がいたんです。
参加する以上は支払ってもらわなければ困るので、詳しく話を聞いてみると、給料が月1万円ほど、そこから昼食などの手当てを引かれるという、障害のある人の労働実態を知ることになりました。
その給料から活動費を支払うのはかなりの負担です。まずは稼ぐ支援をしなければ、遊ぶ支援なんてできないのではないか。そんな問題意識が生まれ、その社会教育関係団体で障害のある人の就労を支援したり改善をめざしたりする勉強会や講演会を企画し始めました。
紆余曲折があり、その社会教育関係団体を離れることになってしまいましたが、その後は障害のある人がつくった商品のセールス・プロモーションや仕事受注などを担うセンターに入職。そのセンターで、奈良県にある120カ所ほどの福祉施設の実態調査に関わったことで、障害のある人が稼げるビジネスモデルがないことに気がつきました。
福祉的就労において、障害のある人は自分たちがした仕事で出た利益を配分します。利益が増えなければ、給料が上がることはないわけですが、現場の様子を見ると、利益を増やそうにもなかなか難しい状況があるように感じました。
たとえば、福祉施設の職員は生活支援については学んできていますが、働く支援や商品のつくり方、マーケティング、セールス・プロモーションなどについては学んできていないことがほとんどです。
ビジネスモデルに問題があるということなので、新しいビジネスモデルを考える必要があるのではないか。私自身は、障害のある人たちが集まって働く福祉的就労より、障害のある人も含めて多様な人たちが働く環境をつくったり、一般就労を促進したりするほうがいいのではないかなと思ったんです。
いろいろ考えて提案などしてみるものの、その組織内でできることには限界がありました。
退職後、前職のセンターで知り合った福祉団体から声をかけられて、障害者就業・生活支援センターに入職。そこは障害のある人を対象にしたハローワークのようなところで、就労支援相談員として地域に暮らす障害のある人をどう仕事につなぐかについて知恵を絞っていました。
その矢先、母の会社を引き継がなければならなくなり、途中で辞めることになってしまったんです。

1つのきっかけから知った現実、そこから問題意識や課題解決のための方法を考えてこられたのですね。
やむを得ない事情でお母さまの会社を引き継ぐことになり、障害者就業・生活支援センターを退職されましたが、以降の仕事や活動において、福祉分野でのそれまでの経験を活かしてされていることはありますか?
やむを得ない事情でお母さまの会社を引き継ぐことになり、障害者就業・生活支援センターを退職されましたが、以降の仕事や活動において、福祉分野でのそれまでの経験を活かしてされていることはありますか?
今はまちづくりに関わる中で、話し合いの場に障害のある人など多様な人たちに参加してもらえるように声をかけるなど、多様な視点を取り入れるように意識しています。
長年、障害のある人に関わってきたということもありますが、キャンプリーダー時代に、多様な人たちが存在することの大切さを実感した経験もあったからです。
その経験というのは、グループの中にハンディキャップのあるメンバーがいた場合、子どもたちが自主的に「その子がどうしたら参加できるか」を考え、互いに支え合う関係性ができていたこと。
一人ひとりが自力で何とかできる状態だったら、他人とつながる意味がないので分断しか起きないように思います。それぞれに得意・不得意なことがあり、それが共有されることでつながる力になるのだと、その時に実感しました。
私が言う「障害」とは、個人側にあるものではなく、社会側にあるものを意味しています。その社会や地域に存在する「誰かにとっての障害」を明らかにし、解消していくことにより、多くの人たちにとって生きやすい社会になるのではないかと考えているんです。
長年、障害のある人に関わってきたということもありますが、キャンプリーダー時代に、多様な人たちが存在することの大切さを実感した経験もあったからです。
その経験というのは、グループの中にハンディキャップのあるメンバーがいた場合、子どもたちが自主的に「その子がどうしたら参加できるか」を考え、互いに支え合う関係性ができていたこと。
一人ひとりが自力で何とかできる状態だったら、他人とつながる意味がないので分断しか起きないように思います。それぞれに得意・不得意なことがあり、それが共有されることでつながる力になるのだと、その時に実感しました。
私が言う「障害」とは、個人側にあるものではなく、社会側にあるものを意味しています。その社会や地域に存在する「誰かにとっての障害」を明らかにし、解消していくことにより、多くの人たちにとって生きやすい社会になるのではないかと考えているんです。
それぞれでの経験や実感が、次、また次の仕事や活動の中で活きていくのですね。なかたにさんが「変えたくなるもの」には、何か共通点がありますか?
私が自分のミッションと思っていることは、目の前の人の可能性を信じ、幸せをサポートし、自分以外への貢献へとつないでいくことです。
前提として「すべての人は幸せになるために生まれてきた」ということが、私の中に確信としてあります。クリスチャンの母に連れられて通った教会で教わったことが、自分の中に自然に入っているのかなと思います。
また、幸せになるためには「自分がしたいことをすることがいい」とも考えています。これはキャンプリーダー時代に、子どもたちが決められたプログラムをこなしている時よりも、自由時間のほうがイキイキとしていたからです。
私自身「フリーキャンプ」に参加して、自分の興味や関心を起点に、したいことに取り組むことで、心が喜ぶと教わりました。
すべての人が幸せを感じられる社会じゃないとだめだと思っているので、それを阻害するものは変えたくなると言いますか、変えていけるのではないかなと思うんです。
そうは言っても難しいことは多くあります。
たとえば、地元の自治会会長を務めていた時、入会者は少ないし、役員になりたくないとの声も多かったので、「自治会の仕組みを変えたらいいんじゃないですか?」など提案しましたが、結局は何も変わりませんでしたし、きっと「うるさい人が来た」と思われているとも思うんですけど(笑)。
幸せになれない仕組みがあるなら、それを変えたらいいんじゃないかなと動いてしまうんです。
前提として「すべての人は幸せになるために生まれてきた」ということが、私の中に確信としてあります。クリスチャンの母に連れられて通った教会で教わったことが、自分の中に自然に入っているのかなと思います。
また、幸せになるためには「自分がしたいことをすることがいい」とも考えています。これはキャンプリーダー時代に、子どもたちが決められたプログラムをこなしている時よりも、自由時間のほうがイキイキとしていたからです。
私自身「フリーキャンプ」に参加して、自分の興味や関心を起点に、したいことに取り組むことで、心が喜ぶと教わりました。
すべての人が幸せを感じられる社会じゃないとだめだと思っているので、それを阻害するものは変えたくなると言いますか、変えていけるのではないかなと思うんです。
そうは言っても難しいことは多くあります。
たとえば、地元の自治会会長を務めていた時、入会者は少ないし、役員になりたくないとの声も多かったので、「自治会の仕組みを変えたらいいんじゃないですか?」など提案しましたが、結局は何も変わりませんでしたし、きっと「うるさい人が来た」と思われているとも思うんですけど(笑)。
幸せになれない仕組みがあるなら、それを変えたらいいんじゃないかなと動いてしまうんです。
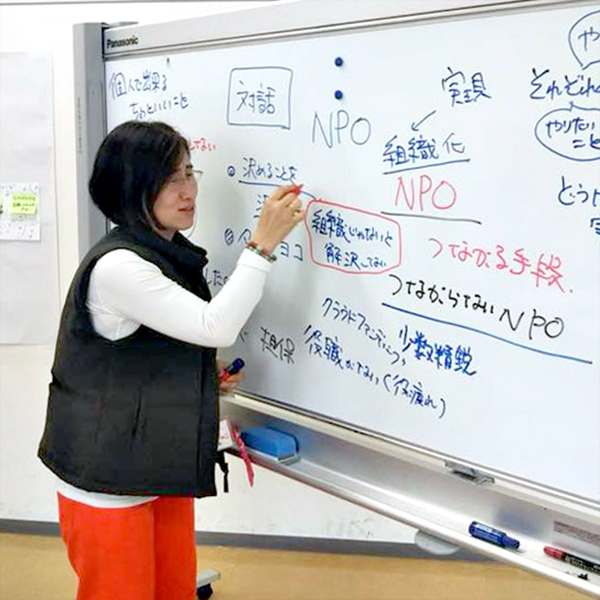
「こうじゃなきゃ」という執着を手放す
さまざまな仕事や活動、さまざまな人たちに関わりながら取り組む中での、「壁」または「悩み」はありましたか?
プロジェクトに応じてさまざまな団体や個人とつながって仕事や活動に取り組んでいるので、さまざまな考えや意見、フィードバックを受けます。
中には、「あなたは間違っているのよ」と自分の正義を振りかざしたり、「これまでの経験によると、こうするといいのに」と過去の成功体験を押し付けたりする人もいました。
それをどう受け止めるかが大事だなと思います。
「だから、私はだめなんだ」「私が間違っていたんだ」と自分の中にいる裁判官を発動させて、自分の存在や能力、してきたことをジャッジし、自分で自分を傷つけてしまうことがあると気がついたんです。
その人が言うことが正しいことではありませんし、個人の成功体験がどの事例でも有効ならば苦労することはありません。
「その人には私が間違っているように見えるんだ」「その人はこの方法で『成功した』と思った経験があるんだ」という事実があるだけ。「この人はこう思うんだ」という事実を受け止めて、参考になりそうなことは取り入れたらいいくらいのことだと思うようにしました。
中には、「あなたは間違っているのよ」と自分の正義を振りかざしたり、「これまでの経験によると、こうするといいのに」と過去の成功体験を押し付けたりする人もいました。
それをどう受け止めるかが大事だなと思います。
「だから、私はだめなんだ」「私が間違っていたんだ」と自分の中にいる裁判官を発動させて、自分の存在や能力、してきたことをジャッジし、自分で自分を傷つけてしまうことがあると気がついたんです。
その人が言うことが正しいことではありませんし、個人の成功体験がどの事例でも有効ならば苦労することはありません。
「その人には私が間違っているように見えるんだ」「その人はこの方法で『成功した』と思った経験があるんだ」という事実があるだけ。「この人はこう思うんだ」という事実を受け止めて、参考になりそうなことは取り入れたらいいくらいのことだと思うようにしました。
多様な人たちと関わることは、それだけ多様な意見を受けるということ。確かに、他人から何かを言われた時、その内容ではなく、「だから、私はだめなんだ」と思って落ち込んでしまうことや傷ついてしまうことがあります。
事実として受け止めることによって、自分で自分を傷つけませんし、冷静に意見やアイデアなどとして受け取ることもできますね。
事実として受け止めることによって、自分で自分を傷つけませんし、冷静に意見やアイデアなどとして受け取ることもできますね。
もう一つ、「結局は一人なんだ」という意識や強さを持っていないと乗り越えられないことがあります。さまざまな人たちが関わるほどに、一人ひとりそれぞれに事情を抱えていますし、状況も変わっていくものだからです。
たとえば、最初は同じくらいの想いや熱量で取り組んでいても、途中で「プロジェクトをやめたい」などメンバー間に温度差が出てくることがあります。
お互いに「やめたい」で一致すればいいのですが、こちらに「続けたい」という気持ちがある場合、相手に対して「なんで?」と思ってしまうんです。
その「なんで?」という言葉には、相手がそう思い至った理由を知りたいというより、「なんで、こんな途中で?」と腹を立てている気持ちのほうが多く含まれていることがあります。
そうなると、関係性を悪くしてしまいますし、今後会う時も気まずくなってしまいます。そういう人に限って、また会ってしまうんです。
そこで、相手にも自分にも「このプロジェクトをやらなければならない」「このメンバーでずっとしなければならない」と縛らないようにしています。「メンバー」と「そうじゃない人」という分断もつくらず、「去る者は追わず」の精神で自由度を持たせた関係性がいいのではないかなと思うんです。
「こうだ」と思った時から執着が生まれてしまうのは、自分自身の在り方にも言えることかもしれません。
たとえば、最初は同じくらいの想いや熱量で取り組んでいても、途中で「プロジェクトをやめたい」などメンバー間に温度差が出てくることがあります。
お互いに「やめたい」で一致すればいいのですが、こちらに「続けたい」という気持ちがある場合、相手に対して「なんで?」と思ってしまうんです。
その「なんで?」という言葉には、相手がそう思い至った理由を知りたいというより、「なんで、こんな途中で?」と腹を立てている気持ちのほうが多く含まれていることがあります。
そうなると、関係性を悪くしてしまいますし、今後会う時も気まずくなってしまいます。そういう人に限って、また会ってしまうんです。
そこで、相手にも自分にも「このプロジェクトをやらなければならない」「このメンバーでずっとしなければならない」と縛らないようにしています。「メンバー」と「そうじゃない人」という分断もつくらず、「去る者は追わず」の精神で自由度を持たせた関係性がいいのではないかなと思うんです。
「こうだ」と思った時から執着が生まれてしまうのは、自分自身の在り方にも言えることかもしれません。
「自分自身の在り方にも言える」とは?
「私はこうです」「私の仕事はこれです」としてしまった瞬間に、「こうじゃなきゃ」という執着が生まれる気がします。そのままではうまくいかなくなってきているのに、その執着をなかなか手放せなくなってしまうことがあるように思うんです。
新型コロナウイルス感染症の影響で社会が大きく変わっていく中でも、柔軟に変化していける企業とそうでない企業がありました。その様子を見ていると、何屋さんにこだわらずにいることが、これからの時代はますます重要になってくるのではないかなと感じるんです。
私の場合は気がついたら、こうなっていただけなのですが(笑)。「何屋さん」であるかより、自分は何をしたいのか、自分の喜びはどこにあるのかのほうが大事。
その表現方法の一つが仕事であり、活動であるだけだから、どう表現するかについては一つの方法に執着せず、その時々で柔軟に変えていってもいいのではないかなと思うんです。
新型コロナウイルス感染症の影響で社会が大きく変わっていく中でも、柔軟に変化していける企業とそうでない企業がありました。その様子を見ていると、何屋さんにこだわらずにいることが、これからの時代はますます重要になってくるのではないかなと感じるんです。
私の場合は気がついたら、こうなっていただけなのですが(笑)。「何屋さん」であるかより、自分は何をしたいのか、自分の喜びはどこにあるのかのほうが大事。
その表現方法の一つが仕事であり、活動であるだけだから、どう表現するかについては一つの方法に執着せず、その時々で柔軟に変えていってもいいのではないかなと思うんです。

「出会うべきものがある」という予感
近い将来、実現したいことを教えてください。
具体的には2つ、考えていることがあります。
1つは、奈良県でSDGsを推進すること。
SDGsの取り組みに関する全国調査によると、奈良県は下から2番目でした。まずは企業に周知し、取り組んでもらうためのプラットフォームをつくりたいと動いています。
同時に、何かに取り組むには資金が必要になってくるので、自分たちのまちの取り組みには自分たちのまちで資金を用意できるように、コミュニティ財団をつくりたいとも考えているところです。
もう1つは、リトリートハウスをつくること。
今の世の中、忙しく生きている人が多いです。そんな人たちが日常から離れて、自分の想いや考えにつながって自分自身に還ることのできる、非日常スペースが必要ではないかなと思っています。
1つは、奈良県でSDGsを推進すること。
SDGsの取り組みに関する全国調査によると、奈良県は下から2番目でした。まずは企業に周知し、取り組んでもらうためのプラットフォームをつくりたいと動いています。
同時に、何かに取り組むには資金が必要になってくるので、自分たちのまちの取り組みには自分たちのまちで資金を用意できるように、コミュニティ財団をつくりたいとも考えているところです。
もう1つは、リトリートハウスをつくること。
今の世の中、忙しく生きている人が多いです。そんな人たちが日常から離れて、自分の想いや考えにつながって自分自身に還ることのできる、非日常スペースが必要ではないかなと思っています。
これからも、さまざまなことにつながって広げたり深めたりされていかれるのですね。今のなかたにさんにとって、「心が喜ぶこと」とはどんなことでしょうか?
「自分がしたいことを、したい人たちとできること」もそうですし、「今まで知らなかったことに出会えること」でしょうか。あと、学ぶことも好きなんです。
自分がまだまだ知らない世界があって、そこで出会うべきものがあるんだろうなと感じています。
自分がまだまだ知らない世界があって、そこで出会うべきものがあるんだろうなと感じています。
なかたに みさこさん
大学卒業後から企業や大学、社会教育関係団体、福祉団体、まちづくり団体などで、さまざまな仕事や活動に携わる。2008年に「ひとまち元気カンパニー」を立ち上げ。現在は同カンパニー代表として、福祉やまちづくり、市民活動などの仕事や活動に携わるほか、株式会社サン・ナカタニ代表取締役、一般社団法人地域づくり支援機構理事なども務めている。
HP: https://hitomachigenki.jimdofree.com/
FB: https://www.facebook.com/hitomatigenki
(取材:2020年10月)
なかたにさんがこれほどまでに多様な仕事や活動に取り組むきっかけは、興味や関心を持ったこと、会社での配属、やむを得ない事情で関わったこと、知り合った方からの誘いなどさまざまでした。
その先々で「この現状をどうにかできないか」「こうしたらいいのでは」と動いてこられたことで、それぞれの分野について深めていくことにつながっておられましたし、それぞれでの知識や経験を仕事や活動の領域を超えて活かしておられました。
柔軟に仕事や活動に取り組んでいけるのも、目標が「こんな仕事をしたい」「こんな活動をしたい」と絞ったものではなく、「目の前の人の可能性を信じ、幸せをサポートし、自分以外への貢献へとつないでいくこと」という広くて大きなものだから。その広くて大きな目標に、さまざまな方法で向かっておられるのだと思います。
最後に、「自分がしたいことをすることがいい」について、なかたにさんからいただいたメッセージを紹介します。
「『したいことがないんです。どうしたらいいんですか?』という人もいますし、『何をしてもいい』と言われることのほうが苦痛という人もいます。何か探さなきゃと焦らなくてもいいと思います。自分の心がこんなことで喜んでいるなという発見を大切にして、自分がしたいことが思い浮かぶまで待つのも一つではないでしょうか」
HP: 『えんを描く』
その先々で「この現状をどうにかできないか」「こうしたらいいのでは」と動いてこられたことで、それぞれの分野について深めていくことにつながっておられましたし、それぞれでの知識や経験を仕事や活動の領域を超えて活かしておられました。
柔軟に仕事や活動に取り組んでいけるのも、目標が「こんな仕事をしたい」「こんな活動をしたい」と絞ったものではなく、「目の前の人の可能性を信じ、幸せをサポートし、自分以外への貢献へとつないでいくこと」という広くて大きなものだから。その広くて大きな目標に、さまざまな方法で向かっておられるのだと思います。
最後に、「自分がしたいことをすることがいい」について、なかたにさんからいただいたメッセージを紹介します。
「『したいことがないんです。どうしたらいいんですか?』という人もいますし、『何をしてもいい』と言われることのほうが苦痛という人もいます。何か探さなきゃと焦らなくてもいいと思います。自分の心がこんなことで喜んでいるなという発見を大切にして、自分がしたいことが思い浮かぶまで待つのも一つではないでしょうか」

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(起業家) 記事一覧
-
「たくさんの失敗の上に失敗しないレシピが生まれる」味付けアドバイザーとしておいしい家庭料理を広げる魚森さん
-
「幸せになれない仕組みがあるなら変えたらいい」地域貢献や福祉計画など多様な分野に関わるなかたにさん
-
「私が歩いた道が、道になる」思い立ったら即行動。地域社会のためにさまざまなプロジェクトを展開する下田さん。
-
「切り花から始まって行き着く先は森」ひらめきからスタートして30年。植物と共に歩む八田さん
-
「ヌード撮影は女性が生まれ変わるきっかけ」200人以上の女性の人生の転機にヌード撮影をしてきた中田さん
-
「手のひらにのる「ドイツ」を届けたい」ドイツの木工芸品やクリスマス雑貨の魅力を伝える藤井さん
-
「おせっかいが出発点だった」オフィス街のビルの屋上に作った「空庭」から六次産業サポートする山内さん
-
「かかりつけの写心屋さんでありたい」柳田さんと多賀さんのお二人で始めた家族写真専門のスタジオ
-
「やりたいことをやらないことが一番もったいない」子どもたちの真のやる気と情熱を育てる古賀さん
-
「今ここ、自分にできる精一杯のことをすれば無敵」さまざまなジャンルのイベントで出会いをつなぐ四方さん
-
「自分の想いの量が、仕事になっていく」10年のキャリアを持つ看護師から、「産後ケア」で起業された間宮さん
-
「素晴らしい庭には、人生をも変える力がある」独自の視点で日本庭園の魅力を伝える烏賀陽さん
-
「子どもは大人が焦らなくとも自らグングン伸びる」お受験講師から転身。幼児教室を営む上杉さん
-
「シェアハウスは暮らし方の提案を含めた事業」オリジナルでユニークなシェアハウスを運営する井上さん
-
「自己実現だけでなく、応援される人になってほしい」キャリアモチベーターとして女性起業家を支援する山田さん
-
「アートを体験が人々の視点を変えていく」地域密着型のアートプロジェクトを手掛ける柳本さん。
-
「とりあえずやってみろ精神。それが何よりも近道」韓国のデザイン雑貨に魅かれて起業した松田さん
-
「ひとつづつ乗越えていく。10年やるとなんとかなる」アルバイトから会社設立。学会の事務局業務を請け負う林さん
-
「こだわりのぶどうを作る主人の想いを伝えたい」農家に嫁ぎ、ご主人と共にぶどう畑とワイン作りに励む仲村さん
-
「外国人の目線で話す会話から今までにない発想が生まれる」アメリカ人のご主人と「カフェ英会話」を運営する瑞穂さん
-
「英語はチャンスを掴むツール。大事な時間を英語に取られるのはもったいない」こども塾を運営する岡田さん
-
「京都にほっこり癒されて欲しい」京都を舞台に1人1人に合った癒しの旅を案内する眞由美さん
-
関西出身で大学から東京で23年。お子さんが産まれて関西へ帰ることを機にコーチとして独立された小川さん
-
「茶葉を引き出すことはコーチングと同じ」京都造形芸術大学のラーニングカフェで学生たちに「紅茶の教室」をされている原野さん



































