HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(起業家)
■関西ウーマンインタビュー(起業家)
![]() 烏賀陽 百合さん(ガーデンデザイナー/日本庭園案内人)
烏賀陽 百合さん(ガーデンデザイナー/日本庭園案内人) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(起業家)
烏賀陽 百合さん(ガーデンデザイナー/日本庭園案内人)

素晴らしい庭には、人生をも変える力がある
烏賀陽 百合さん
ガーデンデザイナー/日本庭園案内人
ガーデンデザイナー/日本庭園案内人
石萌えする庭、紅葉や苔の美しい庭、親子三代の想いをつなぐ庭、泣ける庭、生き方をも変えてしまう庭・・・独自の視点で、京都にある日本庭園を案内する烏賀陽百合さん。
ガーデンデザイナーとして主に西洋庭園のデザインを手掛けながら、何をきっかけに日本庭園案内人の仕事をされるようになったのでしょうか? 烏賀陽さんにとって、日本庭園の魅力とは?
ガーデンデザイナーとして主に西洋庭園のデザインを手掛けながら、何をきっかけに日本庭園案内人の仕事をされるようになったのでしょうか? 烏賀陽さんにとって、日本庭園の魅力とは?
庭オタク&歴史好きがつながって
技術翻訳・取扱説明書制作から庭に関する仕事へ。何がきっかけだったのですか?
音楽からインスピレーションを受けて、音楽に合わせた庭をつくり、それを見た人たちが癒される・・・チェロ奏者のヨーヨー・マとガーデンデザイナーのジュリー・M・メサビーがコラボした『ミュージック・ガーデン』のドキュメンタリーを観た時、私もやっぱり庭に関わる仕事をしたいと思い立ったんです。
子どもの頃から母が庭で花やハーブを育てたり、その庭の花を部屋に飾ったりハーブを料理に使ったり、高校時代にはワンダーフォーゲル部で先生からさまざまな高山植物を教えてもらったりと、庭や植物と親しんできました。
社会人になって、イギリスでガーデンショーを見た時には「庭をつくる仕事があるんだ」「自分が好きなことを仕事にできる!」と大発見したような気持ちになったものの、すぐには決断できず・・・そんな私の背中を押してくれたのが、あのドキュメンタリーです。
30代を前にして「今だ!」とばかりに、国内外の園芸学校で専門的に植物や庭のデザインについて学びました。現在はガーデンデザインや庭イベントのプロデュース、寄せ植え教室の講師のお仕事をしています。
子どもの頃から母が庭で花やハーブを育てたり、その庭の花を部屋に飾ったりハーブを料理に使ったり、高校時代にはワンダーフォーゲル部で先生からさまざまな高山植物を教えてもらったりと、庭や植物と親しんできました。
社会人になって、イギリスでガーデンショーを見た時には「庭をつくる仕事があるんだ」「自分が好きなことを仕事にできる!」と大発見したような気持ちになったものの、すぐには決断できず・・・そんな私の背中を押してくれたのが、あのドキュメンタリーです。
30代を前にして「今だ!」とばかりに、国内外の園芸学校で専門的に植物や庭のデザインについて学びました。現在はガーデンデザインや庭イベントのプロデュース、寄せ植え教室の講師のお仕事をしています。

日本庭園案内人として活躍され、本も出版していますね。どうして、日本庭園に注目したのですか?
今でこそ、自称「日本庭園オタク」ですが、生まれも育ちも京都でありながら、淡路の園芸学校に通うまでは行ったことがなかったんです。
日本庭園史の授業をきっかけに、京都のあらゆる日本庭園を見てまわるようになりました。海外の庭園も多く見ましたが、その中でも日本庭園は魅力的。日本の文化や歴史、価値観、美意識が宿っています。
石を「まるで滝を鯉がのぼっているようだ」と見立てて登龍門として配置するなど、自然にあるそのままの石や白砂、苔、木、草花で、極楽浄土や禅の教えを表してしまう表現力。
見る者によって「どんなメッセージが込められているのだろう?」と想像を広げられる余白のあるデザイン。どんな人が庭をつくったのかがわかれば、趣味趣向やメッセージも浮かび上がるおもしろさ。
石なんて、何千年、何億年も前から地球上に存在していたかもしれませんから、その石を通して大昔とつながることも・・・日本庭園の話をし出したら、つきません(笑)。
大学では日本文化史を専攻するほど、昔の人の風習や暮らしを調べるのも想像するのも好きだったので、庭オタク&歴史好きがつながったのだと思います。
最初は「海外の旅行者を案内してほしい」という依頼がきっかけでしたが、今では仕事の柱の1つです。
日本庭園史の授業をきっかけに、京都のあらゆる日本庭園を見てまわるようになりました。海外の庭園も多く見ましたが、その中でも日本庭園は魅力的。日本の文化や歴史、価値観、美意識が宿っています。
石を「まるで滝を鯉がのぼっているようだ」と見立てて登龍門として配置するなど、自然にあるそのままの石や白砂、苔、木、草花で、極楽浄土や禅の教えを表してしまう表現力。
見る者によって「どんなメッセージが込められているのだろう?」と想像を広げられる余白のあるデザイン。どんな人が庭をつくったのかがわかれば、趣味趣向やメッセージも浮かび上がるおもしろさ。
石なんて、何千年、何億年も前から地球上に存在していたかもしれませんから、その石を通して大昔とつながることも・・・日本庭園の話をし出したら、つきません(笑)。
大学では日本文化史を専攻するほど、昔の人の風習や暮らしを調べるのも想像するのも好きだったので、庭オタク&歴史好きがつながったのだと思います。
最初は「海外の旅行者を案内してほしい」という依頼がきっかけでしたが、今では仕事の柱の1つです。

自然や植物、庭が持つ力を伝えるために
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
庭や植物が持つ魅力や美しさをどうおもしろく、わかりやすく伝えることができるかと、伝え方で苦しみました。
たとえば、寄せ植え教室を始めた当初、私にとって植物を育てたり土をいじったりすることは楽しいことだから、みなさんにも一人ひとりそれぞれの楽しみを見つけてほしいと解説は控えめにしていたんです。
すると、受講後のアンケートで、「ほったらかしにされた」「『自由にやってほしい』と言うが、どうしたらいいのかわからない」という声が。
自分が楽しいと思っているだけでは熱量は伝わらない。私がどこをおもしろい、良いと思っているのかを伝えないとダメなんだと気づきました。
「私はこの花のこんなところがいいと思ったから、今回選びました」「私がこの植物を育てている時、こんなところで苦労したので気をつけてください」「庭のここに私の萌えるポイントがあります」と私が感じたり思ったり考えたりしたポイントを話すようにしました。
そうするうち、私の仕事は人を楽しませる要素が強い、エンターテイメントではないかと思うようになったんです。
たとえば、寄せ植え教室を始めた当初、私にとって植物を育てたり土をいじったりすることは楽しいことだから、みなさんにも一人ひとりそれぞれの楽しみを見つけてほしいと解説は控えめにしていたんです。
すると、受講後のアンケートで、「ほったらかしにされた」「『自由にやってほしい』と言うが、どうしたらいいのかわからない」という声が。
自分が楽しいと思っているだけでは熱量は伝わらない。私がどこをおもしろい、良いと思っているのかを伝えないとダメなんだと気づきました。
「私はこの花のこんなところがいいと思ったから、今回選びました」「私がこの植物を育てている時、こんなところで苦労したので気をつけてください」「庭のここに私の萌えるポイントがあります」と私が感じたり思ったり考えたりしたポイントを話すようにしました。
そうするうち、私の仕事は人を楽しませる要素が強い、エンターテイメントではないかと思うようになったんです。
日本庭園案内人や講師の仕事は「エンターテイメント」。それはどういうことでしょうか?
庭園案内や教室にお越しくださるみなさんは、休日に、わざわざ費用を払って、参加してくれています。
仕事や家庭などでストレスを抱え、日常を離れて「楽しみたい」「癒されたい」という思いをお持ちの方も多い。
そんな人たちが、ほっと癒されるような、「ああ、楽しかった。今日一日、いいことがあった!」と気が晴れるような時間になればと思っています。
癒しの部分は自然や植物、庭が担ってくれるので、私はそれらが持つ力を感じられるようにお話したり、一人ひとりがゆっくりと向き合う時間を設けたりするだけです。
仕事や家庭などでストレスを抱え、日常を離れて「楽しみたい」「癒されたい」という思いをお持ちの方も多い。
そんな人たちが、ほっと癒されるような、「ああ、楽しかった。今日一日、いいことがあった!」と気が晴れるような時間になればと思っています。
癒しの部分は自然や植物、庭が担ってくれるので、私はそれらが持つ力を感じられるようにお話したり、一人ひとりがゆっくりと向き合う時間を設けたりするだけです。

癒され、自らの生きる力を取り戻す
烏賀陽さんにとって「癒し」が一つの大切なテーマになっている気がします。
私自身が庭に癒されてきたので、それを共有したいんだと思います。カナダのナイアガラ園芸学校に留学している時は英語でのコミュニケーションに苦戦し、友だちがなかなかできませんでしたし、授業も力仕事が多く、毎日ハードでつらくなることもありました。
でも、3年間乗り越えられたのは、自然や植物と接していたからだと思うんです。
土を触るだけで、ほわっと癒される。育てている植物の芽が出たり、つぼみが花を咲かせたりするだけで、元気になる。
季節ごとの植物の移り変わりを見ていると、「同じ状態は長く続かないから悪いことも続かないよ」と励まされる。人を感動させる日本庭園をつくった作庭家も40代からのチャレンジと聞けば、「まだまだ、私も頑張れる!」と勇気をもらう。
600年前につくられた庭を眺めていると、「今の私の悩みはちっちゃいことかも」と思える・・・自然や植物によって癒され、生きる力を取り戻せます。
でも、3年間乗り越えられたのは、自然や植物と接していたからだと思うんです。
土を触るだけで、ほわっと癒される。育てている植物の芽が出たり、つぼみが花を咲かせたりするだけで、元気になる。
季節ごとの植物の移り変わりを見ていると、「同じ状態は長く続かないから悪いことも続かないよ」と励まされる。人を感動させる日本庭園をつくった作庭家も40代からのチャレンジと聞けば、「まだまだ、私も頑張れる!」と勇気をもらう。
600年前につくられた庭を眺めていると、「今の私の悩みはちっちゃいことかも」と思える・・・自然や植物によって癒され、生きる力を取り戻せます。
自然や植物、庭が持つ力ですね。
今まで2人、庭を見て泣いた人がいました。眺めているだけで、「今までの自分の人生は何も間違ってないと言われたような気がして、心が軽くなった」「今までの苦労が報われた気がして、肩の荷が降りたような気分になった」と。
この庭の作庭家は、多くの庭を手掛けていますが、晩年に「この庭を超えられなかった」と語るように、持てる渾身の力と情熱を注いでつくったのでしょう。
その彼も、順風満帆とは言えない紆余曲折ある人生だったので、時空を越えて心と心がつながったのかもしれません。
私が今、この仕事をしているのも『ミュージック・ガーデン』のドキュメンタリーを観て、背中を押されたからです。素晴らしい庭には、人生をも変える力があると思っています。
この庭の作庭家は、多くの庭を手掛けていますが、晩年に「この庭を超えられなかった」と語るように、持てる渾身の力と情熱を注いでつくったのでしょう。
その彼も、順風満帆とは言えない紆余曲折ある人生だったので、時空を越えて心と心がつながったのかもしれません。
私が今、この仕事をしているのも『ミュージック・ガーデン』のドキュメンタリーを観て、背中を押されたからです。素晴らしい庭には、人生をも変える力があると思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
皆さんも素晴らしい庭に出会って欲しい。同時に、私自身も、誰かを癒せる庭をつくりたい。
これまで個人宅の庭をデザインしてきましたが、さまざまな人たちが訪れるパブリックな場所の庭のデザインもしていきたいと考えています。
その第1弾として、ニューヨークのグランドセントラル駅の構内に期間限定で、京都の庭師さんと一緒に日本庭園をつくりました。国内でも実現したいですね。
これまで個人宅の庭をデザインしてきましたが、さまざまな人たちが訪れるパブリックな場所の庭のデザインもしていきたいと考えています。
その第1弾として、ニューヨークのグランドセントラル駅の構内に期間限定で、京都の庭師さんと一緒に日本庭園をつくりました。国内でも実現したいですね。
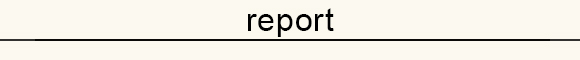
京都市北区紫野の『大徳寺』内にある塔頭寺院『瑞峯院(ずいほういん)』の庭は、1961年頃に完成したと言われています。


昭和9年の室戸台風によって京都の多くの庭園が荒廃した際、復元・修理のために日本各地の庭園を実測調査して『日本庭園史図鑑』を刊行します。
それがきっかけで、『東福寺』の庭園を作庭することになり、作庭家としても活躍するようになりました。
日本画を描くアーティストとしての感性と、庭園を実測調査した研究家としての視点を持ち合わせたデザインは絶妙です。
伝統的な石の立て方を踏襲しつつ、1個だけ異なる石を置いて全体を引き締めるバランス感覚、まるで絵を描くような流れるラインなど、庭という域を超えたアート作品となっています。』

瑞峯院:京都府京都市北区紫野大徳寺町81
拝観時間:9:00~17:00
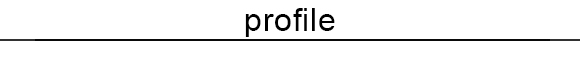
烏賀陽 百合さん
同志社大学文学部文化史学科卒業。兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門課程卒業、カナダのナイアガラ園芸学校に留学して園芸やデザインなどについて学ぶ。イギリスのキューガーデン付属ウェークハースト庭園にてインターンシップを経験。これまで25ヵ国を旅し、世界の庭園を見てまわる。ガーデンデザインや庭のイベントプロデュースのほか、大阪や東京、名古屋など全国各地で庭園講座やガーデニング教室などを開催。また京都では日本庭園ツアーを主催している。著書に『一度は行ってみたい京都「絶景庭園」』(光文社知恵の森文庫)がある。
FB: ugayagarden

一度は行ってみたい
京都「絶景庭園」
烏賀陽 百合(著)
光文社知恵の森文庫
烏賀陽さんが好きでよく行くという京都の「絶景庭園」を、自身の体験や庭のテーマ、見どころ、作庭家のエピソードを交えながら紹介した一冊。帰りに立ち寄りたい、おいしいおやつを味わえるお店紹介付き。京都「絶景庭園」
烏賀陽 百合(著)
光文社知恵の森文庫
⇒ご購入はこちら(光文社)
(取材:2017年02月)
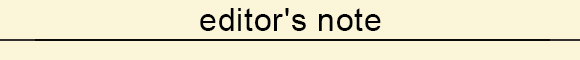
「家」はハードスケープ=かたいもの、「庭」はソフトスケープ=やわらかいもの。かたい家の中だけではぎすぎすしてしまうから、やわらげる要素として庭が必要で、家と庭のバランスがうまくいけば、精神や人生のバランスをうまくとれる。
現代は庭のない家も多いので、パブリックな場所にある庭園がそれを補えるのではないかと烏賀陽さんは考えていると言います。
今回『瑞峯院』で取材しました。眺めているだけで、目の前の風景がそのまま心の中にも広がって、ほっとした気持ちに。
自然の美しさ、やさしさ、過去に生きてきた人たちの価値観や美意識、現在は過去の延長線上にあることなど、さまざまな視点に思いを馳せることでき、ガチガチに凝り固まっていたものが、ふにゃふにゃになるような気がしました。「まあ、いいか」「また、ここから」と、バランスを整えることができたように思います。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(起業家) 記事一覧
-
「たくさんの失敗の上に失敗しないレシピが生まれる」味付けアドバイザーとしておいしい家庭料理を広げる魚森さん
-
「幸せになれない仕組みがあるなら変えたらいい」地域貢献や福祉計画など多様な分野に関わるなかたにさん
-
「私が歩いた道が、道になる」思い立ったら即行動。地域社会のためにさまざまなプロジェクトを展開する下田さん。
-
「切り花から始まって行き着く先は森」ひらめきからスタートして30年。植物と共に歩む八田さん
-
「ヌード撮影は女性が生まれ変わるきっかけ」200人以上の女性の人生の転機にヌード撮影をしてきた中田さん
-
「手のひらにのる「ドイツ」を届けたい」ドイツの木工芸品やクリスマス雑貨の魅力を伝える藤井さん
-
「おせっかいが出発点だった」オフィス街のビルの屋上に作った「空庭」から六次産業サポートする山内さん
-
「かかりつけの写心屋さんでありたい」柳田さんと多賀さんのお二人で始めた家族写真専門のスタジオ
-
「やりたいことをやらないことが一番もったいない」子どもたちの真のやる気と情熱を育てる古賀さん
-
「今ここ、自分にできる精一杯のことをすれば無敵」さまざまなジャンルのイベントで出会いをつなぐ四方さん
-
「自分の想いの量が、仕事になっていく」10年のキャリアを持つ看護師から、「産後ケア」で起業された間宮さん
-
「素晴らしい庭には、人生をも変える力がある」独自の視点で日本庭園の魅力を伝える烏賀陽さん
-
「子どもは大人が焦らなくとも自らグングン伸びる」お受験講師から転身。幼児教室を営む上杉さん
-
「シェアハウスは暮らし方の提案を含めた事業」オリジナルでユニークなシェアハウスを運営する井上さん
-
「自己実現だけでなく、応援される人になってほしい」キャリアモチベーターとして女性起業家を支援する山田さん
-
「アートを体験が人々の視点を変えていく」地域密着型のアートプロジェクトを手掛ける柳本さん。
-
「とりあえずやってみろ精神。それが何よりも近道」韓国のデザイン雑貨に魅かれて起業した松田さん
-
「ひとつづつ乗越えていく。10年やるとなんとかなる」アルバイトから会社設立。学会の事務局業務を請け負う林さん
-
「こだわりのぶどうを作る主人の想いを伝えたい」農家に嫁ぎ、ご主人と共にぶどう畑とワイン作りに励む仲村さん
-
「外国人の目線で話す会話から今までにない発想が生まれる」アメリカ人のご主人と「カフェ英会話」を運営する瑞穂さん
-
「英語はチャンスを掴むツール。大事な時間を英語に取られるのはもったいない」こども塾を運営する岡田さん
-
「京都にほっこり癒されて欲しい」京都を舞台に1人1人に合った癒しの旅を案内する眞由美さん
-
関西出身で大学から東京で23年。お子さんが産まれて関西へ帰ることを機にコーチとして独立された小川さん
-
「茶葉を引き出すことはコーチングと同じ」京都造形芸術大学のラーニングカフェで学生たちに「紅茶の教室」をされている原野さん



































