HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(起業家)
■関西ウーマンインタビュー(起業家)
![]() 間宮美穂さん (『有限会社 ビ・マインド』代表取締役)
間宮美穂さん (『有限会社 ビ・マインド』代表取締役) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(起業家)
間宮美穂さん (『有限会社 ビ・マインド』代表取締役)

自分の想いの量が、仕事になっていく
間宮 美穂さん
『有限会社 ビ・マインド』代表取締役
『有限会社 ビ・マインド』代表取締役
提携する産婦人科内のサロンで、妊娠中から産後までのケアプログラムを展開する『有限会社ビ・マインド』。看護師歴10年のキャリアを持つ間宮美穂さんが、2001年に立ち上げた会社です。
最近でこそ、国や地方自治体が「産後ケア」の推進を始めましたが、間宮さんは16年も前から「産後ケア」プログラムを展開し、その必要性を訴えてきました。
間宮さんが起業家に転身したきっかけとは? 「産後ケア」に注目した理由とは何だったのでしょうか?
最近でこそ、国や地方自治体が「産後ケア」の推進を始めましたが、間宮さんは16年も前から「産後ケア」プログラムを展開し、その必要性を訴えてきました。
間宮さんが起業家に転身したきっかけとは? 「産後ケア」に注目した理由とは何だったのでしょうか?
看護師から起業家へ
起業するきっかけは何だったのですか?
もともと自立心が強く、看護師になったのも手に職をつけたかったから。ある時、理容師から美容家に転身した女性起業家の生き方や考え方を知って、彼女のように自分で仕事をつくって働いていきたいと思ったんです。
看護師から起業する人がまわりにいなかったので、「辞めるなんてもったいない」とよく言われましたが、何がもったいないのか、わからなくって。夜勤もしなくていいし、収入も自分次第になるのにと思っていました。それに病院内にサロンを開設したので、今でも「看護師を辞めた」とは思っていないんです。
看護師から起業する人がまわりにいなかったので、「辞めるなんてもったいない」とよく言われましたが、何がもったいないのか、わからなくって。夜勤もしなくていいし、収入も自分次第になるのにと思っていました。それに病院内にサロンを開設したので、今でも「看護師を辞めた」とは思っていないんです。
どうして、「病院内」で「ボディケアサロン」を開設しようと考えたのですか?
 病院の婦人科に勤務していた時、子宮ガンの患者さんの足がパンパンに腫れてつらそうにしていたから擦ると、「気持ちいい。ありがとう」と喜んでもらえたことが原点にあります。自分自身がボディケアを受けるのも好きだったので、それからは体験した施術を見よう見まねで患者さんにするようになっていったんです。
病院の婦人科に勤務していた時、子宮ガンの患者さんの足がパンパンに腫れてつらそうにしていたから擦ると、「気持ちいい。ありがとう」と喜んでもらえたことが原点にあります。自分自身がボディケアを受けるのも好きだったので、それからは体験した施術を見よう見まねで患者さんにするようになっていったんです。そうやってコミュニケーションする中で、入院生活にこうした癒しの時間があると、日々の楽しみになり、生きる希望につながると感じたことで、病院内にボディケアサロンを開設したいと考えるようになりました。
その後、美容学校に通い始め、同時に産婦人科で働くようになると、出産後のお母さんにボディケアをするようにも。評判になって他の病院に出向いて行うようになっていきました。知り合いの産婦人科医が独立開業したのを機に、産婦人科内でサロンを開設できることになったんです。
当時はまだ産婦人科内のサロンは珍しく、その時からずっと「最先端のことをやっていく」という気持ちでいます。
想いを育てながら、次の、また次の目標へ
「『最先端のことやっていく』という気持ち」とは?
常にチャレンジする姿勢で、「必要だと思う、ほかにはない」ものを導入し続けてきました。「最先端」ということは、世の中でほとんど認知されていないことでもあるので、その必要性を訴え続けてきました。
 起業当初は妊娠中と出産後のトリートメントだけだったのですが、まもなく私自身が妊娠・出産を経験しましたから、そこからは自分の経験や実感に基づいて、事業を広げていきました。
起業当初は妊娠中と出産後のトリートメントだけだったのですが、まもなく私自身が妊娠・出産を経験しましたから、そこからは自分の経験や実感に基づいて、事業を広げていきました。
自分の子どもにベビーマッサージをやりたいと勉強して資格をとって、サロンで行うように。また産婦人科勤務時代に「妊娠中はこの人、出産は病院、産後はほかの人」と妊娠・出産・産後でケアをする人たちに一貫性がなく、人によって言うこともバラバラなことに疑問を持っていたので、一貫してケアするプログラムをつくりました。そのほか、セミナーやお茶会の開催、出張サービスなどにも取り組み、今秋からは子育てを楽しめる考え方を学ぶ親子向け知能教育も。
次は「産後ケアセンター」開設に向けて動いています。韓国には、出産後のお母さんが入院しながら産後ケアを受けたり子育てについて学べたりする「産後院」があって、それによって産後うつが減ったというデータもあるそうです。産後の体の回復がまだだったり、授乳への体づくりができていなかったりする一番大変な時期をフォローできる施設を設立したいと考えています。
 起業当初は妊娠中と出産後のトリートメントだけだったのですが、まもなく私自身が妊娠・出産を経験しましたから、そこからは自分の経験や実感に基づいて、事業を広げていきました。
起業当初は妊娠中と出産後のトリートメントだけだったのですが、まもなく私自身が妊娠・出産を経験しましたから、そこからは自分の経験や実感に基づいて、事業を広げていきました。自分の子どもにベビーマッサージをやりたいと勉強して資格をとって、サロンで行うように。また産婦人科勤務時代に「妊娠中はこの人、出産は病院、産後はほかの人」と妊娠・出産・産後でケアをする人たちに一貫性がなく、人によって言うこともバラバラなことに疑問を持っていたので、一貫してケアするプログラムをつくりました。そのほか、セミナーやお茶会の開催、出張サービスなどにも取り組み、今秋からは子育てを楽しめる考え方を学ぶ親子向け知能教育も。
次は「産後ケアセンター」開設に向けて動いています。韓国には、出産後のお母さんが入院しながら産後ケアを受けたり子育てについて学べたりする「産後院」があって、それによって産後うつが減ったというデータもあるそうです。産後の体の回復がまだだったり、授乳への体づくりができていなかったりする一番大変な時期をフォローできる施設を設立したいと考えています。
間宮さんは、想いを育てて、次の、また次の目標へと進んできているように感じます。
 自分自身が年齢も経験も重ねるにつれて、チャレンジしたい目標が1つ、また1つと出てきます。その土台には「体をケアすると日常を快適に過ごせるから、心地よい体でいてほしい」という願いが、変わらずにあります。
自分自身が年齢も経験も重ねるにつれて、チャレンジしたい目標が1つ、また1つと出てきます。その土台には「体をケアすると日常を快適に過ごせるから、心地よい体でいてほしい」という願いが、変わらずにあります。願いの源は、自分自身の実感によるもの。私は産婦人科勤務経験もありましたから、1人目の時は特に苦労しなかったのですが、年子で双子の子育てはしんどかった・・・ボディケアをしてもらうだけで、どれほど体も心もラクになったことか。施術をしながら、さまざまなお母さんの話を聞く中でも、体と心は連動しているんだなあと思います。
サロンでボディケアを受けた後は、体がラクに軽やかになるからか、帰り道に「甘い物でも買って帰ろうかなあ。みんなで食べよう」という気持ちになるようです。外に出かけたい気持ちになったり、家族に対してやさしい気持ちが芽生えたり。いつもなら、赤ちゃんが泣くことに神経質になったりイライラしたりするところも、「大丈夫だ」と思える心の余裕が生まれます。
喜んで子育てできる「子育て期」をつくることで、まずはお母さんが幸せになってほしい。その幸せはやさしさや心の余裕となって表れて、家族にも伝わっていく。ひいては、幼児虐待や育児放棄など社会問題の1つの解決策にもつながるのではないか、と。お母さんにも、家族にも、社会にも、いい循環が広がっていくイメージを持っています。

振り返らず、芽生えた想いを大切にする
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
起業の際に、全国各地にサロンを展開し、学校も経営する女性起業家をモデルとしていたので、会社として規模を拡大することも考えていました。一般向けのアロマサロンを開設したこともありますし、事務所兼教室やセミナーの開催拠点を持ったこともありますが、いずれも経営がうまく行かず、3年ほどで閉めてしまったんです。
「どうしたらうまく経営できるのか」と経営セミナーで聞いたさまざまなことに取り組み、人の話を聞けば聞くほどにわからなくなった時期もあります。自分の性格もあるし、スタンスもあるから、まねをしようとするとしんどくなるだけだと気づきました。
それからは話を聞いて納得できることがあればやってみるし、会社を無理に大きくしようと思わなくてもいいんじゃないか、とも。自分のできる範囲のことを自分で決めて、コツコツやっていこうと思いました。
「どうしたらうまく経営できるのか」と経営セミナーで聞いたさまざまなことに取り組み、人の話を聞けば聞くほどにわからなくなった時期もあります。自分の性格もあるし、スタンスもあるから、まねをしようとするとしんどくなるだけだと気づきました。
それからは話を聞いて納得できることがあればやってみるし、会社を無理に大きくしようと思わなくてもいいんじゃないか、とも。自分のできる範囲のことを自分で決めて、コツコツやっていこうと思いました。
起業して16年。ここまで長年継続できた理由は何だと思いますか?
「振り返りをしない」ことでしょうか。
起業してまもなく子育てが始まったこともあって、過去のことより、毎日のこと、未来のことを考えてきました。そうやって振り返りをしないで走ってきたからこそ、16年も続けてこられたのかなと今になって思います。「あれも、これも失敗だった」と思っていたら、前に進めませんから。
もちろん、院外のサロンや拠点を閉める時は、スタッフに辞めてもらわないといけないなどありましたから、つらくて落ち込みました。次のチャレンジをするのが恐くもなりました。でも、その時々の巡り合わせなどによって「やっぱり、やらないといけない」「チャレンジするしかない」と。
最近、看護学生から「どうしたら独立できますか?」「独立する時、何に着目したらいいですか?」「キャリアはどのくらい必要ですか?」など質問を受けることがあるのですが、「やりたい!」という想いや情熱こそが大切だと話します。
それさえあれば、どんなに苦労してでも実現に向かって進んでいけるし、どうすればいいかわからなくても、なんとかしようと調べたり行動したりするから。自分の想いの量が、仕事になっていくんだと思います。
起業してまもなく子育てが始まったこともあって、過去のことより、毎日のこと、未来のことを考えてきました。そうやって振り返りをしないで走ってきたからこそ、16年も続けてこられたのかなと今になって思います。「あれも、これも失敗だった」と思っていたら、前に進めませんから。
もちろん、院外のサロンや拠点を閉める時は、スタッフに辞めてもらわないといけないなどありましたから、つらくて落ち込みました。次のチャレンジをするのが恐くもなりました。でも、その時々の巡り合わせなどによって「やっぱり、やらないといけない」「チャレンジするしかない」と。
最近、看護学生から「どうしたら独立できますか?」「独立する時、何に着目したらいいですか?」「キャリアはどのくらい必要ですか?」など質問を受けることがあるのですが、「やりたい!」という想いや情熱こそが大切だと話します。
それさえあれば、どんなに苦労してでも実現に向かって進んでいけるし、どうすればいいかわからなくても、なんとかしようと調べたり行動したりするから。自分の想いの量が、仕事になっていくんだと思います。
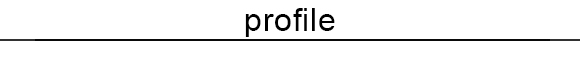
間宮 美穂さん
1971年生まれ。近畿大学附属看護専門学校卒業。近畿大学医学部附属病院や猿渡レディスクリニックなどで看護師として10年勤務。途中、美容学校に通い、エステの技術を学ぶ。2001年に『間宮美穂ビューティ・ライン』を開業し、2004年に『有限会社 ビ・マインド』に改組。産婦人科内のサロンで「産後ケア」プログラムを展開するほか、他社と連携して産後グッズの開発やスクール運営にも取り組む。2010年には、大阪市や大阪市商工会議所等が主催する『CB(コミュニティ・ビジネス)プランコンペおおさか2010』で準グランプリを獲得した。
HP: http://www.bmind.jp/
BLOG: https://ameblo.jp/mmbl/
FB : https://www.facebook.com/bmind8/
(取材:2017年10月)
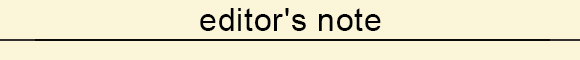
そんな私にとって印象的だったのは、「振り返りをしない」という間宮さんの言葉。過去よりも、反省よりも、後悔よりも、「やりたい」「これが必要なんだ」という想い・・・その想いの量が前に進む原動力になるのだ、と。
間宮さんは振り返りをしなくても、現在進行形で経験している中で、反省や後悔なども含めて次の想いや目標に変換しているように思いました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(起業家) 記事一覧
-
「たくさんの失敗の上に失敗しないレシピが生まれる」味付けアドバイザーとしておいしい家庭料理を広げる魚森さん
-
「幸せになれない仕組みがあるなら変えたらいい」地域貢献や福祉計画など多様な分野に関わるなかたにさん
-
「私が歩いた道が、道になる」思い立ったら即行動。地域社会のためにさまざまなプロジェクトを展開する下田さん。
-
「切り花から始まって行き着く先は森」ひらめきからスタートして30年。植物と共に歩む八田さん
-
「ヌード撮影は女性が生まれ変わるきっかけ」200人以上の女性の人生の転機にヌード撮影をしてきた中田さん
-
「手のひらにのる「ドイツ」を届けたい」ドイツの木工芸品やクリスマス雑貨の魅力を伝える藤井さん
-
「おせっかいが出発点だった」オフィス街のビルの屋上に作った「空庭」から六次産業サポートする山内さん
-
「かかりつけの写心屋さんでありたい」柳田さんと多賀さんのお二人で始めた家族写真専門のスタジオ
-
「やりたいことをやらないことが一番もったいない」子どもたちの真のやる気と情熱を育てる古賀さん
-
「今ここ、自分にできる精一杯のことをすれば無敵」さまざまなジャンルのイベントで出会いをつなぐ四方さん
-
「自分の想いの量が、仕事になっていく」10年のキャリアを持つ看護師から、「産後ケア」で起業された間宮さん
-
「素晴らしい庭には、人生をも変える力がある」独自の視点で日本庭園の魅力を伝える烏賀陽さん
-
「子どもは大人が焦らなくとも自らグングン伸びる」お受験講師から転身。幼児教室を営む上杉さん
-
「シェアハウスは暮らし方の提案を含めた事業」オリジナルでユニークなシェアハウスを運営する井上さん
-
「自己実現だけでなく、応援される人になってほしい」キャリアモチベーターとして女性起業家を支援する山田さん
-
「アートを体験が人々の視点を変えていく」地域密着型のアートプロジェクトを手掛ける柳本さん。
-
「とりあえずやってみろ精神。それが何よりも近道」韓国のデザイン雑貨に魅かれて起業した松田さん
-
「ひとつづつ乗越えていく。10年やるとなんとかなる」アルバイトから会社設立。学会の事務局業務を請け負う林さん
-
「こだわりのぶどうを作る主人の想いを伝えたい」農家に嫁ぎ、ご主人と共にぶどう畑とワイン作りに励む仲村さん
-
「外国人の目線で話す会話から今までにない発想が生まれる」アメリカ人のご主人と「カフェ英会話」を運営する瑞穂さん
-
「英語はチャンスを掴むツール。大事な時間を英語に取られるのはもったいない」こども塾を運営する岡田さん
-
「京都にほっこり癒されて欲しい」京都を舞台に1人1人に合った癒しの旅を案内する眞由美さん
-
関西出身で大学から東京で23年。お子さんが産まれて関西へ帰ることを機にコーチとして独立された小川さん
-
「茶葉を引き出すことはコーチングと同じ」京都造形芸術大学のラーニングカフェで学生たちに「紅茶の教室」をされている原野さん



































