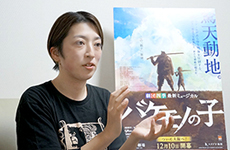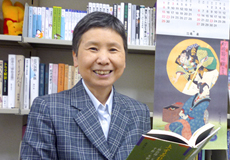HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
![]() 向平 美希さん(松尾塾子供歌舞伎 塾長助手)
向平 美希さん(松尾塾子供歌舞伎 塾長助手) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
向平 美希さん(松尾塾子供歌舞伎 塾長助手)
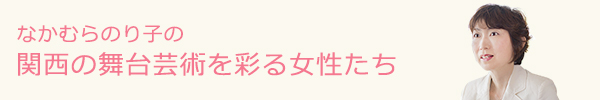

| 向平 美希さん 松尾塾子供歌舞伎 塾長助手 大阪府出身。2歳より常磐津、3歳より日本舞踊を習う。6歳よりお囃子、長唄を始める。9歳で松尾塾子供歌舞伎に入塾。15歳で卒塾。卒塾後、元市川少女歌舞伎 市川梅香に師事。21歳より松尾塾子供歌舞伎 松尾昌出子塾長助手を勤める。現在、お囃子 望月太明一郎、長唄 杵屋勝彦、常磐津 常磐津美佐季に師事。京都・山科子供歌舞伎塾の指導も行っている。 |
| 子供歌舞伎指導というお仕事について教えていただけますか。 |
| 子供歌舞伎は全国各地にあり、歌舞伎専門月刊誌『演劇界』でも、毎月どこかの子供歌舞伎が特集されているほどですが、その規模もさまざまです。「松尾塾子供歌舞伎」は公益財団法人松尾芸能振興財団の助成を受け、1988年に開設されました。3才から15才までの男女児が常時22〜23人在籍し、年に一度開催する東京と大阪での公演に向けて、月間平均15日の稽古に励んでいます。私はその子供たちの指導にあたっています。 |
 |
| お仕事の中で、どんなことに力を入れていますか? |
| 松尾塾長の意志を違えることなく子供たちに伝えることです。「子供にこそ本物を」という先代塾長の意志を引き継ぎ、現在の塾長先生が引き継がれました。三味線や長唄などの指導者は、一線で活躍されている先生方ばかり。塾の目的は、プロの役者を輩出するのではなく、歌舞伎を通して身につける礼儀作法や、年齢の違う仲間とひとつの舞台を創り上げるチームワークなどが、子供たちのその後の人生の財となることを願っています。 また、芝居技術の向上はさることながら、お稽古に取り組む姿勢やお芝居の内容、演じている人物の心情などが子供たちの成長過程において何らかの形で活きることを願い指導にあたっています。テクニック的にも、子供が老若男女の役をするのですから、そのように見える方法など、実践的な技術も伝えるよう心がけています。 私自身も塾生でしたので、当時聞き流していたことも、今になって思い出すこともありますね。稽古中に出ることばが、かつて自分が言われていたことばだということに気がついて、はっとなることがあります。理にかなって説明してくださっていたからこそ、身についていたんだなと実感する瞬間ですね。 |
 |
| なぜ今のお仕事を選ばれましたか? |
| 小学校3年生で松尾塾子供歌舞伎に入塾し、歌舞伎の面白さ、楽しさに魅了されました。 そして、何よりも松尾塾長の側で一流のスタッフの中で歌舞伎を勉強させていただきたいと思いました。また、多感な時期の子供たちの成長を目の当たりにしたときの感動はひとしおです。 入塾時には、じっとしていることができなくて、扇子を投げたりして、塾長先生など叱られていた男の子が、妹さんが入ってきたことを境に、きちんと見本を示すようになったり(笑)稽古で指導する中では、理解する顔つき、目つきになっていく、取り組む姿勢が変わっていく様子を見るときに、成長を感じますね。 70%でなく100%でやって!と厳しいことを要求するのですが、途中でやめる子は一人もおらず、卒塾しても公演前にお手伝いに来てくれるのですが、やんちゃだった男の子が高校生になって、「お元気ですか」ときちんと挨拶しにきてくれたりしたときも、感慨深いですね(笑) 公演本番は、舞台袖でみていて、稽古で何度も練習したシーンを上手に演じてくれたときは、泣きそうになります。本当に指導者冥利に尽きる瞬間ですね。また、何事もなく芝居が終わり、お客さんの拍手を聞きながら無事に幕が降りたときは、感無量のひとことです(笑) |
 |
| このお仕事への転機を教えてください。 |
| 小さい頃から三味線や鳴物の音が聞こえる空間が好きでした。中学では吹奏楽部などにも入りましたが、1年ほどで、迷わず子供歌舞伎一本に。卒塾後の高校時代には、元市川少女歌舞伎 市川梅香に師事。松尾塾を卒塾してからもずっと公演のお手伝いには伺っておりましたが、数年挑んでいた東京芸術大学受験の浪人時に、塾長から助手をやってみないかと声をかけて頂き、1度大学受験には区切り付け、塾長助手としてお手伝いさせていただくことを決断しました。 |
| 子どもたちを指導する中でぶつかる壁などはありますか? |
| 子供に何をしてもどうやっても正しく伝わらない壁は毎年感じます。押し付けず個々に伝え方を変えることを学びました。また、同じ様に毎年経験する壁は、私自身が熟知していなければいけないことの多さです。 各役の衣裳、かつら、化粧や小道具から音やキャストの出入りのきっかけ、お囃子の間。数えるときりがない程です。勉強しても分からないこと、知らないことは正直に専門家の方に教えを乞わなければいけないと学びました。そこから専門家の先生方がおっしゃることが理解できるまでにはとても時間がかかりました。 |
 |
| 「自分の時間」をどのようにすごされていますか? |
| 基本的に24時間営業と思っています。自分の時間=自分の技術向上の時間かなと感じ、自分の習っているお囃子や長唄、常磐津のお稽古に費やすことが多いですね。 |
| 人生のきっかけになった本、あるいは心に残る本をご紹介してください。 |
| 中村勘九郎さんの「勘九郎とはずがたり」と市川左團次さんの「俺が噂の左團次だ」です。小学生の頃何度と無く読み返しては歌舞伎への憧れが膨らみました。そして、分からない下題や役名が出てくれば調べていました。本に出てくるお芝居のワンシーンが、ここのことか!とわかったときは嬉しかったものです。 |
 |
| 最後にメッセージをお願いします。 |
| 常に自分の仕事に興味を持つことができ、毎年公演を重ねる度に自分自身のスキルが上がっていくのを実感しています。同じ演目、同じキャストでも同じ舞台は1日もありません。100年以上昔に作られた演目なのに常に新しく、洗練される歌舞伎を子供が演じる。それにお客様が共感してくださる。そこにマンネリ化は決してありません。 そんな歌舞伎は決して難しいものでも取っ付きにくいものでもありません。いつの時代もドラマになる人間関係は、義理や人情、親子の情愛など、同じものだと思います。この業界がもっと女性の活躍できる場になることを切に願っています。 |
| 向平美希さん、ありがとうございました。 |
 私にとっては初めて知る「子供歌舞伎」の世界でした。日本全国、地域の中に根付いている物も多く、地域振興、地域文化のひとつとして継承されているものも多いそうです。大阪という地には、文楽を代表として伝統文化が根付いています。「子供歌舞伎」もそのひとつで、敷居の高い伝統芸能を、無償で子供たちに伝えるという意志の尊さに感銘しました。歌舞伎を通して、人生の財産となるようなものを子供達に。日本文化のバトンを次世代に手渡していってもらいたいと思いました。 私にとっては初めて知る「子供歌舞伎」の世界でした。日本全国、地域の中に根付いている物も多く、地域振興、地域文化のひとつとして継承されているものも多いそうです。大阪という地には、文楽を代表として伝統文化が根付いています。「子供歌舞伎」もそのひとつで、敷居の高い伝統芸能を、無償で子供たちに伝えるという意志の尊さに感銘しました。歌舞伎を通して、人生の財産となるようなものを子供達に。日本文化のバトンを次世代に手渡していってもらいたいと思いました。 |
|
|
| 取材協力:松尾塾子供歌舞伎 東京都港区青山6-1-3 http://www.kodomokabuki.jp/ |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧
-
「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート
-
「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん
-
「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん
-
「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん
-
「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん
-
「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん
-
「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん
-
「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん
-
「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん
-
「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん
-
「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん
-
「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん
-
「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん
-
「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。
-
「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん
-
「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん
-
「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん
-
伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。
-
「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。