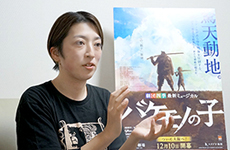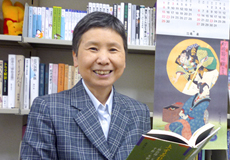HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
![]() 森本加奈子さん(大道具/関西舞台株式会社)
森本加奈子さん(大道具/関西舞台株式会社) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
森本加奈子さん(大道具/関西舞台株式会社)
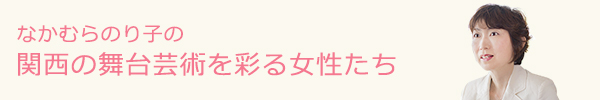

| 森本加奈子さん 大道具/関西舞台株式会社 兵庫県立宝塚北高校演劇科出身。ピッコロシアター舞台技術学校卒業。 劇場小屋や大道具工場でのアルバイト経験を経て現職。 |
| お仕事の内容を教えてください。 |
| 現在は、主に古典芸能の大道具を担当しています。会社は国立文楽劇場にあり、古典芸能の舞台(文楽、歌舞伎、日本舞踊、能、落語等)の製作設営業務を行っています。大道具の仕事は大きく分けて、製作と舞台付きにわかれており、製作は道具をつくる人と絵を描く人のことをいい、舞台付きは、舞台の設営(組み立て)、運搬、転換、障子を開けたり閉めたりといった「きっかけ」を担当します。 |
 |
| 舞台を支える裏方というお仕事を選ばれたきっかけは? |
| 高校は演劇科だったので、バレエや役者など表方の勉強をしていたのですが、大学は普通科に進学し、演劇活動もせず。たまたま、2年の時にピッコロシアター舞台技術学校へふらっと入学。気まぐれに裏方も勉強してみようかなという軽い気持ちでした。 そこから3年間、舞台技術を学び、大学を卒業したものの、ずっと働いていたアルバイト先が無くなってしまい、フラフラしていたところ、ピッコロシアターで道具を教えてもらっていた先生から、忙しい時期に1か月だけ手伝わないかと紹介され、今の職場に入ったのがきっかけです。 これで食べていこうという気持ちは全くなかったですし、アルバイトをしながら、劇団のお手伝いができればいいなと思う程度でした。最初は1カ月だけのはずだったのですが、古典の面白さにはまってしまい、そのまま就職することになりました(笑)。26歳でしたね。 |
 |
| これまでにぶつかった「壁」はあったのでしょうか? |
| まず、入社したときにとまどったのが「定式道具」という専門用語です。入った頃はちょうど日本舞踊の舞台が続く時期で、渡された道具表には、「定式」という言葉が並んでいるだけ。何を準備していいのかわからず、とまどいました。 この「定式道具」というのは、演目に対して道具が決まっており、その一式を用意するのですが、キャリアを積んでいる方は、その一式が全部頭の中に入っているわけです。「定式道具」は演目ごとに手書きで描いた絵としてファイルされており、新人は、まずそれを覚えるところから始まります。調べながら勉強して、できることを見つけていくのが、最初の頃の仕事でした。 「定式道具」は奥が本当に深く、10年以上経った今でも、いまだに全部覚え切れていないです。めったにでない演目などはお目にかかる機会も少なく、すべて覚えられていないですね。道具の数や種類は演目によってまちまちで、20分くらいの作品でも、屋台がいっぱい出たりするものもあれば、屏風一枚のみということもあります。「定式道具」制覇には、数をこなし、覚えようとする気持ちしかないと思っています。 |
| 大道具という仕事のおもしろみはどこにあると感じていらっしゃいますか? |
 舞台付きの仕事のひとつに「きっかけ」があるのですが、「障子を開ける」動作ひとつとっても、気持ちが入るんです。人形遣いさんもその役として芝居をしています。裏方もその瞬間は芝居をしているんです。 舞台付きの仕事のひとつに「きっかけ」があるのですが、「障子を開ける」動作ひとつとっても、気持ちが入るんです。人形遣いさんもその役として芝居をしています。裏方もその瞬間は芝居をしているんです。お姫様の登場シーンなら、お姫様になりきってすーっと開けたり、お侍の登場では、ぱっと開けたり。たかが「きっかけ」ですが、されど「きかっけ」です。 ひとつの舞台、ひとつひとつの役を多くの人が支えて舞台が成り立っている。これが舞台のおもしろみですね。演劇科での学びがここに生きていると感じています。 |
| いままで何か失敗はありましたか? |
| 一番は縫い物の失敗でしょうか。背景幕のミシンがけをすることもあるのですが、幕って大きすぎるので、実物大サイズがわかりにくいですよね。そのサイズを間違えてしまったことがありました。背景幕に製作担当が絵を描いていくのですが、絵のサイズは規定通りに描いていくので、最終的に合わなくなり、大目玉。本番までにやりなおす時間もなく、そのままいったこともありました。ひとつひとつ確認しながら進めることを学んだ出来事でした。 |
| お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか? |
 男性中心の世界なので力の差は当然ありますし、優先順位もつけられますが、入った当時はとにかく負けたくない一心でがむしゃらに働いていました。 男性中心の世界なので力の差は当然ありますし、優先順位もつけられますが、入った当時はとにかく負けたくない一心でがむしゃらに働いていました。今は自分で出来ることできないことがわかっているので、できることのスキルを上げる努力をしています。道具のことだけでなく、古典の常識、芝居の流れを念頭に置くようにしています。 たとえば、定式道具の知識では右に出る者がいない頭領がいるのですが、私も「あの人に聞けば何でも答えてもらえる」といわれるようになりたいですね。 保管場所の把握はもちろん、芝居の内容を理解していないと、なぜこの道具が必要になってくるかわからないので、そのことも理解した上での知識を身に付けていきたいと思っています。 |
| お仕事をする女性として、オフなどの自分の時間はどう過ごされていますか? |
| 自由時間はなかなか取れないのですが、自分の時間やオフの日には、接骨院に行ったり、体のメンテナンスに時間をかけてます。体力勝負の世界ですし、チームで仕事をするので、自分の不調が他の人の迷惑や、舞台にも影響してくることは避けたいですね。 |
| 同じ業界を目指したいと考える方に、アドバイスをいただけますか? |
| やはり最初はがむしゃらに負けん気で働いて欲しいです。女だからという考えは一旦横に置いて、何でもやりたいという気持ちで怖れずにチャレンジしてほしいです。 |
| 森本加奈子さん、ありがとうございました。 |
 スタッフの方々が奈落で作業されてる中でのインタビュー。頭上の舞台ではまさに文楽公演の真っ最中で、取材中もお囃子や成り物、拍手の音が漏れ聞こえていました。海外でも注目される古典芸能の世界。演目ごとに決まっている道具のお話には、歴史ある日本の伝統芸能の奥深さを感じました。 スタッフの方々が奈落で作業されてる中でのインタビュー。頭上の舞台ではまさに文楽公演の真っ最中で、取材中もお囃子や成り物、拍手の音が漏れ聞こえていました。海外でも注目される古典芸能の世界。演目ごとに決まっている道具のお話には、歴史ある日本の伝統芸能の奥深さを感じました。 |
|
|
| 取材協力:関西舞台株式会社 大阪市中央区道頓堀1丁目東5-7 http://kansai-butai.com |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧
-
「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート
-
「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん
-
「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん
-
「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん
-
「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん
-
「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん
-
「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん
-
「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん
-
「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん
-
「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん
-
「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん
-
「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん
-
「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん
-
「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。
-
「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん
-
「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん
-
「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん
-
伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。
-
「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。