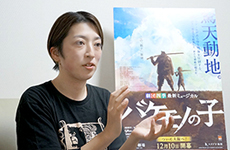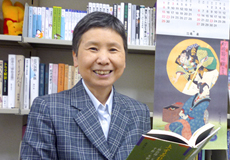HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
![]() 高橋 晃子さん(国立文楽劇場 文楽技術室 床山)
高橋 晃子さん(国立文楽劇場 文楽技術室 床山) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
高橋 晃子さん(国立文楽劇場 文楽技術室 床山)
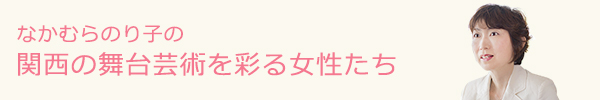

| 高橋 晃子さん (国立文楽劇場 文楽技術室 床山) 東京都(西東京市)出身。中学・高校時代の古典芸能部入部を機会に、伝統芸能の世界に魅了される。大学卒業後、米国に留学。帰国してからは遺跡発掘、プログラマーを経て、30歳から現職。国立文楽劇場初の女性床山。 |
| 文楽の「床山」とはどんなお仕事ですか? |
| ひと言でいえば人形の美容師さんのことです。歌舞伎や日本舞踊などの人間のものと違うところは、鬘をつくる「かつら屋」と髪を結う「床山」の両方の仕事をすることと、「びん付け油」を使わずに結髪することです。 以前は文楽も「かつら屋」と「床山」は別々でしたが、私の師匠である名越昭司先生が始めはかつら屋として文楽の世界へ入ったこともあり、現在の文楽は、自分で作って、自分で結う「かつら床山」スタイルとなりました。 仕事は、髪を結う前のかつら作りから始まります。土台となる台金を銅板で切り抜き、金槌などで打ち出してつくり、そこに「蓑毛」を縫い付けて髪を完成させます。「蓑毛」とは二本の麻糸の間に毛髪を数本ずつ束にして結びつけたもので、これも自分達で編みます。 かつらができたら、それぞれの役柄に応じた髪形を結っていきます。一度結い上げられた髪は基本的には1公演もつように作りますが、役によっては演出上で、毎日髪をさばくものもあり、メンテナンスや次の公演の準備、また突発的な修復のために、公演中は必ず楽屋に待機しています。 年間のスケジュールは、大阪公演5か月、東京公演が4か月、そして地方巡業2か月。その合間を縫って、短い地方公演や技芸員さん個人の公演などがあるので、1年中芝居をしている状態ですね。文楽に関する公演すべての心臓部は大阪の国立文楽劇場にあるんです。 現在のかつら床山担当の職員は、私と5年ほど前に入った八木千江子さんの2人です。これだけの公演を実質2人で切り盛りしています。覚えの早い彼女は、もう多くの仕事を担ってくれるようになり、今はとても助かっています。しかし、人員が十分だとはいえませんから、それぞれの健康管理も大切な仕事だといえますよね(笑)。 |
 |
| もともと文楽に興味があったのですか? |
| 東京郊外の田無という町で育ちました。人形が好きで、日本髪や着物が大好きな子供でした。それも自分が日本髪を結ったり着物を着たりしたいのではなくて、古典の日本髪や着物そのものが好きだったんです。なので、時代劇ばかり見てるTVっ子でした。友達がアイドルに熱を上げている頃でも、中村錦之助や大川橋蔵、大友柳太朗ですから(笑)。時代劇の「東映アワー」を毎週楽しみにしているような時代遅れの変わった子供でしたね。 父も母も中学の教員をしていて、今のように託児所もない時代でしたので、近所のおばちゃんに家に来てもらいお世話してもらっていました。昔の人ですからバービー人形を持っていくと髪を結ってくれて、余り布で着物を縫ってくれました。 桃割れや島田など、髷の部分だけですけれど、可愛い日本髪を結ってくれて、私が日本髪を結いたいと強く思うようになったのは、明治45年生まれだったその方の影響が大きいと思います。私自身、バービーの髪結いに飽きると、友達の妹の髪を結ったり、自分の七五三の着物を持ち出して、その子に着せて遊んでいました。  中学から東京女子美術大学付属中学校に入学し、古典芸能部へ入部しました。文化祭などで歌舞伎や仕舞などを行うクラブなんですが、舞台の表に立つのではなくて、衣裳とかつらに触れるかもしれないぞ、と思って入部したんです。 中学から東京女子美術大学付属中学校に入学し、古典芸能部へ入部しました。文化祭などで歌舞伎や仕舞などを行うクラブなんですが、舞台の表に立つのではなくて、衣裳とかつらに触れるかもしれないぞ、と思って入部したんです。中学・高校の6年間、古典芸能部に所属し、歌舞伎三昧の、今から考えると夢のような、そして今につながる幸せな時代を過ごすことになりました。 東京女子美大の日本画学科へ進むものの、古典芸能部もなく、燃え尽き症候群的な大学生活でしたが、その間に、着付けの免許を取得し、文化祭の時には大学の茶道部の着付けなどをしたり、卒業謝恩会に出る友人の着物の着付けをしたりと、けっこう楽しんでいましたね。人様に着せるのは今でも好きです。 20歳のとき、成人式の晴れ着の代わりにと母に頼み込み、大学からのヨーロッパ美術研修に参加させてもらい、英語の必要性を痛感して帰国しました。そのこともあり、大学卒業後、半年して米国へ留学しました。 いきなり海外で親がかりの生活から初めて独立したわけですが、頼る人のいない生活がどんなに大変なことか、親の有難さが身に浸みました。 足かけ4年の留学生活の後、帰国したのが27歳のとき。帰って来て就いた仕事が遺跡の発掘のアルバイト(笑)。 その後、コンピューターグラフィックの世界へと進みたくてプログラマーに。第2次PCブームで、入った会社で一からプログラミングを学ぶことになりました。数学的な言語が増えてくるに連れ、「これは違う。私がしたかった仕事はなんだった?」という考えが湧いてきたんです。 どんな仕事をするにしても、一人前になるためには10年はかかるだろう、と考えた時に、「これは自分の好きなことじゃない」と思ったんです。 「好きなことで10年を使いたい」。 そして、考えて、考えて、やっぱり「古典の髪が結いたい!」この結論に達しました。 |
 |
| 床山として働くことになったきっかけは? |
| 「古典の髪が結いたい!」と思ったものの、舞台の仕事は、私にとって「聖域」でした。聖域だからこそ、やりたいけど怖くて踏み込めない世界。ここで挫折してしまうと、二度と立ち上がることができないような気がしていたんです。お客として舞台を楽しむ世界のままにしておきたいという気持ちでした。 ただ、この時すでに30歳。あと10年で40歳、これはラストチャンスだろうとも考えました。 迷いに迷っていたときに、紹介していただける方がいらっしゃったので、 床山の名越昭司先生を東京公演の楽屋にお訪ねすることになりました。 ちょうどその頃、先生の後継者のことを考え劇場は床山を募集していたのですが、そんなこととは何も知らぬまま国立劇場の楽屋へ向かいました。 「女がやる仕事じゃない。男社会だし」最初は100%断られました。  首(かしら)担当の先生、名越先生や長年、楽屋にお越しのお客様たち、みなさんに「女性には無理だから」と言われました。「拘束時間は長いし、巡業もあるし、子ども抱えて巡業にはいけないだろう。親の死に目にも会えないよ」と説得されましたね。 首(かしら)担当の先生、名越先生や長年、楽屋にお越しのお客様たち、みなさんに「女性には無理だから」と言われました。「拘束時間は長いし、巡業もあるし、子ども抱えて巡業にはいけないだろう。親の死に目にも会えないよ」と説得されましたね。ただ、楽屋に座っていたら、舞台の音が聞こえてくるんですよ。鳴り物や浄瑠璃の音が…。そして楽屋部屋には、そこかしこにかんざし、日本髪の結われたかしら、廊下には衣裳を付けた人形が並んでいるんです。 「やっぱりこの世界…、高校を卒業してから離れていた芝居の世界に居たい!」 鳥肌が立つような感覚でした。 一生懸命、あきらめるように説得してくださる名越先生でした。その説得が私には逆効果で、かえって『この先生について行きたい!』と思い込んだんです。ほぼ毎日、楽屋に押しかけて、ただそこにいるという日々を続けました。東京公演中、毎日訪ねては先生の手元をじっと見ていました。当時の私は、かつらが大好きで、ただ髪が結いたいという一心でした。すごく邪魔だったでしょうね(笑)。 東京公演が終わり、6月から大阪公演となっても、東京から何度か大阪の楽屋を訪問しました。そして、7月1日には大阪へ引っ越して来ました(笑)。 文楽の大夫さんの夫人となられた先輩が「この子を掃除機だと思って置いてください」と、半ば強引に私を文楽劇場の床山部屋に置いて行かれました。そのあとは、もう毎日道具に触れられることがうれしくて、片付けが楽しくて。そして、9月からアルバイトとして契約していただきました。その後、私には有難いことに床山の募集に応募してくれる男子(女子も)いなくて、そのまま私が採用されました。 |
 |
| この仕事のおもしろさとは? |
| 「曽根崎心中」のお初、「野崎詣り」のお染など、その役それぞれの髪を創ること自体が楽しいです。髪型はその登場人物の性格や身分、立場を現すものなんです。特に封建時代は、身分によって髪型や着物の着方などが定められていましたから、既婚者と10代の独身女性の髪型は違います。ただ髪を結うだけではなくて、その人物の生活や生き方を創る、それがやりたくてこの世界に入らせて頂きました。 私は、髪も舞台で一緒にお芝居をしていると思っています。たとえば、八百屋お七がやぐらにのぼる時に髪がさばけていなかったら、劇的な演出効果は半減すると思うんです。悲惨さ、哀れさなど、かつらを通して一緒に芝居を創っているつもりでいます。役を創るたのしさ、芝居に参加できる楽しさは、学生時代から同じ気持ちかも知れませんね。 「一生勉強だから」と師匠は言います。かつら屋は何でも屋だとも。新作などで文楽とかけ離れた髪型を創ることもあるので、創造していく楽しさは一生あります。あとは、体力との闘いかな(笑)。 |
| この業界を目指す人へメッセージをいただけますか? |
| この業界に限らないですが、10しなくてはいけない仕事のうちの2が好きだったら、それはすごいことだと思います。出来る出来ないにかかわらず、仕事はお金をいただくわけですから、大変で当たり前なんじゃないかな。10全てが楽しいことはなかなかなくて、仕事とはそういうことですよね。 この世界に入って気が付いたのですが、お金をいただきながら学ぶのがプロで、お金を払って教えてもらうのは生徒(お客さん)だということです。たとえ10円でもお金をいただいて仕事を覚える以上はプロなんじゃないかな。これって大きな違いですよね。与えられた機会や時間を自分のものにできるかできないかは自分次第だということでしょう。 入門させて頂きたくて楽屋に通いつめていたとき、断られたあとのことは考えていませんでした。開くかもしれない扉の前から、このまま立ち去ってしまったら、絶対扉は開かない。扉の開くことだけを思って門の前に立ち続けていました。好きなことに自分の人生をかけたくて。 |
| 高橋晃子さん、ありがとうございました。 |
 古典のイメージが強い文楽ですが、「孫悟空」などの子ども向け演目やシェイクスピアなどの洋物タイトルも上演されることもあるそうです。高橋さんのお話を下敷きにして文楽を鑑賞をすると、また違った世界が見えてきそうです。 古典のイメージが強い文楽ですが、「孫悟空」などの子ども向け演目やシェイクスピアなどの洋物タイトルも上演されることもあるそうです。高橋さんのお話を下敷きにして文楽を鑑賞をすると、また違った世界が見えてきそうです。床山は根気のいる仕事です。女性初の床山として文楽を支える高橋さんのプロ意識の高さに、学び多い取材でした。伝統芸能に触れるひとつの機会として、夏休みなどに上演される子ども向け演目での親子文楽鑑賞をおすすめします。 |
|
|
 国立文楽劇場 国立文楽劇場http://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧
-
「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート
-
「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん
-
「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん
-
「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん
-
「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん
-
「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん
-
「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん
-
「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん
-
「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん
-
「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん
-
「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん
-
「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん
-
「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん
-
「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。
-
「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん
-
「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん
-
「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん
-
伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。
-
「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。