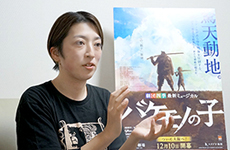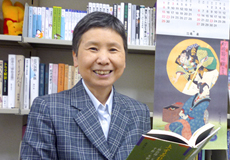HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
![]() 辻野 美加さん(松竹衣裳株式会社 大阪本部営業部 舞踊課主任)
辻野 美加さん(松竹衣裳株式会社 大阪本部営業部 舞踊課主任) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
辻野 美加さん(松竹衣裳株式会社 大阪本部営業部 舞踊課主任)
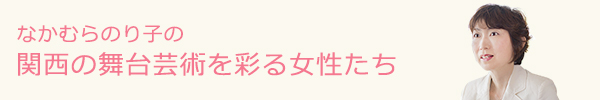

| 辻野 美加さん 松竹衣裳株式会社 大阪本部営業部 舞踊課主任 大阪府泉佐野市出身。2006年入社。以来、舞踊課にて邦楽舞台、時代劇などの衣裳を専門に担当。 |
| 具体的な衣裳担当というお仕事内容を教えていただけますか。 |
| 弊社は東京と大阪にあり、歌舞伎、時代劇、演劇、TVドラマ、日本舞踊、一般イベントでの和洋衣裳や小道具の制作、貸出、管理などを行っています。その中で、私は大阪の舞踊課という和(着物)の衣裳を扱う部署で、主に日本舞踊に関する衣裳を担当しています。 具体的には、日本舞踊の会を行う劇場に出向いて着付けをしたり、衣裳を貸し出すにあたって手入れ、修繕を行います。 |
| お仕事の中で、どんなことに力を入れていますか? |
| 着付けの腕を上げたいと思って日々稽古をしています。出演するお客様にとっては踊りやすい、そして、舞台を見たお客様には「綺麗な帯結び」と思っていただけるようになりたいですね。また、時代背景などによってカツラや着物も違いますので、事前の衣裳見(衣裳合わせ)の段階から関わり、曲のイメージと日本舞踊の先生方の持っていらっしゃるイメージ、個々の思いを理解して、納得いく衣裳選びをしていただけるお手伝いをしたいと思っています。 |
| なぜ今のお仕事を選ばれたのでしょうか。 |
| 中学生の頃からお笑いが好きで、この頃はお笑い芸人になりたいと思っていました(笑)たまたま中学時代に見た社寺での奉納狂言を見て、すっかり魅了されてしまい、大阪府立東住吉高校芸能文化科では、狂言も習えることを知り、受験・入学したんです(笑)。そこで、古典芸能や上方芸能、舞台裏のことを学び、最初は舞台に立つ方に進みたいなと思いながら学生時代過ごしていました。狂言の授業といっても内容は稽古と同じで、本気で狂言師を目指しましたが、狂言も歌舞伎と同じで女人禁制の世界。しかたなく、狂言師になる夢はあきらめました。 |
 |
| ターニングポイントとなった出来事を教えてください |
| 大学も古典芸能を学べる大学に進み、そこで、日本舞踊専攻の方と一緒にお稽古を受けさせていただいたのが、この仕事を選んでいく転機になりました。大学には、講師として日本舞踊家の花柳寿南海(はなやぎとしなみ)先生が東京から教えに来てくださっており、その授業に魅了され、授業とは別に個人指導を懇願したんです。先生は日本舞踊初心者の私の思いを快く受けてくださり、大学4年間、基礎からお稽古をつけていただきました。 その中で「踊り手にとって、衣裳、小道具、大道具、かつらなど、知ってないといけないことはたくさんあって、またそれをしていただく人がいて、踊り手を支えてくださってる」と言われた一言が心に残り、プロの舞踊家にはなれないけれど、何かしら舞踊家さんを支える仕事がしたいと思ったんです。 毎年、学生の舞台発表があるのですが、当時お金がなかったので、自分の踊る演目「手習い子」の小道具(手習い草紙)を手作りすることにしました。先生の指導で、文字通りイチから、昔から続く決まり事などを含めて、横につきっきりで教えていただき、小道具を完成させたんですね。「踊り手だけでは舞台は成り立たない」という言葉に感銘していたこともあり、就職活動では、小道具担当希望でこの会社を受けました。そのときは、小道具は募集しておらず、衣裳ならということで入社したんです。 |
| これまでにぶつかった壁などはありましたか? |
| 着物に関しては何も知らなかったので、入社してからは、ただひたすら同じ着物を畳んでは広げ、広げては畳む毎日でした。両膝をついて前に屈んだ姿勢が続くので、1日の終わりには立ち上がれないこともありましたね。針仕事も苦手で、着物の襦袢の襟を縫うのに何日もかかったり(笑)。家に帰っても、運針の稽古をして、ただひたすら縫うことを練習しました。衣裳担当の基礎の基礎は、着物を畳むことと着物の修繕のための針仕事に尽きますね。 「引き抜き」と呼ばれる舞台上での早変わりには、仮留めした糸を引き抜くことで、変身となるのですが、これも衣裳担当の役割になってきます。ちゃんと縫われていなかったりすると、着ていても崩れてきたり、パッと引っ張っても外れなかったり(笑)。重要な仕掛けを担うのも衣裳の針仕事にかかっているんです。 また、着付けは自分の腕一つです。稽古をして、本番着付けに臨むのですが、本番では予想外のことが起きたり。ひとたび幕が開き、曲が始まると止めることはできないので、衣裳の早着替えでは何とか着替えを間に合わせて、出演者を舞台に送り出さねばなりません。裏方も踊り手と同じように緊張感に包まれます。着付けに失敗しても、舞台を止めて「待ってー」と言えないのがプロの現場なので、「出来て当たり前」で臨まないといけないというのが最初に感じた壁でした。 |
 |
| 公演の合間の休日はどのように過ごされていますか? |
| 体力勝負の仕事なので、夜にジムなどに通って体力を付けるようにしています。また、どんなに忙しくても、学生時代から習っている長唄の稽古には今も通っています。亡くなった長唄の杵屋駒吉先生に稽古で怒られたり褒められたり、人として素直に生きるということを教えていただきました。 日本舞踊の衣裳の仕事と長唄と、同じ邦楽の世界でプライベートも仕事も、一緒のようだと人からは見られるのですが、衣裳の仕事で自分自身素直になれてない時、稽古に行くと気持ちがまた素直になれます。1人で深呼吸すると気が落ち着いたり、自分が素直な気持ちを取り戻せるように自分に向き合う時間を作ろうと心掛けていきたいです。 時間があれば他の舞台を観に行ったりします。立ち方さんの姿にも感動しますが、裏で衣裳を見るのと、舞台袖で見るのと、客席から見るのとでは、全然違うので、着付ける方によって同じ着物、同じ帯でも全く違うバランスがあります。そんな経験値を積んで行こうと思っています。 |
| この業界を目指す女性へアドバイスをお願いします。 |
| 昔から、男性社会の衣裳付けの仕事ですが、最近は若い女の子が増えてきて女性も頑張っています。男性のような力仕事はできなくても、女性にしかない目線や気配りを持って進んでいけたらと思います。また、女は愛嬌という言葉もありますし、笑顔で、周りの話を素直に聞いて感謝を忘れないで、いつまでも初心の素直な気持ちを持ちつつ真のある仕事ができたらいいなと思います。 |
| 辻野美加さん、ありがとうございました。 |
 インタビュー場所として案内されたフロアは、舞踊課の中でも和の衣裳を扱う部門で、衣裳部屋の棚には、美しく整理された着物や帯が一目でわかるように収まっていました。部屋の片隅には使用して戻ってきた着物や、今から出すものなどが、広すぎると思える空間に置かれています。着物はひとつひとつ広げてキチンとたたみ直したり、修繕に回されたりするため、それだけの空間が必要なのだと説明を受け、納得しました。 インタビュー場所として案内されたフロアは、舞踊課の中でも和の衣裳を扱う部門で、衣裳部屋の棚には、美しく整理された着物や帯が一目でわかるように収まっていました。部屋の片隅には使用して戻ってきた着物や、今から出すものなどが、広すぎると思える空間に置かれています。着物はひとつひとつ広げてキチンとたたみ直したり、修繕に回されたりするため、それだけの空間が必要なのだと説明を受け、納得しました。また、天井からは、その場所を明るく照らすいくつものスポットライトが設置されています。不思議に思っていると、「衣裳見」と呼ばれる衣裳合わせのために、舞台に近い照明で着物が見られるようになっていると教えてもらいました。 美しい衣裳が舞台やTVで登場する陰には、多くの人の手が関わり、繊細な配慮があってこそなのだな、とあらためて感じた取材でした。 |
|
|
| 取材協力:松竹衣裳株式会社 大阪本部 大阪市中央区北久宝寺町2丁目5-7 TEL 06-6224-0331(代) http://www.shochiku-costume.co.jp |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧
-
「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート
-
「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん
-
「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん
-
「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん
-
「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん
-
「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん
-
「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん
-
「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん
-
「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん
-
「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん
-
「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん
-
「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん
-
「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん
-
「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。
-
「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん
-
「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん
-
「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん
-
伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。
-
「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。