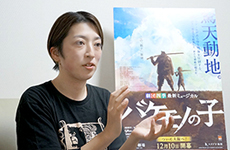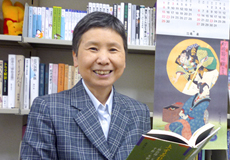HOME![]() ■関西の舞台芸術を彩る女性たち
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
![]() 福島 史子さん(神戸アートビレッジセンター プログラムディレクター)
福島 史子さん(神戸アートビレッジセンター プログラムディレクター) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西の舞台芸術を彩る女性たち
福島 史子さん(神戸アートビレッジセンター プログラムディレクター)
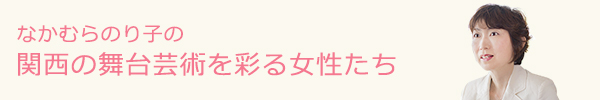

| 福島 史子さん (神戸アートビレッジセンター プログラムディレクター 大学卒業後、兵庫県伊丹市アイホール演劇学校にて舞台制作を学ぶ。扇町ミュージアムスクエアでの劇場製作を経て、現職。 |
| プログラムディレクターとはどのような仕事ですか |
| 神戸アートビレッジセンターでは、貸館での公演が多いのですが、それ以外の演劇やダンスのプログラム企画から公演、ワークショップなどを年間で組んでいく仕事です。 プロデューサーというと、お金を集めてきて公演するというイメージが強いように思いますが、神戸アートビレッジセンターでは神戸市からの補助などで公演運営をするので、100%資金繰りをするプロデューサーというものとは少し違うと思っています。プログラムディレクターはもっと企画よりな感じ。企画を立て、それを実施するところまで持っていくというのがお仕事です。 |
| 具体的にどんなことをされているのですか |
| 普段からリサーチを大切にしています。マーケティングといったら大げさなんですけど、今どういう劇団が注目されているのかとか、別の地域ではどういうものが受けているのか、作家、演出家、若手でどんなところがでてきているとか。神戸で上演するならどんな作品が良いか。普段からさまざまな公演を観に行ったりしてリサーチしています。 常にアンテナを立てて、演劇やダンスも含めて口コミやSNSでどういう人が話題になっているか、どれだけの人が話題にしているかなど、情報収集しています。 そして、なるべくその公演に出向き、実際に目で見るようにしています。実際行ったときには、客席もよくみますね。どれくらい埋まっているかというのもありますし、どういう客層か、年齢の比率とか、男女比などもみています。 |
 |
| 年間どのくらいの公演を企画されていますか。 |
| 持ち込み企画なども含めて、年間で約6本くらいですね。持ち込み企画に関しては、最短で2ヶ月前という場合もありますが、自分で企画する場合は、やはり1年くらい前から取りかかります。 やりたい企画が決まれば、公演の日を調整して、それまでの過程をどう過ごすかということを劇作家や演出家、制作担当も含めて、スケジュールを立てていきます。 そして、チラシやプログラムを作っていくのですが、最終的に集客という部分が、一番気がかりです。その選んだ演目が評価されるようなことなんで。 まず前売りが始まる前にチラシを撒いて、新聞社に連絡し、記事として取りあげてもらえるように取材をセッティングしたり、広報活動をしていきます。 次に、チケットが販売されたら、その動き方をみますね。その動向によって、これはちょっと厳しいかもしれないと思ったら、個別にDMを送ったりといったアプローチもします。 |
| このお仕事で一番やりがいを感じてらっしゃる部分は、どういう点でしょう |
| 格好をつけて言えば、演劇を通してお客様に豊かなものを持って帰ってもらう、そういうものをお渡しできるときにやりがいを感じています。具体的には、帰っていかれる顔を見たときに、入場前と表情が変わっていたり、ふっと顔がゆるんでいらっしゃったりすると、すごく嬉しいですね。なにか、公演を通じて感じてもらえたのかなと思って。 毎年夏に「ゴー!ゴー!ハイスクールプロジェクト」という、神戸市内の高校生と創り上げる舞台があるのですが、彼ら彼女らの変化が本当にすごいんです。 1日目は、みんな初対面ですごく緊張しているんですけど、稽古をはじめるとすぐに仲良くなっていくんですよね。仲が良いだけではなくて、ライバルという部分も含めて、稽古期間中に切磋琢磨してどんどん調子が上がって行くんです。そういう成長に触れるたびに感動しますね。 この公演では、大抵、前の年に卒業した子に照明とか音響とかを手伝ってもらうのですが、卒業して演劇を続けたいと芸大に行く子や、東京の俳優塾に行く子などがすごく増えています。そして、そういう子たちがまた帰ってきて自分たちの劇団を作ったりとか。これはこのプロジェクトがなければ、出てこなかった現象だと思いますね。 |
 |
| 舞台への興味を持ったのはいつですか? |
| 思い返せば、小学校のときから演劇好きでした。クラスの中で、お別れ会などのたびに脚本を書いて、演劇を作っていました。 中学では演劇にはほとんど関わりませんでしたが、高校では有志で劇団を作って、休み時間に理科室で上演するなどしていました。家から持ってきた電気スタンドを並べて照明にしたり(笑)。コンセントを抜き差ししてON・OFFするんです(笑)。 その後、大学のサークルで役者をやったものの、役者には向いていないと実感し、それでも人と演劇を通して“もの”を作るのが好きだったので、舞台制作の仕事に就きたいなと思うようになりました。 卒業後、伊丹のアイホールの演劇学校に入学し、そこで「制作をしたい」と言っていましたら、そこの外部プロデューサーだった方が、事務所に来ないかと声をかけて下さったんです。 その事務所は、外部ブレーンとしてホールへ企画を提案したり、実施するという会社で、そこに入り、さまざまな劇場での公演の制作などに関わらせてもらいました。 その後、扇町ミュージアムのプロデューサーと知り合い、欠員が出るので来ないかと言われまして、転職。そこから、劇場プロデューサーという、今の仕事につながることをするようになりました。 扇町ミュージアムでは演劇が専門で、ダンスはほとんどなかったんですが、東京から来る劇団の宿泊のお世話をしたり、広報活動、ちらし撒きなど、大体の演劇制作の仕事はここで覚えました。 |
| 現在、演劇・ダンスを専門にされていますが、今後の構想などありますか |
| そうですね。大きいことをしたいですね。国とか年齢・性別に関係なくボーダーレスに、街に賑わいがつくれるようなものを仕掛けていきたいですね。以前、日仏ダンサー混合で通訳を入れながら公演したことがあるんですが、やはりフランスの方は日本人とは感覚が少し違うので、日本のダンサーに刺激にもなりました。神戸という土地柄もあり、外国の方も多く居住していらっしゃいます。そういう意味ではボーダレスでの仕事がしたいですね。 |
| 舞台の企画・制作をやりたいと思っている方へのメッセージがあればお願いします |
 舞台制作という仕事は、人と人をつなぐ仕事です。人と人との間にいるだけに、時には大変なこともありますが、人が好きということも大事な要素ですね。女性ならではの気遣いなどがとても活かせる仕事だと思っています。 舞台制作という仕事は、人と人をつなぐ仕事です。人と人との間にいるだけに、時には大変なこともありますが、人が好きということも大事な要素ですね。女性ならではの気遣いなどがとても活かせる仕事だと思っています。 |
| 福島史子さん、ありがとうございました。 |
 神戸アートビレッジセンターのある新開地は、元々は川だった場所で、氾濫する川を埋め立てて、新しく拓いた地だから「新開地」と名付けられました。町ができ、そこに次々と大衆演劇小屋や、歌舞伎小屋などが立ち並び、戦前は「西の浅草」と呼ばれるほど、西日本最大の繁華街だったそうです。チャップリンも歩いたという写真が残っています。 神戸アートビレッジセンターのある新開地は、元々は川だった場所で、氾濫する川を埋め立てて、新しく拓いた地だから「新開地」と名付けられました。町ができ、そこに次々と大衆演劇小屋や、歌舞伎小屋などが立ち並び、戦前は「西の浅草」と呼ばれるほど、西日本最大の繁華街だったそうです。チャップリンも歩いたという写真が残っています。ところが、第二次世界大戦後には、あたり一帯が軍に没収されて新開地が孤立し、神戸の中心が三宮の方に移りました。1980年代になって、賑やかだった昔の新開地に戻したいという「新開地アートビレッジ構想」が立ち上がりました。 中心に神戸アートビレッジセンター、まわりに芸術村を配し、さまざまな芸術家が住む町にするという計画でしたが、バブルもはじけ、阪神淡路大震災もあり、センターの計画だけが残り、震災翌年の1996年4月にオープンしました。 西日本一の舞台芸術の歴史ある場所として、アートビレッジ計画の再開に期待しています。 |
|
|
 神戸アートビレッジセンター 神戸アートビレッジセンター http://kavc.or.jp/ 〒652-0811 神戸市兵庫区新開地5丁目3-14 TEL:078-512-5500 開館時間:10:00-22:00 休館日/毎週火曜日・年末年始 |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子Splus+hスプラッシュ 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー 舞台芸術に関わる取材コーディネートも多く、観劇数は年々増え続けている。自らも市民演劇に参加するなど、舞台の表と裏からの視点を持つ。インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけ、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西の舞台芸術を彩る女性たち 記事一覧
-
「見えないところへのこだわりが、舞台の基盤をつくりあげていく」初日の幕が開く時が新たな作品へのスタート
-
「三人だからこそ人形の想いを表現できる」大阪府の伝統芸能事業として、能勢人形浄瑠璃を伝える橋本さん
-
「パズルを考えるようにたまらなく楽しい」役者と一緒に芝居する舞台美術こそ、転換の妙と話す加藤さん
-
「緊張感は裏も表も一緒。自分の作品に妥協はしない」劇団四季で俳優のヘアメイクを担当する芳賀さん
-
「役者は出会いが大事な世界」17年在籍した劇団四季を退団後、俳優として活躍する傍ら後進の育成に力を注ぐ森さん
-
「この仕事を「点」ではなく、どんなに細くとも「線」にしていきたい」無形文化財保持者の豊澤住輔さん
-
「好きな分野なら勉強も楽しむ余裕を持てる」歴史と古典芸能好きが高じて業界へ。現在は上方芸能研究家の森西さん
-
「失われた中国五千年の伝統文化を伝えたい」20年以上の専業主婦から一転、中国の伝統文化の継承を担う徐さん
-
「どれだけ目から鱗を落とせるかが勝負」1冊の本に出会い、建築士から劇作家に転身された石原さん
-
「三味線は魂の生きものといえる楽器」常磐津節三味線方の三都貴さん
-
「洗練された歌舞伎を子供が演じる。そこにマンネリ化は無い」子供にこそ本物をと子供歌舞伎を教える向平さん
-
「着付けは自分の腕ひとつ」日本舞踊の舞台を彩る衣装を担当されている松竹衣裳株式会社の辻野さん
-
「女だからという考えは一旦置いて、とにかくがむしゃらに働く」国立文楽劇場の大道具として舞台を支える森本さん
-
「大好きだから苦しさは喜びへの道でしかない」ダンサーとして振付師として国内や海外の舞台で活躍する福島さん。
-
「社会の様々なシーンで演劇の力を活かしていきたい」公立劇場で働くことを選んだ古川さん
-
「演劇する“場”が好き」クラシック音楽専用いずみホールでコンサート広報の魁として働く森岡さん
-
「舞台制作という仕事は人と人をつなぐ仕事」プログラムディレクターとして数々の演劇公演を企画されている福島さん
-
伝統芸能に魅了され「女がやる仕事じゃない」と断られながらも国立文楽劇場初の女性床山となった晃子さん。
-
「舞台の裏方で働く仕事は、そこにだけしかない面白さと楽しさがある」衣装が大好き!と笑顔がはじけるコスチューム担当の竹井さん。