HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(社会事業)
■関西ウーマンインタビュー(社会事業)
![]() 岩城 あすかさん(箕面市立多文化交流センター 館長)
岩城 あすかさん(箕面市立多文化交流センター 館長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(社会事業)
岩城 あすかさん(箕面市立多文化交流センター 館長)

世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい
岩城 あすかさん
(箕面市立多文化交流センター 館長)
(箕面市立多文化交流センター 館長)
国籍や世代を問わず、さまざまな市民が出会い、交流し、ともに学べる『箕面市立多文化交流センター』。
館長を務める岩城あすかさんは、子どもの頃から「外国」に興味を持ち、「外国語をしゃべれるようになりたい」「外国に行きたい」と思いを膨らませて、大学ではトルコ語を専攻します。
しかし、大学に入学して、「自分が外国に出ていくことばかり考えても、自分の足元にある社会の矛盾に向き合わない限り、自分で自分をごまかすみたいなもので、地に足がついた生き方ができないのではないか」と思い至り、その実感が現在につながっていると言います。
そう思い至った理由とは? 現在にどうつながっているのでしょうか。
館長を務める岩城あすかさんは、子どもの頃から「外国」に興味を持ち、「外国語をしゃべれるようになりたい」「外国に行きたい」と思いを膨らませて、大学ではトルコ語を専攻します。
しかし、大学に入学して、「自分が外国に出ていくことばかり考えても、自分の足元にある社会の矛盾に向き合わない限り、自分で自分をごまかすみたいなもので、地に足がついた生き方ができないのではないか」と思い至り、その実感が現在につながっていると言います。
そう思い至った理由とは? 現在にどうつながっているのでしょうか。
「外」と「内」を見つめて
大学ではトルコ語を専攻されていたそうですね。どうして、トルコ語だったのですか?
外国にすごく興味があって、何か語学を学びたいと思っていました。
「ブラジルが気になるので、ポルトガル語がいいかな」「ベトナムやタイも気になる!」と想像を膨らませながら、大阪外国語大学のパンフレットを見ていたら、トルコ語専攻が新しく開設されたというニュースが。
新しい専攻であり、「日本でトルコ語のプロは少ないだろうから、希少価値があるのでは?」とパイオニア精神から興味しんしんに。調べてみると、東洋と西洋の交差点など国自体にも興味が湧いたので選びました。
「ブラジルが気になるので、ポルトガル語がいいかな」「ベトナムやタイも気になる!」と想像を膨らませながら、大阪外国語大学のパンフレットを見ていたら、トルコ語専攻が新しく開設されたというニュースが。
新しい専攻であり、「日本でトルコ語のプロは少ないだろうから、希少価値があるのでは?」とパイオニア精神から興味しんしんに。調べてみると、東洋と西洋の交差点など国自体にも興味が湧いたので選びました。
もともと「外国」に興味があったそうですが、きっかけは何ですか?
 中学1年生の時に母を亡くし、その悲しみを癒すために、家族総出で母が好きだった『アルプスの少女ハイジ』の舞台と言われるスイス・グリンデンワルドへ。ドイツ、フランス、デンマークもツアーで巡りました。
中学1年生の時に母を亡くし、その悲しみを癒すために、家族総出で母が好きだった『アルプスの少女ハイジ』の舞台と言われるスイス・グリンデンワルドへ。ドイツ、フランス、デンマークもツアーで巡りました。中学生という多感な時期に、日本を飛び出して外国に触れるという経験は大きかったようで「世界は広い」と感じたのが、そもそものはじまりかもしれません。
とにかく、子どもの頃から好奇心が異様に強い! いったん興味を持つと、粘り強く関わっていくタイプで、今も変わりません。
最初は「外国語をしゃべれるようになりたい」「外国に行きたい」と外に向かって好奇心が広がっていましたが、大学に入学して変わりました。
自分が外国に出ていくことばかりを考えても、自分の足元にある社会の矛盾と向き合わずにいる限りは、自分で自分をごまかすみたいなもので、地に足がついた生き方ができないのではないか。
外国のことを知りたいと思うのなら、日本にある在日外国人の問題と向き合うことを同時にやる必要があるのではないかと思い至ったんです。
「日本にある在日外国人の問題と向き合う」必要性を感じた理由は?
知人に誘われて「在日韓国・朝鮮人問題研究会(=のちに「在日外国人との共生を考える会」に改名)という大学のサークルに所属したことがきっかけです。
在日コリアンをはじめとする、外国人の子どもたちを対象に勉強を教える中で、「言葉や文化の違いから、親や先生に十分に思いを伝えられない」「日本と母国の間でアイデンティティが揺れる」「進学や就職で悩む」など子どもたちが置かれている厳しい状況を目の当たりにしました。この現実を前に、無力さを感じたんです。
在日コリアンをはじめとする、外国人の子どもたちを対象に勉強を教える中で、「言葉や文化の違いから、親や先生に十分に思いを伝えられない」「日本と母国の間でアイデンティティが揺れる」「進学や就職で悩む」など子どもたちが置かれている厳しい状況を目の当たりにしました。この現実を前に、無力さを感じたんです。

「無力さ」とは?
私が育ってきた環境、まわりで見てきた環境とはあまりにも状況が違っていました。
私は両親が教師で、家には本がたくさんあって、当たり前のように大学に進学しましたが、ある在日外国人の集住地域での進学状況は、最高学歴が短大1名のみ、という状況でした。
家に勉強部屋どころか、机そのものがない。親が就職先を決め、家計が苦しいから中学を卒業したら働く子もいる・・・。
中学卒業を控えた子どもたちは「勉強が嫌いだから進学しなくてもいい」と話していたのですが、合宿などでは「本当はみんなと一緒に高校に行きたい」と泣きながら心の内を吐露する子もいました。
ボランティアや本人の頑張りで、なんとか高校に進学できたとしても、いろんな事情で中退せざるを得ない現実がある。本人や私一人が努力しても越えられないものが横たわっていると感じたんです。
私は両親が教師で、家には本がたくさんあって、当たり前のように大学に進学しましたが、ある在日外国人の集住地域での進学状況は、最高学歴が短大1名のみ、という状況でした。
家に勉強部屋どころか、机そのものがない。親が就職先を決め、家計が苦しいから中学を卒業したら働く子もいる・・・。
中学卒業を控えた子どもたちは「勉強が嫌いだから進学しなくてもいい」と話していたのですが、合宿などでは「本当はみんなと一緒に高校に行きたい」と泣きながら心の内を吐露する子もいました。
ボランティアや本人の頑張りで、なんとか高校に進学できたとしても、いろんな事情で中退せざるを得ない現実がある。本人や私一人が努力しても越えられないものが横たわっていると感じたんです。
生身の出会いがもたらすもの
現在のお仕事を選んだ理由は?
大学時代に感じた「無力感」、その時に考えたこととこれまでの経験が、すべて帰結する仕事だと思ったからです。
さまざまなマイノリティの人たちのしんどさ、生きづらさを目の当たりにする中で、常に「じゃあ、あなたはどうするの?」と突きつけられてきたように思います。
根本から改善するためには、長期的な戦略を練り、市民や行政を巻き込みながら、地域ぐるみで粘り強く彼らを支える仕組みづくりに向けて試行・実践する必要がある・・・それを実現したいと考えました。
さまざまなマイノリティの人たちのしんどさ、生きづらさを目の当たりにする中で、常に「じゃあ、あなたはどうするの?」と突きつけられてきたように思います。
根本から改善するためには、長期的な戦略を練り、市民や行政を巻き込みながら、地域ぐるみで粘り強く彼らを支える仕組みづくりに向けて試行・実践する必要がある・・・それを実現したいと考えました。
現在のお仕事に就いて12年。どんなことを試行・実践されていますか?
日本語教室や多言語広報、相談をはじめ、地域在住の在日外国人が日替わりで家庭料理のランチを提供するコミュニティカフェ『comm cafe(コムカフェ)』の営業など、安心してチャレンジできる場づくりを行なっています。
在国外国人をエンパワメントしたり、社会参加の選択肢を増やしたりするとともに、日本人に対する取り組みも大切にしています。
日本人が多く暮らす日本においてマジョリティとなる日本人が変わらなければ、マイノリティの生きやすさにつながらないから。マジョリティが気づいて、どう行動できるかが、肝心なのです。
在国外国人をエンパワメントしたり、社会参加の選択肢を増やしたりするとともに、日本人に対する取り組みも大切にしています。
日本人が多く暮らす日本においてマジョリティとなる日本人が変わらなければ、マイノリティの生きやすさにつながらないから。マジョリティが気づいて、どう行動できるかが、肝心なのです。

『コムカフェ』には現在12カ国20名のシェフが登録。この日のメニューはインド料理(バターチキンカレー、ごはん、グリーンサラダ、ピクルス、ドライフルーツケーキ)
「日本人に対する取り組み」として、具体的にどんなことを行なっていますか?
『コムカフェ』運営や月刊情報誌『めろん』制作には、多くの日本人ボランティアに関わってもらっています。
たとえば、月刊情報誌『めろん』では、国際化に関わる地域の課題や外国人市民の声、取り組みなどを取材して地域に発信するのですが、制作過程を通してさまざまなことに気づいたり、考えたりする機会に。
編集会議では、全然意見が合わない人とも、議論を交わすことができています。お互いに話ができるのは救いですし、もめるくらいが健全です。
そうやって多様な人たちと出会い、コミュニケーションする中で、自分の無意識にある差別的なもの、暴力性に気づけることがあります。 私自身がそうでした。
大学時代に、在日外国人の子どもたちの家を訪問し、勉強後に家庭料理をいただきながら、さまざまな話をうかがいました。実際に会って話を聞くという生身の出会いがあり、いろんな挫折や失敗を重ねたことが、今につながっています。
ボランティア活動してくださった方からは「今まで特に考えることもなかったことに気づけて視野が広がった」「家族や身近な人に対する接し方が変わった」などと言ってもらっています。マジョリティにとっても、気づけたほうが生きやすくなることもあるんです。
たとえば、月刊情報誌『めろん』では、国際化に関わる地域の課題や外国人市民の声、取り組みなどを取材して地域に発信するのですが、制作過程を通してさまざまなことに気づいたり、考えたりする機会に。
編集会議では、全然意見が合わない人とも、議論を交わすことができています。お互いに話ができるのは救いですし、もめるくらいが健全です。
そうやって多様な人たちと出会い、コミュニケーションする中で、自分の無意識にある差別的なもの、暴力性に気づけることがあります。 私自身がそうでした。
大学時代に、在日外国人の子どもたちの家を訪問し、勉強後に家庭料理をいただきながら、さまざまな話をうかがいました。実際に会って話を聞くという生身の出会いがあり、いろんな挫折や失敗を重ねたことが、今につながっています。
ボランティア活動してくださった方からは「今まで特に考えることもなかったことに気づけて視野が広がった」「家族や身近な人に対する接し方が変わった」などと言ってもらっています。マジョリティにとっても、気づけたほうが生きやすくなることもあるんです。
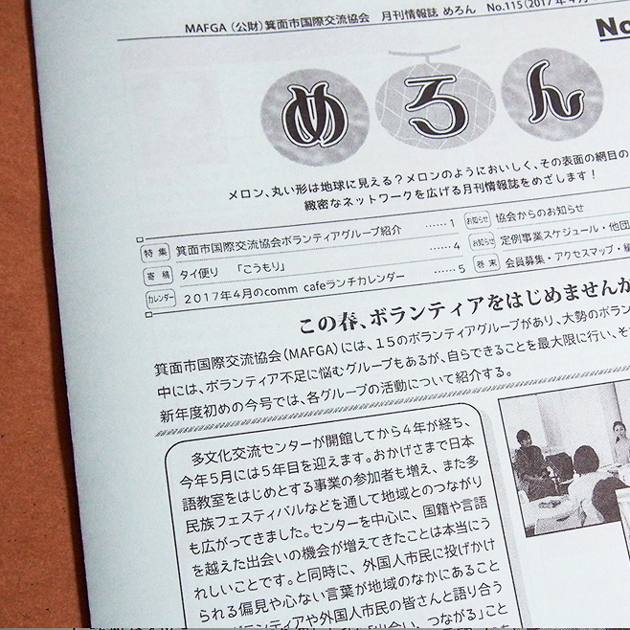
市民ボランティアと一緒に制作する月刊情報誌『めろん』
お互いの居心地のよさを求めて
多様な人たちとコミュニケーションする中で、大事にしていることは何ですか?
マジョリティとマイノリティの立場の違いを常に忘れないように心がけています。
同じように発せられた言葉であったとしても、重みが全然違うから。 たとえば、ヘイトスピーチのデモを見て嫌な気持ちになったとしても、当事者でなければ、見ないふりをすることも、一週間後に忘れることもできます。
でも、当事者のダメージは一生残る。「自分の家族に危害が及ぶのではないか」「将来、結婚する人に迷惑がかかるのではないか」などと不安がつきまとう。 そんな不安や危険を抱えた上で、発言している人たちがいます。
私が話す10倍以上のエネルギーを使って、覚悟を決めて話しているんだと気づいたから、どうしたら対等に話せるだろうかと意識して行動するようになりました。
同じように発せられた言葉であったとしても、重みが全然違うから。 たとえば、ヘイトスピーチのデモを見て嫌な気持ちになったとしても、当事者でなければ、見ないふりをすることも、一週間後に忘れることもできます。
でも、当事者のダメージは一生残る。「自分の家族に危害が及ぶのではないか」「将来、結婚する人に迷惑がかかるのではないか」などと不安がつきまとう。 そんな不安や危険を抱えた上で、発言している人たちがいます。
私が話す10倍以上のエネルギーを使って、覚悟を決めて話しているんだと気づいたから、どうしたら対等に話せるだろうかと意識して行動するようになりました。
「対等に話す」ために、どんなことをされていますか?
「対等」というのは、「お互いにとって居心地のいい」関係性のこと。実践していることはとてもシンプルなんです。
たとえば、「在日外国人の語り合いカフェ」の企画会議では、日本人と在日外国人の割合が半々だったら、「ここは日本だし、日本人の言うことは一理あるから」と遠慮してしまう。
外国人を8割、日本人を2割だけにすると、バランスがよくなり、おもしろい議論ができるようになるんです。
自己紹介も「はじめて参加する人からどうぞ」という場面をよく見受けますが、場に慣れているベテランの方からするようにする。そんな小さなことですが、それだけで雰囲気は変わるんです。
自分が無意識的にやっていることで、他の人にとって暴力的になっていることはないか・・・。その都度確認しながら、工夫や改善を繰り返しています。
たとえば、「在日外国人の語り合いカフェ」の企画会議では、日本人と在日外国人の割合が半々だったら、「ここは日本だし、日本人の言うことは一理あるから」と遠慮してしまう。
外国人を8割、日本人を2割だけにすると、バランスがよくなり、おもしろい議論ができるようになるんです。
自己紹介も「はじめて参加する人からどうぞ」という場面をよく見受けますが、場に慣れているベテランの方からするようにする。そんな小さなことですが、それだけで雰囲気は変わるんです。
自分が無意識的にやっていることで、他の人にとって暴力的になっていることはないか・・・。その都度確認しながら、工夫や改善を繰り返しています。

箕面市の在日外国人グループ『チームシカモ』メンバーと一緒に。『コムカフェ』の中心的メンバーであり、異文化理解のための交流会イベントなども企画・開催している
近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
『コムカフェ』は、在日外国人の「中間就労の場」として十分機能していますが、より多くの就労につながる場として発展させるために、外国人当事者を主体とした会社法人を組織し、その法人へ運営の一部を委託できればいいなと考えています。
また、センター内にとどまらず、外にも飛び出していきたいとも。世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」を、もうちょっと交通の便の良い場所につくれたら、今よりもっと多くの人たちとつながることができ、不穏な空気の漂う世界を平和な方向へ一歩近づけられるのではないかと思っています。
また、センター内にとどまらず、外にも飛び出していきたいとも。世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」を、もうちょっと交通の便の良い場所につくれたら、今よりもっと多くの人たちとつながることができ、不穏な空気の漂う世界を平和な方向へ一歩近づけられるのではないかと思っています。
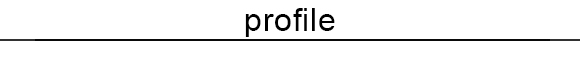
岩城 あすかさん
大阪外国語大学トルコ語専攻を卒業後、1997~2001年までトルコ共和国のイスタンブール大学(院)に留学する。留学中の1999年にトルコ北西部地震が発生。日本の新聞社や出版社、テレビ番組等のトルコ語通訳・コーディネーター業に従事するほか、復興支援プロジェクトにも携わる。帰国後はトルコ共和国大使館商務部や国連UNHCRなどの臨時通訳をつとめた後に、お惣菜メーカーに就職して路面店の店長を経験。2005年に箕面市の外郭団体である『公益法人箕面市国際交流協会』の事務局長に就任、2013年に箕面市小野原地区に新設された『箕面市立多文化交流センター』の館長となる。現在は『公益法人箕面市国際交流協会』総務課長兼『箕面市立多文化交流センター』館長として、地域の国際化を進めるための事業を展開している。
箕面市立多文化交流センター
箕面市小野原西5-2-36
HP: http://minoh-tabunka.jp/
(取材:2017年4月)
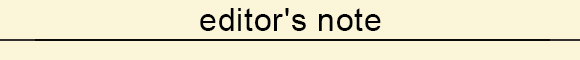
時にはシンナーをやめようと努力する中、禁断症状で苦しむ姿を見ることも。 「世間やメディア等にとらわれない、生身の出会いがいっぱいあったのがよかった。
世の中にはいろんな人がいて、一人一人の中にもいろんな姿があるとわかったから、キャパシティが広くなりましたね」と岩城さんが語るように、「生身の出会い」は尊い。さまざまな出会いを大切にできるように、自分の感受性を磨いていたいなあと思いました。
話は少し逸れるのですが、この記事を書きながら、以前キャリアカウンセリングに関する講座で教わったことを思い出しました。
すでに知っている人でも、会うたびに「また新しいあなたと出会う」感覚で出会い直すこと。「この人はどんな人かな?」という好意的な興味や関心を、はじめて出会う人にも、すでに出会っている人にも持つ。決めつけない、思い込まない・・・相手も私も成長するし、見せ方や見え方によって変わるから。
一度「こうだ!」と思ったイメージを持ち続けることは、無意識の暴力性につながるのではないか・・・もし自分だったら、とてもしんどいことだから、気をつけようと思いました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP:『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(社会事業) 記事一覧
-
「自分が納得のいく生き方をしたい」『窓ぎわのトットちゃん』の出会いから自由な教育を目指す藤田さん
-
「どこにいても誰といても、私は私」高齢者介護からシングルマザー支援と地域に根差してさまざまな活動を広げる安木さん
-
「困りごとから動いていたらこうなっていた」昔の長屋のようなコミュニティづくりに取り組む桃子さん。
-
「価値観を変えたい」障害があっても働くには、自分で事業所をつくるしかないと起業した圭子さん。
-
「流される中でも選んで今」自分の居場所を探し続けて「里山」と出会い、副代表理事として活動する西川さん
-
「人生1回こきり。できると思ってもいい」「一人ひとりが大切にされる働く場」の実験として豆腐屋を営む永田さん
-
「楽しい「」と「人」に出会って、気づいたら今がある」さをり織りと音楽活動を通して地域活動に取組む伊藤さん
-
「世界のあちこちに通じるリアルな「どこでもドア」をつくりたい」在日外国人の語り合いの場を創る岩城さん
-
「好きでやりたいことを置いてでも、やって意味のあること」自らの経験を生かし、薬物依存症回復を支援する倉田さん
-
「互いに信頼し合えるからこそ表現できる」大阪西成区・釜ヶ崎で、詩業家として表現の場を創る上田さん。
-
「音でのコミュニケーションは、言葉では越えられない壁を越えられる」歌、叫び、踊りを通して自分を表現するナカガワさん
-
「想像して創造することはおもしろい」芸術文化を通して障がいのある人たちの居場所を創る鈴木さん
-
「誰かにやってもらうのではなく自分たちで行動する」国際協力に「自分が生きている意味」を見つけた沙良さん
-
「若い人が夢を持ってNPOで働くために「安心」の強い基盤を作りたい」地域の人たちと音楽推進活動する西野さん
-
「手書きの手紙は優しい心の贈り物」ご主人を亡くされてから52歳で起業。残された10行の手紙を心の支えに元気を広げておられます。
-
今年新理事に就任され、2代目リーダーとして事業型NPO運営のモデルを目指す諸田さん。



























