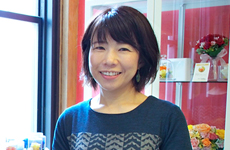HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
![]() 太田 眞実さん(幼保連携型認定こども園「若竹こども園」園長)
太田 眞実さん(幼保連携型認定こども園「若竹こども園」園長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
太田 眞実さん(幼保連携型認定こども園「若竹こども園」園長)

今できることを諦めず、一所懸命に取り組んでみる
太田 眞実さん
社会福祉法人大東若竹会 理事長
幼保連携型認定こども園「若竹こども園」園長
社会福祉法人大東若竹会 理事長
幼保連携型認定こども園「若竹こども園」園長
幼保連携型認定こども園「若竹こども園」、小規模保育園「わかたけ保育園」、児童発達支援・放課後等デイサービス「POSSE」の3施設を運営する社会福祉法人大東若竹会。理事長であり、「若竹こども園」園長も務める太田眞実さん。
同法人・園は太田さんのお父さまが立ち上げられました。太田さんは「将来、おまえが園長になるんだ」と言われて育ち、保育士資格の取得できる短大を卒業するも、すぐに同園に入職とはならず。本格的に保育園に関わり始めたのは50代に突入してからのことだったそうです。
「実はそれまでにも入職するチャンスが3度あり、4度目にしてようやくでした」と太田さん。「1度目の時に何の問題もなく、入職して、園長になっていたら、今頃は子どもたちの気持ちも、職員の気持ちもわからない園長になっていたかもしれません」と振り返ります。
過去3度も出入りされることになった理由とは? 1度目、2度目、3度目それぞれの経験が、どんな転機をもたらしたのでしょうか。
同法人・園は太田さんのお父さまが立ち上げられました。太田さんは「将来、おまえが園長になるんだ」と言われて育ち、保育士資格の取得できる短大を卒業するも、すぐに同園に入職とはならず。本格的に保育園に関わり始めたのは50代に突入してからのことだったそうです。
「実はそれまでにも入職するチャンスが3度あり、4度目にしてようやくでした」と太田さん。「1度目の時に何の問題もなく、入職して、園長になっていたら、今頃は子どもたちの気持ちも、職員の気持ちもわからない園長になっていたかもしれません」と振り返ります。
過去3度も出入りされることになった理由とは? 1度目、2度目、3度目それぞれの経験が、どんな転機をもたらしたのでしょうか。
いつか「父の保育園」の園長に
お父さまが社会福祉法人を設立され、保育園を開園されたそうですね。
父はもともと不動産会社を経営していました。大東市で宅地開発した際にお世話になった方から「保育園が少なくて困っている」という話を聞いて、地域貢献できたらとの想いから、保育園を1975年に開園したんです。
父が法人の理事長になり、父の知人が園長先生を務めてくださっていました。
開園当時、私は中学生。住まいは他市だったため、父が保育園を開園したと言っても実感はありませんでした。ただ、父から「園の壁面に、タイルで絵を描こうと思うんだけど、何がいい?」と聞かれてリクエストしたキャラクターの絵が、旧園舎の壁面に描かれていたことを覚えています。
父からは「将来、おまえが園長になるんだ」と言い聞かされていたので、「いつか、父の保育園の園長になる」と思ってきたんです。
父が法人の理事長になり、父の知人が園長先生を務めてくださっていました。
開園当時、私は中学生。住まいは他市だったため、父が保育園を開園したと言っても実感はありませんでした。ただ、父から「園の壁面に、タイルで絵を描こうと思うんだけど、何がいい?」と聞かれてリクエストしたキャラクターの絵が、旧園舎の壁面に描かれていたことを覚えています。
父からは「将来、おまえが園長になるんだ」と言い聞かされていたので、「いつか、父の保育園の園長になる」と思ってきたんです。
その通り、園長になられたのですね。
園に本格的に関わり始めたのは、今から6年前の2014年のことなんです。実はそれまでにも入職するチャンスが3度あり、4度目にしてようやくでした。
過去3度は、予定を延期することになったり、入職するも数カ月~2年半ほどで辞めたり。そのたびに辛い思いもたくさんしてきましたが、その過程があったことがよかったんだなと、今振り返って思います。
1度目の時に何の問題もなく、入職して、園長になっていたら、今頃は子どもたちの気持ちも、職員の気持ちもわからない園長になっていたかもしれません。
そう思うくらい、1度目、2度目、3度目それぞれに、出会いや気づき、学びがありました。
過去3度は、予定を延期することになったり、入職するも数カ月~2年半ほどで辞めたり。そのたびに辛い思いもたくさんしてきましたが、その過程があったことがよかったんだなと、今振り返って思います。
1度目の時に何の問題もなく、入職して、園長になっていたら、今頃は子どもたちの気持ちも、職員の気持ちもわからない園長になっていたかもしれません。
そう思うくらい、1度目、2度目、3度目それぞれに、出会いや気づき、学びがありました。

経験を重ねる中で、想いを強く、深く
1度目、2度目、3度目それぞれに出会いや気づき、学びがあったとのこと。1度目はどんなタイミングで、どんなことがありましたか?
父は「短大卒業後に保育園に就職を」と考えてくれていたようで、父から言われるままに、保育士資格が取得できる短大に進学しました。私は「父がそう言うのなら」という感じで、その進路を決めたんです。
前提として、父は昭和一桁生まれで、一代で会社を興したワンマン社長でした。その世代の価値観として「男尊女卑」が色濃くあり、私は幼少期に女性蔑視の中で育ったんだと思います。
子どもとしてはかわいがってもらいましたが、「女は仕事をすると生意気になる」「女は感情で物事を考えるからだめだ」といったことを聞いて育ちましたし、4人きょうだいの中でも2人の弟たちとは違うと思ってきました。
何より、家族のことは父が決めるという感じで、自分で何かを考えてもことごとく否定されてきましたから、いつしか自分で考えることをしなくなっていたんです。
短大で学び始めてからも、保育の仕事に対して自分なりのやりがいを見出せず。自分がどうしたいかというよりも、卒業したら父の保育園で働くのかなと思うばかりでした。
そしたら、卒業するタイミングで、保育園のほうでさまざまな出来事があり、立て込んでいたようで、父から「もう少し先がいいだろう」「何でもいいから好きなことをやれ」と言われて、「えーっ!!」となったのを覚えています。
「突然『好きなことをやれ』と言われても」と戸惑い、「世間では語学留学が盛んだから」という理由で語学の専門学校へ。英語を学ぶ中で、コミュニケーションが豊かになっていくのが楽しくて、卒業後は児童向けの英語教室で講師を務めることになりました。
教室で子どもたちと接するうち、「なんか、子どもっておもしろいな」と関心を持ち始めたんです。
前提として、父は昭和一桁生まれで、一代で会社を興したワンマン社長でした。その世代の価値観として「男尊女卑」が色濃くあり、私は幼少期に女性蔑視の中で育ったんだと思います。
子どもとしてはかわいがってもらいましたが、「女は仕事をすると生意気になる」「女は感情で物事を考えるからだめだ」といったことを聞いて育ちましたし、4人きょうだいの中でも2人の弟たちとは違うと思ってきました。
何より、家族のことは父が決めるという感じで、自分で何かを考えてもことごとく否定されてきましたから、いつしか自分で考えることをしなくなっていたんです。
短大で学び始めてからも、保育の仕事に対して自分なりのやりがいを見出せず。自分がどうしたいかというよりも、卒業したら父の保育園で働くのかなと思うばかりでした。
そしたら、卒業するタイミングで、保育園のほうでさまざまな出来事があり、立て込んでいたようで、父から「もう少し先がいいだろう」「何でもいいから好きなことをやれ」と言われて、「えーっ!!」となったのを覚えています。
「突然『好きなことをやれ』と言われても」と戸惑い、「世間では語学留学が盛んだから」という理由で語学の専門学校へ。英語を学ぶ中で、コミュニケーションが豊かになっていくのが楽しくて、卒業後は児童向けの英語教室で講師を務めることになりました。
教室で子どもたちと接するうち、「なんか、子どもっておもしろいな」と関心を持ち始めたんです。
1度目は保育園に入職する話は出ていたものの、実現しなかったとのこと。その後、児童英語講師になられたことで、子どもに関心を持つきっかけになったのですね。2度目にはどんなことがありましたか?
児童英語講師として15年ほど仕事をしていたのですが、2人目の子どもを出産した38歳の頃に、父から「そろそろ、保育園で働かないか?」と声をかけてもらいました。父も年齢を重ね、事業承継を考えているようでした。
私は事務職として入職し、ゆくゆくは園長になることを視野に入れ、保育園運営を学びたいと思っていたのですが、そんな私の気持ちは空回りしていたようです。父と衝突する出来事があり、「まだ時期ではないのかもしれない」とまもなく辞めることになりました。
まだこの時点でも「いつか、父の保育園の園長になる」と思っていただけで、自分自身として保育園や保育に対する想いがあったわけではありません。それが、この2度目に辞めた後、その想いを持つようになるんです。
きっかけになった出来事が2つあります。
1つは、子どもが通う保育園の保護者会で、くじ引きによってやむを得ず、会長を務めたことです。今でこそ、「イクメン」という言葉があるように、男性も家事や育児に関わるようになってきましたが、私が子どもを保育園に通わせている時代は、女性が育児も家事も仕事もすべて担って当たり前な時代でした。
保護者会も1人を除いては全員女性。みんな、育児も家事も仕事もと多忙な中で、保護者会活動でもそれぞれが得意なこと、できることを分担し、資料作成も配布も会議も段取りよくテキパキと。イレギュラーな事態が起こっても対応力がすごいんです。同じ働くお母さんたちのパワーに感動しました。
もう1つは、家族のことで大変な時期に、保育園の先生方に支えていただいたことです。父の入院時に24時間、家族が交替で付き添うことになりました。私も病院に宿泊するなど生活が不規則になり、その影響もあって、子どもたちが精神的に不安定になっていた時期があります。
その時、保育園の先生が「おうちが大変なのはわかっているから、子どもたちのことは私たちに任せて」と言ってくれたことが、どれほど心強かったか。
それらの出来事を通して、「私も保育という仕事を通して、働くお母さんたちを応援したい」「自分が助けられた分、今度は働くお母さんたちを助けたい」と思うようになったんです。
私は事務職として入職し、ゆくゆくは園長になることを視野に入れ、保育園運営を学びたいと思っていたのですが、そんな私の気持ちは空回りしていたようです。父と衝突する出来事があり、「まだ時期ではないのかもしれない」とまもなく辞めることになりました。
まだこの時点でも「いつか、父の保育園の園長になる」と思っていただけで、自分自身として保育園や保育に対する想いがあったわけではありません。それが、この2度目に辞めた後、その想いを持つようになるんです。
きっかけになった出来事が2つあります。
1つは、子どもが通う保育園の保護者会で、くじ引きによってやむを得ず、会長を務めたことです。今でこそ、「イクメン」という言葉があるように、男性も家事や育児に関わるようになってきましたが、私が子どもを保育園に通わせている時代は、女性が育児も家事も仕事もすべて担って当たり前な時代でした。
保護者会も1人を除いては全員女性。みんな、育児も家事も仕事もと多忙な中で、保護者会活動でもそれぞれが得意なこと、できることを分担し、資料作成も配布も会議も段取りよくテキパキと。イレギュラーな事態が起こっても対応力がすごいんです。同じ働くお母さんたちのパワーに感動しました。
もう1つは、家族のことで大変な時期に、保育園の先生方に支えていただいたことです。父の入院時に24時間、家族が交替で付き添うことになりました。私も病院に宿泊するなど生活が不規則になり、その影響もあって、子どもたちが精神的に不安定になっていた時期があります。
その時、保育園の先生が「おうちが大変なのはわかっているから、子どもたちのことは私たちに任せて」と言ってくれたことが、どれほど心強かったか。
それらの出来事を通して、「私も保育という仕事を通して、働くお母さんたちを応援したい」「自分が助けられた分、今度は働くお母さんたちを助けたい」と思うようになったんです。

想いを実現するための、知識と経験も積み重ねて
ご自身として保育に関わる仕事をしていきたいとの想いが芽生えたということで、「いよいよ、入職して園長に」という感じがするのですが、3度目にはどんなことがありましたか?
2度目に辞めてから5年後、私が43歳の頃のことです。父と和解し、「そろそろ、また保育園に」という話が出ていた矢先、父が亡くなりました。弟のひとりが法人の理事長になり、私もゆくゆくは園長になることをめざし、まずは事務職として再入職したんです。
事務室から園の様子を見ていて、保育に対して「なんで、そうするんだろう?」と疑問に思うことがありました。自分自身の子育て経験や私の子どもが通う保育園を見ていて「こんな保育がいいな」と思っていたことがあったから、そことのズレが気になったんだと思います。
保育士としての実務経験がないため、「こういうものなのかな」と思いながらも、だんだんと抑えきれなくなってきました。
とはいえ、園長先生は開所当初から長年、この保育方針で運営されています。私がいいと思う保育をめざすならば、それを実現できる保育園をつくるしかないのではないか。ちょうど、公立保育所の民間委託募集があったので、法人として新たに保育園を開園できないかを模索し始めました。
保育園などのコンサルティングをされている先生に相談にのってもらい、申請書類を作成するところまで話が進んだのですが、その先生に「保育方針と目標は何ですか?」と聞かれた時、自分でもびっくりするくらい、何も出てこなかったんです。
保護者の立場から想うことはあっても、保育方針や目標に落とし込めるくらい、保育に対する知識も経験もありませんでした。結局、新たな保育園を開園する話はなくなり、保育園も辞めることにしたんです。
この時は1カ月ほど寝込むくらい、落ち込みました。「いつか、父の保育園の園長になる」という心のよりどころになっていたものを失ったと思う出来事でしたから。
事務室から園の様子を見ていて、保育に対して「なんで、そうするんだろう?」と疑問に思うことがありました。自分自身の子育て経験や私の子どもが通う保育園を見ていて「こんな保育がいいな」と思っていたことがあったから、そことのズレが気になったんだと思います。
保育士としての実務経験がないため、「こういうものなのかな」と思いながらも、だんだんと抑えきれなくなってきました。
とはいえ、園長先生は開所当初から長年、この保育方針で運営されています。私がいいと思う保育をめざすならば、それを実現できる保育園をつくるしかないのではないか。ちょうど、公立保育所の民間委託募集があったので、法人として新たに保育園を開園できないかを模索し始めました。
保育園などのコンサルティングをされている先生に相談にのってもらい、申請書類を作成するところまで話が進んだのですが、その先生に「保育方針と目標は何ですか?」と聞かれた時、自分でもびっくりするくらい、何も出てこなかったんです。
保護者の立場から想うことはあっても、保育方針や目標に落とし込めるくらい、保育に対する知識も経験もありませんでした。結局、新たな保育園を開園する話はなくなり、保育園も辞めることにしたんです。
この時は1カ月ほど寝込むくらい、落ち込みました。「いつか、父の保育園の園長になる」という心のよりどころになっていたものを失ったと思う出来事でしたから。
子どもの頃からあった「いつか、父の保育園の園長になる」という想い。心のよりどころでもあったものを「失った」と思う出来事はとても辛かったと思います。そこからどのようにして立ち上がることができたのですか?
先ほどのコンサルティングの先生が若手園長会に誘ってくださいました。参加する立場にないと思いながらも、せっかく誘っていただいたので、参加してみたことが転機になったんです。
訪問先の園長先生が「生きているといろいろなことがあって、大変だなと思うこともあるけれど、5年、10年経った時に今のことが必然だと思える日がきますよ。人生は瞬きするのと同じくらい、あっという間だから。今やるべきことをしっかりとやりましょう」という言葉をかけてくださいました。
その一言をきっかけに、「5年、10年前の自分はどうだっただろう?」と、これまでを振り返ることになったんです。
父が会社を経営していて、何不自由なく生活してきましたし、「いつか、父の保育園の園長になる」ということを疑わずに生きてきました。正直、おごりや傲慢さがあったんだと思います。
振り返ったことで、過去の自分を改めて捉え直せ、自分の気持ちの持ち方を変えることで、変えられるんじゃないかなと思えたから。「私ってかわいそう」と泣いている場合じゃない。その後すぐに知り合いの保育園の園長先生にお願いして、保育士としての実務経験を積むことにしました。
私の子どもたちが通う保育園の先生からは「太田さん、今から保育士デビューなんて、チャレンジャーやね」と言われたくらい、体力的にも大変な日々で(笑)。そんな日々の中で、若い保育士さんたちが目の前の子どもたちとひたむきに向き合う姿に心を動かされたんです。
訪問先の園長先生が「生きているといろいろなことがあって、大変だなと思うこともあるけれど、5年、10年経った時に今のことが必然だと思える日がきますよ。人生は瞬きするのと同じくらい、あっという間だから。今やるべきことをしっかりとやりましょう」という言葉をかけてくださいました。
その一言をきっかけに、「5年、10年前の自分はどうだっただろう?」と、これまでを振り返ることになったんです。
父が会社を経営していて、何不自由なく生活してきましたし、「いつか、父の保育園の園長になる」ということを疑わずに生きてきました。正直、おごりや傲慢さがあったんだと思います。
振り返ったことで、過去の自分を改めて捉え直せ、自分の気持ちの持ち方を変えることで、変えられるんじゃないかなと思えたから。「私ってかわいそう」と泣いている場合じゃない。その後すぐに知り合いの保育園の園長先生にお願いして、保育士としての実務経験を積むことにしました。
私の子どもたちが通う保育園の先生からは「太田さん、今から保育士デビューなんて、チャレンジャーやね」と言われたくらい、体力的にも大変な日々で(笑)。そんな日々の中で、若い保育士さんたちが目の前の子どもたちとひたむきに向き合う姿に心を動かされたんです。
「心動かされた」とは?
「ああ、この人たちは自分にできることを一所懸命にしているんだ」と思ったんです。
私は園長になることばかりを考えていたかもしれないと気づきました。それに、3人の子育てをしてきたのに、保育士が日々、どのように子どもたちと向き合っているのかを知らなかったんです。
私も、ただただ目の前にいる子どもたちのために頑張って勉強していきたいとの想いを強くしました。
その後は放課後等デイサービスの児童指導員として、障害のある子どもたちの発達を支援する療育にも関わります。
前職では親に寄り添う支援を行いながらも、どこか腑に落ちないところがあったんです。「わが子なんだから、親が頑張らなきゃ」と思っていたところがありましたし、仕事が休みの日に子どもを預けて遊びに出かける親御さんにもやもやしたこともありました。
でも、放課後等デイサービスでの経験によって、その考え方は変わります。
たとえば、発達障害のあるお子さんが「あんたなんかあっちにいけ」「あんたなんかいらん」とぼそぼそと口にしているのを見かけました。親に言われている言葉を、そのまま言っていたんです。
それだけを聞くと、虐待されているのではないかと思ってしまいますが、親御さんと接する中で、その子のことをとても愛していることが伝わってきました。
愛しているけれども、経済的に生活が大変で、精神的にも余裕がなく、その子を育てるのにも手を焼いているところがあって、つい言ってしまうんです。だからと言って、子どもを傷つけることは許されないけれど、それぞれにさまざまな事情を抱えていて、その家庭だけで解決できることばかりではありません。
子どもも親も、ともに支援していくことが、いかに大切なのかを痛感しました。
私は園長になることばかりを考えていたかもしれないと気づきました。それに、3人の子育てをしてきたのに、保育士が日々、どのように子どもたちと向き合っているのかを知らなかったんです。
私も、ただただ目の前にいる子どもたちのために頑張って勉強していきたいとの想いを強くしました。
その後は放課後等デイサービスの児童指導員として、障害のある子どもたちの発達を支援する療育にも関わります。
前職では親に寄り添う支援を行いながらも、どこか腑に落ちないところがあったんです。「わが子なんだから、親が頑張らなきゃ」と思っていたところがありましたし、仕事が休みの日に子どもを預けて遊びに出かける親御さんにもやもやしたこともありました。
でも、放課後等デイサービスでの経験によって、その考え方は変わります。
たとえば、発達障害のあるお子さんが「あんたなんかあっちにいけ」「あんたなんかいらん」とぼそぼそと口にしているのを見かけました。親に言われている言葉を、そのまま言っていたんです。
それだけを聞くと、虐待されているのではないかと思ってしまいますが、親御さんと接する中で、その子のことをとても愛していることが伝わってきました。
愛しているけれども、経済的に生活が大変で、精神的にも余裕がなく、その子を育てるのにも手を焼いているところがあって、つい言ってしまうんです。だからと言って、子どもを傷つけることは許されないけれど、それぞれにさまざまな事情を抱えていて、その家庭だけで解決できることばかりではありません。
子どもも親も、ともに支援していくことが、いかに大切なのかを痛感しました。

「心に住む人」の存在が力に
3度目では保育士として「どうありたいか」という姿勢を持ったり、想いを深めたりするきっかけになったのですね。そして、いよいよ4度目。そこから現在に至るわけですが、どんなタイミングだったのでしょうか?
前任の園長先生が退任されることになり、園長先生ご本人や理事長との相談のもと、再び入職することになりました。それが2014年のことです。今は園長と法人の理事長を務めています。
1度目、2度目、3度目それぞれでの経験があるからこそできていることがあるのかなと思います。
保育園の運営全体に関することはもちろん、日々の中でも若い職員から「ここまでするんですか」とびっくりされたこともありました。
1度目、2度目、3度目それぞれでの経験があるからこそできていることがあるのかなと思います。
保育園の運営全体に関することはもちろん、日々の中でも若い職員から「ここまでするんですか」とびっくりされたこともありました。
「びっくりされたこと」とは?
たとえば、以前あるご家族が生活を立て直していく過程に携わりました。きっかけは、ご家族からの「今日は保育園に行けないんです」という電話でした。
本来なら「お休みなんですね。わかりました」で終わっていたかもしれません。でも、園でも気にかけていたお子さんで、親御さんも事情を正直に話してくださったので、家庭でさまざまな問題を抱えておられることがわかりました。
その子自身は登園できる状態ということだったので、迎えに行くことにしたんです。
親御さんの許可を得て、その子が朝ごはんをまだ食べていないと言うので、園で食べてもらうことに。また、家の中が散らかっていたので、保育園に関わっている私の弟や妹を呼び寄せて掃除したり、洗濯したり。長期的な支援が必要だと判断し、支援機関に連絡して連携体制をつくりました。
どうして、そこまで踏み込んでいけたのかを考えると、保育園や放課後等デイサービスでさまざまなご家族を見てきましたし、関わってきました。私の人生でも、いろいろなことがありましたから。一つひとつの事象から、想像できることがあったんです。
何より、目の前にいるその子のことを考えると、無視できませんでした。その子と日々向き合っている園の先生のことも知っていますから、ここを無視して、保育園でいくら保育をしても、その子の人生はよくならないと思ったんです。
時には、問題が大きくて、「私なんかに何ができるんだろう」と思うこともあります。でも、自分に今できることを諦めず、一所懸命に取り組んでみることが大切なんだと思い直すんです。
これまでの一つひとつの経験や、その時々の実感が、私を動かしてくれているのだと思っています。
本来なら「お休みなんですね。わかりました」で終わっていたかもしれません。でも、園でも気にかけていたお子さんで、親御さんも事情を正直に話してくださったので、家庭でさまざまな問題を抱えておられることがわかりました。
その子自身は登園できる状態ということだったので、迎えに行くことにしたんです。
親御さんの許可を得て、その子が朝ごはんをまだ食べていないと言うので、園で食べてもらうことに。また、家の中が散らかっていたので、保育園に関わっている私の弟や妹を呼び寄せて掃除したり、洗濯したり。長期的な支援が必要だと判断し、支援機関に連絡して連携体制をつくりました。
どうして、そこまで踏み込んでいけたのかを考えると、保育園や放課後等デイサービスでさまざまなご家族を見てきましたし、関わってきました。私の人生でも、いろいろなことがありましたから。一つひとつの事象から、想像できることがあったんです。
何より、目の前にいるその子のことを考えると、無視できませんでした。その子と日々向き合っている園の先生のことも知っていますから、ここを無視して、保育園でいくら保育をしても、その子の人生はよくならないと思ったんです。
時には、問題が大きくて、「私なんかに何ができるんだろう」と思うこともあります。でも、自分に今できることを諦めず、一所懸命に取り組んでみることが大切なんだと思い直すんです。
これまでの一つひとつの経験や、その時々の実感が、私を動かしてくれているのだと思っています。
今回お話しくださったこと以外にも、いろんなことがおありになったと思います。そのたびに壁や悩みにぶつかってこられたと思いますが、何が乗り越える力になっているのですか?
次から次へと壁や悩みが降って湧いて出てくるので、乗り越えてきたという感覚がなく、気づいたら何とかなっていました。
高校時代の同級生であり、私にさまざまな経験を積む機会を与えてくれ、自信をつけさせてくれた夫を亡くした時は、「自分の人生も終った」と思うくらい、辛く、悲しかったんです。でも、悲しみに浸かっている時間がないほどに、家庭の中でもさまざまな出来事があって、子どもたちのためにも明るく元気に生きていこうと思っていました。
生きていると、本当にいろいろなことがあります。その時々に、まわりの人たちから親切にしてもらったり、その人たちがひたむきに生きている姿に元気をもらったりしたことが、乗り越える力になっていたのかもしれません。
たとえば、コンサルティングの先生が落ち込んでいる私を元気づけようと若手園長会に誘ってくださったり、その訪問先の園長先生が私の様子を見て察してくださったのか、「5年、10年経った時に今のことが必然だと思える日がきますよ」と言葉をかけてくださったり、保護者会活動で出会った仲間が、内緒にしていたのに、夫の通夜や葬式に駆けつけてくれたり。
祖父母や姑から聞いていた苦労話も支えになってました。子どもの下宿代が払えず、はりまや橋のふちで泣いたとか、幼い子どもを連れて師走の道頓堀を集金してまわったとか。
そんなふうに、「あの時にあの人があんなことを言っていたな」「きっとあの人も、その渦中にいた時は大変だったんだろうな」と思い出せたり、想像できたりすることがあるから。
人に歴史あり。代々お母さんたちが苦労しながらも、乗り越えたりやり過ごしたりして、子どもを育て、命をつないできたんだなと思うんです。そんな出会ったいろいろな人たちが「心に住む人」になっていて、困った時や悩んだ時、迷った時に、顔が思い浮かんできます。
「自分一人じゃない」「しんどいけれど、みんなが応援してくれるから頑張れる」と勇気づけてくれたり、さらには「自分にできることはあるのに、それを放棄したら『太田さん、何しているの?』と言われてしまうから、このままにはできない」と奮い立たせてくれたりしているんです。
高校時代の同級生であり、私にさまざまな経験を積む機会を与えてくれ、自信をつけさせてくれた夫を亡くした時は、「自分の人生も終った」と思うくらい、辛く、悲しかったんです。でも、悲しみに浸かっている時間がないほどに、家庭の中でもさまざまな出来事があって、子どもたちのためにも明るく元気に生きていこうと思っていました。
生きていると、本当にいろいろなことがあります。その時々に、まわりの人たちから親切にしてもらったり、その人たちがひたむきに生きている姿に元気をもらったりしたことが、乗り越える力になっていたのかもしれません。
たとえば、コンサルティングの先生が落ち込んでいる私を元気づけようと若手園長会に誘ってくださったり、その訪問先の園長先生が私の様子を見て察してくださったのか、「5年、10年経った時に今のことが必然だと思える日がきますよ」と言葉をかけてくださったり、保護者会活動で出会った仲間が、内緒にしていたのに、夫の通夜や葬式に駆けつけてくれたり。
祖父母や姑から聞いていた苦労話も支えになってました。子どもの下宿代が払えず、はりまや橋のふちで泣いたとか、幼い子どもを連れて師走の道頓堀を集金してまわったとか。
そんなふうに、「あの時にあの人があんなことを言っていたな」「きっとあの人も、その渦中にいた時は大変だったんだろうな」と思い出せたり、想像できたりすることがあるから。
人に歴史あり。代々お母さんたちが苦労しながらも、乗り越えたりやり過ごしたりして、子どもを育て、命をつないできたんだなと思うんです。そんな出会ったいろいろな人たちが「心に住む人」になっていて、困った時や悩んだ時、迷った時に、顔が思い浮かんできます。
「自分一人じゃない」「しんどいけれど、みんなが応援してくれるから頑張れる」と勇気づけてくれたり、さらには「自分にできることはあるのに、それを放棄したら『太田さん、何しているの?』と言われてしまうから、このままにはできない」と奮い立たせてくれたりしているんです。
取材前に「若竹こども園」ウェブサイトの挨拶で、「園の子どもたちに『心に住む人を、たくさんつくってほしい』と願っている」と書いておられたことが、とても印象に残っていました。
1人でぐっと悩んだり落ち込んだりした時、「心に住む人」の存在が「あの人だったら、どうするだろう?」「あの人だったら、なんと言うだろう?」と、自分とは異なる角度から考えたり捉え直したりできる視点を与えてくれるようにも思いました。そのことが、力にも支えにもなりますね。
最後に、近い未来、お仕事で実現したいことを教えてください。
1人でぐっと悩んだり落ち込んだりした時、「心に住む人」の存在が「あの人だったら、どうするだろう?」「あの人だったら、なんと言うだろう?」と、自分とは異なる角度から考えたり捉え直したりできる視点を与えてくれるようにも思いました。そのことが、力にも支えにもなりますね。
最後に、近い未来、お仕事で実現したいことを教えてください。
近年、発達障害や配慮の必要な子どもが増えていると言われていますし、保育をする日々の中でもしんどさを抱えている子が増えてきていると感じますので、若竹こども園のそばに児童発達支援の施設をつくりたいと考えています。
「大きな集団=若竹こども園」と行き来できる、「小さな集団」となれる施設です。
集団の中だからこそ育める力もありますから、多様な子どもたちが集まる大きな集団も大切ですが、みんなで一斉に「何々をしましょう」と言われてもついていけなかったり、興味を持てなかったりなど、大きな集団ばかりではしんどい子もいます。
そんな時に、その子の気持ちや、その子に合う方法を大切にできる小さな集団も必要です。小さな集団でゆったりとした気持ちで好きな遊びをしたり、少人数のお友だちと遊んだりしながら力をつけて、また大きな集団に入っていけるようにします。
そんなことを実現できればと考えているところです。
「大きな集団=若竹こども園」と行き来できる、「小さな集団」となれる施設です。
集団の中だからこそ育める力もありますから、多様な子どもたちが集まる大きな集団も大切ですが、みんなで一斉に「何々をしましょう」と言われてもついていけなかったり、興味を持てなかったりなど、大きな集団ばかりではしんどい子もいます。
そんな時に、その子の気持ちや、その子に合う方法を大切にできる小さな集団も必要です。小さな集団でゆったりとした気持ちで好きな遊びをしたり、少人数のお友だちと遊んだりしながら力をつけて、また大きな集団に入っていけるようにします。
そんなことを実現できればと考えているところです。
太田 眞実さん
短大卒業後、語学の専門学校に進学。卒業後、児童英語講師として15年ほど勤める。その後、事務職や保育士、放課後等デイサービスの児童指導員などを経て、社会福祉法人大東若竹会に入職。現在は同法人の理事長と、「若竹こども園」の園長を務めている。
幼保連携型認定こども園 若竹こども園
大阪府大東市深野5-7-27
HP: http://wakatake-kodomoen.com/
(取材:2020年11月)
「いつか、父の保育園の園長になる」というお父さまやご家族への想いが、出発点。
ご自身として保育園や保育に対する想いがなかったところから、「子どもに関心を持つ」「保育園や保育に対する想いを持つ」「その想いを実現するための知識や経験を得る」という一つひとつの段階を経られ、関心と想い、知識・経験が結びついて、現在があります。
そこにたどり着かれるまで、20代から50代にかけてという長き期間があり、その時々に辛い出来事があったともうかがいました。でも、目の前のことに一所懸命に取り組んでこられたからこそ、太田さんの転機になった「5年、10年経った時に今のことが必然だと思える日がきますよ」という園長先生の言葉を実感できる現在につながったのだと思います。
巡り合うさまざまなことに対して、「自分にできるか、できないか」ではなく、「今できることを諦めず、一所懸命に取り組んでみる」。太田さんのそのメッセージが、心に残っています。
HP: 『えんを描く』
ご自身として保育園や保育に対する想いがなかったところから、「子どもに関心を持つ」「保育園や保育に対する想いを持つ」「その想いを実現するための知識や経験を得る」という一つひとつの段階を経られ、関心と想い、知識・経験が結びついて、現在があります。
そこにたどり着かれるまで、20代から50代にかけてという長き期間があり、その時々に辛い出来事があったともうかがいました。でも、目の前のことに一所懸命に取り組んでこられたからこそ、太田さんの転機になった「5年、10年経った時に今のことが必然だと思える日がきますよ」という園長先生の言葉を実感できる現在につながったのだと思います。
巡り合うさまざまなことに対して、「自分にできるか、できないか」ではなく、「今できることを諦めず、一所懸命に取り組んでみる」。太田さんのそのメッセージが、心に残っています。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(会社経営) 記事一覧
-
「今できることを諦めず一所懸命に取り組んでみる」過去3度の出入りを経て父の保育園の園長となった太田さん
-
「ゼロから始めることで新たな成長や飛躍につながる」平凡な社員から転職。社長に就任した神田さん
-
「心の叫びに気づくことが大切」「手に職を」と思い立ち、プリザーブドフラワー専門店を開いた志摩子さん
-
「お客さんが飽きないように商いを続ける」尼崎の昭和6年創業「蓬莱湯」の3代目を継ぎ、次世代へ繋ぐ里美さん
-
「まずは私自身が変わらないといけない」老舗家業の3代目として事業承継。新たな歴史を創る吉田さん
-
「行動を起こすことで少しでもよくなるなら私がする」2代目社長として新たな発想で会社経営に取り組む角井さん
-
「笑顔の裏側に、自分への厳しさと緊張感を」老舗旅館の女将として伝統を受け継ぎ、次の世代に継ぐ南さん
-
「壁にぶち当たっても、その先はもっと開けて明るい」グラスアート「ロクレール」の技法を引き継ぐ向井さん
-
「見えないところで努力する。それが伝統を受け継いでいくこと」160年続く老舗の婚礼衣装店、5代目の熊谷さん
-
「女性船員も雇用できる魅力ある会社にしたい」船が好きで海運会社の三代目後継者として働く紗苗さん
-
「なんとなく成長するなんて不可能」学者志望から家族の会社を継承、シルク製品の自社ブランドを作る明子さん
-
「この道を選ぶならブレずにまっしぐら。GIRLS, be ambitious!」創業38年イノベーションし続ける長谷川社長
-
「女性をキレイにする旅」をコンセプトに、海外1人旅のコーディネートからユニークな京都旅プランまで「女性の旅」をプロデュース
-
宝塚の情報誌「宝塚ROSE」を発行して10年。元ジェンヌのプロデュースなど宝塚の活性を担う事業を手がける井川さん
-
1000人のロールモデルを創るネオウーマン の代表でもあり、苦難を乗り越えて会社を守る経営者でもある菊川さん