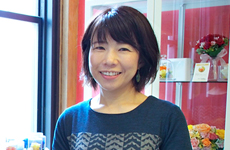HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
![]() 稲 里美さん(蓬莱湯 女将)
稲 里美さん(蓬莱湯 女将) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
稲 里美さん(蓬莱湯 女将)

お客さんが飽きないように、商いを続ける
稲 里美さん
蓬莱湯 女将
蓬莱湯 女将
阪神・尼崎センタープール前駅から歩いて5分のところにある、1931(昭和6)年創業の「蓬莱湯」。
銭湯の営業に加え、ペットシャワーや温泉の自動販売機の設置、温泉宅配、温泉を濃縮したスキンケア商品や尼崎土産「尼崎ジンジャー」といった商品開発・販売、落語会や「おふろバー」といったイベント開催など、次から次へとさまざまなことを仕掛け、話題に事欠かない銭湯です。
温泉が湧き出るかのごとく、次々とアイデアを出しているのは、3代目の稲里美さん。ホテルでの接客、テレビやラジオ番組の構成作家、宅地建物取引士資格を取得して建築事務所で営業といった経歴の持ち主で、蓬莱湯経営には1993年から関わっています。
「お客さんが飽きないように、商いを続けることが大事」と稲さん。アイデアが湧き出る秘密とは?
銭湯の営業に加え、ペットシャワーや温泉の自動販売機の設置、温泉宅配、温泉を濃縮したスキンケア商品や尼崎土産「尼崎ジンジャー」といった商品開発・販売、落語会や「おふろバー」といったイベント開催など、次から次へとさまざまなことを仕掛け、話題に事欠かない銭湯です。
温泉が湧き出るかのごとく、次々とアイデアを出しているのは、3代目の稲里美さん。ホテルでの接客、テレビやラジオ番組の構成作家、宅地建物取引士資格を取得して建築事務所で営業といった経歴の持ち主で、蓬莱湯経営には1993年から関わっています。
「お客さんが飽きないように、商いを続けることが大事」と稲さん。アイデアが湧き出る秘密とは?
子どもの頃から「いつかは銭湯を」と思っていた
「蓬莱湯」は創業して88年。創業者からお父さまが継承し、稲さんは3代目になられるのですね。
親戚に銭湯を経営している人がいて、そのつながりで、父と母は銭湯を転々としながら住み込みで働いてきました。
私が4歳だった1963(昭和38)年に「朝日湯」という銭湯を譲り受け、事業主として銭湯を営むようになるのですが、高速道路建設のために立ち退きになってしまいます。その後、1981(昭和56)年に「蓬莱湯」を創業者から譲り受けました。以降38年に渡って、蓬莱湯を営んでいます。
父と母が事業主として銭湯経営を始めた昭和40~50年代と言うと、「銭湯バブル期」でした。ピーク時は尼崎市内に160軒ほどの銭湯があったと言われていて、今でいう「コンビニ」状態。お風呂のない家が多かったので、生活に欠かせない場所として、すごく賑わっていたんです。
銭湯が忙しかったから、私も小学生の頃から番台に座るなど手伝ってきました。
私が4歳だった1963(昭和38)年に「朝日湯」という銭湯を譲り受け、事業主として銭湯を営むようになるのですが、高速道路建設のために立ち退きになってしまいます。その後、1981(昭和56)年に「蓬莱湯」を創業者から譲り受けました。以降38年に渡って、蓬莱湯を営んでいます。
父と母が事業主として銭湯経営を始めた昭和40~50年代と言うと、「銭湯バブル期」でした。ピーク時は尼崎市内に160軒ほどの銭湯があったと言われていて、今でいう「コンビニ」状態。お風呂のない家が多かったので、生活に欠かせない場所として、すごく賑わっていたんです。
銭湯が忙しかったから、私も小学生の頃から番台に座るなど手伝ってきました。

継ぐことを意識したのはいつですか?
一人っ子で、母から「かまどの下の灰まで全部あんたのもんやから、好きにせえ」と言われて育ちました。「いずれは父と母の世話をしながら、銭湯の仕事をするのかな」と感じ取っていたんです。
大学卒業後は接客を学ぶためにホテルに就職したものの、銭湯が忙しくなってきたので2年ほどで退職し、銭湯を手伝いながらできる仕事をしてきました。この時点では「跡取りとして」というより、父も母も元気でしたから「忙しいから手伝わなあかん」という感じで関わっていたんです。
もともと文章を書くことが好きだから、シナリオライターの学校に通った後、フリーランスの構成作家として、テレビやラジオ番組のクイズのネタを書いたり、下町のおもしろい人を紹介するコーナーの企画を考えたり。
テレビやラジオ業界は、実力主義で浮き沈みが激しかったので、安定かつ社会貢献できる仕事をと考え、宅地建物取引士の資格を取得して、建築事務所で週3日ほど働くようになりました。
その事務所のつながりで、「変わり者同士、お似合い」と、目からしゃぼん玉を出す特技でテレビ番組への出演経験がある主人を紹介してもらい、32歳の時に結婚。
主人が暮らす神奈川県で2年ほど暮らしましたが、父親が60代後半と高齢になってきたので「そろそろ、家業を」と実家へ。この時、システムエンジニアとして会社勤めをしていた主人も一緒に、家業を手伝ってくれることになったんです。
大学卒業後は接客を学ぶためにホテルに就職したものの、銭湯が忙しくなってきたので2年ほどで退職し、銭湯を手伝いながらできる仕事をしてきました。この時点では「跡取りとして」というより、父も母も元気でしたから「忙しいから手伝わなあかん」という感じで関わっていたんです。
もともと文章を書くことが好きだから、シナリオライターの学校に通った後、フリーランスの構成作家として、テレビやラジオ番組のクイズのネタを書いたり、下町のおもしろい人を紹介するコーナーの企画を考えたり。
テレビやラジオ業界は、実力主義で浮き沈みが激しかったので、安定かつ社会貢献できる仕事をと考え、宅地建物取引士の資格を取得して、建築事務所で週3日ほど働くようになりました。
その事務所のつながりで、「変わり者同士、お似合い」と、目からしゃぼん玉を出す特技でテレビ番組への出演経験がある主人を紹介してもらい、32歳の時に結婚。
主人が暮らす神奈川県で2年ほど暮らしましたが、父親が60代後半と高齢になってきたので「そろそろ、家業を」と実家へ。この時、システムエンジニアとして会社勤めをしていた主人も一緒に、家業を手伝ってくれることになったんです。

阪神・淡路大震災が、人生の分岐点に
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
銭湯経営に関わり始めた2年後の1995年、阪神・淡路大震災を経験しました。
私たちが暮らし、銭湯を営む尼崎市南部地域も、家屋の倒壊や路面の亀裂などの被害を受けましたが、銭湯は営業できる状態だったので営業していたところ、市内はもちろん、他市からも被災された人たちがお風呂に入りに来られ、とても喜んでもらえたんです。
こうして災害時に入浴の機会を提供できる銭湯は、地域の中で大事な場所なんだと実感し、銭湯を存続させる使命感を持ちました。この時に、銭湯を継ぐ覚悟ができたように思います。
ただ、震災を機に、風呂の付いていないアパートや文化住宅が取り壊されて家風呂のある住宅が普及したり、住宅のあった場所が駐車場になったり、常連のお客さんの中には高齢になって施設に入居される方がいたりして、お客さんが激減し、売上がピーク時の半分ほどに減ってしまいました。
「これまで通り」では銭湯を存続できない状況に陥り、銭湯の多くは「廃業か、リフォームか」の選択を迫られ、廃業される銭湯も数多くありました。
私たちが暮らし、銭湯を営む尼崎市南部地域も、家屋の倒壊や路面の亀裂などの被害を受けましたが、銭湯は営業できる状態だったので営業していたところ、市内はもちろん、他市からも被災された人たちがお風呂に入りに来られ、とても喜んでもらえたんです。
こうして災害時に入浴の機会を提供できる銭湯は、地域の中で大事な場所なんだと実感し、銭湯を存続させる使命感を持ちました。この時に、銭湯を継ぐ覚悟ができたように思います。
ただ、震災を機に、風呂の付いていないアパートや文化住宅が取り壊されて家風呂のある住宅が普及したり、住宅のあった場所が駐車場になったり、常連のお客さんの中には高齢になって施設に入居される方がいたりして、お客さんが激減し、売上がピーク時の半分ほどに減ってしまいました。
「これまで通り」では銭湯を存続できない状況に陥り、銭湯の多くは「廃業か、リフォームか」の選択を迫られ、廃業される銭湯も数多くありました。

稲さんは廃業されませんでした。どんな想いや考えで、どんな選択をされたのですか?
父は高齢でしたし、主人は38歳と再就職を考えるギリギリの年齢だったので、廃業することも頭をよぎりました。
でも、廃業するにも土地に懸念事項があり、容易に選択できる状況ではなく、何より銭湯が地域にある意義も感じていたので、なんとか存続できないだろうかと模索したんです。
「家にお風呂があっても行きたくなる銭湯とは?」と考える中で、「お風呂にゆっくりと入って体を洗う」という原点に立ち戻り、お湯に使う水を研究していたところ、たどり着いたのが温泉でした。温泉を掘削するには条件がありますが、幸いなことに、その条件にもパチッと当てはまったんです。
父は「温泉が出る可能性が高いと言っても、掘削して出なかった場合のリスクが高い」と猛反対。そこを母が「若い子がやりたいと言うてるんやから、頑張らしたら」とフォローしてくれて、私に一任してもらえることになったんです。
資金繰りなど課題は山積みで、まわりから見ても「絶対に無理や」と言われる状況からのスタートでした。私自身、7割は温泉を掘削しようと決意しつつも、あとの3割は資金などが調達できなければ、今の状態でできるところまで営業して廃業するしかないという気持ちもありました。
でも、この道にかけたいから「できる」という気持ちで、突き進んでいったんです。
構成作家や宅地建物取引士、建築事務所での営業といったさまざまな経験を活かし、蓬莱湯の現状や未来について資料にまとめ、プレゼンテーションしてまわりました。応援してもらえる方々を増やし、銀行とも数カ月かけて何度も何度も交渉を重ねたんです。
その結果、銀行から「そこまで言うのでしたら、こんなふうにしてはどうでしょうか」と打開策を提案してもらえました。まさにオセロの9割が黒だったのが、白にひっくり返ったような出来事です。信念を持ってやろうとすれば、道が拓ける可能性は「ゼロではない」ということを実感しました。
2001年に温泉を掘削し、翌年には温泉銭湯としてリニューアルオープン。その後、売上をV字回復させることができました。
でも、廃業するにも土地に懸念事項があり、容易に選択できる状況ではなく、何より銭湯が地域にある意義も感じていたので、なんとか存続できないだろうかと模索したんです。
「家にお風呂があっても行きたくなる銭湯とは?」と考える中で、「お風呂にゆっくりと入って体を洗う」という原点に立ち戻り、お湯に使う水を研究していたところ、たどり着いたのが温泉でした。温泉を掘削するには条件がありますが、幸いなことに、その条件にもパチッと当てはまったんです。
父は「温泉が出る可能性が高いと言っても、掘削して出なかった場合のリスクが高い」と猛反対。そこを母が「若い子がやりたいと言うてるんやから、頑張らしたら」とフォローしてくれて、私に一任してもらえることになったんです。
資金繰りなど課題は山積みで、まわりから見ても「絶対に無理や」と言われる状況からのスタートでした。私自身、7割は温泉を掘削しようと決意しつつも、あとの3割は資金などが調達できなければ、今の状態でできるところまで営業して廃業するしかないという気持ちもありました。
でも、この道にかけたいから「できる」という気持ちで、突き進んでいったんです。
構成作家や宅地建物取引士、建築事務所での営業といったさまざまな経験を活かし、蓬莱湯の現状や未来について資料にまとめ、プレゼンテーションしてまわりました。応援してもらえる方々を増やし、銀行とも数カ月かけて何度も何度も交渉を重ねたんです。
その結果、銀行から「そこまで言うのでしたら、こんなふうにしてはどうでしょうか」と打開策を提案してもらえました。まさにオセロの9割が黒だったのが、白にひっくり返ったような出来事です。信念を持ってやろうとすれば、道が拓ける可能性は「ゼロではない」ということを実感しました。
2001年に温泉を掘削し、翌年には温泉銭湯としてリニューアルオープン。その後、売上をV字回復させることができました。

「変えないもの」と「変えていくもの」
温泉銭湯としてリニューアル後も、ペットシャワーや温泉宅配、化粧品開発、銭湯イベント、最近では地元・尼崎市に尼崎城が再建されたということで「尼崎ジンジャー」というお土産物を開発されました。次から次へとさまざまなアイデアを出して、形にされていますね。
温泉があれば安泰とはいきません。魅力がなければ、お客さんには来てもらえなくなります。
次から次へとアイデアを出すことは、利益を出し続けるためには必要であり、どんなにアイデアを出しても、来てくださるかどうかを決めるのはお客さんです。アイデアを出していくことで、それに対してお客さんから反応を得られ、ニーズをキャッチし続けられるのだとも思います。
お客さんが飽きないように、商いを続けることが大事なんです。
やみくもにアイデアを出していくのではなく、「変えないもの」と「変えていくもの」という視点と、近江商人の心得「三方良し」という考え方を持っています。
「美と健康に貢献する」という蓬莱湯の経営理念は「変えないもの」。「美と健康にどうやって貢献するのか」という方法は「変えていくもの」。つまり、「美と健康に貢献する」という根本は変えず、時代に応じてお客さんのニーズは変わっていくので、方法を変えていきます。
「三方良し」というのは、「客良し、店良し、世間良し」。お客さんにとっていいこと、お店にとっていいことはもちろん、世間にとっていいことであるかどうかも大事です。
さまざまな経営者を見てきた中で、「お客さんと自分のお店さえ、よければいい」と同業者に不利益になるようなことをしていたら、まわりから応援されませんし、自分自身も疲弊してしまうから、長続きできないように思ったからです。
私がこうしてさまざまなアイデアを形にするのも、「銭湯でこんなことができる」という1つの指標になって、ほかの銭湯の参考になればと思うからですし、地域の活性化につながればと願うなど、世間に対してどう役に立てるのかという視点も忘れません。
次から次へとアイデアを出すことは、利益を出し続けるためには必要であり、どんなにアイデアを出しても、来てくださるかどうかを決めるのはお客さんです。アイデアを出していくことで、それに対してお客さんから反応を得られ、ニーズをキャッチし続けられるのだとも思います。
お客さんが飽きないように、商いを続けることが大事なんです。
やみくもにアイデアを出していくのではなく、「変えないもの」と「変えていくもの」という視点と、近江商人の心得「三方良し」という考え方を持っています。
「美と健康に貢献する」という蓬莱湯の経営理念は「変えないもの」。「美と健康にどうやって貢献するのか」という方法は「変えていくもの」。つまり、「美と健康に貢献する」という根本は変えず、時代に応じてお客さんのニーズは変わっていくので、方法を変えていきます。
「三方良し」というのは、「客良し、店良し、世間良し」。お客さんにとっていいこと、お店にとっていいことはもちろん、世間にとっていいことであるかどうかも大事です。
さまざまな経営者を見てきた中で、「お客さんと自分のお店さえ、よければいい」と同業者に不利益になるようなことをしていたら、まわりから応援されませんし、自分自身も疲弊してしまうから、長続きできないように思ったからです。
私がこうしてさまざまなアイデアを形にするのも、「銭湯でこんなことができる」という1つの指標になって、ほかの銭湯の参考になればと思うからですし、地域の活性化につながればと願うなど、世間に対してどう役に立てるのかという視点も忘れません。

どんなきっかけで、どんなアイデアが生まれていますか?
たとえば、ペットシャワー。最初のきっかけは、うちの犬がノミアレルギーで肌が弱く、何かいいものはないかと、温泉水で洗ってみたらよくなったからです。同じように悩んでいる飼い主がいるかもしれないと設置したら、「このシャワーを使ったらよくなった」と喜んでもらえました。
また、「温泉銭湯に似合う建物に」とデザイナーズ銭湯にリニューアルした際は、改築を祝う会を開いて、番台で職人に寿司を握ってもらったところ、大盛り上がり。次はイタリアンシェフを呼んでコース料理を提供したら、これも好評で、お客さんから「こんなことをしてみたい」「あんなこともしてみたい」と要望や企画が出てくるようになりました。
今では落語会や「おふろバー」など、「落語=笑い=健康」といった「美と健康に貢献する」という経営理念にも合う、おもしろくて誰かの役に立つイベントをしてもらえるようになっています。
そんなことを継続していたら、何か知らんけど、力になってくると気づきました。
イベントではさまざまな人たちが企画を持ち込んでくれていて、自分たちだけではできないことができるようになっています。その人たちを通して、蓬莱湯に関わる人たちが増え、広がりが大きくなっているとも感じています。
また、「温泉銭湯に似合う建物に」とデザイナーズ銭湯にリニューアルした際は、改築を祝う会を開いて、番台で職人に寿司を握ってもらったところ、大盛り上がり。次はイタリアンシェフを呼んでコース料理を提供したら、これも好評で、お客さんから「こんなことをしてみたい」「あんなこともしてみたい」と要望や企画が出てくるようになりました。
今では落語会や「おふろバー」など、「落語=笑い=健康」といった「美と健康に貢献する」という経営理念にも合う、おもしろくて誰かの役に立つイベントをしてもらえるようになっています。
そんなことを継続していたら、何か知らんけど、力になってくると気づきました。
イベントではさまざまな人たちが企画を持ち込んでくれていて、自分たちだけではできないことができるようになっています。その人たちを通して、蓬莱湯に関わる人たちが増え、広がりが大きくなっているとも感じています。

あと、温泉宅配をしているのですが、もともとは温泉自動販売機設置から始まりました。なかなか売上につながらないと思い、お客さんに意見をうかがってみたら「重いから持ち帰りにくい」と。「だったら、宅配すればいい」と温泉宅配につながりました。
これまで銭湯で待つだけだったのが、宅配を通して銭湯の外に飛び出してみると、「手術の傷跡を見せたくないから銭湯には行けないけれど、温泉に浸かりたい」「バリバリ仕事をして疲れるから、1日の終わりに温泉に入りたい」「身体の具合の悪いおじいさんとおばあさんに温泉に入らせてあげたい」など、お客さんのニーズがより聞こえてくるようになったんです。
今は日々の銭湯営業だけで手一杯で、宿泊施設に週に1回宅配するだけで広く展開できていませんが、細々と続けています。ここで「人手が足りないからやめよう」「儲けにならないからやめよう」と諦めてしまうと、そこで途切れてしまいますから。
細い糸でもいいから続けていれば、見えてくるものがあるし、いつかのメシの種につながるのではないかなと考えています。新しい価値を創造するには、何もないところから始めるよりも、すでにあるものから膨らませていくほうが創造しやすいと思うからです。
これまで銭湯で待つだけだったのが、宅配を通して銭湯の外に飛び出してみると、「手術の傷跡を見せたくないから銭湯には行けないけれど、温泉に浸かりたい」「バリバリ仕事をして疲れるから、1日の終わりに温泉に入りたい」「身体の具合の悪いおじいさんとおばあさんに温泉に入らせてあげたい」など、お客さんのニーズがより聞こえてくるようになったんです。
今は日々の銭湯営業だけで手一杯で、宿泊施設に週に1回宅配するだけで広く展開できていませんが、細々と続けています。ここで「人手が足りないからやめよう」「儲けにならないからやめよう」と諦めてしまうと、そこで途切れてしまいますから。
細い糸でもいいから続けていれば、見えてくるものがあるし、いつかのメシの種につながるのではないかなと考えています。新しい価値を創造するには、何もないところから始めるよりも、すでにあるものから膨らませていくほうが創造しやすいと思うからです。

これは「失敗だったな」というものはありますか?
「こんなん、どうやろう?」という思いつきレベルのものはたくさんあり、それを熟成させた10つほどを実行に移して、そのうち3つだけが育っているという感じです。あとの7つは失敗しています。
たとえば、以前、旅行会社から持ち掛けられて、濃縮温泉を中国に向けて販売しようと考えたことがありました。3000個ほどつくってほしいとの依頼だったのですが、本格的につくる前にモニター調査として100個ほどつくって販売してみたところ、売れたのはたったの3個。
中国のお風呂事情を調べたら、シャワーがほとんどで、お風呂に浸かる習慣があるのは、一部のセレブな人たちだけだったということがわかったんです。
マーケティングがちゃんとできていなかったのが問題ですが、リスクに備えてモニター調査をしたおかげで、かすり傷くらいで済みました。どんなふうに失敗するかも大事ですし、失敗しても「7つ失敗するうちの1つかな」くらいに思ったら挑戦しやすくなるのでいいのかなと思います。
失敗しても「やってみた」ことにはかわりないので、自分の経験値にもなるんです。この時は、中国ではお風呂に浸かる習慣のある人たちは少ないから、温泉に関する商品開発は日本向けに展開していくほうがいいなということが学びになりました。
たとえば、以前、旅行会社から持ち掛けられて、濃縮温泉を中国に向けて販売しようと考えたことがありました。3000個ほどつくってほしいとの依頼だったのですが、本格的につくる前にモニター調査として100個ほどつくって販売してみたところ、売れたのはたったの3個。
中国のお風呂事情を調べたら、シャワーがほとんどで、お風呂に浸かる習慣があるのは、一部のセレブな人たちだけだったということがわかったんです。
マーケティングがちゃんとできていなかったのが問題ですが、リスクに備えてモニター調査をしたおかげで、かすり傷くらいで済みました。どんなふうに失敗するかも大事ですし、失敗しても「7つ失敗するうちの1つかな」くらいに思ったら挑戦しやすくなるのでいいのかなと思います。
失敗しても「やってみた」ことにはかわりないので、自分の経験値にもなるんです。この時は、中国ではお風呂に浸かる習慣のある人たちは少ないから、温泉に関する商品開発は日本向けに展開していくほうがいいなということが学びになりました。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
次の代への引き継ぎを始めていて、昨年から長女が銭湯経営に関わり始めてくれています。
人手が増えたので温泉宅配を期間限定で広く展開したほか、娘企画で「蓬莱市」というイベント名で、お風呂のない銭湯を楽しもうと、お風呂場のお湯を抜いて音楽コンサートや脱衣所でフリーマーケットを開催したところ、150人ほどの来場者があって賑わいました。
私は私で、次の目標に向かっていっています。
銭湯に関わる商品開発をしていきたいなと思いますし、蓬莱湯経営を通してさまざまな経験ができたので、ほかの人に対してイベントや商品開発の経験を共有したり、自分のアイデアを提案したり、私が今までしてきたことを、誰かの役に立つことにつなげられたらいいなと考えているんです。
人手が増えたので温泉宅配を期間限定で広く展開したほか、娘企画で「蓬莱市」というイベント名で、お風呂のない銭湯を楽しもうと、お風呂場のお湯を抜いて音楽コンサートや脱衣所でフリーマーケットを開催したところ、150人ほどの来場者があって賑わいました。
私は私で、次の目標に向かっていっています。
銭湯に関わる商品開発をしていきたいなと思いますし、蓬莱湯経営を通してさまざまな経験ができたので、ほかの人に対してイベントや商品開発の経験を共有したり、自分のアイデアを提案したり、私が今までしてきたことを、誰かの役に立つことにつなげられたらいいなと考えているんです。
稲 里美さん
1982年に大学を卒業後、ホテルに就職。2年ほど勤め、接客を学ぶ。1984年から銭湯を手伝いながら、フリーランスでテレビやラジオ番組の企画やネタを考えたり、宅地建物取引士として建築事務所で勤めたりする。1991年に結婚し、一時期は実家を離れるものの、1993年に夫と2人で実家に戻り、銭湯経営に関わり始める。2002年に温泉銭湯としてリニューアルオープン。2012年に先代から事業を継承し、3代目となる。市内の銭湯イベントなどにも尽力している。
蓬莱湯
兵庫県尼崎市道意町2-21-2
HP: https://houraiyu.jp/
FB: onsenlove
(取材:2019年10月)
「継続していたら、何か知らんけど、力になってくる」と稲さん。
稲さんにとって、さまざまなアイデアを出すことは、お客さんや社会とコミュニケーションすることにもなっているのかなあと思いました。「アイデアを出す=発信する」で終わるのではなく、アイデアに対する反応やニーズを受けて、改善したり発展させたり。
そうやってコミュニケーションを積み重ねた先に、最初は細い糸状だったものが、いつしか紐状になるなど、太く、長くなっていっていて、「蓬莱湯といえば、これもあれもそれも、話題に事欠かない」という今につながっているのではないかと思いました。
もう1つ、印象に残っている話があります。「1日1時間でもいいから、自分と向き合う時間を持つこと、本を読むなど自分を鍛錬する時間を持つこと。1年間で365時間も違いが出てくることになるので、全然違ってきます」と稲さんはおっしゃっていました。
稲さんのアイデアのベースにあるのは、経験と、そういった日々で積み重ねてきた知識や情報があり、さまざまな点が結びついて、アイデアを生み出しているのだと思います。
1日1時間、その時間を持つか持たないか。たった1時間とはいえ、目の前にやるべきことがあるとそれを優先してしまい、「また今度」と先伸ばしてしまう恐れがあるので、なかなか難しいこと。続ける努力が伴うものです。
だからこそ、その時間を持ち続けられるかどうかの差は大きいのだと、稲さんのお話をうかがって感じました。
HP: 『えんを描く』
稲さんにとって、さまざまなアイデアを出すことは、お客さんや社会とコミュニケーションすることにもなっているのかなあと思いました。「アイデアを出す=発信する」で終わるのではなく、アイデアに対する反応やニーズを受けて、改善したり発展させたり。
そうやってコミュニケーションを積み重ねた先に、最初は細い糸状だったものが、いつしか紐状になるなど、太く、長くなっていっていて、「蓬莱湯といえば、これもあれもそれも、話題に事欠かない」という今につながっているのではないかと思いました。
もう1つ、印象に残っている話があります。「1日1時間でもいいから、自分と向き合う時間を持つこと、本を読むなど自分を鍛錬する時間を持つこと。1年間で365時間も違いが出てくることになるので、全然違ってきます」と稲さんはおっしゃっていました。
稲さんのアイデアのベースにあるのは、経験と、そういった日々で積み重ねてきた知識や情報があり、さまざまな点が結びついて、アイデアを生み出しているのだと思います。
1日1時間、その時間を持つか持たないか。たった1時間とはいえ、目の前にやるべきことがあるとそれを優先してしまい、「また今度」と先伸ばしてしまう恐れがあるので、なかなか難しいこと。続ける努力が伴うものです。
だからこそ、その時間を持ち続けられるかどうかの差は大きいのだと、稲さんのお話をうかがって感じました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(会社経営) 記事一覧
-
「今できることを諦めず一所懸命に取り組んでみる」過去3度の出入りを経て父の保育園の園長となった太田さん
-
「ゼロから始めることで新たな成長や飛躍につながる」平凡な社員から転職。社長に就任した神田さん
-
「心の叫びに気づくことが大切」「手に職を」と思い立ち、プリザーブドフラワー専門店を開いた志摩子さん
-
「お客さんが飽きないように商いを続ける」尼崎の昭和6年創業「蓬莱湯」の3代目を継ぎ、次世代へ繋ぐ里美さん
-
「まずは私自身が変わらないといけない」老舗家業の3代目として事業承継。新たな歴史を創る吉田さん
-
「行動を起こすことで少しでもよくなるなら私がする」2代目社長として新たな発想で会社経営に取り組む角井さん
-
「笑顔の裏側に、自分への厳しさと緊張感を」老舗旅館の女将として伝統を受け継ぎ、次の世代に継ぐ南さん
-
「壁にぶち当たっても、その先はもっと開けて明るい」グラスアート「ロクレール」の技法を引き継ぐ向井さん
-
「見えないところで努力する。それが伝統を受け継いでいくこと」160年続く老舗の婚礼衣装店、5代目の熊谷さん
-
「女性船員も雇用できる魅力ある会社にしたい」船が好きで海運会社の三代目後継者として働く紗苗さん
-
「なんとなく成長するなんて不可能」学者志望から家族の会社を継承、シルク製品の自社ブランドを作る明子さん
-
「この道を選ぶならブレずにまっしぐら。GIRLS, be ambitious!」創業38年イノベーションし続ける長谷川社長
-
「女性をキレイにする旅」をコンセプトに、海外1人旅のコーディネートからユニークな京都旅プランまで「女性の旅」をプロデュース
-
宝塚の情報誌「宝塚ROSE」を発行して10年。元ジェンヌのプロデュースなど宝塚の活性を担う事業を手がける井川さん
-
1000人のロールモデルを創るネオウーマン の代表でもあり、苦難を乗り越えて会社を守る経営者でもある菊川さん