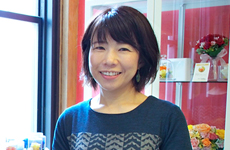HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
![]() 木下 志磨子さん(pundamilia/京都しまうま堂 株式会社 代表取締役社長)
木下 志磨子さん(pundamilia/京都しまうま堂 株式会社 代表取締役社長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
木下 志磨子さん(pundamilia/京都しまうま堂 株式会社 代表取締役社長)

自分が何をしたいかという「心の叫び」に気づく
木下 志磨子さん
pundamilia(プンダミリア)
京都しまうま堂 株式会社 代表取締役社長
pundamilia(プンダミリア)
京都しまうま堂 株式会社 代表取締役社長
京都にプリザーブドフラワー専門店「pundamilia(プンダミリア)」と、思い出のお花をプリザーブドフラワーに加工するお店「Spun(スプン)」を展開する京都しまうま堂株式会社。
クマやウサギ、シマウマ、ヒツジ、アルパカといった愛らしいマスコットと、プリザーブドフラワーを小さな器に組み合わせたお花畑のアレンジメントや、お客さまのオーダーを聞きながらその場でつくるプリザーブドフラワーのアレンジメントが人気です。
「負けず嫌いの私はきっと何かの分野で1位になりたかったのでしょう」と話すのは、代表取締役社長の木下志磨子さん。「一生働くために、手に職を」と考え、広告代理店の営業職からお花に関わる仕事へ。生花店での修業時代に経験した悔しい経験を経て、プリザーブドフラワーに特化した「pundamilia」を2005年に開店しました。
「心の叫びに気づくことが大切」と木下さん。「心の叫び」とは一体、何なのでしょうか。
クマやウサギ、シマウマ、ヒツジ、アルパカといった愛らしいマスコットと、プリザーブドフラワーを小さな器に組み合わせたお花畑のアレンジメントや、お客さまのオーダーを聞きながらその場でつくるプリザーブドフラワーのアレンジメントが人気です。
「負けず嫌いの私はきっと何かの分野で1位になりたかったのでしょう」と話すのは、代表取締役社長の木下志磨子さん。「一生働くために、手に職を」と考え、広告代理店の営業職からお花に関わる仕事へ。生花店での修業時代に経験した悔しい経験を経て、プリザーブドフラワーに特化した「pundamilia」を2005年に開店しました。
「心の叫びに気づくことが大切」と木下さん。「心の叫び」とは一体、何なのでしょうか。
一生働くためには、「自分でやるしかない」
以前は広告代理店に勤めておられたそうですね。
希望の仕事につけなくて、生活のためにひとまず就職したのが広告代理店だったんです。
もともとは「海外で働きたい」という希望を持っていました。子どもの頃にいじめられた経験があり、この狭い世界に嫌気が差して「もっと広い世界に出れば、いじめられないんじゃないか」との思いから、「広い世界=海外」に行きたいと思うようになったんです。
高校時代には、知り合ったアメリカ人の実家に単身で2カ月お世話になるという今思えば無謀な行動をして、さらにはアメリカの州立大学を受験して、進学することも決めていたんです。
その後まもなく、その大学の付近で日本人留学生射殺事件が起き、不安に思った母から大反対され、やむを得ず、国内の大学の英文科に進学することにしました。
大学在学中も、海外で働く希望を持ち続け、「大学卒業後こそは」と海外で日本人向けのツアーガイドや空港職員として働く道を模索するも、時代は就職氷河期。志望先にはことごとく不採用で、結果、広告代理店で営業職として働くことになったんです。
私が勤めた中小企業は当時、まだまだ男性社会で、特に営業職には女性社員自体が珍しく、キャリアアップをめざすなら、結婚や出産を諦めざるを得ない空気を感じました。よっぽどの大企業でない限り、どこの職場も同じだろうなあと、まだ24歳なのに社会に対して冷めていて(笑)。
母は料理人、祖母は建設会社社長と、女性も一生働くというのを当たり前に見てきましたから、私の中に専業主婦になる考えはなく、じゃあ、自分でやるしかないなあと思ったんです。
もともとは「海外で働きたい」という希望を持っていました。子どもの頃にいじめられた経験があり、この狭い世界に嫌気が差して「もっと広い世界に出れば、いじめられないんじゃないか」との思いから、「広い世界=海外」に行きたいと思うようになったんです。
高校時代には、知り合ったアメリカ人の実家に単身で2カ月お世話になるという今思えば無謀な行動をして、さらにはアメリカの州立大学を受験して、進学することも決めていたんです。
その後まもなく、その大学の付近で日本人留学生射殺事件が起き、不安に思った母から大反対され、やむを得ず、国内の大学の英文科に進学することにしました。
大学在学中も、海外で働く希望を持ち続け、「大学卒業後こそは」と海外で日本人向けのツアーガイドや空港職員として働く道を模索するも、時代は就職氷河期。志望先にはことごとく不採用で、結果、広告代理店で営業職として働くことになったんです。
私が勤めた中小企業は当時、まだまだ男性社会で、特に営業職には女性社員自体が珍しく、キャリアアップをめざすなら、結婚や出産を諦めざるを得ない空気を感じました。よっぽどの大企業でない限り、どこの職場も同じだろうなあと、まだ24歳なのに社会に対して冷めていて(笑)。
母は料理人、祖母は建設会社社長と、女性も一生働くというのを当たり前に見てきましたから、私の中に専業主婦になる考えはなく、じゃあ、自分でやるしかないなあと思ったんです。

もともとは「海外で働きたい」という希望があったとのこと。どうして、お花に関わることをお仕事にしようと思われたのですか?
「一生働くために、何か手に職をつけよう」と考えた時、自分が好きな手芸かお花に関わることを仕事にしようと思ったんです。
子どもの頃からバービー人形の洋服を手づくりしたり、学校では編み物クラブに入ったりなど手芸が好きでした。
また、実家は長野県の山奥で、子どもの頃、ひいおじいちゃんがネジバナといった高山植物やお花を摘んで私にプレゼントしてくれていたんです。子ども心に、お花をもらうことがすごく嬉しくて。
母に「枯れちゃうから、とっておきたい」と言ったら、「押し花というのがあるよ」と教えてもらい、電話帳に挟んで押し花にしていたことを思い出します。
「毛糸屋さんで働きたいなあ」「手芸店をするのもいいかも」など思い浮かびましたが、自分にはお花が合う気がしました。
手芸には決まり事があって、レシピ通りに編まないとマフラーは出来上がりませんが、お花は決まり事がなく、「こうしたらどうだろう」と思い付きなども含めて感覚的にアレンジメントをつくることができるので、そちらのほうが楽しいなあって。
もともとやりたかった海外で働くことも頭を過りました。でも、気づいたんです。手に職をつければ、それを通じて海外に行くことができるんじゃないかって。お花の仕事を通じて、海外で仕事ができればいいなあと思いました。
子どもの頃からバービー人形の洋服を手づくりしたり、学校では編み物クラブに入ったりなど手芸が好きでした。
また、実家は長野県の山奥で、子どもの頃、ひいおじいちゃんがネジバナといった高山植物やお花を摘んで私にプレゼントしてくれていたんです。子ども心に、お花をもらうことがすごく嬉しくて。
母に「枯れちゃうから、とっておきたい」と言ったら、「押し花というのがあるよ」と教えてもらい、電話帳に挟んで押し花にしていたことを思い出します。
「毛糸屋さんで働きたいなあ」「手芸店をするのもいいかも」など思い浮かびましたが、自分にはお花が合う気がしました。
手芸には決まり事があって、レシピ通りに編まないとマフラーは出来上がりませんが、お花は決まり事がなく、「こうしたらどうだろう」と思い付きなども含めて感覚的にアレンジメントをつくることができるので、そちらのほうが楽しいなあって。
もともとやりたかった海外で働くことも頭を過りました。でも、気づいたんです。手に職をつければ、それを通じて海外に行くことができるんじゃないかって。お花の仕事を通じて、海外で仕事ができればいいなあと思いました。

広告代理店を退職した後に渡米されたのには、そういった想いがあったからなんですね。
世界の花屋も見ておきたいとアメリカで1年間、お花の勉強をしたり、花屋で働いたりしました。
アメリカの花屋にはお花だけではなく、お花に合うワインや雑貨なども置いていて、すごくおしゃれで素敵。見聞きしたことすべてが刺激的でした。
最初から30歳くらいには独立したいと考えていたので、渡米前に老舗の花屋で経営について学び、帰国後は心惹かれたお花のアレンジメントをつくる方に弟子入りしたほか、掛け持ちでアルバイトした花屋では会場装花や教室運営について経験を積みました。
「手に職を」と思い立って5年、29歳の時に独立して、プリザーブドフラワー専門店「pundamilia」を開店したんです。
アメリカの花屋にはお花だけではなく、お花に合うワインや雑貨なども置いていて、すごくおしゃれで素敵。見聞きしたことすべてが刺激的でした。
最初から30歳くらいには独立したいと考えていたので、渡米前に老舗の花屋で経営について学び、帰国後は心惹かれたお花のアレンジメントをつくる方に弟子入りしたほか、掛け持ちでアルバイトした花屋では会場装花や教室運営について経験を積みました。
「手に職を」と思い立って5年、29歳の時に独立して、プリザーブドフラワー専門店「pundamilia」を開店したんです。

悔しい経験も、独自性を切り拓く力に
複数の生花店で経験を積まれて独立されました。お花の中でも、どうして「プリザーブドフラワー専門店」としたのですか?
自分にしかできないことについて考える出来事があったからです。
独立直前までアルバイトをしていた花屋で会場装花を担当していました。ずっと担当していたお客さまから、ある時「今度、桜の木を使った装花をしたいから、担当を男性にかわってほしい」と言われたんです。ものすごく悔しい出来事でした。
確かに枝ものを使う大掛かりな装飾は体力面から男性に敵わないと思う部分があります。負けず嫌いの私はきっと何かの分野で1位になりたかったのでしょう。生花の分野では難しいけれど、どの分野だったら1位になれるかを考え、頭に浮かんだのがプリザーブドフラワーでした。
プリザーブドフラワーのことは、アメリカで働いていた花屋で知りました。
アメリカは国の面積が大きいので、遠方の人に贈る場合、生花よりプリザーブドフラワーのほうがいいですし、インテリアとして楽しまれていました。帰国後に師匠に弟子入りしたのも、師匠はプリザーブドフラワーを扱った作品をつくっていたからでした。
師匠から「自分の好きなようにつくってみたら」と言われた時につくったのが、今の世界観につながるものです。エンゼルの置物を置いて、まわりを囲むようにお花を飾りました。すると、エンゼル単体で見た時と、お花に囲まれた状態で見た時とでは、エンゼルの表情が全然違って見えたんです。
「お花ってすごいなあ」と改めて思い、お花と何かを組み合わせて、その器の中に世界をつくることがすごく楽しいなあって。もともと手芸などものづくりが好きだから、それを活かせる表現なのだと思います。
独立直前までアルバイトをしていた花屋で会場装花を担当していました。ずっと担当していたお客さまから、ある時「今度、桜の木を使った装花をしたいから、担当を男性にかわってほしい」と言われたんです。ものすごく悔しい出来事でした。
確かに枝ものを使う大掛かりな装飾は体力面から男性に敵わないと思う部分があります。負けず嫌いの私はきっと何かの分野で1位になりたかったのでしょう。生花の分野では難しいけれど、どの分野だったら1位になれるかを考え、頭に浮かんだのがプリザーブドフラワーでした。
プリザーブドフラワーのことは、アメリカで働いていた花屋で知りました。
アメリカは国の面積が大きいので、遠方の人に贈る場合、生花よりプリザーブドフラワーのほうがいいですし、インテリアとして楽しまれていました。帰国後に師匠に弟子入りしたのも、師匠はプリザーブドフラワーを扱った作品をつくっていたからでした。
師匠から「自分の好きなようにつくってみたら」と言われた時につくったのが、今の世界観につながるものです。エンゼルの置物を置いて、まわりを囲むようにお花を飾りました。すると、エンゼル単体で見た時と、お花に囲まれた状態で見た時とでは、エンゼルの表情が全然違って見えたんです。
「お花ってすごいなあ」と改めて思い、お花と何かを組み合わせて、その器の中に世界をつくることがすごく楽しいなあって。もともと手芸などものづくりが好きだから、それを活かせる表現なのだと思います。

自分の世界観を表現するのが楽しいのなら、作家という道もあったと思います。お客さまのオーダーを聞いてつくる「オーダーメイドのプリザーブドフラワー」もメインとされているのには、何か理由があるのですか?
オーダーを受注するきっかけは、売れるかどうかわからないものをたくさんつくるより効率的だったからと、プリザーブドフラワーを生花のような感覚で楽しんでほしいという想いがあったからです。
加えて、お店をする中で深まってきたものがあります。
独立するまでは「お花を売る」というスタンスで、「どうしたら、売れるか」という販売者側の視点でいたように思います。それが独立して、一人ひとりのお客さまの大切さをひしひしとわかるようになると、「どうして、お客さまはお花を買うのだろう」と突き詰めて考えるようになりました。
お花は食べられるものでも、使えるものでもなく、生きていく上で直接的に何か役に立つものではありません。こんなにもいろいろなものが溢れる世の中で、どうしてお花を選んでくださるんだろう。そう考える中で、気づいたんです。
お花を買う時点で、そのお花は私のものではなく、お客さまのものになります。
たとえば、「ご病気の方に、お花を見て、元気になってほしい」というお客さまがいます。その時点で、このお花にはとても大事な役割が生まれるんです。私は、そのお客さまの想いをお花にのせる代理店みたいなものだなあと思いました。
それからは「お花を売っています」というおこがましい気持ちではなく、「お客さまの想いが伝わるようなお花をつくっています」という気持ちでいます。
お客さまから贈る相手のことや相手への気持ち、シチュエーションなどをうかがって、そのことを思い浮かべながらつくると、お花の表情も変わってくると信じています。だから、オーダーメイドをメインとしているんです。
加えて、お店をする中で深まってきたものがあります。
独立するまでは「お花を売る」というスタンスで、「どうしたら、売れるか」という販売者側の視点でいたように思います。それが独立して、一人ひとりのお客さまの大切さをひしひしとわかるようになると、「どうして、お客さまはお花を買うのだろう」と突き詰めて考えるようになりました。
お花は食べられるものでも、使えるものでもなく、生きていく上で直接的に何か役に立つものではありません。こんなにもいろいろなものが溢れる世の中で、どうしてお花を選んでくださるんだろう。そう考える中で、気づいたんです。
お花を買う時点で、そのお花は私のものではなく、お客さまのものになります。
たとえば、「ご病気の方に、お花を見て、元気になってほしい」というお客さまがいます。その時点で、このお花にはとても大事な役割が生まれるんです。私は、そのお客さまの想いをお花にのせる代理店みたいなものだなあと思いました。
それからは「お花を売っています」というおこがましい気持ちではなく、「お客さまの想いが伝わるようなお花をつくっています」という気持ちでいます。
お客さまから贈る相手のことや相手への気持ち、シチュエーションなどをうかがって、そのことを思い浮かべながらつくると、お花の表情も変わってくると信じています。だから、オーダーメイドをメインとしているんです。

どん底の経験が、経営者として成長につながった
「プンダミリア」を開店して15年目。これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
壁なんてものすごくありますが、大きな出来事で言うと2つあります。
独立当時はプリザーブドフラワーが今のように認知されていなかったので、お客さまから見ると「プリザーブドフラワーって、何?」というところからの始まりでした。
花屋の先輩や仲間からも「プリザーブドフラワーだけでは、やっていけないのでは?」と心配されました。自分自身も「これでいける」とは思っておらず、不安な気持ちがあったのも確かです。でも、「みんなと同じことをやっていても仕方がない」という気持ちもあって(笑)。
前の職場でのつながりから百貨店内に出店できることになったので、自分が1から始めるのとは違い、百貨店のお客さまがついているところからのスタートでしたから、「プリザーブドフラワーって、何?」というのが逆に物珍しくていいのではないかなあと思い直しました。
一人ひとりのお客さまを大切にして、日々経営していく中で、リピーターが少しずつ増えていき、そうしている間に、世間でもプリザーブドフラワーの認知度が上がってきました。
今では、SEO対策らしいことをしていなくても、インターネットで「プリザーブドフラワー 京都」で検索すると上位に出てくるようになっていて、それを見て来てくださるお客さまがいます。専門店と振り切ったこと、専門店として長年続けてきたことで、今もこうして続けられています。
もう1つが大きな壁だったのは、「人を雇う」ことです。
独立当時はプリザーブドフラワーが今のように認知されていなかったので、お客さまから見ると「プリザーブドフラワーって、何?」というところからの始まりでした。
花屋の先輩や仲間からも「プリザーブドフラワーだけでは、やっていけないのでは?」と心配されました。自分自身も「これでいける」とは思っておらず、不安な気持ちがあったのも確かです。でも、「みんなと同じことをやっていても仕方がない」という気持ちもあって(笑)。
前の職場でのつながりから百貨店内に出店できることになったので、自分が1から始めるのとは違い、百貨店のお客さまがついているところからのスタートでしたから、「プリザーブドフラワーって、何?」というのが逆に物珍しくていいのではないかなあと思い直しました。
一人ひとりのお客さまを大切にして、日々経営していく中で、リピーターが少しずつ増えていき、そうしている間に、世間でもプリザーブドフラワーの認知度が上がってきました。
今では、SEO対策らしいことをしていなくても、インターネットで「プリザーブドフラワー 京都」で検索すると上位に出てくるようになっていて、それを見て来てくださるお客さまがいます。専門店と振り切ったこと、専門店として長年続けてきたことで、今もこうして続けられています。
もう1つが大きな壁だったのは、「人を雇う」ことです。

「人を雇うこと」での壁とは?
百貨店は年中無休なのに、どう運営するかについて、何も考えずに1人で始めてしまったので、開店直後から「トイレに簡単に行けない」「昼ごはんを食べる時間もない」「休みもない」と。
ですが、自分が生活していくので精一杯で、人を雇う余裕もなかったので、土日の忙しい時だけ、友だちや花屋の後輩に手伝いに来てもらうようになりました。
1年ほど経つと、それも限界になってきて、求人を出すことにしたんです。友だちに手伝いに来てもらっていた延長線上で雇用してしまったところ、大きなトラブルに発展したんです。
お店を始めて、6年目の出来事でした。
友だちに手伝ってもらうのに、契約書なんてつくらないじゃないですか。約束書きみたいなものを渡して、それで問題なくいっていたので、求人募集したスタッフにも同じようにしていたら、あるスタッフから訴えられてしまったんです。
「残業代をもらっていない」「タイムカードの記録以外にも働いていました」など言われたのですが、残業代は払っていましたし、サービス残業をしてもらったこともありません。でも、契約書をきちんと交わしていない時点で、雇用者側の落ち度ですので、反論のしようがなかったんです。
人を雇うに当たってルールを知っておかないと、お互いの小さな誤解やすれ違いから、溝を生み、大きなトラブルに発展するのだと身に染みてわかった出来事です。
それからは猛勉強して、社会保険労務士さんとも契約しました。その時に社会保険労務士さんから「車の免許を持たずに車を運転していたようなものですよ」と言われて。確かにそうかもしれないけれど、じゃあ人を雇うのも、車の免許を取るみたいにしてほしいと思いながら。
どん底まで落ちる経験でしたが、ぶち当たったおかげで勉強する機会になり、少しずつ会社らしくなっていけたかなあと思います。
独立して11年目には「京都しまうま堂株式会社」を設立しました。花屋は個人事業主が多く、社会保障がないため、将来的に不安というのは、私も雇われている時代に感じていました。人を雇うことについて義務を背負っていきたいと、株式会社化したんです。
ですが、自分が生活していくので精一杯で、人を雇う余裕もなかったので、土日の忙しい時だけ、友だちや花屋の後輩に手伝いに来てもらうようになりました。
1年ほど経つと、それも限界になってきて、求人を出すことにしたんです。友だちに手伝いに来てもらっていた延長線上で雇用してしまったところ、大きなトラブルに発展したんです。
お店を始めて、6年目の出来事でした。
友だちに手伝ってもらうのに、契約書なんてつくらないじゃないですか。約束書きみたいなものを渡して、それで問題なくいっていたので、求人募集したスタッフにも同じようにしていたら、あるスタッフから訴えられてしまったんです。
「残業代をもらっていない」「タイムカードの記録以外にも働いていました」など言われたのですが、残業代は払っていましたし、サービス残業をしてもらったこともありません。でも、契約書をきちんと交わしていない時点で、雇用者側の落ち度ですので、反論のしようがなかったんです。
人を雇うに当たってルールを知っておかないと、お互いの小さな誤解やすれ違いから、溝を生み、大きなトラブルに発展するのだと身に染みてわかった出来事です。
それからは猛勉強して、社会保険労務士さんとも契約しました。その時に社会保険労務士さんから「車の免許を持たずに車を運転していたようなものですよ」と言われて。確かにそうかもしれないけれど、じゃあ人を雇うのも、車の免許を取るみたいにしてほしいと思いながら。
どん底まで落ちる経験でしたが、ぶち当たったおかげで勉強する機会になり、少しずつ会社らしくなっていけたかなあと思います。
独立して11年目には「京都しまうま堂株式会社」を設立しました。花屋は個人事業主が多く、社会保障がないため、将来的に不安というのは、私も雇われている時代に感じていました。人を雇うことについて義務を背負っていきたいと、株式会社化したんです。

「心の叫び」が教えてくれること
同じお仕事をしたいと思う方に、どんなアドバイスをしますか?
独自の色を出していくことが、何事においても必要ではないでしょうか。
売れる店ではなく、私らしい店づくりは何なのかを追求すると、きっと好きな人が集まり、楽しく仕事できるのではないかと思います。
私も時々、見失うんです。だって、売れるほうが、経営していくためには嬉しいじゃないですか。でも、売上をあげることが1番の目的になってしまったら、目先のことばかりにとらわれてしまいます。
たとえば、お花の世界では2~3年前から、ハーバリウムが爆発的な人気があります。問い合わせもすごくありますから、ハーバリウムを取り扱えば、一時的には売上があがると思うんです。でも、ただ「流行っているから」という理由で、取り扱い始めたら、ぶれてしまいます。
「自分のやりたいことって、何なの?」と考える時間を持つようにしています。
売れる店ではなく、私らしい店づくりは何なのかを追求すると、きっと好きな人が集まり、楽しく仕事できるのではないかと思います。
私も時々、見失うんです。だって、売れるほうが、経営していくためには嬉しいじゃないですか。でも、売上をあげることが1番の目的になってしまったら、目先のことばかりにとらわれてしまいます。
たとえば、お花の世界では2~3年前から、ハーバリウムが爆発的な人気があります。問い合わせもすごくありますから、ハーバリウムを取り扱えば、一時的には売上があがると思うんです。でも、ただ「流行っているから」という理由で、取り扱い始めたら、ぶれてしまいます。
「自分のやりたいことって、何なの?」と考える時間を持つようにしています。

木下さんが流行りなどに乗らずに、貫き通せたのはなぜだと思いますか?
そもそもあまのじゃくですから(笑)。
でも、そうやって流行りに乗ってこなかったから、流行り廃りの影響を受けて、お客さまが変動することはほとんどありませんでした。もし流行りに乗ってぶれていたら、ブームに左右されて、苦境を迎えていたかもしれません。
そういえば、独立当初、百貨店に出店したということもあり、いろんな人からアドバイスを受けて2~3万円規模の高級で大ぶりなものをつくって販売していた時期がありました。お客さまがいない時間帯に、自分がかわいいと思うものをつくっていたら、「ほしい」と言われることが重なり、自分では「ええっと!」とびっくり。
それをきっかけに、「高級品を売ることが、私のしたかったことなの?」って。もちろん、売れたらありがたいけれど、違うよねって。それから自分がかわいいと思うものをつくることで、賛同してくれる人たちがいて、今があります。
「自分がやりたいことって、何なの?」「自分が楽しいと思えることって、何なの?」「自分はどうなったら嬉しいの?」と考えて、「本当はこうしたいよね」「こんなことがしたかったよね」という心の叫びに気づくことが、1番大切なことかなと思います。
そういったことを繰り返していると、原点にもたどり着くんです。「世界に通じるような、花屋がやりたかったんじゃないの?」「それが、私がそもそもやりたかったことでしょ」って。独立して15年、そろそろまた一歩踏み出そうとしているところです。
でも、そうやって流行りに乗ってこなかったから、流行り廃りの影響を受けて、お客さまが変動することはほとんどありませんでした。もし流行りに乗ってぶれていたら、ブームに左右されて、苦境を迎えていたかもしれません。
そういえば、独立当初、百貨店に出店したということもあり、いろんな人からアドバイスを受けて2~3万円規模の高級で大ぶりなものをつくって販売していた時期がありました。お客さまがいない時間帯に、自分がかわいいと思うものをつくっていたら、「ほしい」と言われることが重なり、自分では「ええっと!」とびっくり。
それをきっかけに、「高級品を売ることが、私のしたかったことなの?」って。もちろん、売れたらありがたいけれど、違うよねって。それから自分がかわいいと思うものをつくることで、賛同してくれる人たちがいて、今があります。
「自分がやりたいことって、何なの?」「自分が楽しいと思えることって、何なの?」「自分はどうなったら嬉しいの?」と考えて、「本当はこうしたいよね」「こんなことがしたかったよね」という心の叫びに気づくことが、1番大切なことかなと思います。
そういったことを繰り返していると、原点にもたどり着くんです。「世界に通じるような、花屋がやりたかったんじゃないの?」「それが、私がそもそもやりたかったことでしょ」って。独立して15年、そろそろまた一歩踏み出そうとしているところです。

「また新たな一歩を」とのこと。どんなことを考えているのですか?
2年前に、お花の仕入れの関係でベトナムに行った帰りに、20時間のトランジットがあったので、台湾に寄りました。台湾の花文化を知りたいと、花屋や百貨店などをめぐると、日本以上にプリザーブドフラワーが流行っていたんです。
日々を過ごしていると、どうしても目の前のことだけでいっぱいになってしまいますが、台湾の賑わいを見て、プリザーブドフラワーの可能性を広げていきたいという気持ちが湧き出てきました。
宿泊先のオーナーと友だちになり、以降はオーナーが来日してくれたり、台湾の花屋さんを紹介してくれたり、交流を続けています。台湾で何か継続できることをできたらいいなあと話しているところなんです。
具体的にはいろいろ考え中ですが、たとえば、欧米ではお花は身近で、お花を買って帰って日常的に飾る文化があるのですが、日本や台湾では記念や感謝など特別な時に贈るものというイメージがあります。
これからの時代は「物を買う」よりも「思い出を残すなどサービスにお金を使う」ほうが重視されていくと思うので、台湾でも「Spun」というブランドで展開しているような、お花を思い出とともに保存できるプリザーブドフラワーの提案などできないかなあと考えています。
日々を過ごしていると、どうしても目の前のことだけでいっぱいになってしまいますが、台湾の賑わいを見て、プリザーブドフラワーの可能性を広げていきたいという気持ちが湧き出てきました。
宿泊先のオーナーと友だちになり、以降はオーナーが来日してくれたり、台湾の花屋さんを紹介してくれたり、交流を続けています。台湾で何か継続できることをできたらいいなあと話しているところなんです。
具体的にはいろいろ考え中ですが、たとえば、欧米ではお花は身近で、お花を買って帰って日常的に飾る文化があるのですが、日本や台湾では記念や感謝など特別な時に贈るものというイメージがあります。
これからの時代は「物を買う」よりも「思い出を残すなどサービスにお金を使う」ほうが重視されていくと思うので、台湾でも「Spun」というブランドで展開しているような、お花を思い出とともに保存できるプリザーブドフラワーの提案などできないかなあと考えています。
木下 志磨子さん
大学卒業後、広告代理店に就職。2年ほどで退職し、お花に関わる仕事をするため、老舗生花店に入店。その後、お花のデザインと店舗運営を学ぶために、アメリカに1年間留学した。2011年に帰国後、フラワーアーティストに弟子入り、掛け持ちで生花店に入店する。2015年9月に独立し、プリザーブドフラワー専門店「pundamilia(プンダミリア)」を開店。2016年には京都しまうま堂株式会社設立。現在は「pundamilia」2店舗、思い出のお花をプリザーブドフラワーに加工するお店「Spun(スプン)」1店舗を展開している。
pundamilia(プンダミリア)
本店 京都市中京区三条通富小路西入る中之町20 sacraビル2階
Web: https://pundamilia.jp/
Facebook: pundamiliaflower
Instagram: pundamilia87/
(取材:2019年12月)
木下さんが子どもの頃、ひいおじいさまから会うたびにもらっていたというお花。そのお花が嬉しくて「残したい」と、押し花をつくっていたそうです。
そのことを振り返りながら、木下さんご自身も「今思えば、プリザーブドフラワーにつながっているのかもしれませんね」とおっしゃっていましたが、その時の体験や気持ちが今につながっておられるのだと思いました。
それはきっと、木下さんご自身が、その瞬間瞬間の自分の気持ちを大切にされてこられたからではないでしょうか。それを表す言葉が「心の叫びに気づく」だったように思います。
「原点にかえる」とは違う、「心の叫びに気づく」。
「原点=この道を志した時」から、さまざまな経験を経て、考えも気持ちも状況も変わっていくものです。そんな中でも、自分自身が「本当は何をしたいのか」「どうしたいのか」と思っていることは、木下さんがおっしゃられるように「叫び」みたいな感じで、自分の中にあるのではないでしょうか。
HP: 『えんを描く』
そのことを振り返りながら、木下さんご自身も「今思えば、プリザーブドフラワーにつながっているのかもしれませんね」とおっしゃっていましたが、その時の体験や気持ちが今につながっておられるのだと思いました。
それはきっと、木下さんご自身が、その瞬間瞬間の自分の気持ちを大切にされてこられたからではないでしょうか。それを表す言葉が「心の叫びに気づく」だったように思います。
「原点にかえる」とは違う、「心の叫びに気づく」。
「原点=この道を志した時」から、さまざまな経験を経て、考えも気持ちも状況も変わっていくものです。そんな中でも、自分自身が「本当は何をしたいのか」「どうしたいのか」と思っていることは、木下さんがおっしゃられるように「叫び」みたいな感じで、自分の中にあるのではないでしょうか。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(会社経営) 記事一覧
-
「今できることを諦めず一所懸命に取り組んでみる」過去3度の出入りを経て父の保育園の園長となった太田さん
-
「ゼロから始めることで新たな成長や飛躍につながる」平凡な社員から転職。社長に就任した神田さん
-
「心の叫びに気づくことが大切」「手に職を」と思い立ち、プリザーブドフラワー専門店を開いた志摩子さん
-
「お客さんが飽きないように商いを続ける」尼崎の昭和6年創業「蓬莱湯」の3代目を継ぎ、次世代へ繋ぐ里美さん
-
「まずは私自身が変わらないといけない」老舗家業の3代目として事業承継。新たな歴史を創る吉田さん
-
「行動を起こすことで少しでもよくなるなら私がする」2代目社長として新たな発想で会社経営に取り組む角井さん
-
「笑顔の裏側に、自分への厳しさと緊張感を」老舗旅館の女将として伝統を受け継ぎ、次の世代に継ぐ南さん
-
「壁にぶち当たっても、その先はもっと開けて明るい」グラスアート「ロクレール」の技法を引き継ぐ向井さん
-
「見えないところで努力する。それが伝統を受け継いでいくこと」160年続く老舗の婚礼衣装店、5代目の熊谷さん
-
「女性船員も雇用できる魅力ある会社にしたい」船が好きで海運会社の三代目後継者として働く紗苗さん
-
「なんとなく成長するなんて不可能」学者志望から家族の会社を継承、シルク製品の自社ブランドを作る明子さん
-
「この道を選ぶならブレずにまっしぐら。GIRLS, be ambitious!」創業38年イノベーションし続ける長谷川社長
-
「女性をキレイにする旅」をコンセプトに、海外1人旅のコーディネートからユニークな京都旅プランまで「女性の旅」をプロデュース
-
宝塚の情報誌「宝塚ROSE」を発行して10年。元ジェンヌのプロデュースなど宝塚の活性を担う事業を手がける井川さん
-
1000人のロールモデルを創るネオウーマン の代表でもあり、苦難を乗り越えて会社を守る経営者でもある菊川さん