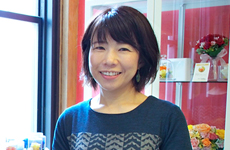HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
![]() 吉田まさきこさん(株式会社ワイングロッサリー 代表取締役社長)
吉田まさきこさん(株式会社ワイングロッサリー 代表取締役社長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
吉田まさきこさん(株式会社ワイングロッサリー 代表取締役社長)

まわりではなく、まずは私自身が変わらないといけない
吉田 まさきこさん
株式会社ワイングロッサリー 代表取締役社長
株式会社ワイングロッサリー 代表取締役社長
フランスやイタリア、スペインといったヨーロッパを中心に世界各国のワインを3000種類以上取り揃える実店舗とウェブショップを展開するほか、ワイン教室やイベントなども開催する株式会社ワイングロッサリー。現社長の吉田まさきこさんは、2代目のお母さまから2013年に事業を承継した3代目です。
食に関わる仕事をしたいとの想いがあり、先代の「この仕事をしたら、おいしいものが食べられるわよ」という一言に魅かれて入社。ワインを販売する仕事にやりがいを感じ、「この仕事を続けていきたい」と思った時、事業を承継する覚悟ができたそうです。
就任時より家族経営から組織経営への改革に着手するなどしてきた吉田さんですが、「ワインを販売する仕事は大好きだけれど、私は経営者に向いていないのかもしれない」と思い悩んだ時期があったと振り返ります。事業承継後に、吉田さんが「ぶつかった壁」とは?
食に関わる仕事をしたいとの想いがあり、先代の「この仕事をしたら、おいしいものが食べられるわよ」という一言に魅かれて入社。ワインを販売する仕事にやりがいを感じ、「この仕事を続けていきたい」と思った時、事業を承継する覚悟ができたそうです。
就任時より家族経営から組織経営への改革に着手するなどしてきた吉田さんですが、「ワインを販売する仕事は大好きだけれど、私は経営者に向いていないのかもしれない」と思い悩んだ時期があったと振り返ります。事業承継後に、吉田さんが「ぶつかった壁」とは?
「この仕事を続けていきたい」という想いが、覚悟に
曾祖父さまが創業され、お父さまとお母さまの代になり、現在は吉田さんが引き継いでおられます。子どもの頃からいずれは継ぐかもしれないと意識されていたのですか?
曾祖父が明治10年に創業した時は酒類や醤油、塩などの小売業をしていました。祖父は早くに亡くなったので、その後は父と母が1975年に承継し、当時は珍しいワインを専門に取り扱うようになったんです。
父は私が中学生の時に亡くなりましたので、以降は長年、母が1人で経営してきました。
私には姉がいて、ふたりとも、母から「継いでほしい」と言われたことがありません。私自身も継ごうなんて考えたことがなく、子どもの頃から食いしん坊で、食べることが大好きだから、大学では栄養学部に進学し、管理栄養士として働くつもりでいました。
でも、卒業前に管理栄養士の研修に行ったところ、「自分が思い描いていたものと何か違うぞ」と。食のおもしろさや楽しさに関わる仕事ができたらいいなあとの想いがあったからです。
迷っていたところ、「この仕事をしたら、おいしいものが食べられるわよ」という母の一言に魅かれて、「じゃあ、1回働いてみようかな」と軽い気持ちで、アルバイトとして1998年に入社しました。
父は私が中学生の時に亡くなりましたので、以降は長年、母が1人で経営してきました。
私には姉がいて、ふたりとも、母から「継いでほしい」と言われたことがありません。私自身も継ごうなんて考えたことがなく、子どもの頃から食いしん坊で、食べることが大好きだから、大学では栄養学部に進学し、管理栄養士として働くつもりでいました。
でも、卒業前に管理栄養士の研修に行ったところ、「自分が思い描いていたものと何か違うぞ」と。食のおもしろさや楽しさに関わる仕事ができたらいいなあとの想いがあったからです。
迷っていたところ、「この仕事をしたら、おいしいものが食べられるわよ」という母の一言に魅かれて、「じゃあ、1回働いてみようかな」と軽い気持ちで、アルバイトとして1998年に入社しました。

アルバイトから社員へ。「この仕事を続けよう」という気持ちに変わったきっかけは?
ワインの勉強を始めると、まるで目の前の霧が晴れるような出来事の連続で、「おもしろい!」と思ったからです。
子どもの頃から耳にしていた母と、同じくワイン関係の仕事をする親戚との会話で飛び交っていた言葉の数々について「ああ、こういうことを話していたんだなあ」と謎が解けていき、自分がワインを飲んでも「好き」「おいしい」「苦い」「酸っぱい」程度にしか思わなかったことが、味わいの理由などがわかるようになっていきました。
ワインをつくる生産者を訪問するようになると、さらにこの仕事の素晴らしさに気づきます。ワインというと一見、華やかに見えますが、生産者が暑い時も寒い時もどんな時も、いいワインをつくるために畑仕事をする日々の積み重ねによって出来上がる農作物です。
生産者の情熱とたゆまぬ努力、その地域の風土や歴史も詰まったワインは、農作物でありながら、まるで芸術品のように人々の心を打ち、感動させることができます。
私の仕事は、ワインをただ流通させるだけではなく、そんな情熱や背景とともに、お客さまに紹介できるのだから、襟を正してしなければならないと思いました。
これからもずっと、この仕事を続けていきたい。そう思った時、会社を継ぐ覚悟ができたように思います。それが、私が29歳の時のことでした。
子どもの頃から耳にしていた母と、同じくワイン関係の仕事をする親戚との会話で飛び交っていた言葉の数々について「ああ、こういうことを話していたんだなあ」と謎が解けていき、自分がワインを飲んでも「好き」「おいしい」「苦い」「酸っぱい」程度にしか思わなかったことが、味わいの理由などがわかるようになっていきました。
ワインをつくる生産者を訪問するようになると、さらにこの仕事の素晴らしさに気づきます。ワインというと一見、華やかに見えますが、生産者が暑い時も寒い時もどんな時も、いいワインをつくるために畑仕事をする日々の積み重ねによって出来上がる農作物です。
生産者の情熱とたゆまぬ努力、その地域の風土や歴史も詰まったワインは、農作物でありながら、まるで芸術品のように人々の心を打ち、感動させることができます。
私の仕事は、ワインをただ流通させるだけではなく、そんな情熱や背景とともに、お客さまに紹介できるのだから、襟を正してしなければならないと思いました。
これからもずっと、この仕事を続けていきたい。そう思った時、会社を継ぐ覚悟ができたように思います。それが、私が29歳の時のことでした。

壁になったのは「社員とのコミュニケーション」
2013年、吉田さんが38歳の時に承継されます。それから6年、これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
社長になる前段階としてマネージャー的な役割を担っていました。だんだんと、私メインで事業を展開するようになっていったので、社長になっても同じようにできるのではないかとの感触があったから、社長を交代したのですが、全然違ったんです。
母はカリスマ性があり、社員のことを家族のように愛してきましたし、理屈より「みんなで頑張ろう」という雰囲気をつくっていました。私には母のような人生経験がまだありませんし、母の代で会社もある程度の規模になりましたので、家族経営から組織経営への変革に取り組むことにしていました。
会社存続に必要であり、かつ社員にとってより充実して働ける環境を整えられると考えての変革で、実店舗、ウェブショップ、業務用卸と3部門に分けて業績管理や目標設定をしたり、各部門に部門長というリーダー的な役割を立てて人材を育成したり、ワイン以外の勉強会を開催したりなど、新しい仕組みや取り組みを取り入れていったんです。
そこでぶつかったのが、社員とのコミュニケーションの壁でした。
母娘とはいえ、代表のキャラクターが変わった上に、これまでとは一変する変革を行い、私自身が経営者の勉強をほとんどしてこなかったため、経営者として未熟な部分があったので、慣れない、戸惑う社員がいました。
今振り返れば、私が経営者として社員にうまく説明できなかったことなどがすれ違いを生んだのだとわかるのですが、当時はわからず、「どうしたら、わかってもらえるのだろう」と思い悩む日々でした。
たとえば、社員が連休を取れるようにするために、年中無休から定休日を設けることにしました。休みで営業時間が削られる分、売上を落としたらいいかというとそうではなく、その分、効率を上げていかなければなりません。効率化を進めると、新たなルールを決めていかなければならず、反対意見が出ることもありました。
その時に、社員が納得できるような説明や気持ちよく働いてもらうためのやりとりができたらよかったのでしょうが、私にはそれができず、距離感が生まれてしまったんです。
1番悩んでいた時期は、会社に行こうと思うだけで、身体が震えて涙が止まらない、電車をなぜか乗り間違えてしまうなど、会社に行くのがつらい気持ちが身体にも表れるようになりました。
ワインを販売する仕事は大好きだけれど、私は経営者に向いていないのかもしれないと思い詰めるようになったんです。
母はカリスマ性があり、社員のことを家族のように愛してきましたし、理屈より「みんなで頑張ろう」という雰囲気をつくっていました。私には母のような人生経験がまだありませんし、母の代で会社もある程度の規模になりましたので、家族経営から組織経営への変革に取り組むことにしていました。
会社存続に必要であり、かつ社員にとってより充実して働ける環境を整えられると考えての変革で、実店舗、ウェブショップ、業務用卸と3部門に分けて業績管理や目標設定をしたり、各部門に部門長というリーダー的な役割を立てて人材を育成したり、ワイン以外の勉強会を開催したりなど、新しい仕組みや取り組みを取り入れていったんです。
そこでぶつかったのが、社員とのコミュニケーションの壁でした。
母娘とはいえ、代表のキャラクターが変わった上に、これまでとは一変する変革を行い、私自身が経営者の勉強をほとんどしてこなかったため、経営者として未熟な部分があったので、慣れない、戸惑う社員がいました。
今振り返れば、私が経営者として社員にうまく説明できなかったことなどがすれ違いを生んだのだとわかるのですが、当時はわからず、「どうしたら、わかってもらえるのだろう」と思い悩む日々でした。
たとえば、社員が連休を取れるようにするために、年中無休から定休日を設けることにしました。休みで営業時間が削られる分、売上を落としたらいいかというとそうではなく、その分、効率を上げていかなければなりません。効率化を進めると、新たなルールを決めていかなければならず、反対意見が出ることもありました。
その時に、社員が納得できるような説明や気持ちよく働いてもらうためのやりとりができたらよかったのでしょうが、私にはそれができず、距離感が生まれてしまったんです。
1番悩んでいた時期は、会社に行こうと思うだけで、身体が震えて涙が止まらない、電車をなぜか乗り間違えてしまうなど、会社に行くのがつらい気持ちが身体にも表れるようになりました。
ワインを販売する仕事は大好きだけれど、私は経営者に向いていないのかもしれないと思い詰めるようになったんです。

「私は経営者に向いていないかもしれない」。その状況をどう乗り越えて、今があるのですか?
経営者の勉強会で聞いた京セラ創業者の稲盛和夫さんの「今自分に起こっていることはすべて自分の心が招いたこと」という考え方が、すっと心に入ってきたんです。
「経営者はうまくいかないと、『どうしてわかってくれないのか』『どうしてこうなるのか』と他人のせいにするが、悪いのはすべて経営者」といった内容で、「そうだなあ」と思い当たることがありました。
社員に対して、どこか「どうして、わかってくれないのだろう」と思っていた部分がありました。「どうして、わかってくれないのだろう」と思う時点で、経営者でありながら、社員と同等の立場でものを見ていたということです。
でも、会社で起こる出来事は、経営者が引き起こしているもの。まわりが変わることを望むのではなく、まずは私自身が変わらないといけないんだと気づいたんです。
経営者仲間と話すと、みなさん、大変なご苦労をされています。「どこも同じような課題があるから、頑張ってね」と励まされ、私も経営者として、逃げない、努力するしかないと覚悟が決まりました。
「経営者はうまくいかないと、『どうしてわかってくれないのか』『どうしてこうなるのか』と他人のせいにするが、悪いのはすべて経営者」といった内容で、「そうだなあ」と思い当たることがありました。
社員に対して、どこか「どうして、わかってくれないのだろう」と思っていた部分がありました。「どうして、わかってくれないのだろう」と思う時点で、経営者でありながら、社員と同等の立場でものを見ていたということです。
でも、会社で起こる出来事は、経営者が引き起こしているもの。まわりが変わることを望むのではなく、まずは私自身が変わらないといけないんだと気づいたんです。
経営者仲間と話すと、みなさん、大変なご苦労をされています。「どこも同じような課題があるから、頑張ってね」と励まされ、私も経営者として、逃げない、努力するしかないと覚悟が決まりました。

まずは私自身が変わることで、まわりも変わる
気づいて、どんなアクションを起こしたのですか?
さまざまな本を読んだり、相談に行ったり、勉強会に参加したりする中での学びを即行動に移しました。
たとえば、相手の話を聞いて、「それは違う」と思っても、「相手はそう思っている」という事実はあるのだから、その事実を認めるだけで話し合いが変わると聞いて、実践してみると、相手の反応が変わってきました。
また、私は少しネガティブに考えてしまうところがあって、質問も声かけも、ネガティブな言葉を選んでいたところがありました。自分に対しても「どうして、私ってダメなんだろう」と思い、落ち込んでいたんです。
そんな一つひとつの質問や声かけ、言葉選びを「この問題を乗り越えたら、こんなスキルがつく」などポジティブなものに変えてみました。
そんなささやかだけれど、確かな一つひとつの努力を積み重ねていくことで、変わっていくものがあったんです。
1番悩んでいた時期から脱出して、4年。今年の4月には、リーダーの役割を担っていた社員から、執行役員が1人増えました。社員一人ひとりが自立し、リーダーが中心となって、目標達成に向けて取り組んでくれています。
おもしろいことに、ステップアップすると、前にいたところからは見えなかった次の問題が見えてくるんです。だから、常に問題はあるのですが、今は多少の問題が起きても動じなくなりました。
社員や会社の雰囲気はもちろん、私自身の心持ちが変わったからです。
以前なら、社員に何か意見を言われたら、自分を否定された気持ちになってつらくなっていたのですが、私を否定しようとしているのではなく、現状に対する意見を述べているだけなんだと冷静に認識できるようになるなど、もともとの性格やこれまでの経験に振り回されなくなりました。
経営者という立場にさせてもらったことで、私自身の修業ができて、本当にありがたいなあと思っています。
たとえば、相手の話を聞いて、「それは違う」と思っても、「相手はそう思っている」という事実はあるのだから、その事実を認めるだけで話し合いが変わると聞いて、実践してみると、相手の反応が変わってきました。
また、私は少しネガティブに考えてしまうところがあって、質問も声かけも、ネガティブな言葉を選んでいたところがありました。自分に対しても「どうして、私ってダメなんだろう」と思い、落ち込んでいたんです。
そんな一つひとつの質問や声かけ、言葉選びを「この問題を乗り越えたら、こんなスキルがつく」などポジティブなものに変えてみました。
そんなささやかだけれど、確かな一つひとつの努力を積み重ねていくことで、変わっていくものがあったんです。
1番悩んでいた時期から脱出して、4年。今年の4月には、リーダーの役割を担っていた社員から、執行役員が1人増えました。社員一人ひとりが自立し、リーダーが中心となって、目標達成に向けて取り組んでくれています。
おもしろいことに、ステップアップすると、前にいたところからは見えなかった次の問題が見えてくるんです。だから、常に問題はあるのですが、今は多少の問題が起きても動じなくなりました。
社員や会社の雰囲気はもちろん、私自身の心持ちが変わったからです。
以前なら、社員に何か意見を言われたら、自分を否定された気持ちになってつらくなっていたのですが、私を否定しようとしているのではなく、現状に対する意見を述べているだけなんだと冷静に認識できるようになるなど、もともとの性格やこれまでの経験に振り回されなくなりました。
経営者という立場にさせてもらったことで、私自身の修業ができて、本当にありがたいなあと思っています。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
現在、自社ビルの建設を計画中です。
近距離ながら、店舗とセミナールーム、倉庫とが点在しているので、それらを1箇所に集めます。働く導線をよくすることで、社員がより充実した気持ちで仕事に当たれるようにしたいですし、その結果としてお客さまにも貢献でき、売上が上がれば、より安心して働ける環境を整えられると考えています。
以前なら、自社ビルの建設といった大それたことは夢にも思い描けなかったと思います。それを今は「できる」と思えるのは、社員とのコミュニケーションに悩んだ壁を乗り越え、関係性を強くできたからであり、私自身の心持ちも変わったからだと思います。
あの時に「私は経営者には向いていないかもしれない」「無理なんだ」と思って諦めていたら、そこで終わっていたかもしれません。「こうしたい」と思い描いて、そこに向かって一歩ずつでも進んできたから、思い描いたことが現実になったのだと思っています。
近距離ながら、店舗とセミナールーム、倉庫とが点在しているので、それらを1箇所に集めます。働く導線をよくすることで、社員がより充実した気持ちで仕事に当たれるようにしたいですし、その結果としてお客さまにも貢献でき、売上が上がれば、より安心して働ける環境を整えられると考えています。
以前なら、自社ビルの建設といった大それたことは夢にも思い描けなかったと思います。それを今は「できる」と思えるのは、社員とのコミュニケーションに悩んだ壁を乗り越え、関係性を強くできたからであり、私自身の心持ちも変わったからだと思います。
あの時に「私は経営者には向いていないかもしれない」「無理なんだ」と思って諦めていたら、そこで終わっていたかもしれません。「こうしたい」と思い描いて、そこに向かって一歩ずつでも進んできたから、思い描いたことが現実になったのだと思っています。

吉田 まさきこさん
大学卒業後、1998年に株式会社ワイングロッサリーに入社。国内外のワイナリーで研修を重ね、ワインを学ぶ。1999年には自身でウェブショップを立ち上げ、メールマガジンを執筆する。マネージャー職を経て、2013年に事業を承継し、代表取締役社長に就任した。
株式会社ワイングロッサリー
店舗: 京都府京都市下京区唐津屋町528
HP: http://kyoto.winegrocery.com
(取材:2019年9月)
誰かや環境に対して「どうして、こうならないのだろう」「どうして、わかってくれないのだろう」と思うことがあり、しんどくなることがあります。誰かや環境を想ってのことであればなおさら、「どうして」と相手や環境に求める気持ちが出てしまうのではないでしょうか。
でも、まわりが変わることを願うより、吉田さんのように「まずは自分自身から」。誰しも互いに影響し合いながら生きているので、誰かや環境に影響を与える自分自身が変わることで、まわりも変化していくのではないでしょうか。
また、「自分が変わる」ということは、それまでとは見え方や捉え方などが変わるということ。吉田さんが「私自身の心持ちが変わった」「ステップアップすると、前にいたところからは見えなかった次の問題が見えてきた」とおっしゃるように、見えてくることも変わってくるでしょうし、向き合う気持ちも変わってくるのでしょう。
そう考えると、「自分1人が変わっても、何も変わらない」ではなく、「自分1人が変わることで、確かに変わるものがある」のだと、吉田さんのお話をうかがって思いました。
HP: 『えんを描く』
でも、まわりが変わることを願うより、吉田さんのように「まずは自分自身から」。誰しも互いに影響し合いながら生きているので、誰かや環境に影響を与える自分自身が変わることで、まわりも変化していくのではないでしょうか。
また、「自分が変わる」ということは、それまでとは見え方や捉え方などが変わるということ。吉田さんが「私自身の心持ちが変わった」「ステップアップすると、前にいたところからは見えなかった次の問題が見えてきた」とおっしゃるように、見えてくることも変わってくるでしょうし、向き合う気持ちも変わってくるのでしょう。
そう考えると、「自分1人が変わっても、何も変わらない」ではなく、「自分1人が変わることで、確かに変わるものがある」のだと、吉田さんのお話をうかがって思いました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(会社経営) 記事一覧
-
「今できることを諦めず一所懸命に取り組んでみる」過去3度の出入りを経て父の保育園の園長となった太田さん
-
「ゼロから始めることで新たな成長や飛躍につながる」平凡な社員から転職。社長に就任した神田さん
-
「心の叫びに気づくことが大切」「手に職を」と思い立ち、プリザーブドフラワー専門店を開いた志摩子さん
-
「お客さんが飽きないように商いを続ける」尼崎の昭和6年創業「蓬莱湯」の3代目を継ぎ、次世代へ繋ぐ里美さん
-
「まずは私自身が変わらないといけない」老舗家業の3代目として事業承継。新たな歴史を創る吉田さん
-
「行動を起こすことで少しでもよくなるなら私がする」2代目社長として新たな発想で会社経営に取り組む角井さん
-
「笑顔の裏側に、自分への厳しさと緊張感を」老舗旅館の女将として伝統を受け継ぎ、次の世代に継ぐ南さん
-
「壁にぶち当たっても、その先はもっと開けて明るい」グラスアート「ロクレール」の技法を引き継ぐ向井さん
-
「見えないところで努力する。それが伝統を受け継いでいくこと」160年続く老舗の婚礼衣装店、5代目の熊谷さん
-
「女性船員も雇用できる魅力ある会社にしたい」船が好きで海運会社の三代目後継者として働く紗苗さん
-
「なんとなく成長するなんて不可能」学者志望から家族の会社を継承、シルク製品の自社ブランドを作る明子さん
-
「この道を選ぶならブレずにまっしぐら。GIRLS, be ambitious!」創業38年イノベーションし続ける長谷川社長
-
「女性をキレイにする旅」をコンセプトに、海外1人旅のコーディネートからユニークな京都旅プランまで「女性の旅」をプロデュース
-
宝塚の情報誌「宝塚ROSE」を発行して10年。元ジェンヌのプロデュースなど宝塚の活性を担う事業を手がける井川さん
-
1000人のロールモデルを創るネオウーマン の代表でもあり、苦難を乗り越えて会社を守る経営者でもある菊川さん