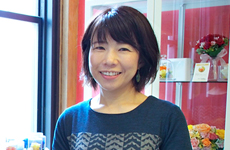HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
![]() 熊谷 昌美さん(株式会社熊谷次 代表取締役)
熊谷 昌美さん(株式会社熊谷次 代表取締役) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(会社経営)
熊谷 昌美さん(株式会社熊谷次 代表取締役)

| 熊谷 昌美さん(株式会社熊谷次 代表取締役)
株式会社熊谷次 〒600-8107 京都市下京区五条通室町北西角東錺屋町189 http://www.m-collection.co.jp/ |
| 御社は160年以上続く老舗だそうですね |
| 幕末のペリーが黒船でやってきた頃、嘉永元年(1848 年)に呉服商として創業しまして、日本で一番古い婚礼衣装メーカーとして、代々、和装婚礼衣装のオートクチュールを手がけてきました。父までは代々長男が継いできましたが、私の代は姉妹二人。長女の私が家業を継いで五代目になります。 子どもの頃から(継ぐことを)周りから言われていましたが、プレッシャーというか、やっぱり気が重いというか、大学生の頃は家業を継ごうかどうか悩みました。大学を卒業後、着物の制作会社に就職したのですが、そこの社長や作家の先生から、「上質な着物の良さ」を教えていただいて、やっぱり自分は着物が好きなんだと感じ、家業を継ぐことを決心しました。 |
| 家業を継がれた後、どのようなご苦労がありましたか? |
| 私が継いだ頃はまだ、打ち掛けを着る和装の婚礼が主流でした。でも今から30年くらい前の1980年代頃から、チャペルでの結婚式が流行るようになって、結婚式の形態がどんどん変わってくるようになったんです。 衣装選びの現場にお手伝いに行ってお客様の動向を見ていると、花嫁さんであるお嬢さんは、和装よりもドレスにすごく興味をお持ちなんです。「和装はお母さんが選ぶものでいいわ」と、和装にあまり関心が無い。ホテルもチャペルが増えてきていましたので、これはいずれドレスの時代が来るなと感じました。  でも当時のドレスといえば白かピンク。フリフリのついた、みんな同じようなドレスしかありませんでした。私自身の結婚式でも感じましたが、着たいと思うようなドレスが無いんです。それならと、婚礼の洋装化に対応できるよう、新規でウェディングドレス部門を立ち上げました。 でも当時のドレスといえば白かピンク。フリフリのついた、みんな同じようなドレスしかありませんでした。私自身の結婚式でも感じましたが、着たいと思うようなドレスが無いんです。それならと、婚礼の洋装化に対応できるよう、新規でウェディングドレス部門を立ち上げました。苦労といういうより、「壁」を感じたのは、和装から洋装に転換するときですね。その頃はまだ景気も良かったので、「和装を売ってるだけでいいんやから、わざわざドレスを売らなくても」と周りは思っていたと思います。昔からの問屋ですから、祖父の代からいる従業員もいますので、「お嬢さんのママゴト遊びやから、1年もしたら辞めはるやろ」という感じはありました。 でも、和装にしても洋装にしても、良いものは良い。根本的には同じだと思うので、本物の和装を選ぶ方は、良い洋装を選ぶはずだと考えたんです。そこで、自分に実力があれば付いて来てくれると思い、自分も一緒にイチから始めるつもりで、ある有名なドレスメーカーのパタンナーをされていた方に師事して洋裁を勉強しました。 その後、ウェディングドレス部門も上手く展開することができ、だんだんドレスのシェアが大きくなっていきました。初めは社内でも抵抗はありましたが、だんだん「やっぱり先見の明があったんやな」という感じになってきたのですが、でもそれには随分時間がかかりましたね。 ここ5年くらい前から、和装の結婚式が見直されてきていますし、娘も手伝うようになりましたので、本来の和装にシフトしつつあります。伝統を守りつつ、若い人にも受け入れられるような和装をご提案させていただいています。 |
| 「和装」という日本の文化を継承していくことについて、どのように考えておられますか? |
| 着物は日本の文化ですが、海外に発信してこそ意味があると思います。海外に行くと日本の文化の素晴らしさを改めて感じる、という方も多いですし、外国の方から、「日本の文化って素晴らしい」と誉めてもらえるとすごく嬉しいですよね。なので、まずは海外に向けて日本の文化を発信して認めてもらうことが一番。着物に限らず、他の日本の文化も、そうすることで残っていけるんじゃないかと考えています。 |
 |
| 京都では観光客用の着物や、若い人たち向けの手軽な着物も増えています。 「本物」を創るお立場から見てどのように感じますか? |
| 「本物」というのは、「ブランドもの」という意味ではなく、人を感動させる、心に何か訴えてくるものがあります。古いものでも、それを残していこうと思えば、見えないところに努力して、手間隙かかっているものでないと残せません。それは着物やドレスだけでなく、絵画や焼き物など、違う業界でも同じです。 清水寺の辺りでは、外国人の観光客や、修学旅行の人たちが、レンタル着物で歩いている方たちがすごく多いですね。観光バスで来て、着物を着てお寺に行って、写真を撮って。それを楽しんでいい思い出になれば、いつか何かのときに、その写真で話題が広がり、興味のきっかけになるかもしれない。それはそれで良いと思います。本物を追求する審美眼のある方は、見ただけで本物かどうか分かると思います。これからは、「本物」でなければいけないというより、両極端の二極化が進んでいくでしょうね。 |
| 今後、どのような展望をお考えですか? |
| 昨年のニューヨークの国連大使館で行われたショーに参加させていただき、弊社の婚礼衣装を各国の大使にご覧いただく機会がありました。また、京都の文化を広める映画の製作プロデュースにも携わらせていただいたり、ここのところ文化的な活動が増えてきています。 和装にシフトすることを機に、だんだん消えていく日本文化を残したいという気持ちも強くなってきましたので、これまで培ってきたブライダル業界のスキルを活かし、日本文化をもっと、グローバルに発信していきたいと考えています。 |
 「熊谷次」さんの打ち掛けを手にされる熊谷昌美さん(左)と娘さんの優希さん(右) |
| 次世代を継がれるお嬢様に、伝えていきたいこととは? |
| 永く続くということは、見えないところで努力していないと難しいんです。よそから見て楽そうに見えても、中では結構つらいことも、大変なこともあります。それが伝統を受け継いでいくことです。 「京都・室町」というのは特殊な町ですから、その文化をも引き継いでいって欲しい。そして日本文化を世界に発信していって欲しいと思っています。婚礼衣装の仕事は、人様の幸せをお手伝いする仕事なので、自分自身の人生も充実させてほしいと願っています。 |
| ありがとうございました。 |
| (取材:2015年11月 関西ウーマン編集部)
|
■関西ウーマンインタビュー(会社経営) 記事一覧
-
「今できることを諦めず一所懸命に取り組んでみる」過去3度の出入りを経て父の保育園の園長となった太田さん
-
「ゼロから始めることで新たな成長や飛躍につながる」平凡な社員から転職。社長に就任した神田さん
-
「心の叫びに気づくことが大切」「手に職を」と思い立ち、プリザーブドフラワー専門店を開いた志摩子さん
-
「お客さんが飽きないように商いを続ける」尼崎の昭和6年創業「蓬莱湯」の3代目を継ぎ、次世代へ繋ぐ里美さん
-
「まずは私自身が変わらないといけない」老舗家業の3代目として事業承継。新たな歴史を創る吉田さん
-
「行動を起こすことで少しでもよくなるなら私がする」2代目社長として新たな発想で会社経営に取り組む角井さん
-
「笑顔の裏側に、自分への厳しさと緊張感を」老舗旅館の女将として伝統を受け継ぎ、次の世代に継ぐ南さん
-
「壁にぶち当たっても、その先はもっと開けて明るい」グラスアート「ロクレール」の技法を引き継ぐ向井さん
-
「見えないところで努力する。それが伝統を受け継いでいくこと」160年続く老舗の婚礼衣装店、5代目の熊谷さん
-
「女性船員も雇用できる魅力ある会社にしたい」船が好きで海運会社の三代目後継者として働く紗苗さん
-
「なんとなく成長するなんて不可能」学者志望から家族の会社を継承、シルク製品の自社ブランドを作る明子さん
-
「この道を選ぶならブレずにまっしぐら。GIRLS, be ambitious!」創業38年イノベーションし続ける長谷川社長
-
「女性をキレイにする旅」をコンセプトに、海外1人旅のコーディネートからユニークな京都旅プランまで「女性の旅」をプロデュース
-
宝塚の情報誌「宝塚ROSE」を発行して10年。元ジェンヌのプロデュースなど宝塚の活性を担う事業を手がける井川さん
-
1000人のロールモデルを創るネオウーマン の代表でもあり、苦難を乗り越えて会社を守る経営者でもある菊川さん