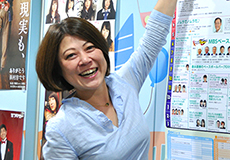HOME![]() ■関西マスコミ・広報女史インタビュー
■関西マスコミ・広報女史インタビュー
![]() 田中 美由紀さん(株式会社みどり会 会員事業部 部長代理)
田中 美由紀さん(株式会社みどり会 会員事業部 部長代理) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西マスコミ・広報女史インタビュー
田中 美由紀さん(株式会社みどり会 会員事業部 部長代理)
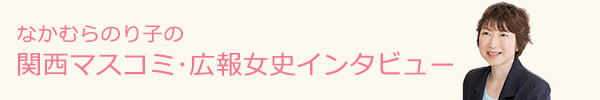

| 田中 美由紀さん(株式会社みどり会 会員事業部 部長代理)
熊本県出身。大学卒業後、株式会社みどり会に入社。メンバー企業とその社員向けサービスを行う会員事業部へ配属され、企業のVIP向けに行われる著名人の講演会、音楽会、野球・テニスなどスポーツ大会レクレショーンなどイベント企画・運営業務を担う。特に新規事業として立ち上げた音楽会、「グリーン交響団」の演奏会は、現在も継続中で今年(2016年)28回目を迎える。1992年、広報担当に異動し、主担当として会報誌の編集に永年携わる。2012年、会報誌の抜本的なリニューアルをプロジェクトチームで実施。チームの中核として“親しみのある紙面・読まれる会報誌”の製作を実現させた。現在は会報誌、HP関連以外にもメンバー企業社員向けのイベント(野球観戦、日帰りバスツアーなど)や、マラソン大会の開催など、社内外に向けての広報活動を精力的に活動中。 株式会社みどり会 大阪市中央区西心斎橋2-2-3 EDGEビル8階 http://www.midorikai.co.jp 会報誌『Midori』弊社株主(メンバーー会社)161社の社員むけ会報誌 |
| 1970年の日本万国博覧会に、当時の三和銀行(現在 三菱東京UFJ銀行)が中心になって出展された「みどり館」。当時はとっても人気のパビリオンの一つでした。その出資企業をメンバーに設立された株式会社みどり会で、広報担当として働く田中 美由紀さん。同社初の女性管理職だったそうです。 |
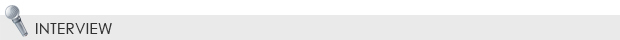
| 田中さんのお仕事の内容を教えてください。 |
| 弊社は、1970年の日本万国博覧会に、「みどり館」を共同で出展した三和銀行(現在 三菱東京UFJ銀行)とその主要親密企業31社の出資を受け、同年12月に設立されました。その後出資企業も増加し、161社の参画をいただいています。 私の所属する会員事業部では、そのメンバー企業161社(株主)の全社員に向けて、各種イベント開催やメンバー企業の情報発信の為の会報誌を発行することにより『みどり会の結束』を強める役割を担っています。広報担当として、みどり会のメンバー企業の情報発信が偏ることなくその企業や社員の方々が数多くご登場いただくようなコンテンツ作りを心掛けています。 その他、交響楽団の演奏会や講演会、交流会、マラソンイベント、ファミリーセールのイベント開催・運営なども行っており、中でも「グリーン交響楽団」は、メンバー会社に勤務されている社員・家族が中心となり1988年に結成されました。メンバー企業の音楽関係のクラブ活動を調査することから開始し、立上げの数年はポップ系のコンサートバンドと交響楽団の二部構成として、まさに『みどり会の音楽会』を実現しました。一から立ち上げた第一回目コンサートの幕が下りた時のやり遂げた感激は、今でも忘れられない経験です。 2014年度から『RUNRUNRUN』(マラソンイベント)を久しぶりの新イベントとして立ち上げました。私は、参加者の気持ち、運営上の問題点を知るために、運営側でありながらランナーとしても参加しています。今までの私には、走るなんて考えられなかったことですが、リレー(5Km×4人)のメンバーの一人としてタスキをつなぐ自分の力がチーム力につながっていく醍醐味を感じました。 |
| お仕事の中で意識されていること、力を入れていらっしゃることは何でしょう。 |
| メンバー企業には新入社員から役員まで幅広い年齢層の方々がいらっしゃいます。昭和45年の大阪万博みどり館に端を発した弊社ながら、大阪万博や出資母体の三和銀行(コーポレートカラーがみどり色)を知らない世代の方々が年を重ねるごとに増えています。「みどり会はどんな会なのですか?」と聞かれることが多くなったことに危機感を持ちました。弊社の広報不足を痛感し、興味を持ってもらえる、親しみを感じてもらえる会報誌や好奇心を抱いてもらえるイベント運営に注力しています。 そのためには、知りたい読みたい内容、参加したいと思われる企画とはどのようなものか?お客様のニーズに合っているのか、世間のブーム・トレンドは?ということを意識しています。そして、メンバー企業(株主)161社の社員の方々はもちろんのこと、作っている・企画している私たちが楽しめて、おもしろがっているかが重要だと思っています。雑誌の発行は、一方通行で押し付けがましいものになってはいけないと常に考えています。 |
| この仕事の醍醐味はどこにありますか。 |
 メンバー企業の多くの方々と接点を持たせてもらったことこそが自分の財産になっていることだと思います。このテーマだったら、この案件だったら、あの企業のあの方に連絡すれば良いみたいに。(一度お会いした方のお顔と名前が一致するのは私のプチ自慢です。) メンバー企業の多くの方々と接点を持たせてもらったことこそが自分の財産になっていることだと思います。このテーマだったら、この案件だったら、あの企業のあの方に連絡すれば良いみたいに。(一度お会いした方のお顔と名前が一致するのは私のプチ自慢です。)また、大手企業のトップはじめ社員の方々に、会報誌を読んでいただきその感想やコメントをいただいた時には嬉しさを感じます。2012年にリニューアルした時には、各社訪問する際に、変化について多くの声が聞けました。時間に追われ、苦労して発行しているだけに、報われた気がします。 以前にこんなことがありました。1994年に当時のオリックス・ブルーウェーブの取材にお伺いし、イチロー選手、1997年に仰木彬監督の取材でインタビューにお伺いさせていただきました。時を経て2012年に新企画のイベント打合せで、オリックス・バファローズ広報部に伺った際に、「この方、お会いしたことがある…あっ!あの時の…」と記憶がよみがえりました。当時のご担当者が広報部長になられていたのです。当時は名刺交換をしただけでしたが、その当時のことが瞬時に思い出されました。 今まで、広報・イベント担当などを長きにわたり担当させてもらったことで、単にビジネス上のおつきあいだけでなく、プライベートでもおつきあいできる友人が大勢できました。仕事を通じてお会いした方々と、アフターファイブでも気軽にお互いの仕事の悩みを相談や情報交換できる関係を時間をかけずに構築できるようになったのもこの職務のおかげだと思っています。 取材がきっかけで、『ふかみどり会』というグループができあがりました。それは、2社のコラボ企画の取材後、両社の方々が『取材慰労もかねて打ち上げをしよう!』ということになりました。打ち上げは大いに盛り上がり旧知の仲のように打ち解け、『今回をきっかけとして、みどり会の広報を通じて集まる会を結成し、さまざまな業種の方々に声かけして輪を広げよう』ということになり、『ふかみどり会』を結成することに至ったのです。ネーミングの由来は、「ふか~くみどり会を考える」というものです。このような異業種交流ができるのも弊社ならではのものですし、メンバー企業のたくさんの方々の新しい出会いを創造できるのもこの仕事のまさに『醍醐味』だと思います。 会報誌、イベントにしても、参加した方々に喜んでいただき、人との輪が大きくなり、そして各々のパイプが太く、強くなっていけることが、今の仕事に携わってきて、本当に幸せを感じます。メンバー企業(株主)全社員が、私の作っている冊子の読者であり、会社同志、社員同志のかけはしになるという特別ものだと思います。 |
| 現在までのターニングポイント(転機)はありましたか。 |
 役席(管理者)に昇格した時(2009年4月)です。当時の上司からは、外出先で必ず、「当社初の女性管理職です」と紹介され、なにかむずがゆい感覚でした。それまで弊社では女性管理職不在で、またその事実に違和感はなかったように私も感じていました。 役席(管理者)に昇格した時(2009年4月)です。当時の上司からは、外出先で必ず、「当社初の女性管理職です」と紹介され、なにかむずがゆい感覚でした。それまで弊社では女性管理職不在で、またその事実に違和感はなかったように私も感じていました。中間管理職として上司の意向と部下の思いをしっかり掌握し、チーム力を高め、後輩達がどんどん後に続いていけるような道を作っていかなければならないと思っています。まだまだ会社が求めるレベルに達することができず、日々勉強ですが(笑)。 また、2012年に弊社広報活動強化の方針が打ち出され、ホームページ、会報誌等弊社の広報媒体を大刷新することとなったこともターニングポイントでした。それまでの私単独で会報誌製作主担当となっていたものが、プロジェクトチームを組成してグループとして動きだしました。 グループで企画製作を行うことは、様々な角度から多様な見方で企画ができあがってきます。チーム活動の中で、それまでの自分一人ではなかった視点でハッとするような発想やアイデアを聞くにつけ、もっと勉強しもっと努力しなければならい、ということに気付いたのです。同時に企画することの楽しさ、苦しさ、読者への思いを強く意識するようになりました。 |
| これまでに「壁」はありましたか。 |
| 長年、一人体制で会報誌を編集してきて、読者の顔が見えず、声も聞くことができませんでした。独りよがりな冊子を発行していたと思います。そして、自分自身成長できているのかどうかもわからない。ただ、期日に追われての発行。自分自身、楽しんで編集しているのか? インターネット情報と変わらないものを、紙に落としているだけではないのか? 答えは、作っている私も、読者もワクワクしていなかったように思います。 ただ、一人で製作を担うことでの責任感で、度胸もしっかりつきました。世界各国をめぐる旅の紙面企画が、前任者より継続されていました。私は、旅行パンフや、インターネットに記載されているような通常情報でなく、弊社会報誌しか載っていないような穴場情報を掲載したいと思いました。そこで、各国の在日政府観光局へ体当たり取材を敢行したのです。 弊社の説明から始まり、どんな冊子なのか、どのようなページにしたいのか説明をして理解を求めました。毎年、東京ビッグサイトで開催される「旅行博」でもくまなくブースをまわって声をかけ、会報誌を広げて話をしました。書店で販売されている雑誌ではないので、説明に時間を要しましたが、ほとんどの政府観光局に承諾が得られ、生きた情報と各国の局長よりPRの掲載に成功しました。 今や、何事もインターネットで情報を得られる時代です。本やネットで得られる事実や知識は基本的なものとして、情報は自分の足で探して五感で感じたものに勝るものはありません。一歩踏み出す勇気と熱意をもって臨めば乗り越えられない壁は存在しないのではないか、と考えるようになりました。 |
| 「自分の時間」はどのように過ごされていますか。 |
| ノー残業デーには、できるだけスポーツクラブで汗を流したり、友人と美味しい食事を楽しみます。スポーツクラブに行き始めたきっかけは、ダイエットのためでしたが、そこで素晴らしいトレーナーと出会い、無理なく減量に成功しました。そして、トレーナーの勧めで、ランニングを始め、当社主催のリレーマラソンに出場(5㎞)、次には大阪城ナイトマラソン(10㎞)に出場。ここでも、特技である“人との距離を一気に縮める”ことで、多くの友人もでき、仕事とは離れた楽しい時間を過ごしています。 また、ソムリエ&利酒師の友人の指導で、ワイン、日本酒の利き酒、お料理とのマリアージュを体験する会に参加するなど、食べる・飲むという共通の趣味でつながる友人たちと過ごしています。ワイン好きが高じて、一時はフランス語を習っていたこともあります(笑)。 |
| 広報PRという仕事を目指したいと考える読者女性へメッセージをお願いします。 |
 大学受験でマスコミ系の学部学科がある短大を受験しましたが、見事に桜散りました。その時、漠然と絵本などの出版社に入るための勉強をしたいと思っていました。 大学受験でマスコミ系の学部学科がある短大を受験しましたが、見事に桜散りました。その時、漠然と絵本などの出版社に入るための勉強をしたいと思っていました。実際は文学部に進み、得意であった書道を極め、4年間、授業、クラブ、師匠につくなど、字を書き続けました。この4年間は、修行僧のような学生生活でしたが、その中で高い目標にチャレンジすること、そのための努力と辛抱強さを培ったと思っています。 入社時は、会員事業のイベント担当が主担当でしたが、会報誌編集担当の先輩の退職に伴ってその仕事を引き継ぎました。何事にも興味を持ち、面白がり、情報に敏感になることが広報担当として重要だと思います。 職業柄かもしれませんが、日常生活でもトレンドをキャッチするために街歩きの最中は、右に左にキョロキョロしてしまいます。普段立ち寄る書店では、ジャンルに関係なく時間をかけて何か有益な情報がないかと探しているように思います。色々な雑誌から、レイアウトや色使い、特集の組み方などを参考にしています。 また、自分の特技と思えるものは、より特化して、道を究めていくのも強みになると思います。 これは、ちょっとした『プチ喜び、プチ達成感』を楽しみながら、自分で好きなこと、他人より少し得意かなと思うことを伸ばしていけば良いと思います。そして、人とのつながりを大切にすること。人との出会いは必然だと聞いたことがあります。思い起こせば、私のターニングポイントには、成長させてくれた人に必ず出会っています。まわりを見渡してみてください。自分にとって宝となる人が必ずいるはず、と思っています。 |
| ありがとうございました。 |
| 取材:2016年7月/所属・役職名等は取材時のものです |
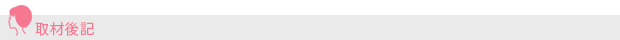
| ひとつの企業の広報ではなく、メンバー企業間の強力なブリッジとして各企業にスポットを当て、編集やイベントを通じて、人と人とのつながりを創り出す田中美由紀さん。好奇心と辛抱強さ、そして、その継続が、広報PRという仕事の最大の武器になっていると感じました。取材時に同席されていた上司の方との関係も、とても自然で明るく、お互いの信頼感を感じるものでした。この雰囲気が社風となり、よい会員事業につながっているのだと思います。なんでも「面白がる」。好奇心のアンテナは常に立てていようと思いました。 |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子S plus+h(スプラッシュ) 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー マスコミ・出版メディアへの取材も多く、インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけている。舞台芸術、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西マスコミ・広報女史インタビュー 記事一覧
-
「記者として一番大事なのは、他人の痛みへの想像力」さまざまな事件やニュースを追い、世の中に伝える木原さん
-
「記者は自分自身が丸ごと問われる仕事」どんな経験も仕事につながると言う新聞記者の寺尾さん
-
「新しい出会いを創造できるのも、この仕事のまさに醍醐味」同社初の女性管理職として働く田中さん。
-
「『聖域』を尊重しつつ女性目線を活かしていきたい」男性中心のプロ野球界で広報として働く香川さん。
-
「アナウンサーは良くも悪くも「人間性」が出る仕事」野球好きが高じてアナウンサーになられた市川さん
-
「どでかい好奇心と辞めない決意」フリーエディターから著名雑誌の編集長に。誰にも作れない記事を目指す中本さん
-
関西の番組らしい「おもしろい」を作りたいテレビ番組制作会社のディレクターとして働く日高さん
-
「職業人、家庭人、地域人三面性をあわせもつ女性が増えて欲しい」育休復帰後に希望の広報で活躍する渡辺さん
-
「必要なのは「達成意欲」の高さ」オフィスで働く女性のための情報誌「シティリビング」の編集デスク、村上敬子さん
-
「PRは情報を提供する企業の顔」人気チョコレート「カファレル」を扱う老舗輸入会社で広報PRとして働く山田さん
-
「目の前の仕事を全うすれば、いずれ自分のフィールドになる」神戸新聞社の記者として活躍する片岡さん
-
「裏方で働く人たちがメインに見えた」からテレビ業界に。打てば響く仕事環境が楽しいと話す弓奈さん
-
「人に伝えるというのは常にアンテナを立てていること」新聞記者から独立され、多くのファンを持つ旅行ジャーナリストの大野さん
-
「24時間夢の中でも仕事のことを考えていた」たくさん怒られたことが今でも仕事のベースになっていているという麻未さん
-
「70歳になっても続けたい」テレビ局のADからディレクターを支えるリサーチャーに転身、関西のテレビ番組の多くに携わる赤松さん。