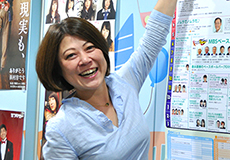HOME![]() ■関西マスコミ・広報女史インタビュー
■関西マスコミ・広報女史インタビュー
![]() 片岡 達美さん(神戸新聞社/報道部 医療・科学チーム 記者)
片岡 達美さん(神戸新聞社/報道部 医療・科学チーム 記者) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西マスコミ・広報女史インタビュー
片岡 達美さん(神戸新聞社/報道部 医療・科学チーム 記者)
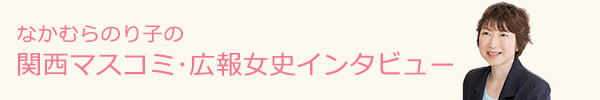

| 片岡 達美さん 神戸新聞社/報道部 医療・科学チーム 記者 大阪市立大学法学部卒業。1992年神戸新聞社入社。以来、編集局文化部、文化生活部で文化、芸能、くらし、医療などを担当。2008年~2010年、姫路支社で播磨・西播磨地域の話題を取材。2010年~2012年、編集局社会部多メディア発信グループ(現在の神戸新聞電子版「ネクスト神戸」)では、ニュースのデジタル発信、コンテンツ企画などに携わった。2012年から文化生活部、2014年10月から報道部で主に医療を担当。 神戸新聞社:http://club.kobe-np.co.jp/corporate/ |
| 現在の具体的なお仕事内容をおしえてください。 |
 現在は、報道部医療・科学チームで主に医療の取材を担当しています。医療、健康に関する話題を集めた「からだ面」(週3面)、1つの病気やけがに焦点を当て、奇数月の毎土曜朝刊掲載の医療特集面「ひょうごの医療」などを取材・執筆しています。 現在は、報道部医療・科学チームで主に医療の取材を担当しています。医療、健康に関する話題を集めた「からだ面」(週3面)、1つの病気やけがに焦点を当て、奇数月の毎土曜朝刊掲載の医療特集面「ひょうごの医療」などを取材・執筆しています。取材ネタは、チームで話し合って、やっていないネタ、別の取材で聞いた話を持ち寄り、編集会議で話し合って、掲載記事の内容を決めていきます。 また、こういう記事を書いてほしいというオファーや情報をいただくこともあります。 わからない案件が出た場合、そこで活躍するのは、いろいろな病院の先生とのネットワークだったりします。取材を通して、多くの人とつながることで、情報がより広く、より深くなるので、記者は人とつながる仕事だと思いますね。 |
| もともと記者志望だったのですか? |
| 新卒で入社し、記者としての人生をスタートさせたのですが、ジャーナリストを目指して、取材現場にあこがれて、というわけではありませんでした。入社当初は、報道部ではなく、文化部に就きました。初めての現場で知らなかいことも多く、恥をかくことも多かったですね。 たとえば、大学教授に取材に行く際に、その方の専門とする分野の言葉や表現がわからなかったり(笑)。取材相手に教えてもらうことも多かったです。聞き返してばかりでは、取材の流れを止めてしまいますし、その時は必死でメモして帰り、後から調べるといった感じで学んでいきました。当時はインターネットもありませんでしたので、辞書で調べたり。今はネットで事前に調べたりできるので時間が短縮できますよね。 |
| 取材する際にある程度の知識が必要なのでは? |
| 記者は、学生時代の学部や専攻に関わらず、先輩の記事などを見て、表現やアプローチの仕方などを勉強していきます。新聞は専門書ではないので、読者である一般の方が読みやすい紙面にするのが基本です。こちらも素人目線で聞き、書くということをベースに取材・執筆しています。専門的な話もかみくだいて記事にしていく。それが新聞記者のスタンスですね。 |
 |
| 取材で重要なことは? |
| 事前の下調べが一番重要ですね。現在では、医療関係の情報はインターネット上にあふれており、専門用語などの解説もあるので、そうしたものからある程度、取材するテーマの輪郭は描いておくようにしています。ただし、ウェブ上の情報は玉石混交なので、必ず取材対象に直接確認するようにしています。 あと、何かひとつだけでも、その取材の中でキーワードを聞き出せるようにと心がけて取材しています。 その方のお話のポイントとなるキーワードが出れば、結果オーライと考えています。 |
| 壁にぶつかったりしたとき、どのように対応されてきましたか? |
| 「現在のポジション」=「担当(医療)」(という意味で)は、自分の意志で決まるものではありません。担当したい分野の希望は会社に伝えますが、あまりかなうことはないんです。そういったことや、社内の人事的な壁は何度も経験しているのですが、そのたびに「与えられたポジションを、とりあえず全うする」と思うようにしています。 仕事の面ではそんなに壁だと感じたことはありませんね。自分の体力などの限界でしょうか(笑)。 最初が文化部で、その後、報道部となり、全く土地感のないところに転勤になったり、夜勤や泊まりなどもあり、体力的にきついときもありますので。でも、それも、目の前の仕事を全うするようにしていれば、いずれ自分のフィールドになりますから。 |
| 印象に残っていることはありますか。 |
| 姫路支社に配属だったときのこと。ひとり夜勤だった晩に大きな火事の発生事件があり、現場へ駆けつけたのですが、真っ暗な現場で、1メートルほどの溝に落ち、全治3カ月の骨折をしたことがありました。カメラが命の取材現場なのに、カメラを壊してしまったことに意識が行き、なんとか溝から上がってきたときには、足首があらぬ方向に曲がっていて(笑)。 救急車で運ばれてしまったことがありました。もちろん取材は後輩に電話で頼み、事なきを得ましたが、後に他の新聞社さんからも無線で記者1名運ばれたと聞いたけど、片岡さんだったの?とあきれられました(笑)。現場にも迷惑となった、今でも冷や汗ものの事件でしたね。 |
| 休日の過ごし方やリフレッシュ法があればおしえてください。 |
 普段から不必要な残業はほとんどしないように心がけています。また、休日は家族や友人と過ごし、趣味などにあてることが多いですね。足首骨折の後のリハビリもかねて、数年前から大人のバレエをはじめまして、それにはまっています。バレエの時は、完全に普段の生活を忘れる時間となっていて、精神的にかなりのリフレッシュとなっています。 普段から不必要な残業はほとんどしないように心がけています。また、休日は家族や友人と過ごし、趣味などにあてることが多いですね。足首骨折の後のリハビリもかねて、数年前から大人のバレエをはじめまして、それにはまっています。バレエの時は、完全に普段の生活を忘れる時間となっていて、精神的にかなりのリフレッシュとなっています。あと、読書ですね。須賀敦子氏の著作の透明感がとても好きで、特にエッセーは、コラムや紀行文を書くようになった際、「あんな風に書きたい」と思っています。須賀先生の作品との出会いは、イタリア旅行の記事を書くことになったことがきっかけだったと記憶しています。参考になる本を探したときに手にしました。 須賀さんはイタリアでの暮らしを本になさっていて、風景の描写や場面の転換の仕方などのほか、いろいろな知識などの取り入れ方が、すばらしかったんです。今でも折に触れ、ページをめくることがあります。あとはロラン・バルトの著作でしょうか。華麗なレトリックを敬愛しています。 |
| 記者になるために必要なことは何でしょうか? |
| 月並みですが、たくさん本を読み、映画を見て、コンサートや芝居にも足を運ぶことだと思います。そうして身につけた知識が、通りいっぺんの記事プラスアルファの記事を書くときの力になってくれます。「仕事に有利な」という理由だけで勉強する分野を選ばない。好きなこと、興味のあることをとことん追求することが大事です。記者は特に何にでも興味を持って取り組むことが必要でしょうね。 |
| 片岡達美さん、ありがとうございました。 |
 取材場所に始終流れる「ピー、ピー」という音の中、インタビューさせていただきました。このピー音の正体は共同通信社の通称「ピーコ」。これから入ってくるニュースを知らせる際の信号音です。 取材場所に始終流れる「ピー、ピー」という音の中、インタビューさせていただきました。このピー音の正体は共同通信社の通称「ピーコ」。これから入ってくるニュースを知らせる際の信号音です。新聞社の報道部記者のイメージは、“24時間体制で髪を振り乱しての取材”といったイメージでしたが(かなりのステレオタイプ!?)、現れた片岡さんはスタイリッシュで現代的な美人。その雰囲気は、無理がなく自然体です。それが取材相手の心のバリケードを解き、奥の深い記事を紡ぎ出す秘訣なのだなと感じました。 もちろん、これまでの体験やスキルアップのための努力があり、そこに片岡さんならではの人脈がプラスされ、人の目を引く企画記事などにもつながっているのでしょうね。 |
 取材:なかむらのり子 取材:なかむらのり子S plus+h(スプラッシュ) 代表 フリーコーディネーター/コピーライター/プランナー マスコミ・出版メディアへの取材も多く、インタビューする方の人生にスポットを当てる取材を心がけている。舞台芸術、教育、医療、地域活性に関する取材など、そのフィールドは広い。 |
■関西マスコミ・広報女史インタビュー 記事一覧
-
「記者として一番大事なのは、他人の痛みへの想像力」さまざまな事件やニュースを追い、世の中に伝える木原さん
-
「記者は自分自身が丸ごと問われる仕事」どんな経験も仕事につながると言う新聞記者の寺尾さん
-
「新しい出会いを創造できるのも、この仕事のまさに醍醐味」同社初の女性管理職として働く田中さん。
-
「『聖域』を尊重しつつ女性目線を活かしていきたい」男性中心のプロ野球界で広報として働く香川さん。
-
「アナウンサーは良くも悪くも「人間性」が出る仕事」野球好きが高じてアナウンサーになられた市川さん
-
「どでかい好奇心と辞めない決意」フリーエディターから著名雑誌の編集長に。誰にも作れない記事を目指す中本さん
-
関西の番組らしい「おもしろい」を作りたいテレビ番組制作会社のディレクターとして働く日高さん
-
「職業人、家庭人、地域人三面性をあわせもつ女性が増えて欲しい」育休復帰後に希望の広報で活躍する渡辺さん
-
「必要なのは「達成意欲」の高さ」オフィスで働く女性のための情報誌「シティリビング」の編集デスク、村上敬子さん
-
「PRは情報を提供する企業の顔」人気チョコレート「カファレル」を扱う老舗輸入会社で広報PRとして働く山田さん
-
「目の前の仕事を全うすれば、いずれ自分のフィールドになる」神戸新聞社の記者として活躍する片岡さん
-
「裏方で働く人たちがメインに見えた」からテレビ業界に。打てば響く仕事環境が楽しいと話す弓奈さん
-
「人に伝えるというのは常にアンテナを立てていること」新聞記者から独立され、多くのファンを持つ旅行ジャーナリストの大野さん
-
「24時間夢の中でも仕事のことを考えていた」たくさん怒られたことが今でも仕事のベースになっていているという麻未さん
-
「70歳になっても続けたい」テレビ局のADからディレクターを支えるリサーチャーに転身、関西のテレビ番組の多くに携わる赤松さん。