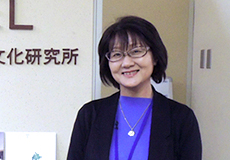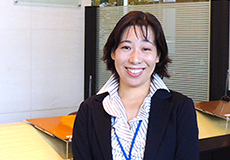HOME![]() ■関西の企業で働く「キャリア女性インタビュー」
■関西の企業で働く「キャリア女性インタビュー」
![]() 加茂 みどりさん(大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所 主席研究員)
加茂 みどりさん(大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所 主席研究員) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西の企業で働く「キャリア女性インタビュー」
加茂 みどりさん(大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所 主席研究員)


| 加茂 みどりさん 大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所 主席研究員 京都大学工学部建築学科卒業後、大阪ガス株式会社入社、営業・商品開発部門を経て現職。少子高齢社会のライフスタイルに対応した住宅や住環境等について研究。大阪ガス実験集合住宅NEXT21の居住実験を担当し、住まい方などについて調査研究を実施。博士(工学)。一級建築士。神戸松蔭女子学院大学・神戸芸術工科大学非常勤講師。大阪府住宅まちづくり審議会委員、神戸市すまい審議会委員、大阪市あんしんマンション有識者会議委員、京都市新築住宅の省エネルギー化推進に向けた検討会議委員等。 大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所:http://www.og-cel.jp/index.html 大阪ガスの実験集合住宅 NEXT21:http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/next21/ |
| お仕事の内容を教えてください。 |
| 住宅に関する研究をしています。具体的には、大阪ガスの実験集合住宅NEXT21の居住実験を担当し、住まい方やライフスタイルなどを調査し、あるべき住宅・住環境についての研究をしています。特に少子高齢社会のライフスタイルに対応した住宅や、環境にやさしい住宅のあり方をテーマとしています。 |
| 大阪ガスに入社されたきっかけは? |
| 1986年入社ですが、大学卒業当時は男女雇用機会均等法の施行1年前、京都大学の男子学生にはダンボール何箱というくらい求人が来ていましたが、女性には一通も来ませんでした。就職担当の教授を通じて、大手のゼネコンやデベロッパーを受けてみましたが、軒並み門前払い。そこで建築業界以外で探してみると、大阪ガスが、男女雇用機会均等法の1年早く大卒の女性を採ろうという方針で求人があったんです。大阪ガスは設備的な業者なので、一社だけでなく全てのゼネコンと関わることができる、横断的に業界をみることができるので面白いかなと思いました。 |
 |
| 働きながら長く介護生活をされていたそうですね |
| 入社してまだ2年目、25歳の時に、母が脳卒中で倒れて寝たきりになり、その2年後に父も倒れ、10年以上両親の介護をしながら働いていました。母は後に施設に入りましたが、父はかろうじて歩けたので自宅介護。今のようにケアマネージャーや介護サービスが無い時代でしたから、この日はヘルパーさんが来るので早く帰らなければいけない、この日は宅配のお弁当でしのいでもらおうと、介護と仕事を往復する毎日。友達と旅行もいけないし、いろんなことを順番に諦めていかないといけませんでした。 入社後しばらくは、営業部署に配属されていましたが、その後、お客様に住宅や設備についていろいろな提案を行う業務に変わり、ある時、高齢者住宅はどうあるべきかという提案書を作ることになったんです。ところが私も介護をしている最中ですから、何をやっても自分のことのように思えてしまう。「高齢者住宅には手すりが必要です」と提案しながらも、自分の中で「ああ、手すりが要るんだよな・・」と、辛くなってしまうことがありました。 |
| 仕事と介護の両立の悩みをどう克服されたのですか? |
 家と仕事の往復に耐え切れなくなってしまい、どうしようと悩んでいた頃、この「NEXT21」実験住宅のR&D(研究開発)の部署に異動になったんです。 家と仕事の往復に耐え切れなくなってしまい、どうしようと悩んでいた頃、この「NEXT21」実験住宅のR&D(研究開発)の部署に異動になったんです。「NEXT21」とは、実験住宅を建て、そこに社員が実際に住み、いろんな試みを行っていくプロジェクトですが、そこでたまたま指導してくださった先生が京都大学の恩師でした。 その先生の導きで「博士とってみないか」という話があり、会社の制度を利用して大学院に社会人入学しました。 大学時代は建築学科でも地域開発の研究室だったので、住宅の勉強はこのプロジェクトに入ってからですが、住宅のあるべき姿を研究することが面白かったんですね。 もう一度学びたいという気持ちもありましたし、家と会社の往復だけの生活の中で、介護でも仕事でも無い、第三の場所、いわゆるサードプレイスが必要だったんです。大学院には週に1回でしたが、それが心の軽さに繋がったと思います。 |
| 研究者として働くことで、大学と企業の違いはありますか? |
| どの企業でも、研究職として働く方の中には、このまま企業内で働くか、大学で働くか迷う方も少なくないと思います。でも企業でなければできない研究もあって、その最たるものがこの「NEXT21」というプロジェクトだと思います。 もともと大阪ガスは実験住宅を建てて、開発中のガス器具を実際に使ってみるということをしてきましたが、このプロジェクトはガス器具だけでなく、建築の専門家が入り、住宅のあり方とエネルギーシステムのあり方の両方を考えようというところに大きな特徴があります。 世の中にエネルギーシステムを提供しているという企業の役割があってこそ可能となるプロジェクトだと思うので、こんなことはなかなか大学ではできません。私の場合、企業の中だからこそ、自分の研究が会社に求められる成果にフィットすると考えています。 |
| どのような研究をされているのですか? |
| 少子高齢者時代に対応した住宅のあり方を研究しています。子育て、高齢小規模世帯、家族の個人化、子育てや介護向けサービス、多様なワークスタイル、個人のネットワーク。これら6つ課題に対する対応を考え、どんな解決をしていけばいいかを研究のテーマにしています。 その一つに、住まいにおける「中間領域」の研究があります。「中間領域」とは、外部空間と内部空間の重なり合う領域、私的空間と公的空間の重なり合う領域という意味です。半屋外の気持ちよさを体感でき、外からの訪問者と気軽にくつろげるような、昔の縁側のような空間を提案しています。 時間に追われ、余裕のないことが多い現代人の生活に、少しでも潤いとゆとりを与える住宅、住環境とはどのようなものだろうかと、常日頃考えています。 |
| 現在は子育てと仕事との両立に奮闘されているそうですね。 |
 父が亡くなった後に結婚しましたが、就職したときから「自分で稼いで食べる」という考えを持っていましたので、結婚しても辞めることは考えませんでした。 父が亡くなった後に結婚しましたが、就職したときから「自分で稼いで食べる」という考えを持っていましたので、結婚しても辞めることは考えませんでした。現在はシングルマザーとして2人の子どもを育てていますが、全部一人でやらなければならないので、自分の時間や仕事の時間の確保が難しく、今でもドタバタです。 育児サービスを駆使したり、学童保育を利用したり、毎日いろんなお稽古ごとを組み合わせて子どもの居場所を作ったり。 手作りの食事にはこだわらず、無理な時には買ってくる。残業の時はお弁当を作っておいたり。とりあえず帰宅した後も、どうしてもしなければならない仕事があれば夜中にする、という感じで、まだまだ「仕事と育児の両立」の綱渡り状態です。 |
| 子育てや介護の両立に悩む方へメッセージをお願いします。 |
| 自分が苦しい時、頼れるものが全くないわけじゃない。友人もいるし、今はいろんなサービスもあります。これらのリソースをうまく組み合わせることや、サードプレイスを作ることで、窮地を乗り越えていって欲しいと思います。 |
| ありがとうございました。 |
|
(取材:2015年10月/所属・役職名等は取材時のものです) |
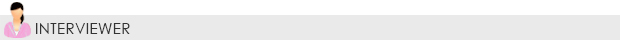
 インタビュアー:諸田 智美 インタビュアー:諸田 智美特定非営利活動法人 女性と仕事研究所 代表理事 佐賀大学卒業後、1987年大手SI会社に入社。SEとして金融情報系システムプロジェクトに従事。退職後、キャリアチェンジにより、マンションリフォーム企画営業を6年、パソコンスクール責任者を6年経験。2006年1月㈱ネットラーニング入社後、2009年11月グループ会社㈱wiwiwへ。2014年4月まで、カスタマーセンター長として大規模セミナー企画・運営、広報等を担当。2014年2月に「男女ともにキャリアと育児の両立を実現するためのシンポジウム」を企画・運営。大阪では、2013年11月に第4回女性活躍推進フォーラムの企画・運営を担当。2014年5月から現職。 |

特定非営利活動法人 女性と仕事研究所
男女ともにあらゆる分野で活躍できる市民社会の構築をめざすNPO法人 大阪市北区堂島浜1-4-17 田中ビル4F TEL:06-6341-3516 HP:http://www.women-work.org |
■関西の企業で働く「キャリア女性インタビュー」 記事一覧
-
「人からの誘いや依頼を断らずにきた」元尼崎市長であり、現在は社外取締役等さまざまな肩書を持つ白井さん
-
「女性だからというより、自分は何ができるかという考え方を選ぶ」部下の育休から復職率100%が自慢という横谷さん
-
「長く働いて長く貢献するんだという気持ちで取組む」女性企業内弁護士のロールモデルとして活躍する片岡さん
-
「キャリアと家庭、どれを優先するかはその人の価値観」キャリアと家庭を効率的に両立されている山崎さん
-
「人生を俯瞰するチャンスはたくさんある」仕事と子育ての両立に悩み、働き続けることを貫いた山元さん
-
「介護や育児と仕事の両立は綱渡り「第三の場所」が心の拠り所になる」学びと研究が心の軽さに繋がった加茂さん
-
女性だからではなく、私が私として働く」女性活躍推進「女性きらきら推進室」のメンターでもある千葉さん
-
合言葉は「ゆいまーる」仕事も育児もとよくばってもいい2人の育児を経て継続勤務30年の繁村さん
-
「まずはやってみよう。人の想いがカタチを作る」多様化するライフスタイルに対応した制度作りに取り組む湯浅さん
-
「自分なりの管理職になろう」保育士から保育所の所長にキャリアアップされた三木さん
-
「自分の環境は今の自分に与えられているもの」家族の介護とワークライフバランスを実践する加治さん
-
「多くの部署を経験したことは必ずどこかで活きる」ウーマンスマイルカンパニーの理念とカタログ「ベルメゾン」千趣会で働くみゆきさん
-
「子どもを預けて仕事に時間を使うなら内容の濃い時間を使いたい」産休育休を経て会社に復帰後、総合職へキャリアアップ
-
「働き続けて良かった」育児をしながら女性が諦めずにキャリアアップするためには?数々のエピソードを交え、勇気づけられるメッセージ
-
一級建築士として働く一方「女性活躍推進チーム」のリーダーとして女性目線で商品開発され同社の活躍を社外でも情報発信されています。
-
事務職に向いていないと思っていた就活時代からキャリアアップ、子育てをしながら働き続けようと思ったきっかけを伺いました。
-
関西人なら誰でも知っている京阪神エルマガジン社の雑誌「Richer(リシェ)」編集長の金馬さん。雑誌が大好きな女の子が編集長になるまで