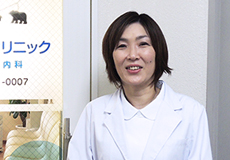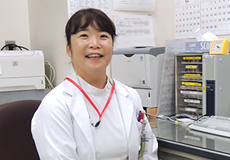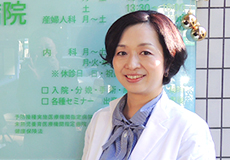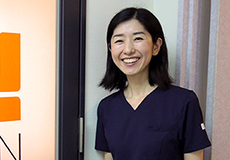HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(医師)
■関西ウーマンインタビュー(医師)
![]() 植木 麻理さん(眼科医/大阪医科大学講師)
植木 麻理さん(眼科医/大阪医科大学講師) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(医師)
植木 麻理さん(眼科医/大阪医科大学講師)

| 植木麻理さん(眼科医/大阪医科大学講師)
大阪医科大学卒。平成3年 大阪医科大学 眼科学教室入局、平成5年北野病院出向、平成8年耳原総合病院、平成11年大阪医科大学助手、平成15年大阪医科大学講師、平成17年高槻赤十字病院部長、平成20年より現職。平成16年 第1回藤田賞(大阪医科大学附属病院診療等功績顕彰)受賞、平成18年 第3回Alcon Japan Clinical Award 受賞 大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7 http://hospital.osaka-med.ac.jp/ |
| お父様のご意思を継いで眼科医になられた植木麻理さんは、緑内障の中でも難治とされる血管新生緑内障の専門医。お子さんを育てながら医師としてのキャリアを積み、お子さんとシッターさんを連れて海外の学会に行かれるなど、パワフルなママドクターです。昨今増えている働き盛りの方や高齢者の緑内障。最新の治療を研究されるだけでなく、患者さん一人ひとりの、その後の生活に想いを馳せてこそ、「医療」であると仰います。 |
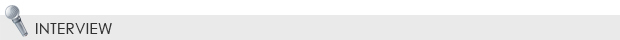
| 朝から夜まで手術の毎日。妊娠を告げるにも戸惑いが。 |
| 植木さんが眼科医になられたのはなぜですか? |
| 父が眼科の開業医だったので、なんとなく私が実家の医院を継ぐんだろうなと思っていました。ですが、大学卒業する直前に父が亡くなってしまって、どうしようか迷いもありましたが、やっぱり父の意思でもあると思い、眼科医になりました。 |
| 眼科医は女性が多いと伺いましたが、皆さん長く働いておられるのですか? |
| 大阪医大の眼科も半数以上が女性医師です。今は子どもができても仕事を継続していけるように変わってきていますが、以前はうちの医局も、女性医師が妊娠すると辞める方がほとんどだったようです。 私も妊娠する前は、朝8時半から夜11時まで手術という毎日。夫と一緒にいるより教授といる時間が長いという生活でした。なので妊娠が分かったときは、教授になかなか言えなくて、6ヶ月になるまで言えませんでした。 妊娠したことを教授に告げると、「えっ」と言ったまま、そのままいなくなってしまったんです(笑)しばらくして、「さっきは驚きすぎました。おめでとうございます」というメールが届きました。びっくりしすぎてどう言っていいかわからなかったんでしょうね。 それからすぐ、私が気兼ねなく当直しないで済むよう配慮していただいて、「妊娠が分かった時点から子どもが3歳になるまで、希望がなければ当直をしなくても良い」という医局の規定を作ってくださったんです。なので、あまり困らずに来れたように思います。 出産後、「子育てするために、1度大学病院を出てみるか?」と言われて他の病院に出向し、9時から5時、遅くとも8時には帰るという、保育園の時間内で勤務をしていましたが、3年もするとそれに飽きてきて(笑)大学病院に戻ってきました。 完全復帰した後は、時短制度を利用していましたが、それでも帰れないこともありますし、夫は長年単身赴任をしているので、子どもを見るのは私だけ。国内外の学会に出たり、地方での講演会に出かけるときは、今も子どもとシッターさんも一緒に連れていくようにしています。 |
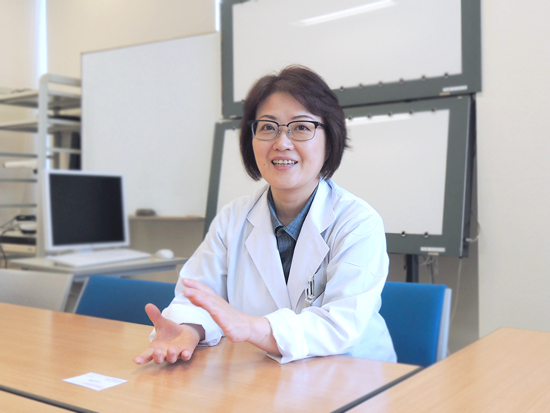 |
| 患者さんの不安に寄り添い、医師ができること |
| 先生は緑内障の中でも、難治とされる「血管新生緑内障」がご専門だそうですね |
| 上司である今の教授が、「網膜硝子体疾患」の専門で、毎年2~3人の医師をピックアップして手術を指導されているのですが、私はその一期生だったんです。糖尿病網膜症が重症になると、血管新生緑内障になっていく人が必ず出てくるので、そうなると網膜だけではなく、緑内障の治療しなければならなくなります。 血管新生緑内障は以前は教科書に「治療方法:Hopeless」と書かれていたほど、この病気になるとほぼ失明すると考えられていましたが、今は薬や手術の方法もいろいろあるので、中には1.0くらいの良い視力を維持できる場合もあります。 ですが、患者さんの中には、ほとんど見る力が残っていない状態で来られる方も多く、「手術して眼圧を下げないと、あと数ヶ月で見えなくなります。でも、手術の侵襲(しんしゅう/身体の中で起こる様々な反応)によっては、(手術が)終わったら見えなくなるかもしれないけど、どうします?」というシビアなことを暗くなりすぎないようにしながら伝えなくてはいけない。そこは非常に難しいです。 |
| これまでの経験の中で、印象に残っていることとは? |
| 私が医者になって1年目の頃、交通事故で一度に両目が見えなくなった女性の患者さんを担当したことがありました。その時、自分は医者としてもまだ何もできないけれど、この人の目はもう見えるようにはならないということだけは分かる。 「この人退院してからどうなるんだろう」とすごく不安に感じて、患者さんの横に座っていることしかできませんでした。患者さんの横に座っていたところで、この人の目が良くなるわけじゃないんですが、その時の私は、患者さんにどう接すれば良いか分からなかったんですね。 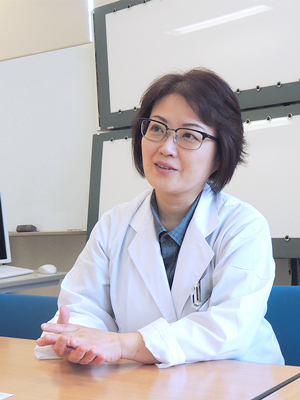 そこで、福祉のことも勉強されている視能訓練士の方に相談すると、訓練できる福祉施設に行ってもらって、日常生活に早く戻れるようにしたほうが良いと教えていただいたんです。 そこで、福祉のことも勉強されている視能訓練士の方に相談すると、訓練できる福祉施設に行ってもらって、日常生活に早く戻れるようにしたほうが良いと教えていただいたんです。それを家族の方に話すと、家族の方の気持ちの中にも葛藤があって、「もう少し待ってくれ」と仰って。でも、見えない不自由さに絶望してしまう患者さんも多いので、早く、早くという思いで、「待っていても時間がもったいないです」と言ってしまったんです。すると患者さんのご主人から「若造に何がわかる!」と言われてしまいました。 その後、その患者さんがライトハウス(社会福祉法人 日本ライトハウス/目の見えない方や見えにくい方のための総合福祉施設)に見学に行く時に、私も行かせていただいて、面談も一緒に受けました。そこでは「見えなくてもできることはたくさんある」ということを教わり、それからは、見えない目をずっとひきずっていくのでは無く、人間には五感があるのだから、それをうまく活用すれば、生活できる状態に持っていける、と考えるようになりました。 |
| その人らしい生活ができるまでケアしてこそ「医療」 |
| ドクターの言葉がけが、患者さんのその後の生活に大きく影響するのですね。 |
| とはいえ、なかなか簡単には受け入れてもらえないことも多く、中には2年も3年もかかる場合もあります。もう少ししか見え難くなっている患者さんに、「白い杖をもらってみたら?」と話しても、「なんでそんなん持たんとあかんねん」と言う人もいます。 そうなると、「春になって桜が咲いているから、杖持って散歩に出てみたら?」と言ってみたり、「秋になって涼しくて気持ち良いから、(杖を持って)散歩に出てみたら?」とか、じわじわ、じわじわ攻めてみたり(笑) 患者さんひとりひとり、生活の中で困っていることは違いますから、診察に来られる度に、「今一番困っていること何?」と聞き続けることが必要なんです。 |
| そうした「気遣い」を若いドクターにどのように指導されているのですか? |
| まず「想像する力」ですね。研修医の先生には「この人がこの状態で家に帰ったらどうなる?」って聞くんです。その患者さんがどういう生活をしているかを想像してみる。この人の住む家は1階なのか2階なのか、2階でもエレベーターがあるのか、階段しかないのか。家に誰がいて、誰がご飯を作ってくれるのか。 それを知るには入院時が一番チャンスなんです。外来では皆さん結構強がって、「大丈夫やから」とあまり家のことを話してくれませんが、入院時だと、ご家族と話をする時間がありますし、家族の方が誰も面会に来なければ、この人は家族と疎遠なんだな、ということも分かります。この人をこのまま帰せるかどうか、帰るまでに患者さんの生活状況を把握しておかなければいけません。 症状だけ見て「網膜はくっつきました」だけではなくて、退院後、ちゃんとその人らしい生活ができるまでケアしてこそ、はじめて「医療」だと伝えています。 |
| 先生ご自身、「医療」を通して、常に心に想うこととは何ですか? |
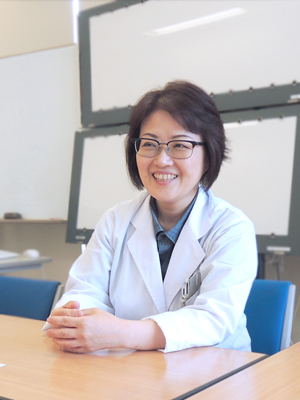 患者さんに「病院に来て良かった」と思っていただけるような治療がしたい、そう思っています。 患者さんに「病院に来て良かった」と思っていただけるような治療がしたい、そう思っています。残念ですが、治療にも関わらず見えなくなってしまう方もおられます。その方たちにも最期のときに、「目は見え難かったけれど、良い人生だった」と思っていただきたい。そのためにも、ロービジョンケア(*1)に対応できるよう考えています。 患者さんにとって、病院に来られる時間はわずかな時間。そこから日常生活を推察することで、1つでも困っておられることが解決できればと思っています。 (*1)ロービジョンケア:患者さんが自立して、できるだけ快適な生活を送れるよう支援する眼科医療や福祉 |
| これから結婚・出産を考える女性医師の方へのメッセージをお願いします。 |
| 私自身は幸いなことに上司や同僚の理解にも恵まれ、子供が産まれてからは、当直や時間外の勤務は基本的に免除していただいてきました。ですが、女性であることや子供がいることで免除されることは、「当たり前ではない」という自覚は必要だと考えています。 そして、長く働き続けていくためには、周りとのバランスも考えてなければなりませんが、無理は禁物。それには、自分のしたいこと、しなければならないことの順序付けをすることです。何でも引き受けていると大切なことができず、続けられなくなってしまいますから、時には「できない」と言う勇気も大切だと思います。 |
| ありがとうございました。 |
| 取材:山部香織(関西ウーマン編集長)/2016年6月 |
■関西ウーマンインタビュー(医師) 記事一覧
-
「「こうなる!」という思い込みから始まって」アフリカでの国際協力から30代で医師になった藤田さん
-
『私らしく』でいいんだ実家での勤務医から独立。母になって自分の想いを実現した田野さん。
-
「目は見え難かったけれど良い人生だった、と思ってもらいたい」難治の緑内障の専門医でありママドクターの植木さん
-
「「その選択は正しかった」と思える人生を歩んで欲しい」大阪府女医会副会長として女性医師を支援する澤井さん。
-
「自分の生きたい「生き方」が選べるサポートをしたい」認知症や難病の方を往診される山田さん
-
「諦めないコツはやってみたいことを見つけること」子育てしながらリハビリの専門医として働く土岐さん
-
「自分の想いだけでは人の命は救えない」救急診療のプロフェッショナルとして働く松嶋麻子さん
-
「女性が受診しやすいクリニックを作りたい」子育てしながら仕事を続けたいと「開業」を選ばれた今村さん。
-
「特殊な環境は与えられたものではなく自分で開拓していったもの」3児の母として産科麻酔科医として働く魚川さん
-
「マニュアルの無いクリエイティブな要素が魅力的」と形成外科・美容外科として開業されている林さん
-
「働く女性たちがイキイキと長く輝く場を築いていきたい」数少ない矯正専門の歯科医として女性歯科医の支援も考える恵美子さん
-
「自信のある笑顔がステキな人をたくさん作りたい」矯正歯科のキャリアを積みながら、38歳で開業された阿部さん