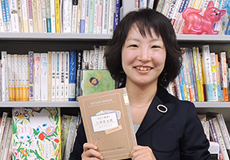HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
![]() 北村 昌江さん(賢明学院小学校 校長)
北村 昌江さん(賢明学院小学校 校長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
北村 昌江さん(賢明学院小学校 校長)

| 北村 昌江さん(賢明学院小学校 校長)
京都教育大学大学院 教育学研究科修了。専門は教育方法学で修士論文は、大正期の新教育の研究。京都市立小学校勤務を経て、ノートルダム学院小学校に23年勤務。2012年より2016年3月まで同校教頭。2016年4月より賢明学院小学校校長に就任。実績としては「生活・総合的な学習の時間」の実践研究やカリキュラムの作成、茶道を中心とした礼法学習の創設運営等、学習支援制度の創設運営、放課後の学童保育システムの創設運営などがある。 賢明学院小学校 堺市堺区霞ヶ丘町4丁3−27 HP:http://kenmei.jp/elementary/ |
| 今年4月から賢明学院小学校の校長先生に就任された北村昌江さん。長く教師として働いてこられましたが、意外にも教師を目指されたのは結婚された後。キャリアを重ねながら二人のお子さんの子育てもされてこられましたが、おおらかで元気はつらつの先生でも、教師から見る「理想の保護者像」を自分に投影してしまい、悩まれた時代があったそうです。そこで自分をどう取り戻されたのか、そして教師としてのスタンスとは何かを伺いました。 |
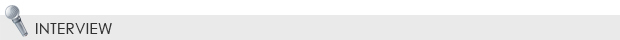
| 楽しく話せば伝わる。それが今の「原点」 |
| 北村先生は今年校長先生に就任されましたが、「校長職」とはどんなお仕事ですか? |
| この3月まで京都のノートルダム学院小学校で23年勤め、長くカトリックの精神の教えを基に私学教育に携わってきました。今年の4月より、現職である賢明学院小学校の校長に就任しましたが、前職同様カトリックの学校ですので、祈りを大切にした心の教育ができますので、違和感なく校長職を勤めています。 校長としての仕事は、登下校時の子ども達との挨拶から始まり、教職員との授業研究や情報交流、保護者の方々に安心してお任せいただけるための説明責任、より良い教育環境の提供や、教育の質を向上させるための取り組みが主な仕事です。また学院の理事として、学院全体の側面から経営戦略のデザインを考える仕事も担っています。 |
| 先生は意外にも「歯科衛生士」をされていたそうですね。 |
| 私の母は看護師でしたが、父は「子どもが小さい時は母親は家に居るものだ」という昔気質の考えでしたので、私が小学校を卒業するまではずっと家にいてくれました。でも母自身は働きたかったと思います。私には「女性は手に職をつけて、自分で生活できるようにならないといけない」といつも言っていました。資格が取れる学校を選びなさいと言われ、大学は栄養士の資格が取れる学校に行きました。 ですが、当時は管理栄養士の資格を取っても、働けるのは学校給食や病院くらい。実習でいろいろまわるうち、自分には向いていないなと思ったんです。母に相談すると、やっぱり医療関係がいいだろうということで、大学卒業後、歯科衛生士の資格が取れる専門学校に入りました。 歯科衛生士の資格を取った後、市役所に勤めることになったのですが、配属されたのが保健衛生科。保健所を周り、1歳半検診や3歳児検診に来られるお母さんたちに、子どもの歯の磨き方を指導することになったんです。最初は人前でしゃべることに苦手意識もありましたが、やってみるとだんだんおもしろくなってきて。 話の中にちょっと「笑い」を入れてみたり、自分なりの工夫してみたりすると、結構お母さんたちにウケたんですね(笑)。それがすごくうれしくて、人前で話をするのって得意かもしれない、という意識を持ちはじめました。せっかくなら楽しく聞いてもらいたい。楽しく話せば大事なことがちゃんと伝わる。その想いは今も私の「原点」になっています。 |
 |
| 歯科衛生士から教師へ。「私も教師になりたい」 |
| ご結婚されてから教師を目指されたそうですが、そのきっかけは? |
| 実は高校の時、小学校の先生になるのもいいなと考えたこともあったんです。でも小学校教師の試験にはピアノが必須で、バイエル100番まで弾けなければいけなかったんですね。私は小学校の時から鍵盤ハーモニカが大嫌い(笑)。図工も体育もできるけど、音楽は無理って自分で決めつけてしまっていたんでしょうね。 歯科衛生士として働いていた頃、当時つきあっていた夫が教師を目指して筑波大学大学院に行くことになったので、結婚して一緒についていくことになったんです。夫は学生でしたから筑波大学の夫婦寮に入れていただいて、私は向こうで歯科衛生士をしながら生活していました。 すると夫婦寮といっても学生寮ですから、周りはみんな教師の卵。その方たちと親しく接する中で、「私も教師になりたい」という思いがだんだん出てきたんですね。とりあえず教師の資格を取ろうと思い準備を始めました。当時の筑波大学はオープンでしたから、ピアノのある空き教室をこっそり借りては独学でピアノの練習をしたり、足りない教職課程は通信教育で勉強しながら、教師の資格を取りました。 京都に帰ってきてからすぐに公立小学校の常勤講師に採用され、教壇に立つことができたのですが、上の娘を出産後、当時は育児休暇が無かったので、やむなく退職することになりました。 |
| 当時は、産後の職場復帰は難しかったのですね。それを機に大学院に行かれました。 |
| 教師の仕事は自分の天職だと思っていましたから、出産後も教師は続けたかったんです。ですが当時はどこも採用試験氷河期。採用がゼロだったり、あっても20人採用のところに500人が殺到するような時代でした。 そこで私は、2年間公立小学校で経験した教師の仕事をもっと深めたいと思い、大学院に行こうと考えたんです。当時、京都教育大学で大学院の一期生を募集していることを聞き、受験することを決めました。 大学院の面接時、「大学院に通うとなると、お子さんはどうされるのですか?」と聞かれ、「もう入れていただくつもりで、保育園を予約してきました」と答えると、「まだ入れると決まってないのに」と苦笑されましたが(笑)、無事合格をいただきました。その時の印象が強烈で「絶対ここで勉強する!」という気持ちが伝わったのかもしれませんね(笑)。 入学すると、吸収できることは吸収し尽くしたくて、受講できる講座は何でも取りました。自分が働いて貯めたお金で勉強しているんだから、聞き漏らすなんてもったいない(笑)ゼミでは常に先生の目の前に座り、先生を質問攻めにして一人しゃべっていましたね。とにかく異質な生徒だったと思います(笑)大学院を卒業する頃、ノートルダム学院小学校で教師の公募があることを聞き、採用されて再び現場に戻りました。 |
| 教師から見る「理想の保護者像」に自ら悩む日々 |
| 先生は教師をしながら子育てもされてきましたが、 家の中でも「良き教師」「良き母」を自分に課してしまうことはありませんでしたか? |
子どもが小さい頃はそこに随分悩みました。子育ても100% 仕事ももちろん100%、何でも全て完璧にしなくてはいけないと思っていた自分がいたと思います。「良い母」を演じようと思っていたのは、やはり教師として、こういう保護者であって欲しいという「理想像」があったんでしょうね。それを自分に投影させてしまっていたと思います。 晩御飯はおかずを何品も作って、必ず子どもと一緒に食べて、歯はしっかり磨かせて、寝る前には本を読み聞かせて。どんなに忙しくても母親とはこうあるべきだと思い込んでいました。 晩御飯はおかずを何品も作って、必ず子どもと一緒に食べて、歯はしっかり磨かせて、寝る前には本を読み聞かせて。どんなに忙しくても母親とはこうあるべきだと思い込んでいました。私学は公立に比べて休日出勤も多いですし、企画部長になったり、生活総合部長になったり、役職がつくと責任も増えてきます。子育てと仕事、何とか両方とも満足いくようにしたいと頑張っていましたが、それが十分できていない焦りと、子育てが十分できていない申し訳なさにさいなまれ、もう自分の中で爆発しそうになっていました。 家族と一緒にいても、全く笑顔が出せない。「死にたい」とさえ考えるようになってしまって、今から考えると「うつ」のような状態だったと思います。そんな私を夫が察知して、「何でも100%しようとせずに、できなかったらごめんって言うたらええよ」と言ってくれたことで、張りつめていた心の緊張がほぐれ、何でもできるスーパーマンを演じようとしていた自分から、ありのままの自分を受け入れようと思うようになりました。 疲れている時は外食でもいいと思えるようになりましたし、仕事の上でも、同僚や上司に対しては、できないことはできませんと言える自分になったんです。でもそれは手を抜くことじゃなくて、自分が責任持ってできないことはできないと割り切る。そこからはもう誰に何を言われても怖くない自分がいました。 |
| 割り切ることで動じなくなる。それは女性が働き続ける上で必要なことなのかもしれませんね。 |
| 何でも引き受けてしまうのは、自分を良く評価してもらおうとするから。できなかったら恥ずかしいとか、失敗したらどうしようとか、内心はいろんな思いがあったと思います。でもまさか、自分が「死にたい」と思うような状況になるなんて思いもしませんでしたから、自分のキャパが分かったんですね。 今は校長として、毎日いろんなお話をさせていただく機会がありますが、上手に話をしようと思った瞬間、上手くしゃべれなくなります。私が私のまま、ありのままのスタンスで話すほうが、自分もラクですし、聞いてくださる方々も聞く耳を持ってくれます。かっこいい教育論を語るよりも、「私のやりたいことはこうだ」ということを自分の言葉で語るほうが、素直に受け止めてくださるように思います。 |
| 子どもたちの成長が嬉しくて辞められない |
| 仕事を辞めようと思ったことはありますか? |
| それがどんなにしんどくても、辞めようとは思いませんでした。2人目を妊娠した頃、つわりがひどくて朝起きられなくても、正門をくぐるとシャキッとするんです。当時の前任校には育児休暇の制度がありませんでしたから、ここでどうやってふんばろうかと考え、制度を作ってもらって、私が一番最初に育児休暇を取りました。 毎日授業をしながら、子どもたちに分かろうとするつぶやきや粘りがあると、それをどうやって引き出すかを考えます。すると、「先生、わかったあ!」「先生、できたー!」と言って来てくれることがあります。それが嬉しくて辞められないんですよ。 卒業生もたくさん来てくれますから、いつも反抗ばかりしていた子が、「先生ごめんな、あの頃の僕、中学受験でしんどかってん」って謝りにきてくれたり、「東京の大学に行くから、北村先生には挨拶してから行きたかってん」と言ってきてくれたり、親になって子どもを連れてきてくれる子もいます。教師という仕事は、100のうち98までしんどいけれど、あとの2は子どもがすてきな光を放ってくれます。長く勤めてきて良かったなと思う瞬間です。 |
| 教師として母として、いつも心にある「想い」は何ですか? |
| 今の若い人は、新卒で入社しても1年以内に辞めてしまう人が30%以上だと聞きます。日本の教育はいったいどうなってるんだと言われますが、子どもを囲い込んで大事にしすぎるからじゃないかと思います。つまり自律する力を育てていないからです。 親はついつい目先の子どもの挙動に一喜一憂してしまいます。問題が起こると、子どものことより親の都合や教師の都合を先行することがあり、その子がどのように成長するかという視点が抜けていることが多いように思います。 ストレスの無い学校生活を送ることも、それはそれで良いかもしれませんが、今後、集団で生きていく以上、子どもたち同士がせめぎ合い、そのストレスに自分なりに打ち勝つためにはどう調整すればいいか。それを学んでいくことが必要だと思います。いろいろな問題に直面したとき、「子どもにとって一番良い解決策は何か」「その子にとって何が大切か」を常に考えることが大切だと思います。 |
 |
| 教師は子どもたちの伴走者。 |
| 先生にとって「教師」という仕事とは? |
| 若い先生たちになぜ教師になったの?と聞くと、よく「子どもが好きだったから」と答えてくれますが、私は子どもは嫌いでした(笑)子どもって勝手なことばかりしますからね。 教師というのは、そういう有象無象の分けのわからないことをする子どもに、ルールに則って自分を律し、自分の中にあるものを発見させる「伴走者」だと考えています。 子どもの横で走りながら、ちょっとこっちに動くとまっすぐ走れるなとか、もう少しこうしたら楽に走れるなとか助言しながら、一緒に泣いたり笑ったり、自分も一緒に成長するのが教育の醍醐味なんです。 でも教師の役割は伴走だけ。「先生ありがとう」って手を振って前を向くときには、もう私のことなんか忘れていていいんです。そして独り立ちしていく後ろ姿を見られたら、教師として満足です。 |
| 働く女性へのメッセージをお願いします。 |
| 仕事は、生活を立てるための生業(なりわい)ではありますが、それだけで終わるのは虚しいと思います。同じやるなら、その道のプロをめざし、おもしろがって仕事に挑戦すること。そして、健康管理も働く女性の必須条件です。体調がすぐれなさそうなときは無理せず休む。いつも健康でいないとやる気も失せますから。 メンタル的にもそれは同じで、へこんだ時には、それを受けとめてくれる人がいて、やりたいことがやらせてもらえる環境にあることを感謝して日々生活することです。文句からは文句しか生まれません。仕事人としても、家庭人として感謝して生きることが大切ではないでしょうか。 |
| ありがとうございました。 |
| 取材:山部香織(関西ウーマン編集長)/2016年7月 |
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック) 記事一覧
-
「愛し愛される活動があるから先生は癒される」伝統ある男子校の興國学園。その3代目校長を務める草島葉子さん
-
「教育は人づくり町づくり。そして私は若作り」41歳で教頭先生になり、現在は大学で教師を育てる善野先生
-
「教師は子どもたちの伴走者」私学カトリックの小学校で長年教師をされ、今年校長に就任された北村さん
-
「心を強くするためには自分自身を大切に思うこと」日本の看護教育に貢献されている江川さん
-
「生活空間を創る側も多様な視点が必要です」生活の中にある課題を研究する「生活科学」の研究者、小伊藤さん
-
「多様化する「家族」に生きる子どもの気持ちに寄り添いたい」子どもの権利を研究する長瀬さん
-
「国産のものを食べたい。私の夢はそこだけ」女性農業者の起業や六次産業を啓蒙する中村さん
-
「有機野菜を買うことで社会が変わる」大学講師をしながらNPOを設立。有機農業の啓蒙活動を続ける中塚さん
-
「研究者で職を得ることは頑張れば報われるとは限らない」流通科学大学で初年次教育を担当される橋本信子先生
-
雇用や労働に関する研究に取組まれている浦坂先生。「計画された偶発性」によってアカデミックの道を歩まれた経緯をお話いただきました。