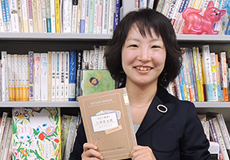HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
![]() 小伊藤 亜希子さん(大阪市立大学 生活科学研究科 教授)
小伊藤 亜希子さん(大阪市立大学 生活科学研究科 教授) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
小伊藤 亜希子さん(大阪市立大学 生活科学研究科 教授)

| 小伊藤 亜希子さん (大阪市立大学 生活科学研究科 教授) 京都大学大学院工学研究科(建築)後期博士課程修了。京都造形芸術大学、京都文教短期大学、日本福祉大学を経て、1999年 大阪市立大学生活科学研究科助教授。2013年 同教授。日本住宅会議会報編集委員長。 主な著書:「子どもが育つ生活空間をつくる」小伊藤亜希子/室崎生子編、かもがわ出版(2009)、「子どもを育む住まい方」、小伊藤亜希子/中井孝章 OMUPブックレットNo.5 大阪公立大学共同出版会(2006)、「「歴史的街区」は再生できるのか」片方信也編著 かもがわ出版(2013)他 大阪市立大学 生活科学研究科 〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 http://www.life.osaka-cu.ac.jp/ 小伊藤研究室:http://life-osaka-cu-koito.com/ |
| 「生活科学」とはどんな分野ですか? |
| 私の専門である住居学でいえば、住宅と暮らし方との間にある矛盾や、空間と生活のズレなど、生活の中で家族が持っている問題、それらは個々の問題に見えますが、同じ課題をたくさんの人が抱えているとしたら、社会的に共通した課題があります。それを社会の問題として抽出し、研究調査して、改善方法や解決方法を見出していく。それが生活を科学するということです。 生活科学部は、以前は「家政学部」という名前でしたが、衣食住だけでなく、生活の問題を解決する新しい分野として、「生活科学部」と名乗ったのは大阪市立大学が最初だそうです。生活科学部住居環境学科では、一級建築士の受験資格も取得できますが、ハードを作る工学部の建築学科と異なり、暮らしの空間を考える分野なので、自分たちの生活体験が活きる学問だと学生たちには言っています。 |
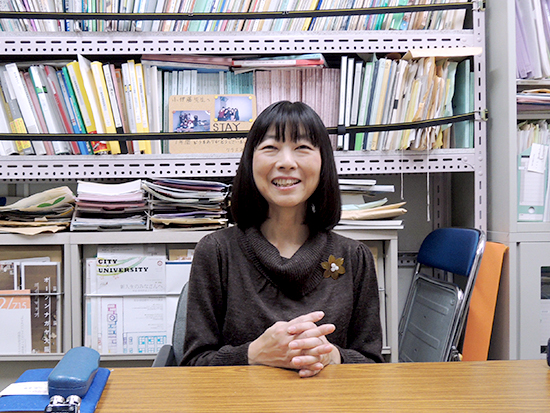 |
| もともと建築家を目指しておられたそうですね。 |
| 将来は建築家になりたいと思ったのは中学3年生の時。母の友人が家を新築したというので、母と一緒に見に行ってすごく感動したのがきっかけでした。一番日当たりの良いところに「奥さん専用の場所」があったり、夫婦の仕事場として掘りコタツ風のカウンターがあったり。それがすごくすてきで、女性の建築家が設計したと聞き、私もこんな仕事がしたいと思いました。 その夢は高校になっても続き、そのまま素直に建築学科を受験したんです。 ところが私は、特に絵や芸術的な才能があるわけではなく、大学での課題をただ真面目に設計しているだけ。同級生たちのすごい作品を見るにつけ、「すごいなあ。ああいうのはできないな」と不安になってきたんです。 4年生になり、どういうところに就職したら良いか、母の知り合いで建築関係の人に相談すると、「まだ自分の建築観というものは無いだろうし、大学院に行ってから社会に出ても遅くないんじゃない?」と言われ、確かに、建築に対する自分の考えというものはまだ無いなと、迷った末に大学院に進みました。 大学院に進むと、同級生や先輩たちと切磋琢磨して研究調査することが楽しくて、そのころ博士課程にいた今の夫の影響もあって、研究者の道を目指すことにしました。中学生からの夢だった設計そのものの仕事はできませんでしたが、研究者として住空間のあり方を考えることができているので、夢は半分叶ったかなと言えるかもしれませんね。 |
| 女性研究者としての壁はありましたか? |
大学院の博士課程を終えてからいくつかの大学を転々としましたので、なかなか安定しませんでした。最初の2つは任期付きポスト、3つめは正規ポストでしたが、京都の自宅から通うのは困難な遠方だったので、夫と長男をおいて1年間の単身赴任をしました。当時長男はまだ2才、覚悟の上で赴任したものの、毎週別れぎわに大泣きされて、どんどん不安定になっていく長男にとまどい、さすがにかわいそうでしたね。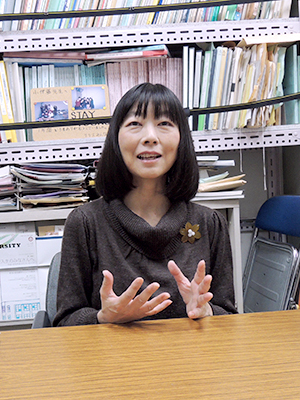 その後、大阪市立大学に赴任し、いつの間にか17年も経ちましたが、子どもが小さい頃は、他の先生方が遅くまで研究しておられる中で、保育園のお迎えに間に合うために、私だけ仕事をブチッと切らざる得ない。しかも私は人より仕事が遅いのに、そのまま思考停止しなくてはいけないことは辛かったですね。同僚の先生たちはどんどん仕事が進んでいるのに、私だけ帰らなくちゃいけない。そういう夢を見るくらい、かなり焦りがありました。 その後、大阪市立大学に赴任し、いつの間にか17年も経ちましたが、子どもが小さい頃は、他の先生方が遅くまで研究しておられる中で、保育園のお迎えに間に合うために、私だけ仕事をブチッと切らざる得ない。しかも私は人より仕事が遅いのに、そのまま思考停止しなくてはいけないことは辛かったですね。同僚の先生たちはどんどん仕事が進んでいるのに、私だけ帰らなくちゃいけない。そういう夢を見るくらい、かなり焦りがありました。でも今思うと、そのときはしんどくても、研究が進まなくても、自分自身の生活体験は全て研究に活きていると思います。学生たちにも言うのですが、生活空間を使う人は多様なので、生活空間を作ったり研究する側もまた、多様な視点が必要です。いろんな経験や体験をしたことは、全部自分の中で蓄積され、必ず仕事に活かされるので、何も無駄にはならないんだなと思います。 |
| これまでどんな研究をされてこられましたか? |
| 専門は住居学なので、家族の暮らしから見た、住宅や生活空間のあり方について研究しています。特に、子育てや子どもが育つ空間をどのように整えればよいのか、に興味があって、自分の子育ての体験に重ねながら研究を進めてきました。 子どもが生まれたころに取り組んだのは、乳幼児がいる住まいの研究です。当時は小さな2階建て住宅に住んでいましたが、急傾斜の階段が危険だったので、ちょっとモノを取りに行くだけでも、いちいち子どもを抱っこして移動しなければいけない。また、子どもを寝かしつけた後も、泣き声にいつも耳をそばだてていた体験から、子ども部屋を想定して個室のたくさんある一般住宅と、乳幼児のいるライフステージの家族の生活とは、かなりズレがあるのではと考え、実際の住み方から求められる住空間のあり方を調査しました。 |
| 住まいの中の「妻の専用スペース」の研究もされたそうですね。 |
| 住まいの中の妻の専用スペース研究は、簡単に残業ができない働く妻は、持ち帰った仕事をするための専用スペースが必要だという思いから取り組みました。夫婦の寝室と子ども部屋しかない「nLDK住宅」には、妻が仕事をする空間は想定されていません。また、「nLDK住宅」は欧米モデルなので、実際の日本人の暮らしとは、かなりズレがあると思います。 (nLDK住宅:2LDKや3LDKなど個室の数とリビング&ダイニングを想定した住宅) 調査した対象は、建築関係や学校の教員、NPOなどの社会活動をしている女性、と職業を絞ったこともありますが、かなりの方が自分専用のスペースを持っていました。もともとそういうスペースを想定していない住宅に住んでいておられますが、リビングや寝室の一角に作っている方や、専用の個室を持っている方もいました。 専用スペースが無い場合、ダイニングテーブルで仕事をされている方がほとんどでした。そうなると、ご飯の度に片付けなくちゃいけない。中には、よくこんなところでご飯を食べているなと思うほど、散らかっているという人もいました。子どもの学校の書類と自分の書類が混ざって、失くしてしまうこともありますし、子どもに触られたくないものもあります。やっぱり途中で家事ができて、モノを失わずにちゃんと安全に置ける場所が必要ですよね。 そこには「子どもの様子を見ながら仕事をしたい」と、「子どもに邪魔されずに仕事をしたい」という2つの要求が存在していて、同じ人の中に両方存在する場合もあります。仕事の内容や子どもの年齢にもよりますが、そこには、「一人になりたい」という要求が混ざっているので面白いですね。中には、「このスペースが無ければ生きていけない」と仰る方もいて、思った以上に、働く女性にはそうした場所が必要なんだなと思います。 |
| 現在、「拠点性を備えた学童保育」の研究も進められていますが、拠点性を備えるとは? |
 今は働くお母さんも増えて、学童保育が広がってきたのは良いのですが、大勢の子どもたちの安全を確保するためには、施設の中に囲い込む傾向があるんです。保育時間もどんどん延びてきて、昔は5時までだったのが、今は普通に6時7時まで預かってくれます。 今は働くお母さんも増えて、学童保育が広がってきたのは良いのですが、大勢の子どもたちの安全を確保するためには、施設の中に囲い込む傾向があるんです。保育時間もどんどん延びてきて、昔は5時までだったのが、今は普通に6時7時まで預かってくれます。すると、子どもたちは家と学校の往復だけで、昔のようにあちこち遊びまわったり、お友達の家に行き来する体験をしないままになってしまいます。それでいいのかな、もっと地域で子どもが育つ居場所ができないかな、という思いから、「拠点性を備えた学童保育」の研究に繋がりました。 大阪市では「児童いきいき放課後事業」といって、誰でも無料で行ける放課後対策を行っていますが、それとは別に、学童保育が法制化される前の時代から、保護者の方たちが地域の空き家やビルの空き室を借りて、学童保育を運営されてきた歴史があります。 そこには学校の中のようなグラウンドはありませんから、子ども達は近所の民家の前で遊んだり、地域の公園で遊ぶんです。公園には他の友達もいて一緒に遊べますし、近所の人に挨拶もできます。週1回100円を貰って近所の駄菓子屋さんに行ったり、友達に家に行くことや習い事に行くことを許可しているところもあります。地域の中に安全な拠点があれば、そこから自然に広がって、普通に家庭にいるのと同じように生活できるんですね。 保護者の方が運営する学童保育は、補助金も出ていますが、お金が無い中でとても苦労されています。まだまだ学童保育は不足していますし、子どもが放課後いきいき過ごせる居場所づくりはとても大切。学校の中に囲い込むだけじゃなく、拠点のある放課後の居場所作りへと転換するためには、もっと公的な支援が必要だということを、声にしていかなくてはいけないなと考えています。 最近、他大学との研究チームで、海外の子どもの放課後施策を調査していますが、そこにさまざまなプログラムは用意されていても、「遊び」という概念が薄れつつあると感じます。やはり昔から、子どもたちの主体的な遊びの世界を大事にしてきた日本の学童保育は、すごいなと改めて思いますね。 |
| 今後、実現したいことは何ですか? |
| この分野は社会と直接繋がっていますから、研究して論文を書いただけでは、なかなか実際の社会は変わりません。これまで、ゴールは遠い彼方にある感覚で、自分や学生の興味に合わせて、あちらこちらのテーマに研究が広がってきてしまいましたが、これからは少し焦点をしぼって、もっと現場で活動されている方たちの力になるような研究結果や情報を、きちんと社会に発信することに力をいれたいと思っています。まずは、子どもたちが安心していきいき過ごせる放課後の居場所づくりに繋がる研究で、成果を出していきたいですね。 |
| ありがとうございました。 |
|
(取材:2016年1月 関西ウーマン編集部) |
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック) 記事一覧
-
「愛し愛される活動があるから先生は癒される」伝統ある男子校の興國学園。その3代目校長を務める草島葉子さん
-
「教育は人づくり町づくり。そして私は若作り」41歳で教頭先生になり、現在は大学で教師を育てる善野先生
-
「教師は子どもたちの伴走者」私学カトリックの小学校で長年教師をされ、今年校長に就任された北村さん
-
「心を強くするためには自分自身を大切に思うこと」日本の看護教育に貢献されている江川さん
-
「生活空間を創る側も多様な視点が必要です」生活の中にある課題を研究する「生活科学」の研究者、小伊藤さん
-
「多様化する「家族」に生きる子どもの気持ちに寄り添いたい」子どもの権利を研究する長瀬さん
-
「国産のものを食べたい。私の夢はそこだけ」女性農業者の起業や六次産業を啓蒙する中村さん
-
「有機野菜を買うことで社会が変わる」大学講師をしながらNPOを設立。有機農業の啓蒙活動を続ける中塚さん
-
「研究者で職を得ることは頑張れば報われるとは限らない」流通科学大学で初年次教育を担当される橋本信子先生
-
雇用や労働に関する研究に取組まれている浦坂先生。「計画された偶発性」によってアカデミックの道を歩まれた経緯をお話いただきました。