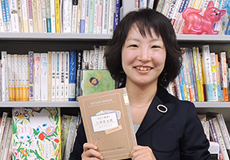HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
![]() 江川 隆子さん(関西看護医療大学 学長/理事長)
江川 隆子さん(関西看護医療大学 学長/理事長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
江川 隆子さん(関西看護医療大学 学長/理事長)

| 江川 隆子さん 関西看護医療大学 学長/理事長 ロングアイランド大学保健学部看護学科 卒業、ニューヨーク市立リーマン大学大学院看護学修士課程修了、医学博士学位授与(大阪大学)。自治医科大学、大阪大学保健学科、京都大学人間健康科学専攻で24年間、学部、修士および博士課程の教育・研究に携わる。京都大学名誉教授を経て、2010年に関西看護医療大学学長就任、2015年に学校法人関西看護医療大学理事長に就任する。専門は、看護診断学・生活習慣病看護学。 関西看護医療大学:兵庫県淡路市志筑1456-4 http://www.kki.ac.jp/ |
| 先生はもともと看護師として現場におられたそうですね。 |
| 看護学校を卒業後、看護師として慶応大学附属病院で、6年程勤務していましたが、その間に2年間休職をして、看護師交換留学制度を使って、留学させてもらいました。帰国半年後に、引きとめられましたが、看護大学での学習を夢見て、再度アメリカに渡り、交換留学での恩師を頼って、ニューヨークのアップタウンにあるコロンビア大学病院:プレスバイテリアン病院で10年ほど勤務しました。なので、合計15年余り現場で勤務していたことになります。その間に、念願であった、看護大学と大学院で看護学の勉強をする事ができました。 私が、再度アメリカに渡った1970年後半から1980年にかけて、アメリカでは、病院に勤務する看護主任や看護師長になるためには大学や大学院を出ることが義務づけられるようになっていました。 |
| その頃、日本はまだ大学には看護の教育は無かったのですね。 |
| いいえ、ないことはなかったのです。高知女子大学、聖路加看護大学、千葉大学など4校ぐらいあったと思います。その他は、短大が国公立にできかかっていましたが、看護学校が主流でした。日本で看護教育が大学で積極的になってきたのは、この20年間だと思います。 現在では、200校以上の大学で看護教育が行われていますし、その約半分の大学で看護の大学院教育が、そして70校以上で看護の博士課程の教育が行われるに至っています。と言うことは、やっと、看護教育のレベルがアメリカの1980年代に追いついたということでしょうか? 最近では、日本でも大きな病院の看護師長さんの中に大学院を出た人が増えていますし、看護部長の中に博士号を持った人たちが増えています。また、大きな病院ほど、看護大学を出た看護師が半数以上も従事するところも増えています。一方で、中小の病院では、まだまだ看護学校を出た看護師が現場たたき上げで主任や看護師長、部長になる病院も少なくありません。 一方、看護大学の教員になるためには、他の大学教員と同じく、大学院以上の学歴に加えて、研究業績が要求されています。教授になるためには博士号と研究業績と大学での教育歴などが不可欠となっています。 |
| 帰国後、現場ではなく「看護教育」にシフトされたのはなぜですか? |
 1984年に帰国して、看護師長にとご紹介いただいた病院も2~3ありましたが、アメリカの大きな病院に10年以上いましたので、日本の病院のシステムがあまりにも古臭く感じてしまって(笑)。 1984年に帰国して、看護師長にとご紹介いただいた病院も2~3ありましたが、アメリカの大きな病院に10年以上いましたので、日本の病院のシステムがあまりにも古臭く感じてしまって(笑)。古臭く感じたのは、大学病院でさえも大学や大学院を出た看護師が少なかったからではないでしょうか?それが看護師を見る目が、つまり看護師に対する社会の評価が卒業当時と変わっていなかったからでないかと今、思います。 私がアメリカでいた頃は、看護師教育の変革の時であり、また大学病院などは、積極的に大学院や博士課程に行くことを、看護部長自らスタッフに勧めていました。だから、大学や大学院を出た看護師が、また大学院や博士課程に通っている看護師が沢山いました。 そんな環境での10年間を勤務した私は、病院の活性化には、また看護の質の向上には、看護教育の充実が最も重要な1つの要素だと思うようになったため、教職に就くことにしたと、今思っています。これまで25年余り看護教育に携わってきましたが、教育によって高学歴の看護師が増えてくると、我々を見る目も違ってくるだろうと信じていますし、実感しています。 |
| 先生は「看護診断」についての著書を多く出されていますが、「看護診断」とは何ですか? |
| 看護師の主な仕事は、治療を行う医師の診療上の補助と患者さんの日常生活の援助です。しかし、今は管理栄養士や介護福祉士など、それぞれの分野の専門資格が出てきましたから、そうすると看護師のアイデンティティって何だろうという学問的な考えが出てきたんだと思います。 診療の補助とADL(日常生活の援助)のケアだけであれば、そんな修士や博士課程を作るほどのこともありません。ですが看護の中において、診療の補助やADLのケアと同等くらいに、病気や病気の進行や治療の過程で生じる心理的な悩み、患者さんの身体的な悩みを理解することが重要です。そのためには、医師と同じように患者が受ける治療・その予後など多方面における知識や技術、更には看護の哲学が重要です。 私はアメリカの大学院で、看護の知識や技術だけでなく、それらの論理性を教えられました。物事の論理がしっかり分かれば、何を「診断」としているか、なぜそうなっているかを読み取ることができます。私たちは「看護概念」といいますが、患者さんにとって今何が必要であるかを見極め、改善へと導くために看護師が独自に判断し、その実践を判断していけるものを確立してきたのが看護診断という領域です。 ただ、「看護診断」はまだまだ臨床を含め、教育においても十分に浸透できていないのが実状です。本学では「看護診断研究センター」を設立し、看護師にとって重要な仕事、「看護診断」の普及を目指して様々な活動を行っています。 |
 |
| 今後日本は看護師不足に陥ると言われ、外国人看護師の受け入れが問題になっています。それについて先生はどう見ておられますか? |
| 私もアメリカでは、いろんな国の看護師と一緒に働いてきましたが、患者さんに優しくしているように見えても、お金を貰える仕事だからと割り切っているようなところもあって、なんとなく違和感を感じたこともあります。日本人は自己中心的な思考ではなく、人の立場に立って考えるという文化を持っていますし、特に日本女性は、細やかな優しさ、犠牲的な精神というものを持っていると思います。 どなたに対しても後ろに三歩下がるという奥ゆかしさ。実際に三歩下がらないにしても、下がっている気持ちは持っています。それが良い意味でも悪い意味でも日本女性の特徴なんですね。外国にはそうした文化はありませんから、同じ優しくすることでも種類が違うような気がします。人を区別をする気はありませんが、日本はまだまだ受け入れ難いんじゃないかという気がしますね。 |
| 貴校のサイトに、看護師の仕事は「知」と「技」に合わせて、「強い心」をもつことだという先生の言葉が掲載されていますが、今の若い人たちが「強い心」を持つために、どのような指導されているのですか? |
| 心が強くなければ人に優しくできません。心を強くするためには、やはり自分自身を大切に思うこと、自分が幸せであると思えることだと思います。今の若い人たちは、自分を大切に思っていないのでは、あるいは自分が幸せだと思っていない人が多いのではないでしょうか。それは、周りから大切にされてきていないんじゃないかという気持ちにつながります。 今の学生を見ていると、家庭の中であまり可愛がってもらっていないのではとか、また学校の先生にしても、優しく甘やかさないと寄ってきてくれないし、厳しくすると親から文句が来るかと思う中で、学生達はそうして誰からも無意味に甘やかされた感じをもっているのではないでしょうか。その実、看護学の学習、特に学生たちは実習で人としての、看護師になるための”心”を鍛えらます。だから、いろんな意味で大人になっていくようです。これはもう本人の体験以外無いと思います。  本校は実践を重きにおいていますから、「こんなに1日中指導者が付いている学校は無いですね」と病院側から言われるほど、実習には必ず5人くらいに一人の指導者が入ってしっかり見ています。 本校は実践を重きにおいていますから、「こんなに1日中指導者が付いている学校は無いですね」と病院側から言われるほど、実習には必ず5人くらいに一人の指導者が入ってしっかり見ています。優しそうな言葉をかけても、本当に患者さんのことに向いているかどうか、患者さんには伝わります。学生の中には、知識があるのに手を出さなかったり、知識が無いのに手を出してしまったり。そんな時、その行為・言動が患者さんにとって危険行動と判断すると、ものすごく学生を怒るだけでなく、即、実習の中止をします。 でも、「先生に怒られると嬉しい」と、怒られて喜ぶ学生もいるんですね。これまで親や先生に怒られたことも無ければ、よくできたねと誉められたことも無い。それだけ大事にされてきていないのでしょうと思ってしまいます。 医療の現場は厳しいですから、できなければ落第させます。あまり落第者が多いと学校の評価に影響するんじゃないかという声もありますが、到達しない人を進級させてもどうしようもありません。そういう厳しさが強い心を育てると考えています。 心を伝えるということは、これが教育の難しいところで、口で伝達するだけでは伝わりません。教員自身も自分を律して生きていなければいけない。その背中を見せることで学生たちが感じ取ってくれると思います。それしか無いように思います。先生の失敗も見せることです。 |
 |
| 最後に、これから看護師を目指す方達に向けて、どんなメッセージを伝えられますか? |
| やはり自分自身を大切に思うことです。自分を大切にするといっても、自己中心的な自己愛ではなく、本当に自分が幸せだと思えるようになってから、他人をケアしてくださいと言いたいですね。そして他人を大切に思い、幸せにするためにどうするかを考えられる、看護者としての心をもってほしいです。 また、決して他人と比べず、お金のためではなく自分の夢のために仕事をすると考えること。仕事場にいるときは仕事が優先、家庭では家庭が優先。それを実行できる人でなければうまく行かないように思います。 何回も挑戦することは良いけれど、自分にはこの職業が向いていないと思うなら、それはもう辞めるべきです。患者さんも不幸にしますし自分も不幸になる。特に「人」に関わる仕事は、そうでなければならないと思います。 |
| ありがとうございました。
|
 取材協力: 取材協力:関西看護医療大学 兵庫県淡路市志筑1456-4 http://www.kki.ac.jp |
|
(取材:2016年2月 関西ウーマン編集部) |
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック) 記事一覧
-
「愛し愛される活動があるから先生は癒される」伝統ある男子校の興國学園。その3代目校長を務める草島葉子さん
-
「教育は人づくり町づくり。そして私は若作り」41歳で教頭先生になり、現在は大学で教師を育てる善野先生
-
「教師は子どもたちの伴走者」私学カトリックの小学校で長年教師をされ、今年校長に就任された北村さん
-
「心を強くするためには自分自身を大切に思うこと」日本の看護教育に貢献されている江川さん
-
「生活空間を創る側も多様な視点が必要です」生活の中にある課題を研究する「生活科学」の研究者、小伊藤さん
-
「多様化する「家族」に生きる子どもの気持ちに寄り添いたい」子どもの権利を研究する長瀬さん
-
「国産のものを食べたい。私の夢はそこだけ」女性農業者の起業や六次産業を啓蒙する中村さん
-
「有機野菜を買うことで社会が変わる」大学講師をしながらNPOを設立。有機農業の啓蒙活動を続ける中塚さん
-
「研究者で職を得ることは頑張れば報われるとは限らない」流通科学大学で初年次教育を担当される橋本信子先生
-
雇用や労働に関する研究に取組まれている浦坂先生。「計画された偶発性」によってアカデミックの道を歩まれた経緯をお話いただきました。