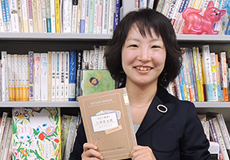HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
![]() 浦坂 純子さん(同志社大学 社会学部教授)
浦坂 純子さん(同志社大学 社会学部教授) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック)
浦坂 純子さん(同志社大学 社会学部教授)

| 浦坂 純子さん 同志社大学 社会学部 産業関係学科教授 大阪府生まれ。大阪市立大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学) 労働市場の流動化を背景に、労働者が生涯にわたって様々な移動を繰り返しつつ持続的にキャリアを形成する過程を、学校、企業、創業、インターバルなどのキャリアステージを拠点に分析し、社会における適材適所の達成を研究している。 浦坂純子研究室 HP:http://www.jurasaka.com/
同志社大学 社会学部 産業関係学科HP:http://ir.doshisha.ac.jp/
 なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか―キャリアにつながる学び方 なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか―キャリアにつながる学び方ちくまプリマー新書/浦坂純子(著) 将来のキャリアを意識した大学の選び方、受験勉強の仕方、大学での学び方とは?就活を有利にするのは留学でも資格でもない!数々のデータから読み解く「大学で何を学ぶか」。⇒amazon |
| 大阪市立大学の経済学部を卒業され、さらに大学院で経済学の博士を取得されましたが、もともと経済学部が第一志望ではなかったそうですね。 |
| 大阪市立大学には行きたかったのですが、第一志望は経済学部ではありませんでした。当時はまだ共通一次試験の終わり頃で、一次でなかなか点が取れず第一志望は諦めざるを得ませんでした。二次でたまたま経済学部を受験して一応合格しましたが、1年間大学に籍を置いたまま1度も大学には行かず、「仮面浪人」となって、再度チャレンジしようと受験勉強をしていました。でもそのセーフティネットを張っての受験勉強というのは、随分と甘えた感じだったんでしょうね。勉強はしてもそこまで自分を追い詰められず、覚悟を決めて経済学部に2年生から戻りました。 |
| 1年間1度も大学に行かずとなると、単位を取り戻すのは大変だったのでは? |
| 1年生の単位はゼロですね。一度担当の先生に呼び出されて、「授業に全く出ていないけど、どうしたんですか?」と聞かれたんです。叱られると思いましたが、受験勉強をしていると話すと、「そうですか。では頑張ってください」と言われて、大学ってこういうところなんだなと思いました(笑)。 大学に戻ってからは、とにかく単位を取らないと留年ですし、第二外国語にドイツ語を取っていたので、外大に来たのかと思うくらい、英語とドイツ語漬けの毎日でした。ドイツ語なんてその1年間でガーッと覚えて、そのあと全部忘れてしまいましたけれど(笑)。 |
 |
| 3年間で卒業すると決めて頑張られましたが、就職は考えておられましたか? |
| それまでは医者になるものだと思っていましたから、経済学部に入ってしまって、この先どうしたらいいんだろうとすごく戸惑いましたね。バタバタと2年生が終わってやっと3年生になると、周りは就職活動を意識し始めるのですが、自分としては単位を取ることで精一杯でしたし、就職活動といっても全くピンとこなかったんです。 当時はバブルの終わり頃でしたから、就職は今よりずっと簡単で、周りは金融業界を中心に早い段階で決まっていきました。経済学部ですから圧倒的に銀行に就職する人が多かったのですが、自分が10年後、銀行で働いている姿が想像できませんでしたし、ダブルスクールをして公認会計士などを目指そうかとも思いましたが、そんな時間もお金もありませんでした。 また、一生懸命勉強したけれど、それで社会に出るということが、ものすごく心もとない感じがあったんですね。資格もありませんし、何の武器も無いような気がして。それで今の勉強の延長線でできることといえば、大学院へ進学することかなと。その段階でもまだ研究者になることは考えていませんでした。 |
| 大学院に行かれてから、アカデミックの道に進もうと思われたのですね。 |
| 周りは研究者を目指している先輩ばかりで影響も受けまして、「大学の先生って、自分もなれるのかな」と思い始めたのは、修士論文を書いていたあたりからですね。 研究のためにいろんなデータを扱っていたので、何時間も図書館の書庫に篭って昔の資料を出してきて、それを手で書き写したり、コツコツと調べたりすることが面白かったというか、手応えを感じていたんでしょうね。自分にはこういうことが合っているのかなと。ドクター(博士課程)に上がった時はもう、そこに向かってがんばろうと思っていました。 その一方で、それはなかなか茨の道だとわかってくるんですね。大学と大学院で、結局10年間大学に在籍しましたので、そのあと就職できませんでした、というのはあってはならないことだと、不安というより恐怖に近いものがありました。とにかく就職したい、チャンスがあれば日本中どこにでも行こうと思っていました。気持ちは貪欲でしたね。 専門外の分野で共同研究のお話をいただいた時も、何かの転換点になるかもしれないとお受けしましたし、博士課程の途中で愛媛の松山大学に専任講師として赴任したり、北海道大学にも客員教員として招いていただいたりしました。基本的にいただいたお話はなるべく受けていこうと思っていました。 |
 |
| 2014年5月に同志社大学コモンズカフェでお話された「計画された偶発性(※1)をものにする」というお話のレポート(※2)がありますが、浦坂先生が大学教授としてアカデミックの道を歩まれてきた経緯も、この「計画された偶発性」を体現されてこられたのですね。
※1)計画された偶発性理論:スタンフォード大学 クランボルツ教授が提案したキャリア論に関する考え方⇒wikipedia
※2)「計画された偶発性をものにする-流されず、逆らわずのキャリアデザイン指南」⇒イベントレポート
|
| そうですね。幼い頃から研究者になりたいとか大学の先生になりたいとか思っていたわけではないので、今自分がこういう立場にいることが信じられないくらいです。もし医学部に合格していたら、今頃は「神の手」と呼ばれる医者になっていたかもしれませんが(笑)。受験に失敗し大きな挫折を味わいましたけれど、そこからいろんなことが起きてきたからこそ、今があると思っています。 それは自分が思い描いていたこととは全然違っていても、振り返ってみると「そういうことだったんだ」と思いますし、決して後悔もありません。やはりキャリアというのはそういう感じで作られていくのかなと、すごく実感するところです。 「計画された偶発性」という理論は、様々な解釈が可能です。「偶発性」と「計画された」は対極の意味を持つ言葉ですが、目標を掲げて一生懸命努力して、その通りにいくこともあれば、全く違うことが起こって、それを受け入れて次に向かうことで、自分の将来に影響を与えるようなこともあります。 でもそれは、自分が何かに一生懸命に立ち向かわなければ出会えません。そういう部分に「計画された」という要素が入ってくることだと考えています。将来に影響を与えるような偶発的なできごとを自分で掴み取っていくという、そんな姿勢がない限り、巡り合えないんじゃないかと思います。 |
| ご著書『なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか-キャリアにつながる学び方-』の中にも、『いろんな悩みも不安もあるけれど、とりあえず目の前のことを一生懸命やりましょう』というメッセージが出てきます。 |
 将来に対する不安に揺れるのは、誰しもあることだと思いますが、それに溺れてしまうと何も手につかなくなります。考えてみれば、昨日から今日で何かが思いきり変わることはあまり無くて、今日の延長線上に明日があるのですから、気持ちの持ちようひとつなんです。 将来に対する不安に揺れるのは、誰しもあることだと思いますが、それに溺れてしまうと何も手につかなくなります。考えてみれば、昨日から今日で何かが思いきり変わることはあまり無くて、今日の延長線上に明日があるのですから、気持ちの持ちようひとつなんです。停滞しているようで落ち着かないときは、今やるべきことをとにかくやる。何か1つでも1ミリでも前に進めたらそれでよしとして自分を励ましていけば、気持ちも落ち着いてきます。 私が大学受験に失敗した時「こんなはずじゃなかった」という気持ちで毎日を過ごすことが一番耐え難いことでした。目標が突然見えなくなって、次は何に向かえばいいんだろうという宙ぶらりんな感じは相当不安です。 そこで、ここに来たことを「必然」にしようと思ったんです。大きな夢は描けなくても、まずは明日のドイツ語、明後日の英語と、目先のことに一生懸命になることで、とことん落ち込まずに済みましたし、自分を支えてこられたと思います。 |
| 研究者の道を歩まれる浦坂先生のロールモデルは? |
| 大阪市立大学名誉教授の竹中恵美子先生が、労働経済論のパイオニアでいらっしゃいますが、ロールモデルというとおこがましく、全くもって憧れの存在ですね。私が学生だった頃、経済学部で唯一の女性の先生で、定年間際の60代でいらっしゃったかと思いますが、とてもお洒落でステキな先生でした。 先生の退任講演で、「向かい風を受けるということは、確かに前に進んでいる証拠。叩けば扉は開かれる」とおっしゃったことが印象に残っています。先生の時代は扉を叩いても開かれなかったけれど、今は叩けば開かれると。当時の私はまだ20代でしたから、そんな扉があるという認識はありませんでしたが、今こうして長く仕事をしているとしみじみ、なるほど、まだ扉はあると感じますね。確かに叩けば開かれるかもしれないし、叩き続ける面白さもあるとも思います。 女性が研究者としてやっていくことが普通ではなかった時代にあって、先生はいろんなご苦労をされたそうですが、何が素晴らしいって、やはり積み重ねの素晴らしさですね。私にとっては北極星のような、そこに向かって行く道しるべのような存在です。 |
 |
| これから社会に出る女子学生をどのように見ておられますか? |
| 今アベノミクスの成長戦略でも「女性の活用」が叫ばれていますが、女子学生が研究テーマを決める際にも、判で押したように「女性の労働」「本当に育児休業は取れるのか」といったテーマが出てきます。つい「またか」と思ってしまうのですが(笑)、そこまで「女性」ということにこだわらなくてもいいんじゃないかとも思うんですね。 「私たち本当に働けるのでしょうか」と不安になるようで、働こうと思えばどこでも働けるのに「ちゃんと福利厚生が整っているところじゃないと心配」とか「転勤は困る」とか言って取り越し苦労をしている。やりたいことがあるなら、まずその視点で会社を選んで、そこでもし制度が整っていないのなら、しっかり働いて自分の存在を認めてもらって、「この人に辞められたら困るから制度を整えよう」というように、会社を変えていくのも面白いんじゃないかと思うんです。 結婚して子どもを産んでもずっと働き続けたいから、そういう会社を選ぶというのも大事な姿勢ですが、結婚するかどうかも、子どもを産むかどうかもわかりませんし、あまり先々まで「女性だから」とがんじがらめになって選択肢を狭めてしまうのは、ちょっと違うかなとも思いますね。 まだまだヘンな野次が飛ぶような厳しい状況はありますが、それでもやれる人は出てきているわけですから、存分にやりたいことをやって、その上で「女性」ということで枠にはめられることがあるのであれば、自分で扉を叩いて壊していこうよと。学生の成績を見ても上位は圧倒的に女子が多いので、能力差なんて考えにくいですし、今の女性にはそれだけの力はあるはずなのに、大学の研究のテーマからして「女性はまだまだだ」ということをやりたがるのは、何とももどかしい気がします。 |
| その感覚はやはり育ってきた環境もありますね。親の価値観も影響しているかと。 |
| ありますね。「私なんかとてもとても」とか「あまり前に出ちゃったらマズイかしら」と無意識に抑制してしまうんでしょうね。育ってきた環境による価値観をゼロにするのは難しいかもしれませんが、可能性やポテンシャルに自分でカギを閉めてしまうようなことはしないで、自分を解き放って欲しいですね。「アナと雪の女王」じゃないですけど(笑)。 |
| ありがとうございました。 |
| (取材:2014年8月 関西ウーマン編集部) |
■関西ウーマンインタビュー(アカデミック) 記事一覧
-
「愛し愛される活動があるから先生は癒される」伝統ある男子校の興國学園。その3代目校長を務める草島葉子さん
-
「教育は人づくり町づくり。そして私は若作り」41歳で教頭先生になり、現在は大学で教師を育てる善野先生
-
「教師は子どもたちの伴走者」私学カトリックの小学校で長年教師をされ、今年校長に就任された北村さん
-
「心を強くするためには自分自身を大切に思うこと」日本の看護教育に貢献されている江川さん
-
「生活空間を創る側も多様な視点が必要です」生活の中にある課題を研究する「生活科学」の研究者、小伊藤さん
-
「多様化する「家族」に生きる子どもの気持ちに寄り添いたい」子どもの権利を研究する長瀬さん
-
「国産のものを食べたい。私の夢はそこだけ」女性農業者の起業や六次産業を啓蒙する中村さん
-
「有機野菜を買うことで社会が変わる」大学講師をしながらNPOを設立。有機農業の啓蒙活動を続ける中塚さん
-
「研究者で職を得ることは頑張れば報われるとは限らない」流通科学大学で初年次教育を担当される橋本信子先生
-
雇用や労働に関する研究に取組まれている浦坂先生。「計画された偶発性」によってアカデミックの道を歩まれた経緯をお話いただきました。