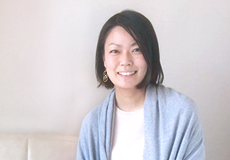HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室)
■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室)
![]() かまい なおみさん(羊毛クリエイター/YAIRA)
かまい なおみさん(羊毛クリエイター/YAIRA) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室)
かまい なおみさん(羊毛クリエイター/YAIRA)

自分の中から湧き上がる、わくわくする気持ちを大切にしたい
かまい なおみさん
羊毛クリエイター/YAIRA
羊毛クリエイター/YAIRA
羊毛クリエイターとして作品を発表するほか、全国各地で教室やワークショップを開講したり、「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA(ヤイラ)」という拠点を構えてイベントを企画・開催したりしている、かまいなおみさん。
創作活動だけではなく、「手を使って自分がわくわくできるものを生み出す楽しさを伝えたい」と教えることにも力を注いでおられます。
「みなさん、『習う』というより『楽しむ』ために来られています」とかまいさんがおっしゃられる通り、教室に参加されている生徒さんは、「こんなのがあったらいいなあ」というイメージから自由に帽子をつくったり、20年前に着ていたコートを羊毛フェルトなどを取り入れながら時代に合ったスタイルに変身させたり。自由にものづくりを楽しんでおられる姿が印象的です。
一人ひとりの「自由にものづくりを楽しむ力」を、どのように引き出しておられるのでしょうか。
創作活動だけではなく、「手を使って自分がわくわくできるものを生み出す楽しさを伝えたい」と教えることにも力を注いでおられます。
「みなさん、『習う』というより『楽しむ』ために来られています」とかまいさんがおっしゃられる通り、教室に参加されている生徒さんは、「こんなのがあったらいいなあ」というイメージから自由に帽子をつくったり、20年前に着ていたコートを羊毛フェルトなどを取り入れながら時代に合ったスタイルに変身させたり。自由にものづくりを楽しんでおられる姿が印象的です。
一人ひとりの「自由にものづくりを楽しむ力」を、どのように引き出しておられるのでしょうか。
手を使ってものづくりする楽しさを伝えたい
かまいさんは「羊毛クリエイター」として創作活動をされています。「羊毛フェルト」を素材として選んだ理由は?
短大卒業後に進学した川島テキスタイルスクール在学中、寮の友だちが持ち帰った羊毛フェルトの帽子が最初の出会いとなりました。
フェルト化するには羊毛を水分と圧力で縮ませるのですが、友だちが持ち帰った帽子はまだまだ縮ませないといけない状態で「ここからどうしたらいいと思う?」と、寮のみんなで「お風呂場で踏む」「洗濯機に入れる」とアイデアを出し合うことに。
作業していくうちにどんどん縮んでいくので、なんておもしろい素材なんだろうと心ひかれ、フェルト作家のジョリー・ジョンソン先生の授業を受けるようになりました。
触って、掴んで、引っ張って。手の中でまるで粘土のように形を変えられるおもしろさと、羊毛の心地よい手触りにほっとする。
これまで絵画や油絵、粘土、糸紡ぎ、染色、織物、布や糸を使うファイバーアートなど、さまざまな表現や技法を学んできましたが、私には羊毛フェルトが一番しっくりきたようです。
フェルト化するには羊毛を水分と圧力で縮ませるのですが、友だちが持ち帰った帽子はまだまだ縮ませないといけない状態で「ここからどうしたらいいと思う?」と、寮のみんなで「お風呂場で踏む」「洗濯機に入れる」とアイデアを出し合うことに。
作業していくうちにどんどん縮んでいくので、なんておもしろい素材なんだろうと心ひかれ、フェルト作家のジョリー・ジョンソン先生の授業を受けるようになりました。
触って、掴んで、引っ張って。手の中でまるで粘土のように形を変えられるおもしろさと、羊毛の心地よい手触りにほっとする。
これまで絵画や油絵、粘土、糸紡ぎ、染色、織物、布や糸を使うファイバーアートなど、さまざまな表現や技法を学んできましたが、私には羊毛フェルトが一番しっくりきたようです。

創作活動だけではなく、講師として教えることにも力を注いでおられますね。
川島テキスタイルスクール時代の体験が、私の活動の原点にあります。
川島テキスタイルスクールに入るまでは「これはこうするもの」「こうしなければならない」という枠に囚われている自分でしたが、そんな枠から飛び出し、自由にものづくりを楽しむ力を引き出してもらいました。
さまざまな発想を持った仲間や自由な制作方法を後押ししてくださる先生方でしたので、新たな自分の世界が広がったんです。
最も心に響いてきたのは、初代理事長がこだわっていた「手の復権」というメッセージ。
「手と脳はつながっていて、『第二の脳』と言われるくらい大切な手。手を使うことで、脳を活性化させられる。だからこそ、楽しくなること、笑顔になれること、わくわくする気持ちを増やすことに、手を使って取り組もう」という考えで、手を使うことが少なくなっている現代で、私もその大切さを伝えていきたいと思ったんです。
卒業後は兵庫県立姫路工業高等学校デザイン科に実習助手として就職しました。生徒に向けて羊毛フェルトワークを行っていると、何をしたらいいのかわからないという子たちが楽しんで取り組んでくれているのを見て、羊毛にはセラピー的な効果があるんじゃないか、と。
もっと幅広い世代の人たちにも体験してほしいと、2002年に勤めた高校を退職し、自宅で教室を始めました。
川島テキスタイルスクールに入るまでは「これはこうするもの」「こうしなければならない」という枠に囚われている自分でしたが、そんな枠から飛び出し、自由にものづくりを楽しむ力を引き出してもらいました。
さまざまな発想を持った仲間や自由な制作方法を後押ししてくださる先生方でしたので、新たな自分の世界が広がったんです。
最も心に響いてきたのは、初代理事長がこだわっていた「手の復権」というメッセージ。
「手と脳はつながっていて、『第二の脳』と言われるくらい大切な手。手を使うことで、脳を活性化させられる。だからこそ、楽しくなること、笑顔になれること、わくわくする気持ちを増やすことに、手を使って取り組もう」という考えで、手を使うことが少なくなっている現代で、私もその大切さを伝えていきたいと思ったんです。
卒業後は兵庫県立姫路工業高等学校デザイン科に実習助手として就職しました。生徒に向けて羊毛フェルトワークを行っていると、何をしたらいいのかわからないという子たちが楽しんで取り組んでくれているのを見て、羊毛にはセラピー的な効果があるんじゃないか、と。
もっと幅広い世代の人たちにも体験してほしいと、2002年に勤めた高校を退職し、自宅で教室を始めました。

一人ひとりのわくわくする気持ちに寄り添って
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
「手の復権」という、手を使って自分がわくわくできるものを生み出す楽しさを伝えたいと思っているのですが、初めて聞いた人は「えっ?手の復権?」となります。
この数年は特にウェブサイトのリニューアルを検討していることもあって、より多くの人に知ってもらうには言葉で説明することも大切と改めて考えているところですが、これまでは「体感してもらうことが一番の近道」と取り組んできました。
活動を始めてまもなくの頃は、羊毛フェルトとはどういうものかを知ってもらうために、個展やグループ展など作品を見てもらえる機会を多くつくりました。
2002年には自宅で教室を始め、2006年に「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」をオープン。教室やワークショップ、イベントなどを通して、羊毛フェルトを広げる活動に努めています。
この数年は特にウェブサイトのリニューアルを検討していることもあって、より多くの人に知ってもらうには言葉で説明することも大切と改めて考えているところですが、これまでは「体感してもらうことが一番の近道」と取り組んできました。
活動を始めてまもなくの頃は、羊毛フェルトとはどういうものかを知ってもらうために、個展やグループ展など作品を見てもらえる機会を多くつくりました。
2002年には自宅で教室を始め、2006年に「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」をオープン。教室やワークショップ、イベントなどを通して、羊毛フェルトを広げる活動に努めています。
楽しさを体感してもらうために、どんな工夫をされてきましたか?
とにかく羊毛に触れてもらう。触りながら「引っ張っても破れない」「手の中で自在に形を変えられる」など感じてもらい、初回はお花のコサージュをつくってもらいます。
つくる過程では「ああして」「こうして」と言わず、「こうすると、こうなりますよ」「こんな形にもできますよ」といろいろな方法や可能性を見せて、最終的に「どうしたいか」は本人に委ねます。
最初は「こうしてもいいのかなあ」と恐る恐るしていたのが、回を重ねるうちに「これは必要ないです」「こんな形にできますか」「色を混ぜたいんです」といった本人の意思が出始めて、「こんなことも、あんなこともできるんだ」と思ってもらえるようになったら、「あんなふうにしてみたい」「次はこんなものをつくりたい」というアイデアや意欲が湧いてくるようになるんです。
私からも「こうしたら、どうですか?」「こんなこともできますよ」「あんなこともできますよ」とアイデアを次々と(笑)。
20年以上前に購入した思い出のコートを変身させるために、袖や襟を大胆にカットして、袖の飾りをポケットに使ったり、虫食い部分はレースや羊毛フェルトで飾り付けたり。
「アポロチョコみたいな感じで」というイメージから、羊毛フェルトで頭頂部分がぴゅっと出た帽子をつくったり。
生徒さん自身の中から湧き上がる、わくわくする気持ちを何よりも大切にしたいから、一人ひとり、取り組む内容が異なるんです。
バッグにポーチ、ルームシューズ、ストール、洋服など、つくりたいものを自由に。ベースは羊毛フェルトですが、織り、編み、染め、ビーズ、レースといった異素材を多く揃え、さまざまな手法で制作してもらっています。
つくる過程では「ああして」「こうして」と言わず、「こうすると、こうなりますよ」「こんな形にもできますよ」といろいろな方法や可能性を見せて、最終的に「どうしたいか」は本人に委ねます。
最初は「こうしてもいいのかなあ」と恐る恐るしていたのが、回を重ねるうちに「これは必要ないです」「こんな形にできますか」「色を混ぜたいんです」といった本人の意思が出始めて、「こんなことも、あんなこともできるんだ」と思ってもらえるようになったら、「あんなふうにしてみたい」「次はこんなものをつくりたい」というアイデアや意欲が湧いてくるようになるんです。
私からも「こうしたら、どうですか?」「こんなこともできますよ」「あんなこともできますよ」とアイデアを次々と(笑)。
20年以上前に購入した思い出のコートを変身させるために、袖や襟を大胆にカットして、袖の飾りをポケットに使ったり、虫食い部分はレースや羊毛フェルトで飾り付けたり。
「アポロチョコみたいな感じで」というイメージから、羊毛フェルトで頭頂部分がぴゅっと出た帽子をつくったり。
生徒さん自身の中から湧き上がる、わくわくする気持ちを何よりも大切にしたいから、一人ひとり、取り組む内容が異なるんです。
バッグにポーチ、ルームシューズ、ストール、洋服など、つくりたいものを自由に。ベースは羊毛フェルトですが、織り、編み、染め、ビーズ、レースといった異素材を多く揃え、さまざまな手法で制作してもらっています。

「楽しくてわくわくできること」を提案し続けるために
活動を始めて26年が経たれますね。お仕事をされる中で、いつも心にある「想い」は何ですか?
「手を使って自分がわくわくできるものを生み出す楽しさを伝えたい」というのが活動を始めた当初からの変わらぬ想いですが、改めて「私がしたいのはこういうことなんだ」と思った出来事があります。
「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」で開催した音楽イベントにたまたま来ていた方が「手芸をしたことがないんですが、つくってみたいんです」とおっしゃられたので、羊毛フェルトワークでお花のコサージュづくりを体験してもらいました。
「まさか自分がつくれるなんて思わなかった」とおっしゃられ、そのコサージュを身に付けて出かけたら「素敵ね」と声をかけられるようになり、「次は何をつくろう?」とつくる楽しみを知ってもらうことができました。
ご家族の介護をされる日々の中で、YAIRAの教室を楽しみにしてくれていて、ご家族からも「今日は教室の日だね」とわかってしまうほど、日常がうきうきし始めたと話してくれました。
彼女のように、日常の中に楽しくてわくわくできることがあると、自然と笑顔になれて、ご自身だけではなく、ご家族やお友だちなど周囲に伝わる。そんな楽しくてわくわくする気持ちが、循環していくといいなあと思っているんです。
「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」で開催した音楽イベントにたまたま来ていた方が「手芸をしたことがないんですが、つくってみたいんです」とおっしゃられたので、羊毛フェルトワークでお花のコサージュづくりを体験してもらいました。
「まさか自分がつくれるなんて思わなかった」とおっしゃられ、そのコサージュを身に付けて出かけたら「素敵ね」と声をかけられるようになり、「次は何をつくろう?」とつくる楽しみを知ってもらうことができました。
ご家族の介護をされる日々の中で、YAIRAの教室を楽しみにしてくれていて、ご家族からも「今日は教室の日だね」とわかってしまうほど、日常がうきうきし始めたと話してくれました。
彼女のように、日常の中に楽しくてわくわくできることがあると、自然と笑顔になれて、ご自身だけではなく、ご家族やお友だちなど周囲に伝わる。そんな楽しくてわくわくする気持ちが、循環していくといいなあと思っているんです。

近い将来、実現したいことを教えてください。
以前は「今、幸せですか?何が幸せですか?」と質問されたら、パッと「今やりたいことをできていることが幸せ」と答えられていたんです。
それが50歳を過ぎて、いろいろなことに整理がつき、自分が実現したいことを見据えて進んでいくことで、同じ想いの人が自然と集まってきました。
「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」の「ヤイラ」とはトルコ語で「春に羊を放牧する時」の言葉で、いろんな人やものが集まり、楽しく遊ぶ気持ちが育ち、ここから自由に広がっていけるスペースでありたいという想いを込めた大切な場所です。
これまで、テキスタイル関係を中心に出会った作家さんや生徒さんなどゆかりのある人たちにスペースを活用してもらったり、ここに集うみんながわくわくできるイベントを企画・開催したりしてきましたが、この場をもっと活かしていきたいと思っています。
活動を始めて26年。色彩研究をしたり、体と心を整える施術のインストラクター資格を取得したりしたことで、さらなる人のつながりができ、YAIRAの世界も広がりました。
これからはさらに、一人ひとりと向き合ったオーダーメイドレッスンや幸せなライフスタイルの提案など、その人の中にある「わくわく」を引き出すお手伝いをしていきたいです。
それが50歳を過ぎて、いろいろなことに整理がつき、自分が実現したいことを見据えて進んでいくことで、同じ想いの人が自然と集まってきました。
「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」の「ヤイラ」とはトルコ語で「春に羊を放牧する時」の言葉で、いろんな人やものが集まり、楽しく遊ぶ気持ちが育ち、ここから自由に広がっていけるスペースでありたいという想いを込めた大切な場所です。
これまで、テキスタイル関係を中心に出会った作家さんや生徒さんなどゆかりのある人たちにスペースを活用してもらったり、ここに集うみんながわくわくできるイベントを企画・開催したりしてきましたが、この場をもっと活かしていきたいと思っています。
活動を始めて26年。色彩研究をしたり、体と心を整える施術のインストラクター資格を取得したりしたことで、さらなる人のつながりができ、YAIRAの世界も広がりました。
これからはさらに、一人ひとりと向き合ったオーダーメイドレッスンや幸せなライフスタイルの提案など、その人の中にある「わくわく」を引き出すお手伝いをしていきたいです。

かまい なおみさん
小学生の時に恩師のすすめで地元の写生大会に参加したのを機に、画家に絵画等を習い始める。県立高校のデザイン科、嵯峨美術短期大学染織科を経て、1987年に川島テキスタイルスクール専攻科に入学。ジョリー・ジョンソン氏に羊毛フェルトの指導を受け、作品制作を始める。1991年に同スクールを卒業後、兵庫県立姫路工業高等学校デザイン科に就職。個展開催やグループ展参加、多くのクラフト展などにも出品する。2002年に退職し、自宅で教室を始め、全国各地で講習会や出張ワークショップなども開催。2006年には「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」をオープン。羊毛クリエイターとして創作活動に励むとともに、「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」を中心に各地で教室やワークショップを開講するほか、門脇織物株式会社のブランド「ASABAN(あさばん)」とコラボした作品づくり、ホスピタルアートとして病院に作品を提案・展示する「NPOアーツプロジェクト」参加など幅広く活動している。

兵庫県姫路市御国野町深志野480-1-1
FB: yaira.hituji
Instagram: naomikamai
(取材:2018年9月)
かまいさんのお仕事の根本にあるのは、「手を使って自分がわくわくできるものを生み出す楽しさを伝えたい」という想い。その想いを実現する方法として、作品づくり、ご自身の教室運営、「ハンドメイドギャラリーカフェYAIRA」運営、イベントの企画・開催を展開されています。
お話をうかがっていると、さまざまなことを展開することで、より多くの人たちに興味を持ってもらう入口が増え、そのさまざまな接点からつながった人たち同士が出会い、つながり、さらなる交流や循環を生むきっかけになっているんだと思いました。
また、かまいさんご自身にとっても、「次はこんなことをやってみよう」「こんなふうにしてみよう」など目の前の目標ができて、イベントの企画に活したり、施術や色研究などを学ぶきっかけになったりされているのだとも。
とはいえ、いくつも展開する大変さはあるものですが、その点については「私はいろんなものを同時進行するタイプらしくて、そのほうが合っているんです」とお話になられていました。
HP: 『えんを描く』
お話をうかがっていると、さまざまなことを展開することで、より多くの人たちに興味を持ってもらう入口が増え、そのさまざまな接点からつながった人たち同士が出会い、つながり、さらなる交流や循環を生むきっかけになっているんだと思いました。
また、かまいさんご自身にとっても、「次はこんなことをやってみよう」「こんなふうにしてみよう」など目の前の目標ができて、イベントの企画に活したり、施術や色研究などを学ぶきっかけになったりされているのだとも。
とはいえ、いくつも展開する大変さはあるものですが、その点については「私はいろんなものを同時進行するタイプらしくて、そのほうが合っているんです」とお話になられていました。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室) 記事一覧
-
「手を使ってものづくりする楽しさを伝えたい」羊毛フェルトに出会い、「手の復権」伝えるかまいさん
-
「キモノを着ると楽しいことがいっぱい!」アンティーク着物とスタイリングでキモノの楽しさを伝えるルミさん
-
「サロネーゼ」は人と人とが関わり合う仕事サロネーゼを目指す方をサポートをする東城さん
-
「「世界で一つのスタジオ」を創りたい」バレエを通し自分の居場所を見つけられた上杉さん
-
「おうちごはん」で家族という最小単位から幸せになる大山崎で生活雑貨と暮らしの教室を主宰する森さん
-
「お茶を通して自分を知る楽しみ」茶道裏千家の講師をされながら、紅茶やハーブティなどをブレンドするお茶会コンシェルジュを主宰する晴子さん
-
「家族にパンを作る。その課程を大切にして欲しい」子ども達にパンを焼きながら自宅教室を始めて10年。京都町屋でパン教室を開く由香里さん
-
英国のル・コルドンブルーで学び、帰国後は人気パティスリー店で実務経験箕面でお菓子教室を開く塩谷さん
-
「好きな仕事を諦めて選んだ道。普通の努力じゃ普通にしかなれない」アナウンサーからパティシエに転身