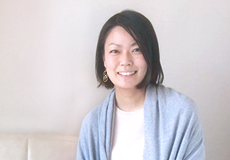HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室)
■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室)
![]() 山口 晴子さん(京都お茶会コンシェルジュ)
山口 晴子さん(京都お茶会コンシェルジュ) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室)
山口 晴子さん(京都お茶会コンシェルジュ)

| 山口 晴子さん 「心で感じて味わう お茶を」のコンセプトでお茶会をひらく京都お茶会コンシェルジュ。 茶道裏千家専任講師 /茶名「宗晴」  京都お茶会コンシェルジュ 京都お茶会コンシェルジュ〒603−8051 京都府京都市北区上賀茂榊田町30−1 HP:http://www.kyoto-ochakai.jp/ |
| 茶道を習われたのは花嫁修業ですか? |
| 全然違うんですよ(笑)高校時代の友人の叔母さんがお茶の先生をされていて、一緒に習いに行かない?と誘われたことがきっかけです。家族の誰もしていませんし、特に興味があったわけでは無いんですが、先生と気が合ったというのもありますし、毎週のお菓子が楽しみで(笑)その先生に習ってもう30年になります。 |
| 山口さんは宗名(茶名)「宗晴」さんとしてもご活躍されていますが、宗名をいただくまで続けるのは難しくありませんでしたか? |
 お茶は楽しいので長く続けてきましたが、結婚後、双子の育児で精神的にも体力的にもしんどかったんでしょうね。宗名(茶名)をいただいたら、それを区切りに辞めようと思っていたんです。 お茶は楽しいので長く続けてきましたが、結婚後、双子の育児で精神的にも体力的にもしんどかったんでしょうね。宗名(茶名)をいただいたら、それを区切りに辞めようと思っていたんです。宗名をいただくと宗名披露のお茶会をするのですが、子どもたちに「そういうもんだったよ」と言うのと、「こういうもんだ」と見せるのとでは、記憶の残り方が違いますし、自分でもちゃんとやったという満足感も欲しかったので、御所を借りて宗名披露をしました。 教えていた子どもたちが振袖を着てお運びをしてくれて、やっぱり晴れ舞台ですから目に艶やかで、私だけじゃなく、子どもたちのご両親もとても喜んでいただけました。写真に残って人に見せるまでを考えると、とても思い出として残るので良かったのですが、その後「私これで辞めます」とは言えなくなって(笑)結局皆さんに背中を押された形で続けることになったんです。 |
| 山口さんは、栄養士でもありカイロプラクティックの資格もお持ちなんですね。 |
| 大学で栄養士の資格を取りましたが、27歳の頃はパソコンのインストラクターをしていまして、生徒の大学生の子たちの「痩せたい」「便秘」「肌がぶつぶつ」といった悩みを聞いているうちに、食べ物などのアドバイスをすることが楽しかったんですね。ちょうど一緒に働いている先生が腰が痛くてカイロに通っていて、カイロの学校があると教えてもらって、大阪の専門学校に3年間通いました。 |
| ずっと健康に興味があったのですか。 |
| 栄養士を取った学生時代は全く意識はありませんでしたが、カイロの学校で東洋医学的なことを学ぶことで、人間は自分で治す力を持っていて、気持ちが落ち込んでも自分で起き上がろうとする強さがあるから、その能力を目覚めさせるお手伝いをすると、気分が良くなるということを知りました。 そうした精神的なもの、目に見えない五感といったことが、茶道と絡まってくるんですね。そこでカイロの考え方と茶道を合体させたいと思って、最初はハーブティと茶道を並行していって、最後に残ったのが「お茶」というキーワードだったんです。 |
 |
| 「お茶会コンシェルジュ」とは何ですか? |
| 抹茶だけでなく、紅茶、コーヒー、中国茶、日本茶、ハーブティーなど、身近なお茶をその人、その日の体調や気分に合わせてブレンドできる方を育てる養成講座です。 茶道は「道」なのできっちりした型がありますが、この異空間の茶室に座ってお茶を出すのと、台所で子どもに抹茶ミルクを出すのとでは、何が違うのかと考えてみると、お茶を媒体にして相手と喋るというのは同じことなんですよね。感じ方の違いはあっても、どちらも何かの会話をしながら飲んでいるんです。  うちは台所にも茶せんがあるので、抹茶を茶せんで振ってお湯で溶かして、ミルクを混ぜて茶せんで混ぜて「はいっ」って出すんです。普通はグリーンティの粉末を溶かすのかもしれませんが、抹茶を使うことで、子どもたちに文化も見せられますね。 うちは台所にも茶せんがあるので、抹茶を茶せんで振ってお湯で溶かして、ミルクを混ぜて茶せんで混ぜて「はいっ」って出すんです。普通はグリーンティの粉末を溶かすのかもしれませんが、抹茶を使うことで、子どもたちに文化も見せられますね。今は急須を知らない子どもたちも増えていますし、ペットボトルのお茶を飲まれますから、まるでコーラと同じ(笑)お茶もハーブも全部自然のものからできているということを、家庭の中で見せるお母さんたちが増えたら、家庭の端々に日本文化が残ると思うんです。 ほうじ茶とカモミールを混ぜると美味しいですし、煎茶とペパーミントも冷やして飲むと爽やかで美味しい。ハーブ同士はよく混ぜるのに、どうして煎茶やほうじ茶と混ぜると、「えっ」と思ってしまうのか。茶葉は茶葉なのに固定観念があるんですね。 インフルエンザが流行っていたら、殺菌効果の高いエキナセアを入れておけば予防になるし、風邪気味だったらカモミールを入れてみようかとか、眠りたい人にはレモンバームを入れようかとか。紅花を入れると黄色いスープになって美味しいし、ご飯と炒めたらサフラワーライスになって、カレーをかけたら冷え症にも効きます。ハーブもなぜお茶でしか飲まないのかという話で、料理人が使うハーブと、茶人が使う茶葉は別という括りになっているけれど一緒なんですよ。  海外には「ティーコンシェルジュ」という執事のような仕事をする人がいて、気分や体調に合わせた飲み物をアドバイスする職業がありますが、そんな人を雇うことができなくても、お母さんならできますよね。 海外には「ティーコンシェルジュ」という執事のような仕事をする人がいて、気分や体調に合わせた飲み物をアドバイスする職業がありますが、そんな人を雇うことができなくても、お母さんならできますよね。お母さんは毎日台所にいて、「今日の体調はどう?」って子どもの気持ちと体の調子を考えたものを食べさせたり飲ませたりできますから。食べ物にも飲み物にもカテゴリ関係なく使えて、それを家庭レベルで「あなたに合いますよ」とアドバイスできて、具体的に作れる方が増えて欲しいですね。 |
| 茶道という日本文化にも触れながら、自分なりに「お茶」をアレンジできるのは面白いですね。 |
| 茶道は元々「見立て」なので、お棗(なつめ)が無ければキャンディポットに入れたらいいし、お茶碗がなければご飯茶碗でもいいし、お水差しはワインクーラーでもいいんです。その雰囲気に合うものがあればすりかえて楽しまれたら良いと思います。「今日のお茶は美味しかった」というだけじゃなくて、その雰囲気と共に、「楽しかった。来て良かった」という経験することが大事なんでしょうね。 うちの生徒さんも、お点前はせずに「お客さん」にある練習だけに来られる方もいます。お茶室の入り方、お茶のいただき方、お菓子の食べ方を、格式あるお茶会に行くと緊張して味も何もわからないので、堂々とその場を楽しめるようになりたいと仰るんですね。また季節のことや京都の行事のしきたりを知りたいという方もいらっしゃって、皆さん求めるものは違いますね。 |
 |
| 気軽に楽しめるということは、敷居が低いということですか。 |
| 「気軽に」ということが私のスタンスですが、やはり「格」にステイタスを感じておられる方が多いので、あまり敷居が下がりすぎて何でもいいとなったらいけませんから、できる時にはちゃんとできる人になってもらわないといけない。なので幅を持たせてTPOに合わせるくらいになると楽しめるんじゃないかと思います。 台所で立ちながらであっても、「あの人は知らないな」という目で見られるのと、「知っててやってはるねんな」と思われるのとでは全く違います。お盆一つ置いてその中ですれば、茶道を心得てはる人やなと分かりますし、道具の置き方にしても、取りやすいように合理的になっていますから、きっとそこが「道」と言われるところなんでしょうね。やはりそこに沿っておかないと、ただの「型無し」になってしまいますから。 |
| 今後のどのような展望を考えていますか |
| お庭に何種類かのハーブがあって、それを自分でチョイスしてお茶にするのですが、どんな理由で採ってきたとしてもその人の弱点が浮かんでくるんです。無意識で選んでもお茶に選ばれるというか。そういうことが何十回とあると、これは偶然じゃないなと思うんです。 人間の潜在意識で必要なものが分かっているから、自分で選んでいるのかもしれないし、自然に選ばれているのかもしれない。採ってきた葉が何かによって自分をみつけ出していく。自然と人が近くなる空間というか、自然も茶道も巻き込んで、そこでお茶ができるサロンをすることが夢ですね。なんか魔女の館みたいになりそうですが(笑) |
| ありがとうございました。 |
| (取材:2014年9月 関西ウーマン編集部) |
■関西ウーマンインタビュー(レッスン教室) 記事一覧
-
「手を使ってものづくりする楽しさを伝えたい」羊毛フェルトに出会い、「手の復権」伝えるかまいさん
-
「キモノを着ると楽しいことがいっぱい!」アンティーク着物とスタイリングでキモノの楽しさを伝えるルミさん
-
「サロネーゼ」は人と人とが関わり合う仕事サロネーゼを目指す方をサポートをする東城さん
-
「「世界で一つのスタジオ」を創りたい」バレエを通し自分の居場所を見つけられた上杉さん
-
「おうちごはん」で家族という最小単位から幸せになる大山崎で生活雑貨と暮らしの教室を主宰する森さん
-
「お茶を通して自分を知る楽しみ」茶道裏千家の講師をされながら、紅茶やハーブティなどをブレンドするお茶会コンシェルジュを主宰する晴子さん
-
「家族にパンを作る。その課程を大切にして欲しい」子ども達にパンを焼きながら自宅教室を始めて10年。京都町屋でパン教室を開く由香里さん
-
英国のル・コルドンブルーで学び、帰国後は人気パティスリー店で実務経験箕面でお菓子教室を開く塩谷さん
-
「好きな仕事を諦めて選んだ道。普通の努力じゃ普通にしかなれない」アナウンサーからパティシエに転身