HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)
■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)
![]() 安喜 万佐子さん(美術家)
安喜 万佐子さん(美術家) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術)
安喜 万佐子さん(美術家)

| 安喜 万佐子さん(美術家)
京都精華大学芸術学部大学院修了後、天然鉱物や顔料を使ったテンペラ等、近代以前の手法を現代美術に持ち込んだ大判絵画制作を中心に、環境や自然、社会と人間の身体や意識、記憶の関わりを浮かびあがらせる作品を国内外で発表し続ける。galerie16(京都)、BASE GALLERY(東京)、Art Complex Center(東京)等での個展の他、英国・米国・韓国・ロシアなどでも発表。近年は異分野アーティストや研究者とのコラボレーションワークも展開。 帝塚山大学、京都精華大学など、非常勤講師として教育の現場にも関わる。2015年文化庁新進芸術家海外派遣作家として渡米他、英国エンジンバラ芸術大学アーティストインレジデンスや、米国アーモスト大学ゲストアーティスト等を含む海外経験も多数。 HP:http://www1.kcn.ne.jp/~yasuki/ FB:masako.yasuki |
| 安喜万佐子さんの作品は、『絵について考える絵である』といわれるように、見る側にさまざまな想起や問いを投げかけます。思春期に感じた「生きづらさ」から、絵を描くことで自身の世界を見つけ、独特の手法で「風景」を描いてこられました。安喜さんの想う「風景」とは何か。なぜ描き続けるのか。また、その壁は何かを伺いました。 |
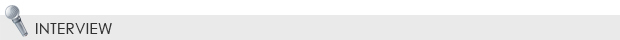
| ある種の「生きづらさ」から見つけた自分の「視点」 |
| 絵を描くことに興味を持たれたのはいつですか? |
| 高校に入る頃までは、芸術系の大学に進学して、今日のような仕事をしている自分は全く想像していませんでした。絵を描いたり、ものを作ることは嫌いではありませんでしたが、ちょっと得意なことの一つ、くらいに捉えていたと思います。 小学生の頃、父の仕事の関係で海外に行き来していた経験からか、中学高校になると少しずつ「生きづらさ」を感じるようになったんです。日本の学校はルールもきっちりしていますし、ものを考えるパターンが皆同じ。「考えさせてもらえない」ように感じてしまったのです。1つの視点だけで生きていることがつまらなく、何か欠落しているような感じがしていて、「日常」ということになっている世界と違う視座を持って生きていたい、と考えるようになりました。 「絵でも描けば、世の中のことがもっとよく見えてくるかな」と、魔が差したように絵を描き始めましたが、作品でも作っていないと生き難い性質だっただけかもしれません。やりだすと何でも徹底的にやっちゃう性格なので、気づいたら美術大学を受験していました。 |
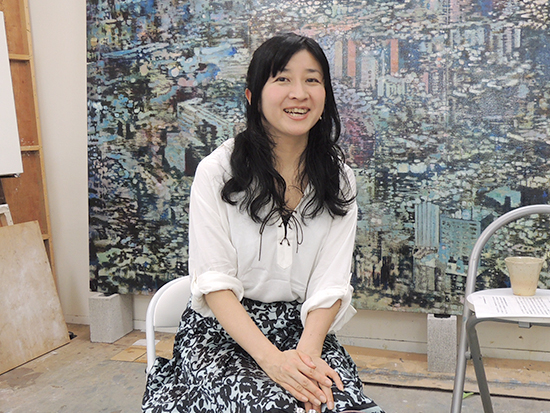 |
| 安喜さんの絵は「風景」が特徴ですが、そこに至ったきっかけとは? |
| 美大に入ってみると、周りは皆すごい絵を描いている人ばかり。もともと絵が大好き少女ではありませんでしたから、今度は、「私、美大向きじゃなかったかも」と悩んでしまいました。一人で海外に行って考えてみたり、やっぱり語学とか英文科の方向へ行ったほうが良かったかなと思ったり。 そうして悩んでいた頃、通学で通っていた下鴨神社の糺ノ森(ただすのもり)で、強い光にさらされた木と、その影を強烈に映す地面を見て、なぜか立ち止まったんです。木は自分が生まれるずっと前から生きていて、そこに太陽が照り付け、その影が地面に映し出されている。普段当たり前に思っているけれど、その時その時間じゃないと起こらない現象がそこにある、ということに、何か尊いもの、本質的なものがあるような気がして、ものを「見る」ことの不思議をすごく感じたんです。 ああそうか、自分が絵に求めたことってこういうことだったかもしれないと、大学に入って初めて、自ら「描いてみたい」と思いました。ちょっと描きだすとすごく描くようになって、そうなると他の人よりスタートが遅かったものですから、時間が足りず、また親を説得して大学院に行くことを許してもらいました。 |
| それが原点なんですね。その感覚は今も脈々と続いているのですか? |
| そうですね。それからそういう人生になるんですけど、どこに行ってもその感覚に出会いに行っている気がします。世界中のいろんな国で、街や森、大地を描きに行きますが、難しいところを描けば描くほど、その感覚は強固に存在します。 例えば、知らない場所、東西南北も分からないようなところに放り出されると、人間はすごく受け身になりますね。不安を感じたり、身体の危機をも感じてしまったり。その中では、普段の自分を中心とする「ものの考え方」や「視点」を捨てざるを得ない状況に追い込まれてしまう。そんな自分の意識と無関係になる場所から、見えてくるものってあるんじゃないかなと考えています。 大学院2年の時に初個展をさせていただいて作家活動を始めましたが、仕事の深度と広がり、とりまく環境は20年の間に変わっても、絵と自分の根本の関係は、びっくりするほど変わっていないですね。 |
 |
| 「画家」としての「視点」 |
| 絵を描くことが仕事になると「売れる作品」を意識しませんか? |
| 20代の頃は、あまりそういう意識は無くて、「売りたくないんです」って平気で言っていましたから(笑)、画廊さんにはご迷惑をおかけしていたに違いないのですが、「先への未知数」というところである程度許してもらえていたように思います。でも画家として20年やっていると、「売れる作品」問題は当然出てきます。それを意識し始めたのは30代前半でしょうか。展覧会の度に、自分の中で重要な問題になってきました。 とはいえ「売れる絵」というのが何なのか、私には未だ分かりません。でも、「売れる」というベクトルではなく、「描かなければいけない」と思う絵を描くこと。それがあって、それをどうすればきちんと社会にお返しできるか、つまり、経済の中にも存在させていけるか、です。それを意識していなければ、本当に描きたい絵も描けなくなりますし、発信にもならないと考えています。 画廊さんは、展覧会ひとつ開催するにも、運営費だけでなくスタッフや広告宣伝の費用もかかっています。そこに作品を出させていただいているのですから、損をさせてしまっては申し訳ないですし、一緒に仕事をしようと言ってくださる方たちには絶対に迷惑をかけたくない。その気持ちが結局仕事に繋がっているんだと思います。一生懸命作品を社会と繋ごうとしてくださっている画廊や関係の方々との打ち合わせは大切しようと思っていますし、実際、楽しいものです。描かせていただくだけじゃなく、それも仕事だと思っています。 |
| 安喜さんは大学でも教えておられますが、芸術で身をたてる難しさをどう伝えていますか? |
| 美大生や若い方にはよく、「自分のメディアを愛しすぎない方がいいのでは?」とお話ししています。自分のメディアが「絵」であってとしても、絵ばっかり一生懸命描いていていれば作家になれるかといえばなれません。どんな表現もツールにすぎないのであって、そこに執着しすぎると、何のためにやっているのか分からなくなったり、壁を越えて行けなくなったりするんじゃないかと思います。 相対化して捉えられないと、人の評価で一喜一憂してしまい、ちょっと良い評価が得られないとすぐに「私はもうだめ」と思ってしまう。それを使って何がしたいのか、作品を作ることを通じて自分がどうありたいか。そこが美術家にとって本当に大事なことだと伝えています。 |
 |
| 「風景」と「人」との関係を考え続ける |
| 描いている時は、どんなことを考えていますか? |
| 街の絵を描くときに一番最初にすることが、その街の地面をフロッタージュしてまわることなんです。東京では「ガン無視」されますけど(笑)、海外ではすごく話かけられるんですね。大阪でも皆好奇心が強いのでよく話かけられますが(笑)。地面に這いつくばってフロッタージュ(※1)をしていると、人が集まってきて、「あの木はずっとあそこにあるんだよ」って昔話を聞かせてくれたり、おじいさんがその街の戦前の写真をわざわざ持ってきて見せてくれたり。そうするといろんな人の目線や記憶が作品に入り込んでくるんです。 アトリエで描いている時、点を一つ一つ打ちながら、「あのおばあちゃん、こんなこと言ってはったな」とか、「あの人の話はおもしろかったな」とか、気が付けば誰かの目線で見ていたり、その人の視点が乗り移ってしまったり、自分と他者が分からなくなっている気がします。違う国、違う文化、年齢も違えば、記憶も気持ちも違う。そういう他人の目線に一瞬にでもなれる。そんな「風景」と「ヒト」との関係をずっと考えています。 |
| (※1)フロッタージュ:表面がでこぼこした物の上に紙を置き、 描画材でこするように描くことで、形状を写し取る技法 |
| 安喜さんにとっての「壁」とは何でしょう |
| ひとつひとつの作品の制作中に必ず「壁」はあります。「壁」があるのは当然で、乗り越えることで、自分のものの見方が解体されている。それが作品を作ることのおもしろさでもあります。ただ、制作の中で気をつけようと思っていることは、「絵になってしまうことに流されない」ことでしょうか。 取材の中で出会ったことは、必ずしもドラマチックであったり、きれいな絵であることとイコールではありません。そこを少し疲れていたりすると、うっかり「良い絵」にしようとしてしまうことがあります。私はテンペラ(※2)を使っていますが、テンペラは油のように伸びないので「点」でしか描けません。サーッときれいな色になってしまうことを避けるための工夫の一つでもあるんです。絵として美しくありたい。でも「きれい」とはまた違うことだと考えています。 |
| (※2)テンペラ:乳化作用を持つ物質を固着材として利用する絵具。 代表的な技法に卵テンペラがあり、西洋絵画で広く使われてきた。 |
 |
| 「縦の時間」と「横の時間」それぞれの出会い。 |
| 今関心を持っておられることは何ですか? |
| これまで作品を作ることで、さまざまな国の人たちや文化と出会う楽しさを実感してきました。これからも国際展を初め、海外での仕事もどんどん増やして行きたいと考えていますが、これを「横の時間との出会い」だとすると、最近とりわけ関心があるのは「縦の時間との出会い」です。 古代の人たちが、私たちの想像を越えた理由で作ったもの、中世の人たちが、今の暮らしと全く違う時間感覚の中で描いたもの。そういう違う時代に描かれた作品とコラボレーションして、現代にリンクしていくおもしろさを感じています。 テンペラというヨーロッパの古典的な手法で描いていると、中世の人たちの気持ちはこうだったのかなと想像したり、日本の伝統的な顔料で描きながら、蛍光灯の無い時代、行灯の光で、冬の京都はすぐに日が暮れてしまうのに、どうやって描いていたんだろうとか、いろんなことを考えます。 100年200年経って、全然違う常識で生きている人たちが、なにかのはずみで私の作品に出会った時、どういうふうに思うんだろう、何を感じるだろうと、未来の時間への意識にも関心を持っています。 |
| この先も、描くテーマやスタイルは変わらないですか? |
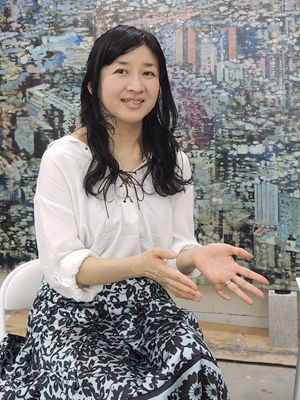 よほどのことが無い限り変わらないと思います。「風景」をずっとテーマにしてきましたが、「風景」というのは、環境問題や自然問題、そして社会の問題、最終的には人間の問題になってきます。 よほどのことが無い限り変わらないと思います。「風景」をずっとテーマにしてきましたが、「風景」というのは、環境問題や自然問題、そして社会の問題、最終的には人間の問題になってきます。テーマとしてやることが多すぎて、キリがなく疑問ややりたいことが生まれてくる。これで人生が終わるんじゃないかと、夢半分、諦め半分で考えています。 私の中や私の作品の中に価値や意味を置くのではなく、作品の前に立たれた方の身体や記憶、気持ちなどを照らす作品、あるいは、観る人の身体を乗せた場、世界に意識が向くような作品を発信したいと思っています。 大それたことを申しますと「世の中が良くなればいいのに」と思っています。いつも「この絵さえ出来れば世界は良くなる」と思って頑張るのですが、なかなか良くはならないですね(笑)。 |
| ありがとうございました。 |

| 安喜万佐子さんの代表作の1つ『pine woods (松林図)』六曲一双(二隻)900cmx600cm 長谷川等伯「松林図」をオマージュされ、金箔で表現されています。動画は映像と金箔絵画の光が干渉し合うインスタレーション。まさに『陰翳礼讃』の世界です。 |

| ――絵の上に金箔を貼っていくんですか? |
 木の絵を避けて赤く塗り、まず全体を金箔で覆います。赤いところだけニカワ(糊)をつけて貼るので、一ヶ月くらいすると、自然にハラハラと落ちて、下の木が現れてくるんです。自分が仕上げるんじゃなくて、時間が仕上げてくれる。そんな絵を描いてみたかったんです。 木の絵を避けて赤く塗り、まず全体を金箔で覆います。赤いところだけニカワ(糊)をつけて貼るので、一ヶ月くらいすると、自然にハラハラと落ちて、下の木が現れてくるんです。自分が仕上げるんじゃなくて、時間が仕上げてくれる。そんな絵を描いてみたかったんです。 |
| ――これを描こうと思ったきっかけは? |
| 東日本大震災の年から描き始めたんです。松は海辺に植えられているが多いので、海からの視点で、等伯の松を考えてみようと思って。これを延々と増やしたいので、しばらくは自分でゾッとするまで描いていこうと思っています。 |
|
取材:山部香織(関西ウーマン編集長)/2016年7月 |
■関西ウーマンインタビュー(美術・芸術) 記事一覧
-
「自分の感受性は自治したい 」素材として光を用いて表現する照明デザイナーの魚森さん
-
「掘り下げれば膨大な水脈が隠れている」自分の創りだしたものにどう責任を持つか、絶えず問い表現する城戸さん
-
「自分のペースで生きていい」文学作品から着想を得て、善悪美醜入り交じる人間の情念を描く松澤さん
-
「既存の型に縛られず、独自の書を追求したい」現代アートの世界で書道家として生きることを選んだ田面さん
-
「自分の絵をこよなく愛し執着する」「マリブルー」と称される青を基調とした絵が印象的な青江鞠さん。
-
「日常の視座と違う視点を持って生きたい」見る側にさまざまな想起を投げかける風景画を描き続けている安喜さん
-
「自分の生きてきた証として書を残していきたい」技術を高める鍛錬が自分の自信になると話すみゆきさん


















