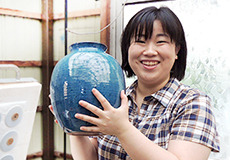HOME![]() ■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)
■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)
![]() 鈴木 優子さん(フリーランス ピアノチューナー)
鈴木 優子さん(フリーランス ピアノチューナー) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人)
鈴木 優子さん(フリーランス ピアノチューナー)

今自分にできる最大限のことを
鈴木 優子さん
フリーランス ピアノチューナー
フリーランス ピアノチューナー
ピアノの音律を整える「調律」、動きの正確さや弾き心地を整える「整調」、音色に変化を与えて全体のバランスを整える「整音」を行い、ピアノの音や響き、弾き心地をつくり出すピアノチューナー。
この道、約40年の鈴木優子さんはフリーランスで、個人宅や保育園、ライブハウス、ギャラリー、コンサート時、レコーディング時などのピアノ調律を手掛けています。
鈴木さんがピアノチューナーを志したのは19歳の時でした。短大卒業後の進路に悩んでいた時、たまたま観たテレビドラマをきっかけに志し、20歳でこの道へ。
いい音をつくる難しさについて、「『これでいい』と思うことはありません。弾き手からいい反応を得られても『たまたまよかったんだ』と思うから、その『たまたま』を多くするために、今自分にできる最大限のことを、丁寧に一つ一つ積み重ねるしかないと思っています」と語る、鈴木さん。
鈴木さんにとって「いい音」とは? どんな音の世界が見えているのでしょうか。
この道、約40年の鈴木優子さんはフリーランスで、個人宅や保育園、ライブハウス、ギャラリー、コンサート時、レコーディング時などのピアノ調律を手掛けています。
鈴木さんがピアノチューナーを志したのは19歳の時でした。短大卒業後の進路に悩んでいた時、たまたま観たテレビドラマをきっかけに志し、20歳でこの道へ。
いい音をつくる難しさについて、「『これでいい』と思うことはありません。弾き手からいい反応を得られても『たまたまよかったんだ』と思うから、その『たまたま』を多くするために、今自分にできる最大限のことを、丁寧に一つ一つ積み重ねるしかないと思っています」と語る、鈴木さん。
鈴木さんにとって「いい音」とは? どんな音の世界が見えているのでしょうか。
「私には調律師しかない」という直感から
ピアノ調律師をめざすきっかけは?
小学1年生から中学3年生までピアノを習い、高校生から短大生までフォークギターを弾きながら歌ったり曲をつくったり仲間と活動したりしていました。本を読むことも好きで、エッセイを少し書いたりもしていたから、仕事をするなら、音楽系か、もの書き系かなと考えていたんです。
就職活動では出版社や放送局などに応募するも、内定倍率が高すぎて。ある出版社では応募者800人中3人のみ採用という状況でしたから、どこにもひっかからず、「どうしよう」と迷っている時、たまたまつけていたテレビ番組に見入ってしまったんです。
女性調律師が主人公の『四季~ユートピアノ~』というドラマで、主人公がバイオリンケースにチューニングハンマーと音叉を入れて旅をしながら、サーカス劇場や古い学校のピアノを調律してまわるという詩的な物語でした。見終えた時、「これだ!私がやることはこれしかない」と思っちゃったんです。
ピアノの音が、子どもの頃からすごく好きでした。
中学生の時、ビートルズの『レット・イット・ビー』のピアノの旋律にひき込まれて、その部分を繰り返し聴き入ったり、ピアノの先生の家にあったアップライトピアノと木目のグランドピアノの音色を聴いて、どうしてピアノによってこんなにも音が違うんだろうと不思議に思ったり。
フォークギターを楽しむようになってからは、ギターのチューニングを覚えて、チューニングをしっかりとしていないときれいな音が出ないし、心地よくないとも感じていました。そういえば、バイオリンを少し習った時も、自分で音をつくるところに魅かれていたんです。
そんな経験の一つひとつが結びついて、「これだ!」となったんだと思います。その翌日か翌々日くらいには、楽器メーカーの販売店に「どうしたら調律師になれますか?」と乗り込んでいました(笑)
就職活動では出版社や放送局などに応募するも、内定倍率が高すぎて。ある出版社では応募者800人中3人のみ採用という状況でしたから、どこにもひっかからず、「どうしよう」と迷っている時、たまたまつけていたテレビ番組に見入ってしまったんです。
女性調律師が主人公の『四季~ユートピアノ~』というドラマで、主人公がバイオリンケースにチューニングハンマーと音叉を入れて旅をしながら、サーカス劇場や古い学校のピアノを調律してまわるという詩的な物語でした。見終えた時、「これだ!私がやることはこれしかない」と思っちゃったんです。
ピアノの音が、子どもの頃からすごく好きでした。
中学生の時、ビートルズの『レット・イット・ビー』のピアノの旋律にひき込まれて、その部分を繰り返し聴き入ったり、ピアノの先生の家にあったアップライトピアノと木目のグランドピアノの音色を聴いて、どうしてピアノによってこんなにも音が違うんだろうと不思議に思ったり。
フォークギターを楽しむようになってからは、ギターのチューニングを覚えて、チューニングをしっかりとしていないときれいな音が出ないし、心地よくないとも感じていました。そういえば、バイオリンを少し習った時も、自分で音をつくるところに魅かれていたんです。
そんな経験の一つひとつが結びついて、「これだ!」となったんだと思います。その翌日か翌々日くらいには、楽器メーカーの販売店に「どうしたら調律師になれますか?」と乗り込んでいました(笑)

即行動に移されたんですね。
楽器メーカーの販売店で調律師の技術学校があることを教えてもらったものの、既に募集が終わっていたこともあり、その後まもなく家庭内でさまざまな出来事が重なったので、就職先を決めぬまま、短大を卒業しました。
アルバイトをしながら仕事を探そうと、レコード店のアルバイト募集に応募したところ、音楽教室の受付業務を担当することになりました。
教室には調律師が出入りしていたので、「実は調律師になりたかったんです」と話したら、「調律師の人手が足りていないから、社長に頼んで会社から技術学校に行かせてもらったらええねん」って。
ちょっと諦めモードに入っていたのに、「もしかしたら!!」と社長のところに乗り込みました(笑)
ですが、社長には即、断られてしまいます。当時は調律師といえば男性が多かったですし、少し前に会社から技術学校に行った女性が1週間でリタイアしたとのことで、二の舞になるのではと危惧されたからです。
私はどうしても諦めきれなかったので、毎日のように社長のところに通い詰め、「私は絶対に途中でやめません」「本当に調律師になりたいんです」と言い続けました。
ついに数カ月後、社長から「あんたには根負けしたわ」と言われ、技術学校に行かせてもらえることになったんです。
20歳の時に、調律師としての一歩を踏み出しました。
アルバイトをしながら仕事を探そうと、レコード店のアルバイト募集に応募したところ、音楽教室の受付業務を担当することになりました。
教室には調律師が出入りしていたので、「実は調律師になりたかったんです」と話したら、「調律師の人手が足りていないから、社長に頼んで会社から技術学校に行かせてもらったらええねん」って。
ちょっと諦めモードに入っていたのに、「もしかしたら!!」と社長のところに乗り込みました(笑)
ですが、社長には即、断られてしまいます。当時は調律師といえば男性が多かったですし、少し前に会社から技術学校に行った女性が1週間でリタイアしたとのことで、二の舞になるのではと危惧されたからです。
私はどうしても諦めきれなかったので、毎日のように社長のところに通い詰め、「私は絶対に途中でやめません」「本当に調律師になりたいんです」と言い続けました。
ついに数カ月後、社長から「あんたには根負けしたわ」と言われ、技術学校に行かせてもらえることになったんです。
20歳の時に、調律師としての一歩を踏み出しました。

2年ほどのブランクを経て、また1から
技術学校を経て、その会社では13年ほど勤めておられたとのこと。その後、34歳で退社された後、2年ほどブランクが開いたそうですね。ブランクが開くことに対する恐さはなかったのですか?
「音はつくることができる」と教えてくれた先輩との出会いが、調律師としての方向性に影響を与えてくれました。
技術学校を出てまもなくの頃は、音を合わせることしか、意識できていませんでした。88つの鍵盤の一つひとつに3本ずつ、全230本ほどの弦が張られているため、その1本1本を整えて音を合わせなければならないという使命感が強く、どんな音にしたいかという想像も目標もありませんでした。
それが、当時は上司だった先輩がコンサートホールの仕事に行く時に、私も同行させてくださり、たとえば鍵盤の下に0.0何ミリの紙を入れたり抜いたりして鍵盤の沈む深さを変えると音色が変わるなど、奥深い世界を教えてくださいました。
ほかにもさまざまなところを触れば音が変わるということだから、私も「音をつくる」という世界に浸かりたいと思うようになったんです。
会社では月50台、1日2~3台の調律と、ピアノ販売のためのチラシ配布といった営業的な業務もありましたから、1台1台にそんなに時間をかけていられません。また、20代、30代の若手は家庭まわり担当で、個人宅用にコンパクトに設計されたアップライトピアノの調律ばかり。
グランドピアノや外国製のピアノなど、さまざまな経験を積んでレベルアップしていきたいという気持ちがどんどん膨らんでいったんです。
退社したタイミングは、音づくりのおもしろさを教えてくれた先輩が退社し、さらには夫の仕事の関係で引っ越す選択肢も出てきた時でした。
この13年の間に結婚と出産もして、子育てをしながら忙しく仕事をしてきたというのもあり、ブランクが開いてしまう恐さよりも、疲れたという気持ちのほうが大きかったように思います。退社して、すぐに何かとはならなかったんです。
技術学校を出てまもなくの頃は、音を合わせることしか、意識できていませんでした。88つの鍵盤の一つひとつに3本ずつ、全230本ほどの弦が張られているため、その1本1本を整えて音を合わせなければならないという使命感が強く、どんな音にしたいかという想像も目標もありませんでした。
それが、当時は上司だった先輩がコンサートホールの仕事に行く時に、私も同行させてくださり、たとえば鍵盤の下に0.0何ミリの紙を入れたり抜いたりして鍵盤の沈む深さを変えると音色が変わるなど、奥深い世界を教えてくださいました。
ほかにもさまざまなところを触れば音が変わるということだから、私も「音をつくる」という世界に浸かりたいと思うようになったんです。
会社では月50台、1日2~3台の調律と、ピアノ販売のためのチラシ配布といった営業的な業務もありましたから、1台1台にそんなに時間をかけていられません。また、20代、30代の若手は家庭まわり担当で、個人宅用にコンパクトに設計されたアップライトピアノの調律ばかり。
グランドピアノや外国製のピアノなど、さまざまな経験を積んでレベルアップしていきたいという気持ちがどんどん膨らんでいったんです。
退社したタイミングは、音づくりのおもしろさを教えてくれた先輩が退社し、さらには夫の仕事の関係で引っ越す選択肢も出てきた時でした。
この13年の間に結婚と出産もして、子育てをしながら忙しく仕事をしてきたというのもあり、ブランクが開いてしまう恐さよりも、疲れたという気持ちのほうが大きかったように思います。退社して、すぐに何かとはならなかったんです。

再開するタイミングやきっかけは? ブランクから、どう再開されていったのですか?
自然豊かな地域に引っ越したというのもあって、日々散歩を楽しんだり、ご近所さんの畑仕事を手伝ったり、中学校の臨時事務職員として働いたりしていたら、あっという間に1年が経っていました。
久しぶりに調律の道具を出したら、「これは何に使う道具だったかな?」とわからなくなってしまっていて、「このままじゃ、忘れちゃう」と焦り、学校や知り合いの家のピアノを調律するところから再開したんです。
また1からレベルアップをめざしたいと、会社員時代にお世話になった先輩に連絡してみることにしました。先輩は会社を退社した後、コンサートのピアノなどを調律するコンサート・チューナーとして活躍されていたので、仕事を見学させてくださいとお願いしたんです。
まもなく、先輩が独立して事務所を構えた時には、声をかけていただいたので、アシスタントとして手伝わせていただくことになりました。
隣で道具を渡すなどしながら先輩の仕事を間近で見たり、リハーサル時のアーティストとのやりとりを見聞きしたり、ホール内のさまざまな位置から音の聴こえ方を確かめたり。
また、いい音を聴かないと、自分の中でのいい音も高まっていきません。
調律師によっても、大中小といったホールの大きさによっても、デュオやトリオ、カルテット、オーケストラといった編成によっても、音の聴こえ方が変わるので、いろんなホールの、いろんなコンサートに足を運びました。
この30代後半から40代前半にかけての5年間は、調律は個人で少し受けていた仕事でするくらいで、多くの時間を先輩の仕事を見て、感じて、そのすべての体験を身体の中に染み込ませていくという感じでした。
そんな修行と研鑽の日々を経て、42歳の時に独り立ちすることにしました。そろそろ私の音を追求する時期なのかなと感じ始めたタイミングでのことです。
久しぶりに調律の道具を出したら、「これは何に使う道具だったかな?」とわからなくなってしまっていて、「このままじゃ、忘れちゃう」と焦り、学校や知り合いの家のピアノを調律するところから再開したんです。
また1からレベルアップをめざしたいと、会社員時代にお世話になった先輩に連絡してみることにしました。先輩は会社を退社した後、コンサートのピアノなどを調律するコンサート・チューナーとして活躍されていたので、仕事を見学させてくださいとお願いしたんです。
まもなく、先輩が独立して事務所を構えた時には、声をかけていただいたので、アシスタントとして手伝わせていただくことになりました。
隣で道具を渡すなどしながら先輩の仕事を間近で見たり、リハーサル時のアーティストとのやりとりを見聞きしたり、ホール内のさまざまな位置から音の聴こえ方を確かめたり。
また、いい音を聴かないと、自分の中でのいい音も高まっていきません。
調律師によっても、大中小といったホールの大きさによっても、デュオやトリオ、カルテット、オーケストラといった編成によっても、音の聴こえ方が変わるので、いろんなホールの、いろんなコンサートに足を運びました。
この30代後半から40代前半にかけての5年間は、調律は個人で少し受けていた仕事でするくらいで、多くの時間を先輩の仕事を見て、感じて、そのすべての体験を身体の中に染み込ませていくという感じでした。
そんな修行と研鑽の日々を経て、42歳の時に独り立ちすることにしました。そろそろ私の音を追求する時期なのかなと感じ始めたタイミングでのことです。

今自分にできる最大限のことを積み重ねて
これまでにどんな「壁」または「悩み」を経験されましたか?
いい音づくりへの技術的な壁は常にあって、その壁を乗り越えても新たな壁が見えてきます。
また、いい音をつくり上げることができても、生ピアノは材質などの関係から演奏量や気候、湿度などの影響を受けて、音が変わっていくので、いい音を保持する技術はこの仕事を続ける限り、永遠の課題です。
そんな中、弾き手の声にしっかりと耳を傾けることを大切にしてきました。
弾き手の「低音がちょっと緩んでいるね」「音は以前よりいいけれど、鍵盤が重くなった」「このへんがすごく気持ちいいね」「この前と音が少し変わりましたね。前は前でよかったけれど、今回も今回でよいですね」という実感が、新たな課題や今後の方向性を考えるヒントを与えてくれます。
プロとの仕事だけに限らず、ご家庭のピアノを調律しに行っても、「子どもが『音がめっちゃきれい』と言っています。『おけいこしなさい』と言っても全然しなかった子が、ピアノから離れません」と、お子さんから教えてもらうこともあります。
自分でも「こうしてみたらどうだろう」「ああしてみたらどうだろう」ということに挑戦して、弾き手の反応を受けながら、今後の方向性を考えていくこともあります。
レコーディング・エンジニアの方と一緒に仕事をするようになってからは、音に対する率直な意見をもらえますし、時には「雑味のある音がほしい」など要求してくれるので、どうしたら雑味をつけられるかなと考えて挑戦する中で、音の世界もどんどん広がっていったんです。
また、一般的にリハーサルや本番への立ち会い依頼がなければ、調律が終わった時点で帰るのですが、私は勉強のためにリハーサルや本番にも数多く立ち会わせていただいてきました。本番も立ち会うことで、屈辱的な場面に遭遇することもあり、それさえも次に活きる経験になるんです。
また、いい音をつくり上げることができても、生ピアノは材質などの関係から演奏量や気候、湿度などの影響を受けて、音が変わっていくので、いい音を保持する技術はこの仕事を続ける限り、永遠の課題です。
そんな中、弾き手の声にしっかりと耳を傾けることを大切にしてきました。
弾き手の「低音がちょっと緩んでいるね」「音は以前よりいいけれど、鍵盤が重くなった」「このへんがすごく気持ちいいね」「この前と音が少し変わりましたね。前は前でよかったけれど、今回も今回でよいですね」という実感が、新たな課題や今後の方向性を考えるヒントを与えてくれます。
プロとの仕事だけに限らず、ご家庭のピアノを調律しに行っても、「子どもが『音がめっちゃきれい』と言っています。『おけいこしなさい』と言っても全然しなかった子が、ピアノから離れません」と、お子さんから教えてもらうこともあります。
自分でも「こうしてみたらどうだろう」「ああしてみたらどうだろう」ということに挑戦して、弾き手の反応を受けながら、今後の方向性を考えていくこともあります。
レコーディング・エンジニアの方と一緒に仕事をするようになってからは、音に対する率直な意見をもらえますし、時には「雑味のある音がほしい」など要求してくれるので、どうしたら雑味をつけられるかなと考えて挑戦する中で、音の世界もどんどん広がっていったんです。
また、一般的にリハーサルや本番への立ち会い依頼がなければ、調律が終わった時点で帰るのですが、私は勉強のためにリハーサルや本番にも数多く立ち会わせていただいてきました。本番も立ち会うことで、屈辱的な場面に遭遇することもあり、それさえも次に活きる経験になるんです。

「屈辱的な場面」とは、どんな場面ですか?
たとえば、独り立ちしてまもなく、10年ほど手付かずだったピアノを調律した時のことでした。
長年放置されてきたため、その放置されていた状態に戻ろうとする力が強くて、途中で「ああ、音が変わってきた」と。途中で音が変わるなんて、調律師としては屈辱的なことで、それを感じ続けるわけです。
でも、それは最後まで立ち会うからこそわかることであり、感じられることで、屈辱を感じることも必要です。ピンの止め方など技術的な問題か、温度か、湿度か、部品の故障かなどあらゆる可能性を考え、いい音を保持する、よりよい方法をさらに考えるきっかけになります。
そんなふうに課題を見つけると、ピアノのどこを触ればいいのか、内部の仕組みを思い浮かべて、「あそこを触るとこう変わるから、あそこも触らないとだめだよな」など頭の中で思い浮かべて考え、よりよい方法を追求し続けることが、この仕事のおもしろさでもあります。
「この方向性でいいんだな」と思うことはあっても、「これでいい」と思うことはありません。
弾き手からいい反応を得られても、「たまたま気温も天気もよくて、ピアノの状態も動かずにすんで、たまたまよかったんだ」と思うから、その「たまたま」を多くするために、今自分にできる最大限のことを、丁寧に一つ一つ積み重ねるしかないと思っています。
長年放置されてきたため、その放置されていた状態に戻ろうとする力が強くて、途中で「ああ、音が変わってきた」と。途中で音が変わるなんて、調律師としては屈辱的なことで、それを感じ続けるわけです。
でも、それは最後まで立ち会うからこそわかることであり、感じられることで、屈辱を感じることも必要です。ピンの止め方など技術的な問題か、温度か、湿度か、部品の故障かなどあらゆる可能性を考え、いい音を保持する、よりよい方法をさらに考えるきっかけになります。
そんなふうに課題を見つけると、ピアノのどこを触ればいいのか、内部の仕組みを思い浮かべて、「あそこを触るとこう変わるから、あそこも触らないとだめだよな」など頭の中で思い浮かべて考え、よりよい方法を追求し続けることが、この仕事のおもしろさでもあります。
「この方向性でいいんだな」と思うことはあっても、「これでいい」と思うことはありません。
弾き手からいい反応を得られても、「たまたま気温も天気もよくて、ピアノの状態も動かずにすんで、たまたまよかったんだ」と思うから、その「たまたま」を多くするために、今自分にできる最大限のことを、丁寧に一つ一つ積み重ねるしかないと思っています。

「今自分にできる最大限のこと」。その積み重ねの先に、今があるんですね。
調律師の技術学校に在籍していた時、卒業試験前日に講師から「明日も今日の調律で」というメッセージをもらいました。
卒業試験という特別な日だからと言って、特別な何かをしようとすると、逆にうまくいかなくなってしまうから。今日の調律を明日もすればいいよ、それが君の実力なんだよって。
そのメッセージが、今も根本にあるのかもしれません。
常にしていることを本番でもするためには、常に100%、120%くらいのことをしていないとだめで、いつもそのくらいのことをしていれば、どんな場面でも「これが私の調律です」と提示でき、実力に対しての評価も得られます。
また、独り立ちしたての頃にこんなことがありました。
ある音楽家が演奏するピアノの調律を2度目に担当した時、その音楽家から「前回と場所もピアノも違うのに、この間のピアノと同じ響きだ。この響きの感覚を覚えている」と言われて、鳥肌が立つくらい驚きました。弾いただけでわかるんだって。
その時に、一つひとつに注ぎ込むことが大切なんだと、より想いを強くしたことを覚えています。
人間だから、「今回はこのくらいで大丈夫かな」と思ってしまうこともあります。でも、自分が納得のいくまでしていないことは、自分をごまかしているということ。そんな時は、音を保持できる期間がいつもより短かったなど、絶対に何か返ってくるんです。
卒業試験という特別な日だからと言って、特別な何かをしようとすると、逆にうまくいかなくなってしまうから。今日の調律を明日もすればいいよ、それが君の実力なんだよって。
そのメッセージが、今も根本にあるのかもしれません。
常にしていることを本番でもするためには、常に100%、120%くらいのことをしていないとだめで、いつもそのくらいのことをしていれば、どんな場面でも「これが私の調律です」と提示でき、実力に対しての評価も得られます。
また、独り立ちしたての頃にこんなことがありました。
ある音楽家が演奏するピアノの調律を2度目に担当した時、その音楽家から「前回と場所もピアノも違うのに、この間のピアノと同じ響きだ。この響きの感覚を覚えている」と言われて、鳥肌が立つくらい驚きました。弾いただけでわかるんだって。
その時に、一つひとつに注ぎ込むことが大切なんだと、より想いを強くしたことを覚えています。
人間だから、「今回はこのくらいで大丈夫かな」と思ってしまうこともあります。でも、自分が納得のいくまでしていないことは、自分をごまかしているということ。そんな時は、音を保持できる期間がいつもより短かったなど、絶対に何か返ってくるんです。

それに、こんな不思議なこともあります。
以前、ライブハウスから「1本だけ、音が止まらない」と連絡があって行ったら、原因がすぐにはわからなくて。その日はライブがないから23時間後の翌朝9時までに解決できれば大丈夫と言われて「えぇー!!」となりながらも、時間があるのは幸いだなと思って、いろんな方法を試すんですが、どれもうまくいかなくて。
結局、原因は見当外れのところにあって、そこにたどり着くまで9時間かかりました。
後日、ほかの仕事で、本番前に同じ現象が起こるわけです。その9時間の経験がありましたから、その時は10分で直せたんです。これは1例で、そのほかにもピアノが「この先大変なことがあるから、今のうちに苦労しとけよ」と事前に教えてくれているんだろうなあと思うような出来事が、よくあるんです。
もし、あの時に「ちょっと音が止まりにくいけど、これくらいで」として、自分が納得できるまで突き詰め、原因や解決法を導き出していなければ、この本番前の危機は回避できませんでした。
自分をごまかさない。今自分にできる最大限のことを丁寧に一つ一つ積み重ねる。その結果に対して弾き手から意見や感想をもらって、さらに挑戦や試行錯誤を積み重ねることで、その「最大限」の幅も少しずつ大きくなっていっているのだと思います。
以前、ライブハウスから「1本だけ、音が止まらない」と連絡があって行ったら、原因がすぐにはわからなくて。その日はライブがないから23時間後の翌朝9時までに解決できれば大丈夫と言われて「えぇー!!」となりながらも、時間があるのは幸いだなと思って、いろんな方法を試すんですが、どれもうまくいかなくて。
結局、原因は見当外れのところにあって、そこにたどり着くまで9時間かかりました。
後日、ほかの仕事で、本番前に同じ現象が起こるわけです。その9時間の経験がありましたから、その時は10分で直せたんです。これは1例で、そのほかにもピアノが「この先大変なことがあるから、今のうちに苦労しとけよ」と事前に教えてくれているんだろうなあと思うような出来事が、よくあるんです。
もし、あの時に「ちょっと音が止まりにくいけど、これくらいで」として、自分が納得できるまで突き詰め、原因や解決法を導き出していなければ、この本番前の危機は回避できませんでした。
自分をごまかさない。今自分にできる最大限のことを丁寧に一つ一つ積み重ねる。その結果に対して弾き手から意見や感想をもらって、さらに挑戦や試行錯誤を積み重ねることで、その「最大限」の幅も少しずつ大きくなっていっているのだと思います。

弾き手が教えてくれる「私の音」
鈴木さんにとって「いい音」とは?
人それぞれ、「いい音」というのは違っていて、究極には好みや嗜好ということになるのだと思うのですが、私はその人がそのピアノを弾いて心地よい何かを感じられることが、いい音だと思っています。
それは音の響きであったりハーモニー感だったりタッチ感であったりすると思っていて、その人が心地よいと感じる何かが、そのピアノから感じられることではないかなと思うのです。
ピアノの音づくりの土台となる整調作業は繊細さを要求されるので、ものすごく細かい作業を重ね、微調整の繰り返しでつくり上げます。その上に調律を乗せることでよりよい音が生まれ、いい音づくりができます。
弾き手が「心地よい」と感じてくれたら、その「心地よい」という感じは、客席にも伝染すると思うんです。
以前、初めて調律を担当することになったライブハウスで、そこによく聴きに来ているお客さまが「いつもとはピアノの音が全然違うと思った。調律によってこんなにもピアノの音や響きが変わるんだね・・・」とわざわざ言いに来てくださって、やったかいがあったなあと報われました。
特に、初めて調律を担当するピアノの場合は、私には手に負えない状態だったらどうしよう、時間に間に合うだろうかといったプレッシャーがあり、前日は眠れないこともあるほどなんです。
だから、弾き手をはじめ、演奏を聴いたお客さまからそう言っていただけると、嬉しくて、次への活力になります。
それは音の響きであったりハーモニー感だったりタッチ感であったりすると思っていて、その人が心地よいと感じる何かが、そのピアノから感じられることではないかなと思うのです。
ピアノの音づくりの土台となる整調作業は繊細さを要求されるので、ものすごく細かい作業を重ね、微調整の繰り返しでつくり上げます。その上に調律を乗せることでよりよい音が生まれ、いい音づくりができます。
弾き手が「心地よい」と感じてくれたら、その「心地よい」という感じは、客席にも伝染すると思うんです。
以前、初めて調律を担当することになったライブハウスで、そこによく聴きに来ているお客さまが「いつもとはピアノの音が全然違うと思った。調律によってこんなにもピアノの音や響きが変わるんだね・・・」とわざわざ言いに来てくださって、やったかいがあったなあと報われました。
特に、初めて調律を担当するピアノの場合は、私には手に負えない状態だったらどうしよう、時間に間に合うだろうかといったプレッシャーがあり、前日は眠れないこともあるほどなんです。
だから、弾き手をはじめ、演奏を聴いたお客さまからそう言っていただけると、嬉しくて、次への活力になります。

聴いているお客さまにもわかるくらい、「鈴木さんの音」というのがあるのですね。
自分では、自分の音がわからなくて、弾き手をはじめ、まわりに教えてもらうことが多いんです。
たとえば、長年調律を担当しているピアニストが、訪問先で流れていたCDを聴いて、「あ、鈴木さんの音だ」とわかったと言うんです。CDのジャケットを見たら、私の名前が書いていて、その場にいた相手の方が「何が、どこが、鈴木さんなんですか!」と仰天したと言います。
また、別のピアニストは、あるお店で開催されたライブに行って、演奏の途中から「あれ、この音の響きは鈴木さん?」と思ったそうです。そのお店のピアノも私が調律しているのですが、彼女はそれを知らなかったのに、ピアノの響きを聴いただけでわかったと言います。
私自身は、風光る感じや美術館で鑑賞した絵のイメージを広げながら調律することはあるものの、自分の音がどんな音なのかはわかりません。ただ、彼女たちは「まあるい音」「あたたかい音」と言ってくれるので、私の音ってそうなんだって。
この5年くらいの間に、そんなことがちょこちょこ起きるようになってきたので、どこの、どのピアノでも、「私の音」というのが、ちょっとずつ出来上がってきているのかなと思うようになりました。
私としては、いつも、どこでも、今自分ができる最大限のことをしているだけなんです。それは、これからも変わりません。
たとえば、長年調律を担当しているピアニストが、訪問先で流れていたCDを聴いて、「あ、鈴木さんの音だ」とわかったと言うんです。CDのジャケットを見たら、私の名前が書いていて、その場にいた相手の方が「何が、どこが、鈴木さんなんですか!」と仰天したと言います。
また、別のピアニストは、あるお店で開催されたライブに行って、演奏の途中から「あれ、この音の響きは鈴木さん?」と思ったそうです。そのお店のピアノも私が調律しているのですが、彼女はそれを知らなかったのに、ピアノの響きを聴いただけでわかったと言います。
私自身は、風光る感じや美術館で鑑賞した絵のイメージを広げながら調律することはあるものの、自分の音がどんな音なのかはわかりません。ただ、彼女たちは「まあるい音」「あたたかい音」と言ってくれるので、私の音ってそうなんだって。
この5年くらいの間に、そんなことがちょこちょこ起きるようになってきたので、どこの、どのピアノでも、「私の音」というのが、ちょっとずつ出来上がってきているのかなと思うようになりました。
私としては、いつも、どこでも、今自分ができる最大限のことをしているだけなんです。それは、これからも変わりません。

近い未来、お仕事で実現したいことは何ですか?
35年くらいずっと、ピアノの調律にうかがっているお宅があって、当時5歳だった子が今はピアノの先生をされ、コンサートを開いたり、口コミで生徒さんがどんどん増えたりなど活躍されています。
初めて出会った時から、すごくいい音を出す子だったから、専門のお仕事をされるんじゃないかなと思っていたら、本当にそうなっているんです。
私が調律したピアノを弾いた子が、将来ピアニストになるかもしれないなあとちょっと想像するようになりました。
今、保育園のピアノを担当しているのですが、ピアノの音を心地よく感じることによって、ピアノを好きになり、将来ピアニストになる子が出てきたら、それはすごいことだなと思うんです。自分で野望を抱くよりもずっと、すごいことじゃないですか。
この数年のうちに体調を壊したこともあり、年齢的にもあと10年くらい仕事ができたらいいのかなと、ふと思うようになりました。いつも「この仕事が最後になるかもしれない」との想いで1台1台と向き合って、ピアノの音づくりという私の使命を果たしながら残る時間を過ごせればいいなと思います。
初めて出会った時から、すごくいい音を出す子だったから、専門のお仕事をされるんじゃないかなと思っていたら、本当にそうなっているんです。
私が調律したピアノを弾いた子が、将来ピアニストになるかもしれないなあとちょっと想像するようになりました。
今、保育園のピアノを担当しているのですが、ピアノの音を心地よく感じることによって、ピアノを好きになり、将来ピアニストになる子が出てきたら、それはすごいことだなと思うんです。自分で野望を抱くよりもずっと、すごいことじゃないですか。
この数年のうちに体調を壊したこともあり、年齢的にもあと10年くらい仕事ができたらいいのかなと、ふと思うようになりました。いつも「この仕事が最後になるかもしれない」との想いで1台1台と向き合って、ピアノの音づくりという私の使命を果たしながら残る時間を過ごせればいいなと思います。
鈴木 優子さん
大妻女子大学短期大学部英文科を卒業後、1980年からヤマハ株式会社特約楽器店の音楽教室でアルバイトを始める。その後まもなく、ヤマハのピアノ調律師の技術学校を経て、調律師として13年ほど勤務。1993年に退社。1994年からフリーランスで調律師の仕事を再開する。技術向上をめざし、コンサート・チューナーのもとで、1997年からアシスタントを始める。5年ほど修行と研鑽を積んだ後、2003年に独立。フリーランスのピアノチューナーとして、個人宅や保育園、ライブハウス、ギャラリー、コンサート時、レコーディング時などのピアノ調律を手掛けている。
(取材:2020年3月)
自分をごまかさない、特別な何かをしようとしない。今自分にできる最大限のことをする。とてもシンプルであり、難しくもあることを、積み重ねてこられた鈴木さん。
「自分らしさ」なんて追い求めなくても、自分ではわからなくても、いい。
今自分にできる最大限のことをしていれば、その行ったことにはちゃんと想いや実力、可能性が宿り、結果的に「自分らしさ」につながったり、誰かの心を動かしたりすることがあるのだと、鈴木さんのお話をうかがって思いました。
長年に渡って、一つひとつを丁寧に積み重ねてきた先の、豊かさや確かなものを感じます。
HP: 『えんを描く』
「自分らしさ」なんて追い求めなくても、自分ではわからなくても、いい。
今自分にできる最大限のことをしていれば、その行ったことにはちゃんと想いや実力、可能性が宿り、結果的に「自分らしさ」につながったり、誰かの心を動かしたりすることがあるのだと、鈴木さんのお話をうかがって思いました。
長年に渡って、一つひとつを丁寧に積み重ねてきた先の、豊かさや確かなものを感じます。

小森 利絵
編集プロダクションや広告代理店などで、編集・ライティングの経験を積む。現在はフリーライターとして、人物インタビューをメインに活動。読者のココロに届く原稿作成、取材相手にとってもご自身を見つめ直す機会になるようなインタビューを心がけている。
HP: 『えんを描く』
■関西ウーマンインタビュー(ものづくり職人) 記事一覧
-
「今自分にできる最大限のことを」この道40年。ピアノの音や響き、弾き心地をつくり出す調律師の鈴木さん
-
「つくることそのものがおもしろい」40代目前でガラス作家への道を決めた美友子さん
-
「オーダーメイドだからこそ鍛えられる」世界で一つだけの手づくりの時計を創る、時計職人の海津さん
-
「幻の器と呼ばれる[京薩摩]」精巧を極めた華麗な職人技で伝統工芸士として[華薩摩]を描く小野さん
-
「採算の取れない仕事。だからこそ楽しい」陶芸が好きで13年。自分の窯を開いた藤原さん。