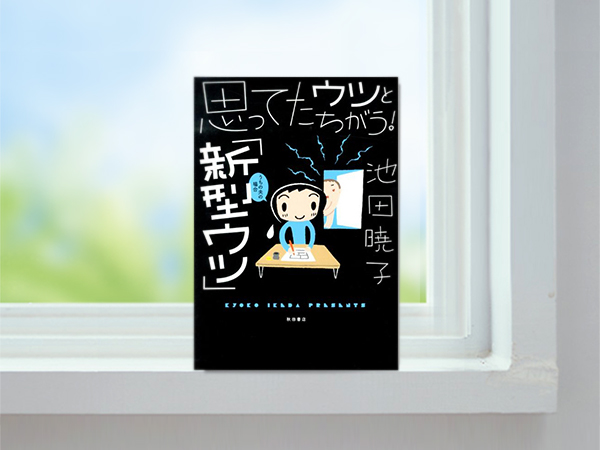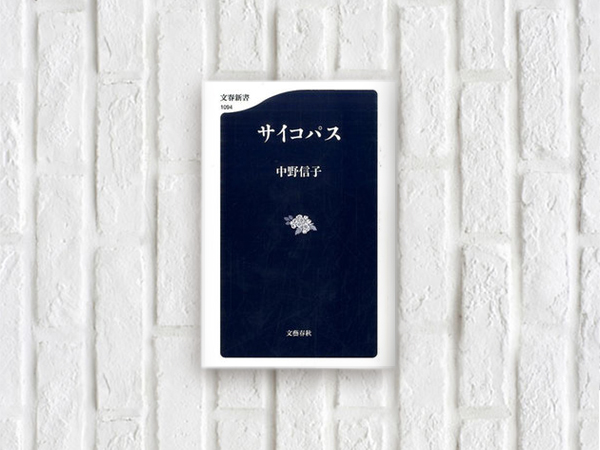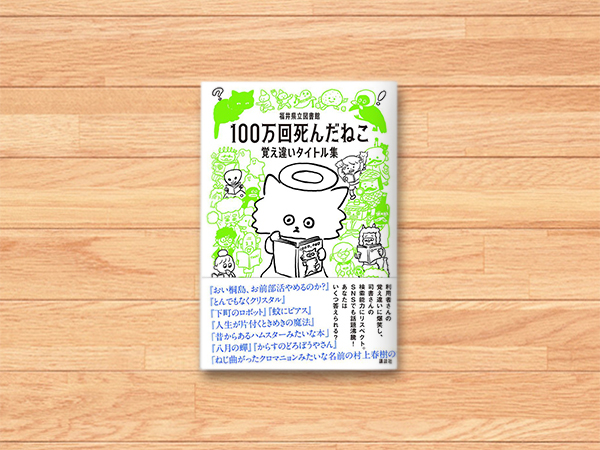類(朝井まかて)
 |
|
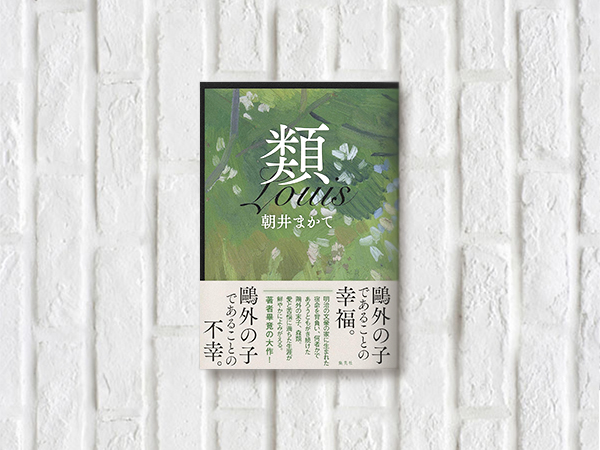 1年以上かかって読み終えた 類
朝井 まかて(著) 朝井まかてさんの『類』をやっとのことで読み終えました。読み始めたのが昨年の春だったでしょうか。1年以上かかって読み終えたことになります。
タイトル『類』とは人の名前です。 これは、日本文学史に燦然と輝く森鴎外の末っ子、森類の生涯を描いた作品なのです。 私が学生だったとき、森鴎外の本名が、森林太郎(もり りんたろう)であることを知り、「なんだかしりとり遊びみたい」と思ったものでした。 その後、森林太郎の子どもたちが皆、外国でも通じるような名前だということを知って、面白いなぁと思ったものです。 長男が於菟(おと)=オットー、長女 茉莉(まり)=マリー、次女 杏奴(あんぬ)=アンヌ、そして次男で末っ子が類(るい)=ルイといった具合です。 今のようにキラキラネームが当たり前の時代ではありません。 明治・大正時代にこのお名前は相当珍しかったのではないでしょうか。名前単独でなく、苗字の「森」に続けて発音すると、より印象深く聞こえる名前です。 そんなことを考えていたのが20代の前半でした。 それから40年ほど経った昨年、本屋さんで『類』を見かけて私は「もしや?」と立ち止まりました。 森鴎外の息子の話なのかな?と。 まさにその通りで、本の帯にはこう書いてありました。 鴎外の子であることの幸福。
鴎外の子であることの不幸。 有名人、スターの子どもに生まれることがどんなものなのか、想像するしかありません。
良いことばかりではないのだろうなぁとは想像がつきます。 特に森鴎外は、当時、規格外の偉人だったはずです。 小説家であり、翻訳家であり、医師でもある。しかも市井の医師ではなく、軍医総監という身分です。 どれか一つの肩書きだけでも非凡なのに、どれもこれも一流、しかも同時並行していたというのですから、スーパーマンでしょう。 のちに茉莉と類は回想します。 「考えれば、パッパは省略しない人だったね。学問も著作も」
そして人生も。どうしたらあんなことができるのだろう。仕事を持ちながら思索し、書き、論じ、そして子供たちをあれほどまでに愛した。何一つ忽せにすることなく、省略しなかった。 (朝井まかてさん『類』P385より引用)
森鴎外の子どもであることは、どれほど誇らしいことだったかと思います。
類たちが回想したように、森鴎外は大変な子煩悩でした。 編集者が原稿を受け取りに来た際、まだ幼かった長女の茉莉が、ずっと鴎外の膝に乗っていたらしいのですが、編集者が帰った後、鴎外がとても不機嫌だったというエピソードを読んだことがあります。 「あの編集者は お茉莉のことを可愛いと言わなかった」と。 森茉莉だけが特別に可愛がられていたわけではなく、森鴎外は本当に子どもたちをそれはそれは可愛がったそうです。 物語の冒頭、類は数えで12歳(ということは11歳)。 父が丹精込めて育てた庭木の中に佇む姿から始まります。 類は誰にともなく、自分の決意を述べています。 これからは勉強を頑張って学校の先生を驚かせてみせるし、中学校受験にも合格してお母ちゃんを安心させるし、植物もちゃんと育てます、と。 彼の決意は、ある願いと引き換えでした。 だからお願いです。パッパ、かえってきて。
(朝井まかてさん『類』P13より引用)
類が11歳の時に、父 森鴎外は亡くなったのです。
類は小学校に上がる年齢になっても、いつもメソメソ泣いている子でした。 母親にちょっと注意されただけでも泣いてしまう。 おまけに学校の成績が悪いのです。小学校3年生になると授業についていけないことが誰の目にも明らかになります。 先生には、お父上はあんなに偉いのにこんなこともわからないのかと怒られる。 お母ちゃんは類の勉強のできなさ加減にイライラしています。 病死した先妻が産んだ長男の於菟は、森鴎外と同じ医師を目指して医大へ進学したと言うのに、自分が産んだ男子 類は小学校の段階で落ちこぼれている、ということに焦りがあったのですね。 脳に問題があるのではと、病院に連れて行くも、全く問題はないと言われてがっかりする始末。 病気で頭が悪いなら仕方ないと思えるのに、ということです。 自分が類だったら、お母ちゃんから伝わってくるこの気持ちに、いたたまれないだろうと思います。 そもそも於菟と類は21歳も歳が離れているのだから、比べなくても良いのにと思いますし。 ちょっと不思議な感じですが、森家の子どもたちは、母親を「お母ちゃん」、父鴎外を「パッパ」と呼んでいました。 パッパ、森鴎外は類を決して怒りません。 メソメソする類を広い庭に連れ出し花の名前を教えたりします。 類はパッパに愛され護られていると実感していたと思います。 また森鴎外は庭の花だけでなく、食事や家具、調度品、物の考え方などにも美学がありました。 それは妻であるお母ちゃんとの共通点でした。 森家の子どもたちは美しいものに囲まれ、パッパに愛されて育ったのです。 文字通り夢のように美しい日々だったことでしょう。 末っ子の類は偉大な庇護者であるパッパとは、11年しか一緒に過ごせませんでした。 パッパを失った時には、もっと頑張って勉強するからパッパかえってきて、と願ったにも関わらず、その後も勉強は全くできなかったようです。 どうなっちゃうんだろうと心配していたら、類は絵画に目覚めました。 すぐ上の姉 杏奴の影響もあったのかもしれません。 二人して絵画を学び、その後二人でフランスに留学します。 元々は杏奴が留学したいと言い出し、女性一人では心配だというお母ちゃんが類にお供をするように命じたのです。 類が20歳の時でした。 この辺りまでは、調子よく読めたのですが、この後、私の読むペースがどんどん落ちてしまいました。 私は森類さんの人生がどんなものか、ほとんど知らずに読み始めたのです。 パリで、杏奴と二人、芸術に触れながら自由に生活している類の様子はとても明るくて読んでいて楽しいものでした。 もしかして類さんは画家になったのかなぁ?なんて思いながら。 ところがですね、類は画家としていつまで経っても芽が出ません。 姉の杏奴が絵でも文筆でも売れ始めても、類は修行の身。 そんな類も結婚します。 妻の父は画家で、妻もその実家も類には最大限の理解を示してくれます。 いつかきっと、画家として一本立ちできるであろう、と。 ところが、類は殻を破れません。全く売れないのです。 いったん絵は置いておき、文章で稼いではどうか、ということになるものの、文筆業でも食べていけない。 才能がないわけではなく、類は絵でも文章でも必死さが足りないのです。 書きたい(描きたい)ものが内からほとばしる…ということもない。 いつもそこそこの題材を、そこそこに練って書く(描く)わけです。 それを指摘されても、必死になれないのが類の個性なのだからどうしようもありません。 妻との仲は良く、子どもはどんどん生まれるけれど、子どもに食べさせるためのお金を稼ぐ人がこの家にはいません。 妻の嫁入り道具である着物を一枚、また一枚と売って凌いでいるのだけれど、その苦労をしているのは妻で、類はちょっと出かけるとカフェに入ってコーヒーなど飲んで帰ってくるのです。 妻は道を歩いていても、食べられる草は生えていないだろうかと目を配っているというのに。 ただし、類には全く悪気はありません。 幼い頃からの延長で、類にとってそれが自然な行動なのです。 ついに妻がキレて、類は働きに出ることになります。 30年間、働いたことがない人がお勤めに出るなんて、想像しただけでもうまくいきそうにないことがわかりますよね。 もちろん、その予想は当たります。 クビになった類に対して、同僚の一人がこう言います。 「役に立つ立たないじゃないんですよ。あなたのような人が生きること自体が、現代では無理なんです」
(朝井まかてさん『類』 P373より引用)
日本が第二次世界大戦で負け、みんな必死で生きている時代です。
類の心は焦りでいっぱい。 自分はまだ何者にもなっていない、森鴎外の息子であることを除いて、と。 もうこの辺りから読むのが辛くて、辛くて。 類は、幼少期から美しいもの豊かなものに囲まれて生きてきて、働く必要もなく、自分の好きなことだけをして生きてきたわけです。 その「好きなこと」で稼げれば良いけれど、そうはいかない。 姉の杏奴、遅れて茉莉も文筆業デビューし、仕事の依頼があるというのに、類にはない。 森鴎外の息子である以外に何もない、とは、どれほど辛いことでしょう。 そして類はお金を稼ぐ能力に乏しいのです。 辛さの挟み撃ちではないですか。 それでも人は生きていかねばなりません。 私は主人公に感情移入してしまうタイプなので、心が重たくなってしまい、1日1ページ読むのがやっと、という感じでした。 類が、年老いた犬と散歩する場面が、私の中での辛さのピークでした。 森類さんは1911年に生まれて1991年にこの世を去ります。 享年80歳。 紆余曲折はあったけれど、天寿をまっとうされたのです。 類が感じた焦りや、寄るべのなさは、歳をとるごとに少しずつ消えていき、読んでいる私の辛さも減っていきました。 『類』は、森鴎外の子であることの喜びと苦悩が、ぎっしり詰まった小説でした。 途中で投げ出さずに、辛くても読み終えてよかったです。 余談ですが、『類』には、与謝野晶子、志賀直哉、佐藤春夫など、錚々たる作家さんが登場します。 作品を通してしか知らない作家さんたちも、確かに生きておられたのだなぁ、と感じました。 また、二代目市川猿之助、「芸術は爆発だぁ」の岡本太郎も登場し、森家の交際範囲が広く華やかだったことを感じました。 類
朝井 まかて(著) 集英社 明治の終わり、森鷗外の末子として生まれた類。愛情豊かな父と美しい母、ふたりの姉と、何不自由なく華やかに暮らした少年期。父の死という喪失を抱えながら画家を志し、パリへ遊学した青年期。戦後の困窮から心機一転、書店を開業。やがて文筆家の道へ。文豪の子という宿命を背負い、何者かであろう懸命に生きた彼の、切なくも愛すべき生涯を描いた大作。著者による講演「鷗外夫人の恋」も載録。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook