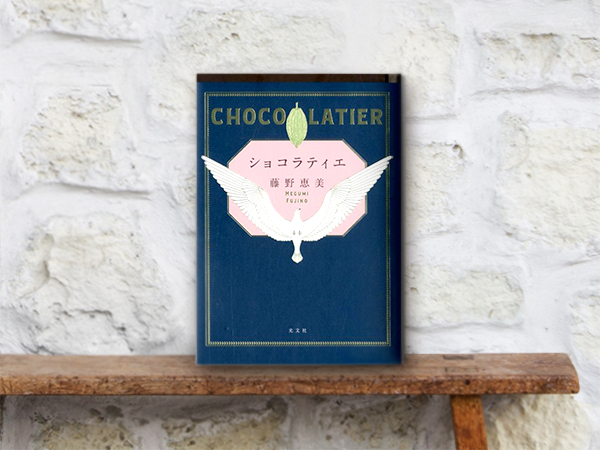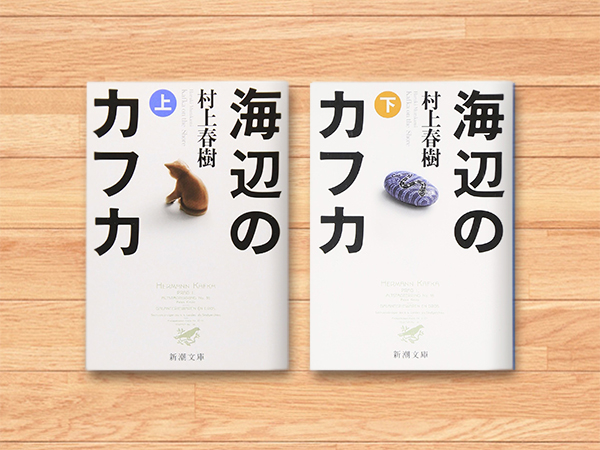敗者の生命史38億年(稲垣栄洋)
 |
|
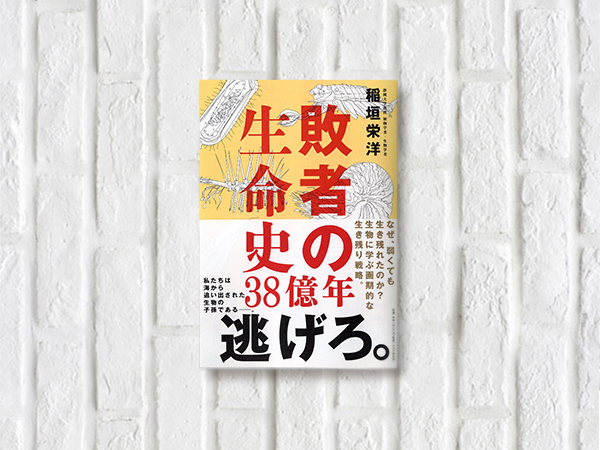 強いだけでは生き残れない 敗者の生命史38億年
稲垣 栄洋(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。
今回ご紹介するのは、稲垣栄洋さんの『敗者の生命史38億年』。 タイトルを見たとき、私は違和感を覚えました。 単細胞生物から始まって、38億年、現在生き残っている生物たちは勝者ではないのか、と。 ところがしばらく読んでいてわかったのです。 「進化」は字面からして、優れたこと、素晴らしいことのように思えるけれど、生物にとってそのままの姿で生き延びていけるのなら、わざわざ変わる必要はないのだということを。 生きた化石と言われるシーラカンスや、ほとんど姿形を変えずに今に至っているサメや鳥類などは、変わる必要がなかったからそのままの姿でいられるわけです。 全ての生命の始まりは海の中でした。 海で生まれ、海で育った生物たちの中で、弱者は強者に追われ、海岸沿いに移動します。 その中の数種類はあえて生きづらい陸に上がり、両生類になっていきます。 さらに海岸でも競争に敗れたものたちは、もっと生きづらい陸に上がり爬虫類へ。 生きづらい場所はそれだけライバルが少ないので、環境に適合するよう進化していけばその分活路が見出せる、進化とはまさに敗者の選択なのかもしれません。 恐竜やマンモスのように、途中で絶滅してしまう種も もちろんあります。 生命史を紐解くと、長い目で見れば一人勝ちするよりも、他者と協力し合うほうが生き残りやすいようです。 その代表は植物。 昆虫や鳥や動物に蜜を与え、実を食べられる代わりに受粉を助けてもらったり、種を遠くに落としてもらったりという恩恵を受け、生き延びていくわけです。 それならば、現在地球を思うさま利用している人間は、いったいこの先どのようになっていくのでしょう。 他の動植物を自分たちの都合で駆逐しながら、ずっとこの先も一人勝ちを続けていけるのか、未来を考えると不安になりました。 それにしても不思議なのは、今地球上にいる全ての生命体は元をたどれば一つだということ。 広大な宇宙の中に生まれたこの地球で、どういったメカニズムかは不明ながら、最初に生まれた生命体がそれぞれに進化し、こんなにも多種多様な生き物へと枝分かれしていくなんて。 稲垣さんはその理由を、生命が生き残るための布石だったと解説しておられます。 気候変動や隕石の落下などが原因で、地球の環境は過去に何度か激変してきました。 同じような種類の生き物だけであれば、栄えているときはいいけれど、過酷な状況になった場合、全滅しかねません。 色々な形、色々な生態の生物に枝分かれしていけば、全滅のリスクは抑えられる、つまり生物にとって大切なのは多様性ということになります。 まとめてみると、 ・過酷な状況になった場合、環境を変えるより、自分が変わる(進化する)ほうが適応できる。 ・一人勝ちするよりも、他者と協力したほうが、結果的に生き残りやすい。 ・多様性を持つことで生き残れる可能性が増える ということになり、38億年もの生命史はそのまま一人の人生と同じ内容なのだなと思いました。 歳月の長さには気が遠くなるほどの差があるのに、不思議なものです。 そして私がこの本でもっとも衝撃を受けたのは、「死」こそ種の繁栄のためのシステムであるという稲垣さんの言葉でした。 細胞分裂をして同じものを増やしていくだけの生物には終わり(死)はありません。死なないかわりに、大きな繁栄もないのです。 稲垣さんは「死」の必要性を陸上競技にたとえて説明しておられます。 例えば、プロのランナー(強者)と小学生(弱者)がマラソンで競い合えば、ランナーが勝つに決まっています。 しかし、小学生チームは一人100メートルだけ走り、次にバトンを渡すルールにしたら、勝敗は簡単には予測できないというのです。 100メートルを全力疾走して、次にバトンを渡す。 限られた期間にパフォーマンスを上げて次に繋げる、それが「死」の意味なのだと。 私はこの本を読んで、自分が今生きている意味がうっすらわかった気がします。 これまで、子どもがいない私は、誰にもバトンを渡さずに虚しく走り終えるランナーなのかと寂しさを感じることもありました。 しかし、38億年の生命史を見れば、元をたどれば皆一つ。 枝の一つ(私)が途切れたとしても、それは本当に小さなこと。 私を形作っている要素のいくつかはどこかの枝に含まれており、また次の世代に引き継がれていくに違いないのです。 「悲しいときは夜空の星を見てごらん、数えきれない星々を見ていたら、あなたの悩みは小さいと気付くだろう」 そういった内容の言葉を耳にしたことがありますが、38億年に渡る生命史の前には、私のどんな悩みも苦しみも、けし粒ほどのものだと思えました。 ただ、けし粒に意味がないわけではありません。小さなことに一喜一憂して生きることにも大きな意味があるのでしょう。 これを突き詰めると哲学になる気がします。 著者 稲垣栄洋さんのご著書を読むのはこれが2冊目。どちらも深く考えさせられるものでした。 稲垣栄洋さん『戦う植物史』の感想はこちら。  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook