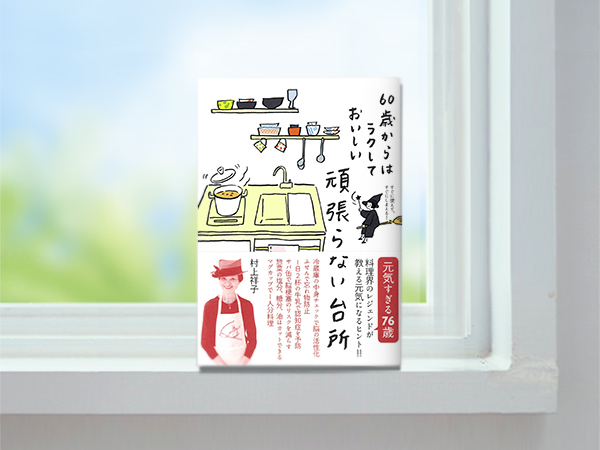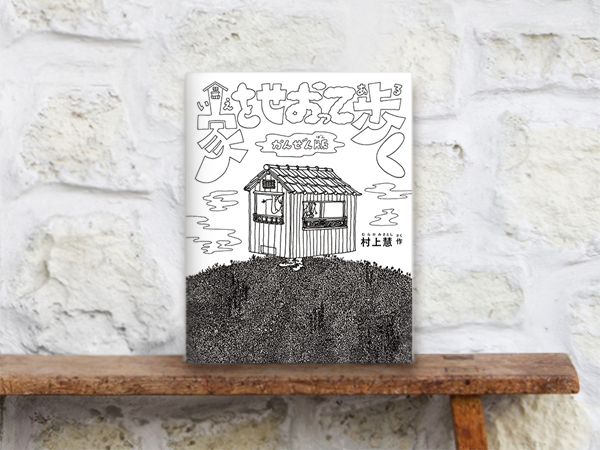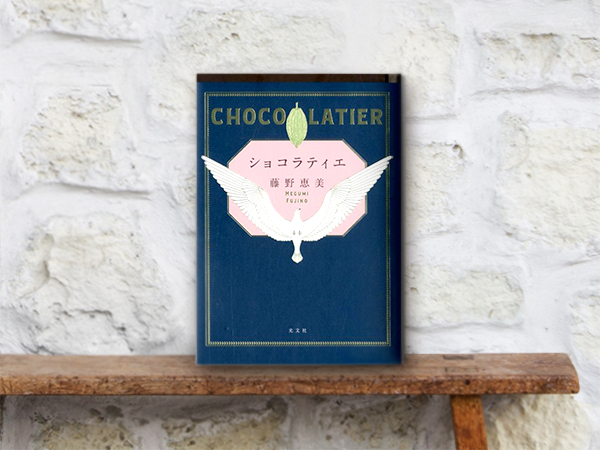迷惑な終活(内館牧子)
 |
|
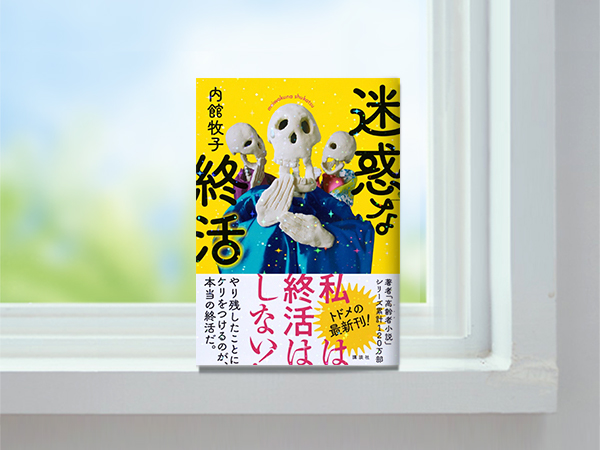 終活は誰のため? 迷惑な終活
内館 牧子(著)
かつては就職活動を意味する言葉だった「シューカツ」が、今や「終活」。世の中は、人生の締めくくりをしてからあの世へ行きましょう、という流れになっている。妻、礼子がせっせと終活しているのを横目に、英太はそんなことはしたくないと思っている。
言霊というものがあるではないか。自分はまだ75歳。今から「死」だ「終活」だなどと口に出したり書いたりしたら、本当に「死」が忍び寄ってきそうで怖い。 しかし、母親の死をきっかけに英太の考えが変わった。自分も終活をすると決めた。 世間一般とは違う、自分なりの終活だ。 (内館牧子さん『迷惑な終活』の出だしを私なりにまとめました。)
主人公 原英太は1948年生まれの75歳で、妻の礼子は71歳です。
二人の子どもも独立して、今は英太の母 キヨを新潟から呼び寄せて3人で暮らしています。 英太は新潟で生まれ育ちました。 東京の大学を卒業して、そのまま故郷に帰らずに就職、結婚。 そしてちょっと頑張って横浜市内に一戸建て住宅を購入。 横浜と言っても海が見えない場所だけれど、その分、庭付きの余裕のある広さの家を購入できたのです。 最近、妻が就活に凝り始めました。 英太は気乗りがしないのですが、老いた母は嫁に教えを乞うて、たどたどしくもエンディングノートなどを書いているようです。 妻に気兼ねをして合わせてくれているのか、それとも本当に必要だと思ってしていることなのか…。 英太自身は、終活に否定的です。生きている時に「死」を意識したくないのですよ。 終活、してらっしゃいますか? エンディングノートなどご準備されていますでしょうか? 私は昨年母を見送って、終活を強く意識するようになりました。 というのも、亡くなった母は何事も先手先手を打つ人で、まだ元気な時から終活を始めたのです。 まずは大好きだった植物を手放しました。 ある時、自力では植木鉢を動かせなくなったことに気がついて「自分でどうにかできないものを置いておいてはいけない」と、植物が好きな親戚やお友達に差し上げたのです。 そこからは、家具、食器、着物、洋服、バッグ……と、誰かに貰っていただける品質のものはどんどん手放していきました。 そして、将来入居する介護施設の予約まで。 結局は入院中に亡くなったので、施設には入らなかったのですが、なんとも手回しがよく、私は自分の親ながら尊敬の念を抱いたものです。 私はこんなふうに店じまいしながら終末を迎えられるだろうか、と。 そんな時にこの本を読んだので、しっかり終活を始めている礼子さんのことも理解できるし、「まだ早い」と思っている英太の気持ちもよくわかりました。 英太は子どものようなところがあって、恐竜が大好き。 息子と孫に手伝ってもらって、庭に実物の3分の1サイズの「カムイサウルス・ジャポニクス」の標本を作り上げ、朝に夕に「カム様」を見ては悦に入っております。 もうすぐ92歳のキヨは嫁に習いながら終活をしています。 家族がみな、互いに少しずつ気を使い合って、波風立てずに平凡だけど幸せな家庭を築いている、良い家族ではありませんか。一種の理想と言えます。 ところが、ある日、キヨが亡くなったことをきっかけに、物語が大きく動き始めます。 やはり人間はいつかは死ぬのだ、と実感した英太が、あれほど嫌がっていた終活を始めると言い出しました。 喜ぶ礼子。でも、英太の終活は礼子が考えているようなものではありませんでした。 新潟にいた15歳の頃、憧れていた女子に会いに行くと言い出しました。 その子は楚々とした美人。家が貧しくて、おとなしい女子でした。 そんな女子に、英太はひどいことをしてしまったそうで、死ぬまでに会って謝りたいというのです。 それが英太にとっての終活。 やり残したこと、心にずっと引っかかっていたことをやり遂げ、人生のケリをつける、それこそが自分の終活だと。 なるほど。心に引っかかっていることを、亡くなるまでに解消するのが終活、というのはわかる気がします。だけど、60年前、学校で起こった「事件」を果たして相手は覚えているものでしょうか? 自分のこととして、想像してみます。 私の場合、中学時代は45年ほど前のことなのですが、忘れられない友だちや、思い出せる人は数えるほどで、クラス全員の顔と名前はもう出てきません。学校で起こったことも、ほとんどが忘却の彼方です。 それが60年前ともなると、どうでしょうか?15歳の時以来一度も会っていないんですよ? 覚えていないんじゃないかなぁ。 だけど英太は自分がこれほど覚えていることを相手が忘れているわけはない、と思い込んでいるんです。 恐竜に寄せる思いと同じように、英太ってどこかまだ子どもの心を残した人なんですねぇ。 妻の礼子も娘も私と同じような感想を持ったようです。 だけどまぁ、生まれ故郷に帰って友人たちと会うのも良いだろうと、穏やかに送り出しました。 その先はご自分でお読みください。 めちゃくちゃ面白いですから。 登場人物のほとんどが70代後半で、それぞれの人生を歩んでいます。 それがとても参考になるのです。 また英太流の「終活」に触発された友だちがイキイキし始めるのも楽しい。 ちょっとだけ匂わせておきますと、ごくごく平凡で幸せに見えた英太の家族にも、ちょっとした波風が立ちます。 ああ、小説とはいえ、人の人生をのぞくって面白いわぁ。 とはいえ、終活について、まじめに考えさせられることも多々ありました。 英太の母親のキヨさんは、お嫁さんに気兼ねして終活をしているのかと思ったら、違いました。 こんなことを言っています。
「んだな。年寄りに終活ほどいい趣味はねぇすけな。
金はかからね、場所はいらね、月謝はいらね、体力いらね、
それで家族に喜ばれてさ。年寄りにこんげいい趣味、他にあろば」
(内館牧子さん『迷惑な終活』 P30より引用)
一方の英太はこう語っています。
「昨今の終活のあり方で、一番間違っているところ、それはだな、
多くが他人本位なところだ。他人が楽なように、他人が難しい決断をしなくてもいいようにと考える。
それは『立つ鳥跡を濁さず』でみごとなことだ。
しかしだ!自分が生きているうちは、自分本位で考えるべきだ。
早々と他人本位なんて、そんな終活があるか。それを強いられては迷惑だ」
(内館牧子さん『迷惑な終活』 P62より引用)
なんだかどちらの言い分もわかる気がします。
どちらも正解のような。 とりあえず「終活」は人に強いるものではない、ということだけは確かな気がしました。 【おまけ】 『迷惑な終活』のあとがきに、講談社の担当編集者さん小林龍之さんへの謝辞がありました。 小林龍之さん?! 私、つい最近、小林さんを拝見しましたよ。 なにげに文士劇旗揚げ公演 『放課後』で教頭の松崎先生役でご出演なさっていました。 何度名前を名乗っても忘れられてしまう面白いお役で。 小林龍之さんは、内館牧子さんの高齢者小説シリーズ『終わった人』、『すぐ死ぬんだから』、『今度生まれたら』、『老害の人』そして今回の『迷惑な終活』のご担当だったんですって。 また、第150回直木賞受賞作 朝井まかてさんの『恋歌』は企画の立ち上げから、第158回直木賞受賞作 門井慶喜さんの『銀河鉄道の父』は連載時から担当されたそうです。 すごい!面白い小説ばかり。 今後、講談社さんの本を読むときは「担当編集者さんはどなたかしら?小林さんだったらいいな」と思いながら読むことになりそう。
音声での書評はこちら
【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 迷惑な終活
内館 牧子(著) 講談社 やり残したことにケリをつけるのが、本当の終活だ。年金暮らしの原夫妻。妻の礼子はいわゆる終活に熱心だが、夫の英太は「生きているうちに死の準備はしない」という主義だ。そんな英太があるきっかけから終活をしようと思い立つ。それは家族や他人のためではなく、自分の人生にケリをつけること。彼は周囲にあきれられながらも高校時代の純愛の相手に会うため動き始める。やがて、この終活が思わぬ事態を引き起こし──。『終わった人』『すぐ死ぬんだから』『今度生まれたら』『老害の人』に続く著者「高齢者小説」第5弾! 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook