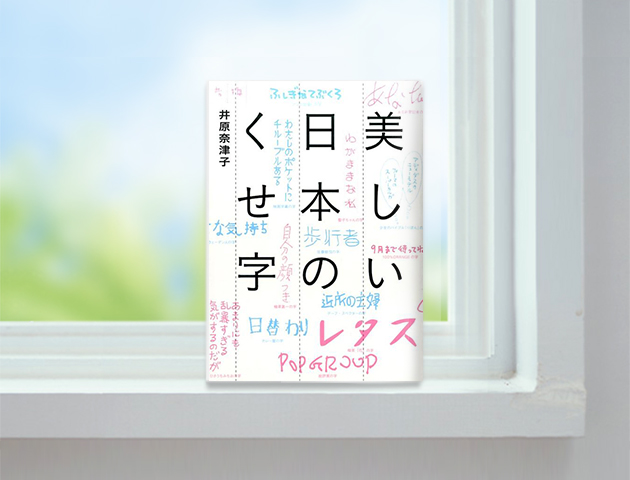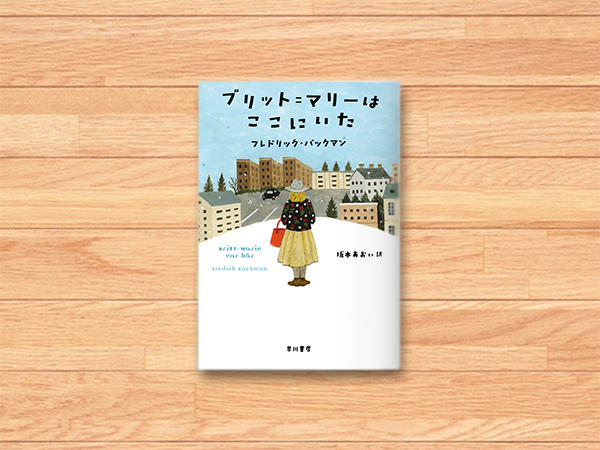私が本からもらったもの(駒井稔)
 |
|
 自分だけの仮想空間 私が本からもらったもの
翻訳者の読書論 駒井稔(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。
今回ご紹介するのは、駒井稔さん編著『私が本からもらったもの 翻訳者の読書論』。 この本の著者である駒井稔さんは1979年に光文社に入社。2006年に古典新訳文庫を創刊され、10年にわたって編集長を勤められました。 この本は、駒井さんがこれまで一緒に仕事をしてきた翻訳者の方に読書や本についてインタビューしたものをまとめたものです。 ドイツ文学、ロシア文学、フランス文学、英米文学など、8人の翻訳者さんに対して、初めての愛読書はなんだったのか、子どもの頃どんな本を読んでいたか、ご家庭での読書環境はどうだったのか、などを質問。 そして若い人たちに、どんな読書をすればいいかのアドバイスと、「私が本からもらったもの」は何なのかを質問されています。 読書にまつわる話の内容もさることながら、翻訳者の皆さんの語り口が非常に興味深かったです。 多少校正されているとはいえ、対談ですから、その人の喋り方、言葉選びに個性が滲み出ているのです。 8人とも、非常に丁寧というか、緻密な言葉遣いをされていて、これが翻訳というお仕事柄なのかしらん、と思いました。 また「読む」こととは直接関係ない部分で、面白い体験や興味深い言葉がたくさんあり、気がつけばいっぱい付箋を貼ってしまっていました。 例えば、ロシア文学翻訳者の貝澤哉(かいざわ はじめ)さんは1990年、留学生として暮らしいていたモスクワで、ヤミの本屋から本を買ったせいで警察に捕まったことがある、そうです。 社会主義体制末期のロシアでは、本屋さんの前に、ダフ屋ならぬヤミ本屋が立っていて、「この本あるよ」と声をかけてくる、それが日常だったんですって。 流通している本であれば、本屋さんに行けば買える、店頭にないならお取り寄せしてもらえるのが当たり前の日本にいては絶対に経験できないことです。 フランス文学の永田千奈さんは、人生最初の愛読書ブルーナの『うさこちゃん』(今はミッフィーちゃんと呼ばれています)をずっとご実家に置いておられました。 ところが保存状況が悪くて気がつけばカビだらけ。 仕方なく泣く泣く処分したところ、旦那様がお誕生日のプレゼントとして買い直してくれました。 いいお話、と思いきや、永田さんはこうおっしゃるのです。 やっぱり新しい本で買い直すとそれは”新しく買い直した本”になってしまって、”自分が持っていた本”が戻ってきたわけではないんですよね。
本って何千部、何十万部、大量生産で同じものがあるはずなのに、 何か特別な一冊、手に馴染んだ一冊というのはあるんだなと。 (駒井稔さん編著『私が本からもらったもの 翻訳者の読書論』P77より引用)
もしかしたらこれは、子どもの頃ずっと抱きしめて眠ったぬいぐるみと同じ感覚かもしれません。
同じ規格のぬいぐるみを新たに買ったとしても、前のぬいぐるみが戻ってきたわけではない、という感覚。 大量生産されているはずの本が、実は持ち主一人一人にとって「違う」本であるというのは、よく理解できるのですが、これまで考えたことがなかったことでした。 駒井さんの質問の一つ「最初の愛読書は何ですか?」に、私も答えさせてください。 私の最初の愛読書は、小学校3年生の時、学校の図書室で見つけたモーリス・ルブランの『奇巌城』です。 泥棒貴族というのでしょうか、決して人を殺さないスマートな犯罪者、しかも恋愛の要素まであって、私はすっかりルパンにハマってしまい、以後、図書室にあったルパンシリーズを片っ端から読みました。 私は一つの作品が気にいると、その作家さんの作品を片っ端から読む癖があるのですが、それはこの時に始まったと思われます。 ちなみに、私は自分がとても本が好きなのだと気がついたのも小学校3年生の時。 それ以前にも本は好きで読んでいたのですが、他の人も同じくらい読んでいるのだろうと思っていたのです。 小学校3年生の時に、住んでいる地域に新たに小学校ができ、通学路が短く、比較的安全になって以来、私は下校時に歩きながら本を読むようになっていました。 本が面白くて面白くて、歩いている時間も惜しかった。昭和の人にしかわからない「二宮金次郎状態」です。 それをご覧になったご近所の方が「千波留ちゃんはどれほど本が好きなのか!電信柱にぶつかるんじゃないかと思ってヒヤヒヤする」と母に注意しに来てくれて、初めて「あれ?他の人はそんなにまでは本が好きではないのかな?」と気がついたというわけ。 この本で紹介されている翻訳者の方達の多くが小さい頃から本を読んでおられます。 ご家族や環境の影響なども興味深く、共感したりヘーッと感心したり。 翻訳者の皆さんが紹介しておられる本の中には「あ、それ読んだ!面白いよね!」と共感したり、「それはまだ読んだことがない。読まなくっちゃ」とメモを取ったり。 そして対談の最後に語られるそれぞれの「私が本からもらったもの」の深みを噛み締めるのでした。 サブタイトル「翻訳者の読書論」の「論」の字に、難しい内容ではないかと構えていましたが、そんなことは全然なくて、学生の頃、読んだ本について語り合った友だちに重ね合わせてしまう方ばかりでした。 読書好きな方にはおすすめしたい一冊です。 ちなみに私が本からもらったものは、「どの時代にでも、どんな場所にでも飛んでいける自分だけの仮想空間」かな。 一種の現実逃避なのかもしれませんが。 私が本からもらったもの
翻訳者の読書論 駒井稔(著) 書肆侃侃房 このまえがきを読んでいる皆さんは、きっと教養や知識、深い内的体験など難しそうな話が満載なのだろうと思っていませんか。ある意味では、もちろんその通りなのですが、対談形式で個性あふれる8人の翻訳者の皆さんが披瀝する本のお話は、そういう話題も実に楽しく読めてしまうのです。筋トレしながら娘の本に関する質問に答えてくれた父親、早く自分の話し相手になって欲しいとひたすら世界の名作を大量に与え続けた母親。どの回も本をめぐる心に残るエピソードが満載です。そして最も重要なことは、読書に関する本質的な事柄がきちんと述べられていることだと思います。(駒井稔) 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook