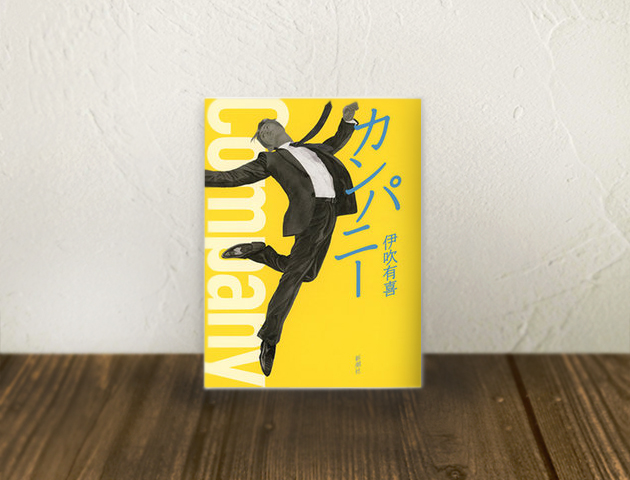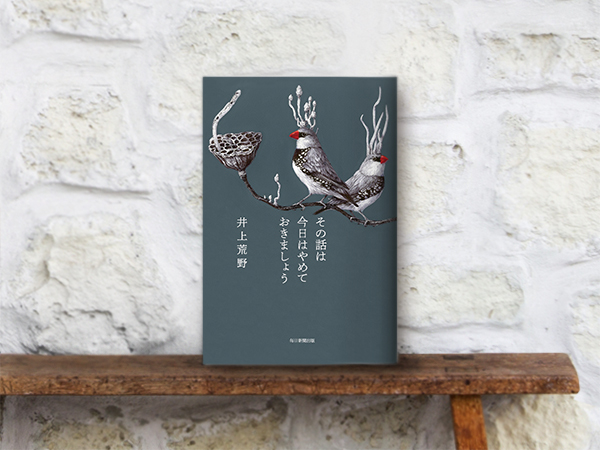流人道中記(浅田次郎 )
 |
|
 苦労のない人生なんかない 流人道中記
浅田 次郎(著) 「この作家さんの作品にハズレなし」と思える方が何人かいらっしゃいます。
浅田次郎さんは間違いなく、その一人です。『流人道中記』上下巻を読み終えて、再認識しました。 見習い与力 石川乙次郎19歳。幕臣としては最下層と言える御手先鉄炮組同心の次男として生まれた。
家族は両親と兄、乙次郎の下に弟と妹が一人ずつの六人家族だが、父の扶持(給料)は三十俵二人扶持、とても食べてはいけない。父をも含む家族全員が内職に精を出し、やっと生活できる状態だ。 長男はそんな「家」でも継ぐことができるし、女の子なら嫁に行くこともできる。しかし次男以下の男は部屋住み、冷や飯食いになってしまう。 乙次郎は幼少期から、勉学や武芸の鍛錬に必死に取り組んだ。今よりマシな家の養子になるために、だ。 幸い、文武ともに秀でていた乙次郎には後援者がつき、長じても学問や剣道に打ち込むことができた。 当主が町奉行与力を務める石川家には立派な嫡男がいた。ところが、不幸にも早逝してしまう。 まだ幼い娘に、いずれ然るべき家から婿を取ろうと算段していたが、数年後、今度は当主が倒れてしまった。 幸い命は取り留めたものの、寝たきりになり、お勤めは叶わない。早く後継を立てねば御家が断絶することになる。 学問もできる、武芸も達者な乙次郎に白羽の矢が立てられた。15歳になった娘きぬの婿に迎えたいというのだ。 周囲の人はもちろん、乙次郎本人が驚くような逆玉の輿で、本来なら一旦家格が釣り合う家の養子になり、その後結婚するというのが通常の手順だが、 届出の期日が迫っていて、体裁を整える余裕もなかった。おかげで、乙次郎の話は奉行所中の噂になり、職場でも悪い意味で注目の的だ。 そんな乙次郎に、奇妙な命令が下された。ある罪人を流刑地まで送り届けよという。 もともとは切腹を申し付けられていたのに、罪人はそれを拒否したという。それならば御手打ちにされそうなものだが、「大名預かり」で刑が確定した。 その罪人の流刑地(預かり場所)は遠く蝦夷。詳しいことを知りたがる乙次郎に対して、上司は「知らない方がいいのだ」という。 かくして、乙次郎は氏素性も犯した罪も知らない罪人を連れ、遥か東北へと旅立つのだったが…… (浅田次郎さん『流人道中記』(上)(下)の冒頭部分を私なりに紹介しました) 罪人の名前は青山玄蕃。切腹すればお家安堵を約束されたのに、「いやだ」と拒みます。
乙次郎から見れば「恥知らずな男」です。おまけにお役人である乙次郎に対して、恐れ入った様子も見せません。 乙次郎は、自分は刑を執行する側であり、青山玄蕃は罪人、折り目けじめをつけたいと思うのですが、徐々に二人の主従関係が逆転してきます。 というのも、乙次郎は江戸から出たことがないのです。街道を歩くコツも知らなければ、どんな宿に泊まるかも決めかねる始末。 それに対して、青山玄蕃はどうやら結構な身分の侍のようで、立ち居振る舞いが美しい。その上旅慣れているし、びっくりするような偉い人とも顔見知り。 お金の使い方も綺麗で、出るところに出れば言葉遣いも立派。とても流刑地に向かう罪人には見えません。 おまけに青山玄蕃は情が深く、宿で出会った人々の苦境を決して見て見ぬ振りをしません。相手の事情をよく見極め、落とし所を見つけ、みんなを納得させてしまいます。 宿ごとに起こる事件と、その解決法が綺麗で面白くて、ページを繰る手が止まりません。 愉快、痛快、面白い! 人情時代劇がお好きな人なら、たまらないと思います。 しかも青山玄蕃は、乙次郎が抱える「家」や「家族」の悩みもお見通し。 まだ19歳で世間知らずな乙次郎にとって、苦労といえば、貧しかった実家のことや、逆玉の輿として入った家での気苦労、そして職場の人間関係くらいのものでした。 しかし旅を続けるうち、誰の人生にも苦労があることに気づきます。そして自分が苦労だと思っていたことの中に「幸せ」があったことにも。 それを教えてくれるのが青山玄蕃、なのです。 青山玄蕃が乙次郎にかける言葉の深いこと。 事件解決の際の、彼の思いやりや優しさと合わせて、私は何度も涙ぐんでしまいました。 苦労している人、困っている人への優しさ、人としての誇りなどこの小説から教えられることがいっぱいあります。 私は何事も白か黒かハッキリさせたい性格なのだけれど、正しくないことを暴くことが常に正義とは限らないのだなと、青山玄蕃から教えてもらいました。 小説の中の乙次郎同様、私も、青山玄蕃が本当に罪人であるのか、わからなくなってしまいます。 その答えが最後にあるのですが、ああ、納得できないわ。 青山玄蕃さん、本当にそれでいいんですか?! この小説は「道中記」なので流人を引き渡すところで終わっていますが、きっと乙次郎さんは立派な人になるだろうと思えるのが救いかしら。 悲しいような、清々しいような、複雑な読後感の『流人道中記』でした。 流人道中記
浅田 次郎(著) 中央公論新社 万延元年(一八六〇年)。姦通の罪を犯したという旗本・青山玄蕃に、奉行所は青山家の安堵と引き替えに切腹を言い渡す。だがこの男の答えは一つ。「痛えからいやだ」玄蕃には蝦夷松前藩への流罪判決が下り、押送人に選ばれた十九歳の見習与力・石川乙次郎とともに、奥州街道を北へと歩む。口も態度も悪い玄蕃だが、道中で行き会う抜き差しならぬ事情を抱えた人々を、決して見捨てぬ心意気があった。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook