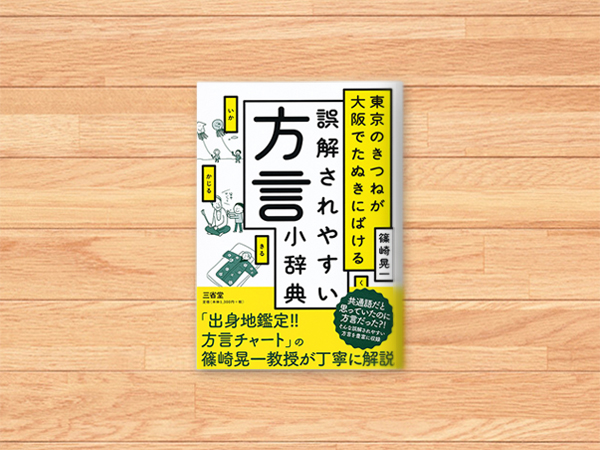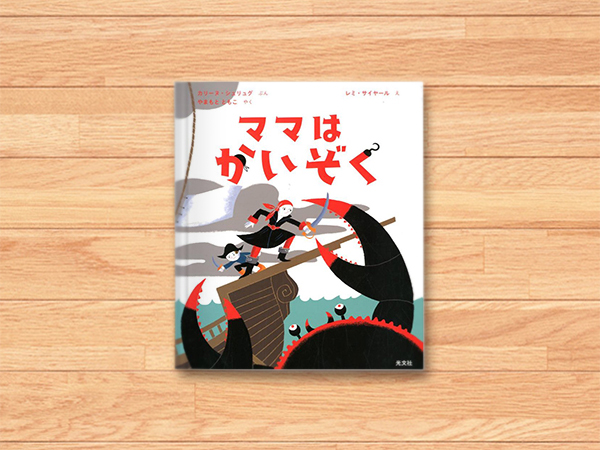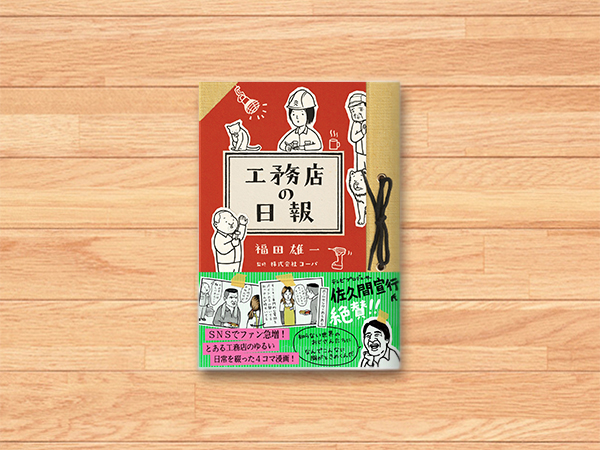ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー(ブレイディみかこ )
 |
|
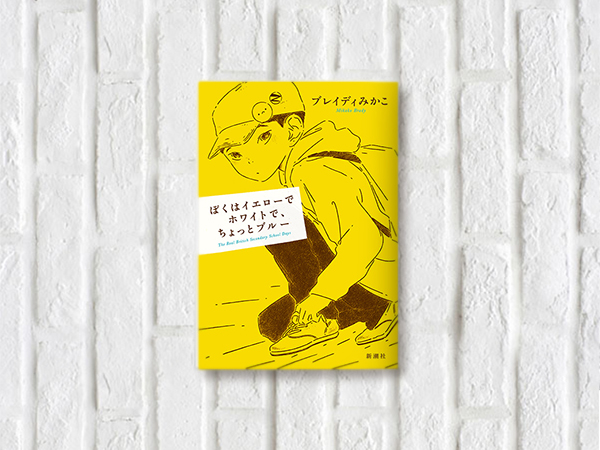 ブルーくんの成長を見守るのが嬉しい ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
ブレイディ みかこ(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。
今回ご紹介するのは、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』 著者 ブレイディみかこさんはイギリスの南端にあるブライトンという街に二十年以上暮らしている、福岡県出身の日本人。アイルランド系の旦那様との間に一人息子がいます。 この本は、息子さんが中学生になってからの約一年半を書いたものです。本の中で名前が明かされない息子さんのことを仮に"ブルーくん"と呼ぶことにします。 新一年生の"ブルーくん"が最初に体験したのは校内ミュージカルのオーディション。 なんでもイギリスの学校には、子どもたちが「表現力」を身に着けるための「演劇」の授業があるんですって。 さすがシェイクスピアの国!なんだかワクワクする…と思ったのですが、そんな甘いものではありませんでした。 というのも、失業率や貧困率が高い地域では、DVや依存症などの問題を抱えた家庭が多く、そんな家庭に育つ子どもの多くは表情に乏しかったり、自分の感情をうまく伝えられないのだそう。 自分の感情をうまく伝えられない子どもの多くは他人の感情を読み取る能力にも問題があり、相手が泣いて嫌がったらやめる、といったことができず、「問題行動」を起こすことが多くなるのだとか。 つまり「演劇」の授業には、芸術的な意味合いより、切羽詰まった目的があるということ。表側だけ聞いてもわからないことですね。 ちなみに“ブルーくん“たちの学年の演目は、ミュージカル『アラジン』でした。 “ブルーくん“は、オーディションで見事にジーニー役をゲット。しかも本番でのアクシデントに臨機応変に対応する姿が誇らしい!まるで親戚のおばちゃんの気分。 舞台で大活躍という、華々しい中学生デビューを遂げた“ブルーくん“ですが、学校生活は気分の良いことばかりではありませんでした。 “ブルーくん“は幼い頃はお父さんに似ていたけれど、だんだんお母さんに似てきました。つまり、東洋人の容貌をしているのです。 “ブルーくん“はカトリック系の小学校を卒業後、家の近くの公立中学校に入学しました。 カトリック系の小学校の生徒は、比較的豊かな家庭の子供ばかりで、穏やか。東洋系の“ブルーくん“に差別的な発言をする人はいませんでした。 しかし中学校では、人種問題や、貧困の問題、性的な問題などが “ブルーくん“の目の前で起こるのです。 例えば人種差別一つとっても、単純ではありません。 移民が多いイギリス。イギリス人が移民を差別するだけではなく、ヨーロッパからの移民が、東洋系やアフリカ系の移民に差別的発言をするなど、差別が階層化しているのです。 当然、“ブルーくん“も差別の対象になることがあります。 タイトルの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、中学校に通い始めたばかりの“ブルーくん“がノートに落書きしていた言葉だったのでした。 そういった土台があるからでしょう。中学校では「多様性を重んじることの大切さ」を教えます。対象は人種だけではなく、貧富やLGBT、思想など幅広いもの。 “ブルーくん“が通う中学校には、「両親がともにママ」「両親がともにパパ」という友人もいて、学校で教えてもらう以上に、自然に「多様性」を受け入れる環境もあります。 また、“ブルーくん“は中学校に通い始めてから、「貧しさ」についても考えることが増えます。 ボタンが弾けそうなパツンパツンの制服、あるいは、擦り切れた制服を着ていて、クラスメートにからかわれる友だちの境遇を知るのです。 同時に、安直な施しや同情が相手の心を傷つけることも学んでいきます。 私は今回の新型コロナウイルス対策について、イギリス在住の高校時代の同級生とメールでやり取りをしたことがありました。 その際、イギリスでは日本のように学校を休校にすることがなかなかできない、と聞きました。 というのも、学校で食べるランチが1日で唯一の栄養補給である子どもが少なからずいるから、とのこと。 「イギリスには広大な領地を持つ貴族がいる反面、本当に貧しい家庭がある。その差は非常に大きい」とメールには書かれていました。 私はイギリスにも給食制度があるのかと解釈しましたが、この本でシステムがわかりました。 貧しい家庭の子どもたちには学校の食堂で使える「ミールクーポン」が与えられます。無尽蔵ではなく、ミールクーポンには上限があります。 ところが新入生はペースを計算せずにクーポンを使いがちで、「そんなに使っていたら、学年後半に使えるクーポンがなくなるよ」と、担任の先生から注意を受けたりするのです。 それをたまたま聞いてしまった“ブルーくん“は、初めて、自分の友だちの家庭が貧しいことを知り、帰宅してからみかこさんと話し合います。 みかこさんは、自身の高校時代を思い出します。 当時みかこさんの家は家計が苦しく、お昼にパン1つしか買えなかったのだけれど、友だちには「ダイエットなの」と言っていたのでした。 貧しいからパンを一つしか買えないことを、友だちには死んでも知られたくなかった、とみかこさんは思い返します。 そして“ブルーくん“に教えます。 周囲の人たちも貧しければ、貧乏話ができるけれど、クラスの中で自分だけ貧しいのは本当に辛いことだと。そして、相手の心を傷つけずに何かできないか、親子で考えるのです。 貧困問題に限らず、みかこさんと“ブルーくん“は、実にいろいろなことを話し合っていて、私はこんな踏み込んだ話を親としたことがないなと、羨ましさを覚えました。 ブレイディみかこさんは長年イギリスに住んでいらっしゃる上、貧困率の高い地域にある託児所で保育士をしていた経験があるため、表面を撫でるだけではない考察をしておられ、今までふんわりとしたイメージを持っていたイギリスについて考えさせられることだらけでした。 とはいえ、この本に出てくるのは深刻な話ばかりではありません。みかこさんの文章には明るさがあり、とても読みやすいです。何より“ブルーくん“の成長を見守るのが嬉しい。 様々な世代の人にお勧めしたい『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。今なら、新潮社の特設サイトで4章分試し読みができます。ぜひ読んでみてください。 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ 特別サイト ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
ブレイディ みかこ(著) 新潮社 大人の凝り固まった常識を、子どもたちは軽く飛び越えていく。世界の縮図のような「元・底辺中学校」での日常を描く、落涙必至のノンフィクション。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook