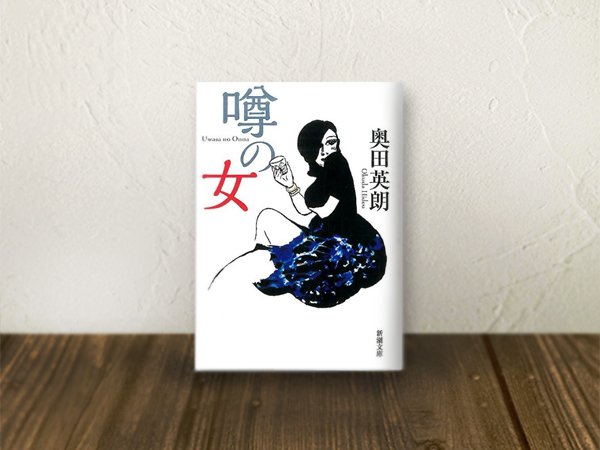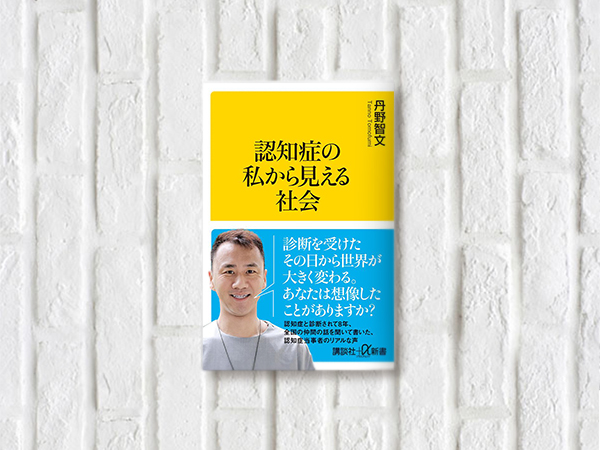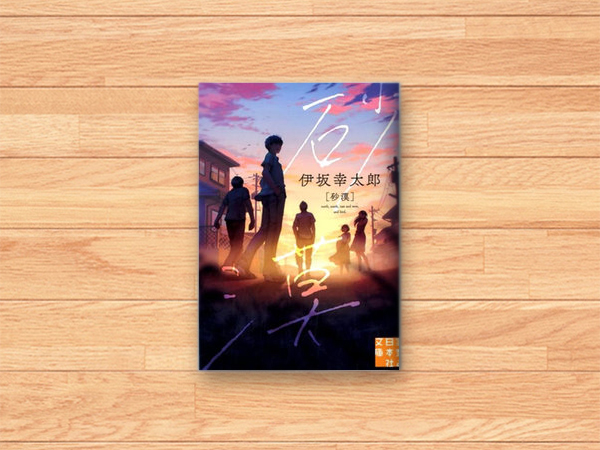文豪の凄い語彙力(山口謠司)
 |
|
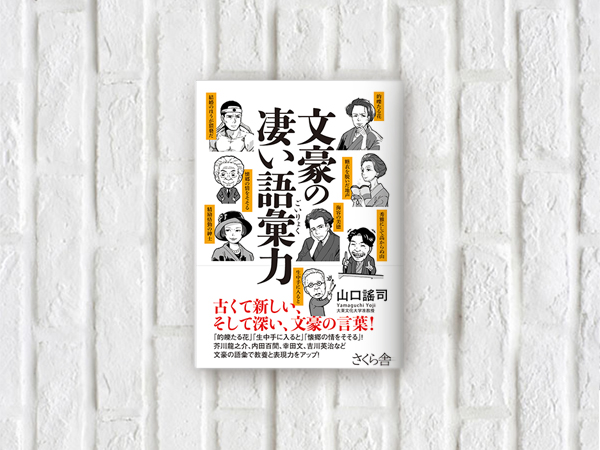 作家の言葉選びは時代も反映していて面白い 文豪の凄い語彙力
山口謠司(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では週に一度、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。
今回ご紹介するのは、山口謠司さんの『文豪の凄い語彙力』。 小説家というのは、物語を紡ぐ人です。しかしいくら面白いストーリーを考えついたとしても、それを伝える力がなければ意味がありません。 そういう意味で、小説家というのは結局のところ、言葉をじょうずに操る人と言えるかもしれません。そして言葉の選択の積み重ねが独自の文体となり、作家の個性になっていくのでしょう。 著者 山口謠司さんは、明治から昭和までの文豪63人の語彙力に注目。彼らの作品の中から、印象的な言葉をピックアップして紹介しています。 もっとも印象深かったのは、幸田文『流れる』から引用された 糖衣を脱いだ地声
(山口謠司『文豪の凄い語彙力』 P27より引用)
という言い回しでした。
とある芸者家の玄関先から、中を伺うと中から「どなた?」と甘ったるい声がします。 ところが、玄関先にいるのが見習いの女中さん(小説の中で使われている言葉をそのまま使っています)だとわかった途端、声の主は「糖衣を脱いだ」わけです。 おそらく女性の大多数は「糖衣を脱いだ」ことがあるのでは? 例えば、まだ携帯電話やナンバーディスプレイが普及しない時代、電話というものは、誰からかかってきたかわからないものでした。 だから、受話器に向かって思い切りすました声で「はい、もしもし」と話し、相手がみじかな人物とわかった途端、「なーんだ、◯◯ちゃんかぁ」と、地声になる、これが糖衣を脱いだ地声ということです。 ね?経験があるでしょう? 幸田文が『流れる』を書いたのは昭和30年。時代が変わっても、共感できるのが凄い。 ちなみに「オブラートに包む」という言い回しがありますが、意味がちょっと違いますね。 この本で紹介されている作品の中には、読んだことがあるものもあれば、恥ずかしながら名前すら知らなかった作家さんの作品もあります。 太宰治『グッド・バイ』や、司馬遼太郎『燃えよ剣』などは何度も読み返しているのに、紹介されている単語を全く意識していませんでした。 太宰治の語彙力として紹介されているのは 海容の美徳を示している
(山口謠司『文豪の凄い語彙力』 P138より引用)
海容とは、海のように広い心で相手を許す、という意味。
『グッド・バイ』を読んだのは大学時代。 おそらく前後の文脈で意味はわかったので、そのままさらっと読み飛ばしてしまい、記憶に残らなかったのでしょう。 日常生活では聞いたことがない言い回しなのに、気に留めなかったとは、言葉に対して鈍感すぎるわ、私。 司馬遼太郎の語彙力として紹介されているのは 幕府の爪牙に堕している
(山口謠司『文豪の凄い語彙力』 P234より引用)
歯牙にも掛けないの「歯牙」ならよく聞きますが、「爪牙(そうが)」なんて、これまで聞いたことがありません。
私が『燃えよ剣』を初めて読んだのは中学生の時でした。これまた全く気に留めず読み飛ばしてしまっています。 逆に言えば、読者に「この言葉は何?意味がわからない」と思わせないのは、言葉選びに成功していることになるのかもしれません。 作家の言葉選びは時代も反映していて面白いです。 それにしても、紹介されている単語や言い回しの豊かなこと。 私のボキャブラリなど、足元にも及びません。 多分、一生に一度も使わない言葉も。 さすがは文豪! 文豪の凄い語彙力
山口謠司(著) さくら舎 古くて新しい、そして深い、文豪の言葉!「生中手に入ると」「懐郷の情をそそる」!芥川龍之介、内田百間、幸田文、吉川英治など、文豪の語彙で教養と表現力をアップ! 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook