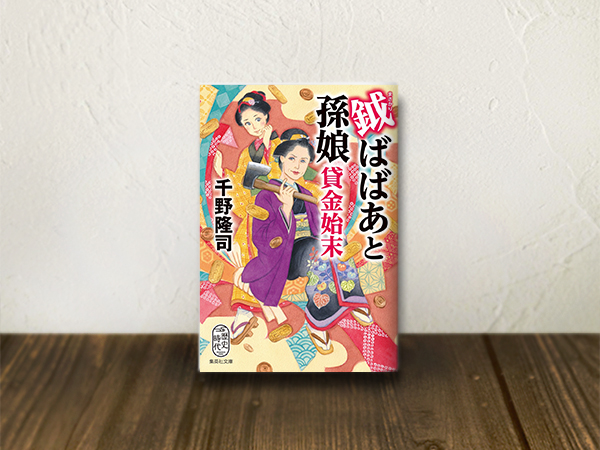青い壺(有吉佐和子)
 |
|
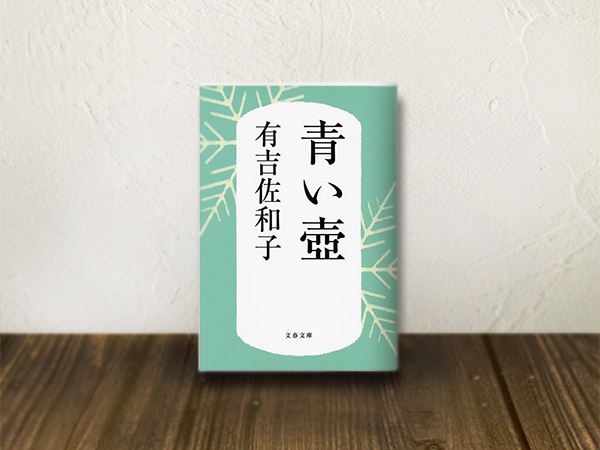 青い壺が見た人生いろいろ 青い壷
有吉 佐和子(著) 昭和51年(1976年)に発表された作品『青い壺』。
著者 有吉佐和子さんが亡くなって40年近く経った令和の時代に復刊され、多くの人に読まれている作品です。 京都在住の陶芸家 省造は40代後半。 芸術作品を手がけて名を上げた父に反発するかのように、省造は美術品ではない日常の陶器を焼いている。 個展なども開いたことがない。だが、50歳を前にして、だんだん父の気持ちがわかるようになってきた。 日用品以外にもちょっとした作品を焼くようになった。 ある日、自分でも驚くほど良い味わいの壺が焼き上がった。青磁の壺だ。 その壺は省造の手を離れ、様々な人の手に渡っていった。 定年退職後の夫婦がお世話になった人へのお礼の品として買い求めた後、 また別の人に贈られたり、盗まれたり…。 ついにスペインにまで渡っていく青い壺は、色々な人の人生を見てきた。 そして十数年後、その青い壺は再び省造の目の前に現れるのだが……
(有吉佐和子さん『青い壺』を私なりにご紹介しました。)
もう少し補足しておきますと、省造は詐欺の片棒を担ぐようなことをしています。
現代の陶器に薬品をかけ、年代物のように仕立て上げる作業です。 その作業は「古色をつける」というらしいですが、物を生み出す人がやっていいことではありません。 最初はお世話になっている道具屋から頼まれて仕方なくやったこと。 ですが薬剤の調合や漬ける時間が絶妙らしく、省造が手掛けると、本物の古美術品のように仕上がるため、たびたび依頼を受けるようになりました。 道具屋はそれを年代物の逸品だと偽って高く売りつけているのでしょう。 省造は、自分でも会心の出来である青い壺が焼き上がった時、これまで頼まれるまま古色をつけ続けたことを後悔することになります。 道具屋が、省造の青い壺を買い取るから、その壺にも古色をつけるようにと告げたからです。 今仕上げたばかりの、自分でも惚れ惚れするほど良い出来の壺に古色をつける、つまりは省造の作品ではなく、何百年も前の陶芸家の作品として売られるということではありませんか。 今まで自分がしてきたことの報いか…と反省する省造。 だけど省造が青い壺に古色をつけることはありませんでした。 青い壺は省造がちょっと留守をしている間に、デパートの展示会に出されることになりました。もちろんそのままの色で。 これは奥さんの計らいです。奥さんの目から見ても、素晴らしい出来栄えの壺だったのです。 この壺に古色なんか付けさせてたまるか、といったところでしょう。 以上がこの小説の第一話。 第二話はデパートで青い壺を買うことになるある夫婦の物語です。 誰が見ても素晴らしい壺なら、一つの家に大切に置いておかれそうなものですが、このつぼは以降、色々な人の手に渡ります。 この小説は第十三話までありますから、最初の省造の家庭を含む、13の人間模様が描かれています。 昭和のお話ですから、生活の環境やしゃべり言葉などに時代を感じる部分はありますが、それでも人間の生き方や感じ方は令和の時代もそう変わらず共感できると思いました。 私が最も面白く読んだのは第七話です。 七話の主人公はご高齢女性です。 青い壺はその女性の息子の手に渡り、家にやってきました。 女性はその青い壺を見て、自分の若い頃を思い出し、息子夫婦に語って聞かせるのでした。 それは第二次世界大戦中のお話。 外交官に嫁いだ女性は、戦争以前には夫の海外赴任にも同行しました。 だからパーティ用のドレスやアクセサリーも持っているし、西洋のマナーも身につけています。 それなのに、美しいドレスやアクセサリーは戦時下では贅沢品として全て封印されています。 食糧事情も悪くて、毎日毎日お芋ばかり。 それでも食べられるだけマシと思わないといけないのですが、海外で買い揃えた素晴らしい食器や銀のカトラリーも今や防空壕にしまいっぱなし。 そんなある日、旦那様が今日は僕がご馳走を作ろう、と言い出しました。 防空壕から食器を引っ張り出し、ドレスを身につけ「晩餐」に臨む女性。 その「晩餐」が素晴らしいのです。 戦時下でも心に余裕があり、ユーモアを忘れないご夫婦。 いえ、外交官だった旦那様は、日本が戦争に勝てないことは承知の上で、お芋しかない中「ご馳走」を作り、妻との時間を大切にしたのでしょう。 青い壺が省造の手を離れてから十数年後、色々な人の人生に青い壺が関わっていきます。 それぞれ次の人の手に渡る経緯が、いかにもあり得そうで、作家の想像力(創造力)はすごいと思いました。 十三の物語の中には「一体いつ、青い壺が出てくるんだろう?」と思うものもありますが、物語が面白すぎてこのまま壺が出てこなくてもいいか、と思うくらいです。 さて十数年後、省造は思いがけず自分の作品と再会するのですが、私の想像を超える展開でした。 私なら「青い壺が元に戻ってきましたよ、めでたしめでたし」にしてしまいそう。 今ふうにいうなら、第十三話の展開は第一話の伏線回収になっていると言えるでしょう。 令和の時代に復刊された『青い壺』の帯には作家 原田ひ香さんの言葉 こんな小説を書くのが私の夢です
が掲載されています。
人気作家さんにそう言わしめるのが納得できる面白い作品でした。
音声での書評はこちら
【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 青い壷
有吉 佐和子(著) 文藝春秋 無名の陶芸家が生み出した美しい青磁の壷。売られ盗まれ、十余年後に作者と再会するまでに壷が映し出した数々の人生。定年退職後の虚無を味わう夫婦、戦前の上流社会を懐かしむ老婆、四十五年ぶりにスペインに帰郷する修道女、観察眼に自信を持つ美術評論家。人間の有為転変を鮮やかに描いた有吉文学の傑作。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook