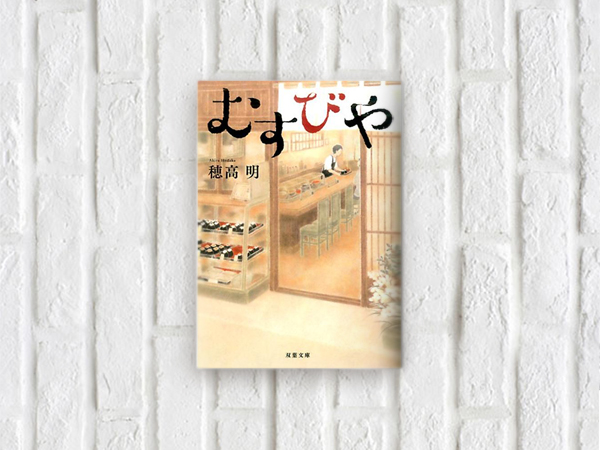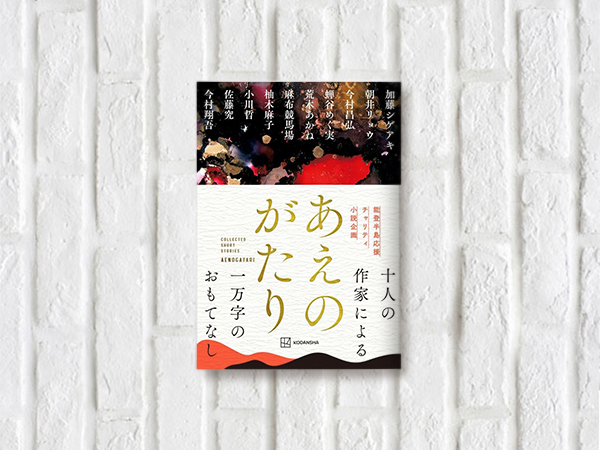すかたん(朝井まかて)
 |
|
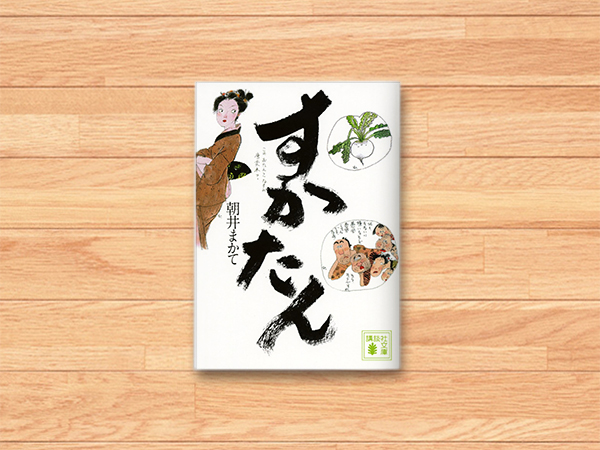 大阪の良いところがいっぱい詰まった すかたん
朝井 まかて (著) すかたんとは何か。
褒め言葉ではないことは、関西人でなくてもお分かりかと思います。 とはいえ「あほ」ほどではなく、罪のない失敗や、的外れでとんちんかんな受け応えに対して使われることが多いと思います。 「すかたん」には「憎めないやつ」というニュアンスが多分にあるのです。 そういえば、私は『すかたん』の著者でいらっしゃる朝井まかてさんご自身の「すかたん」シーンを目撃したことがあります。 それは昨年(2024年)11月17日にサンケイブリーゼで上演された文士劇でのこと。 文士劇とは文士=作家さんが舞台に立って演じる演劇のことで、関西で上演されるのは66年ぶりのことでした。 朝井まかてさん始め、錚々たる関西の作家さんが顔を合わせる演目は、東野圭吾さんの小説『放課後』。話題性は十分な上に、蓋を開けてみると、作家さんたちの予想以上に味のある演技で大いに盛り上がったのでした。 さて その舞台でのこと。 文士劇『放課後』は、役としてセリフを言う「芝居」部分と、台本を朗読する「朗読劇」をミックスした形で進行していきました。役としてセリフを喋ったり、台本を持ってト書き部分を読んだり、結構ややこしいことが求められていたわけです。 場面ごとの切り替えが大変だろうなと思って拝見していたら、とある場面で朝井まかてさんが台本を数行読んで「???」となられました。 どうやら順番を飛ばして違うページを読んでしまった模様。 そこから舞台袖の黒子さん(?)と確認し合ったりして、もう一度最初から読み直し、ということになりました。 朝井まかてさんはその時、慌て騒ぐことなく、客席に向かって状況を説明。お客様に謝ると同時に「やってしまったーてへぺろ」といった感じで自分のおでこをパチンと叩き、客席からは笑いと拍手が起こったのです。 朝井さんご自身は「あー、やっぱりやってしまったぁ」とおっしゃったように記憶しています。すごく焦る状況なのに、朝井さんの口調はとても のんびりしていて、まさに「すかたんやってしまった!」って感じでした。 あの場面の朝井まかて さんを拝見してからこの作品を読む巡り合わせで良かった。 では出だしをご紹介しますね。 まんじゅう屋の娘だった知里はチャキチャキの江戸っ子。美濃岩村藩のお侍に見そめられ結婚。夫の転勤(?)で大坂にやってきたものの、夫は急な病で亡くなってしまった。
たった2年で終わった結婚生活。実家はすでに代替わりしていて兄が店を継いだ。帰っても居場所がない。それより何より江戸に帰る路銀がない。夫は清廉潔白な人で、賄賂などをもらう習慣がなかったし、余ったお金は全て国許に送っていたから家に余分なお金がないのだ。 身寄りもない大坂で一人暮らすことになった知里は子どもたちに手習を教えることで生計を立てようとしたが、知里の江戸弁を面白がる子どもたちにからかわれてばかり。子ども相手についムキになる知里はすぐにクビになってしまう。しかも貧乏長屋に空き巣が入り、金品が奪われて家賃も払えなくなってしまった。 絶体絶命の知里だったが、ひょんなことから天満青物市場の頭取を務める河内屋に住み込みで働くことになった。当面、給金はもらえないが、食事が出て寝るところもある。これ以上望むことはない。 河内屋の跡取り息子は「青物狂い」と言われるくらい、野菜にのめり込むちょっと変わった若旦那。突拍子もないことを考えついては大問題に発展する。それになぜか関わってしまう知里だったが、徐々に若旦那がただの道楽ものではないとわかってくる。それに従って、若旦那が気になって仕方なくなるのだが…… (朝井まかてさん『すかたん』を私なりにご紹介しました。)
この小説にはいくつかの柱があります。
まずは、知里と河内屋の若旦那 清太郎との恋。 亡くなった知里の夫はとても清廉な人柄で、知里は夫のことを尊敬していました。 夫亡きあとも困ったことがあると、心の中で夫に話しかけていたくらいです。 ですが、結婚生活は2年だけ。その後、頼れる人もいない大坂の街で生活していくのです。 しかも住み込みで働かせてもらえることになった青物商の河内屋さんでは、慣れない仕事ばかり。ドーンと構えたお家さん(おかみさん)にしごかれて1日があっという間に過ぎていきます。 くよくよしていられないのです。 また、最初はお金に不自由なく育った不躾なボンボンだと思った清太郎が、意外にも商売について真剣かつ新しい考えを持っていることを知って見直す気持ちに。清太郎はお百姓にも優しく、町民にも人気があります。気持ちが移るのも無理はないですね。この二人がうまくいくといいなぁ、と思いながら読むことになります。 二つ目は、大坂の魅力。 大坂の美味しいもの、いいところがいっぱい紹介されていて、関西人にはたまらなく楽しい。 天王寺蕪、勝間南京、難波村の葱や金時人参など、美味しい名物青物がたくさん登場します。 そんな地場の野菜を使ったまかない料理の美味しそうなこと。 ヒロインの知里は食べることが大好きで、本当に美味しそうにご飯を食べます。 男女の区別なく、美味しそうにものを食べる人には好感が持てますわ。小説の中であっても。 また当時の大坂の名所も色々。 大川の網嶋を帰る川舟の白帆、八軒屋の船着場の夕映え、天王寺は晩鐘で、富吉が暮らす難波の空は落雁、寺の多い生玉は秋月、今宮は夜雨、生駒は暮雪が有名だ。 (朝井まかてさん『すかたん』より引用)
今の大阪にはビルが立ち並んでいてすっかり様相が変わっているとはいえ、その当時の景色や音が想像でき、なんだか嬉しくなってしまうのでした。
三つ目には勧善懲悪の要素が挙げられます。 小説の舞台となる河内屋ではこのように教えられます。 「ええか、皆、よう聞け。これが河内屋の青物やて胸張って言えん物は絶対、売ったらいかん。目先の利ぃに目が眩んでそれをしたら、一日でうちの信用は無うなる。ええか、信用言うもんは何十年もかけんと築けんもんやが、失うんは一瞬なんや。それだけは心せいっ」 (朝井まかてさん『すかたん』P231より引用)
天満青物市場に加盟している青物商が全て河内屋のような気概を持っているわけではありません。民百姓の事などどうでもよく、自分たちさえ儲ければいいという考えのものもいます。役人に賄賂を渡して便宜を取り持ってもらうものも。
そんな人たちにとっては河内屋は目の上のたんこぶ、邪魔な存在といえます。 罪のない「すかたん」なお話の裏にある悪巧み、さぁ、これを若旦那の清太郎は切り抜けることができるのか?! 笑ったりハラハラさせられたり。 色々な女性の境遇に切ない気持ちになったり。 さまざまな感情を味わったあと、スッキリできる小説でした。 ストーリーに直接関係ありませんが、伊藤若冲の名前がチラッと出てきたり、出世魚のように変わる使用人の名前の変遷(長松→長吉→長七→長助→長兵衛)が出てきたり。隅々に面白い要素が詰まっています。 関西人でなくても楽しく読めるでしょうけど、関西人には何倍にも楽しめると思います。
音声での書評はこちら
【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) すかたん
朝井 まかて (著) 講談社 江戸の饅頭屋のちゃきちゃき娘だった知里は、江戸詰め藩士だった夫の大坂赴任にともなって、初めて浪速の地を踏んだ。急な病で夫は亡くなり、自活するしかなくなった知里は、ふとしたはずみから、天下の台所・大坂でも有数の青物問屋「河内屋」に住み込み奉公することに。慣れない仕事や東西の習慣の違いに四苦八苦し、厳しいおかみさんから叱責されながらも、浪速の食の豊かさに目覚め、なんとか日々をつないでいく。おっちょこちょいで遊び人ながらも、幻の野菜作りには暴走気味の情熱を燃やす若旦那に引き込まれ、いつしか知里は恋に落ちていた。障害だらけのこの恋と、青物渡世の顛末やいかに。 書き下ろし長編時代小説。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook