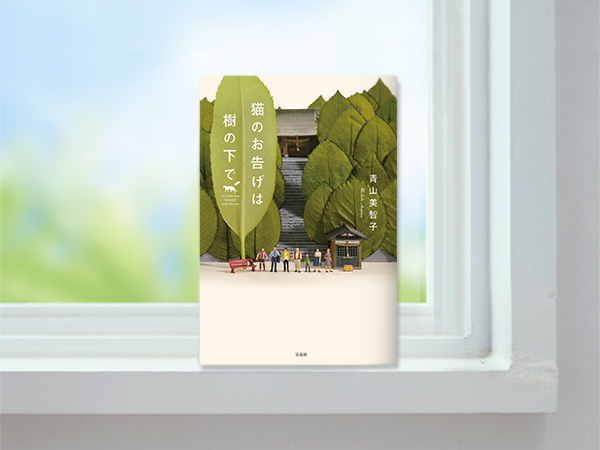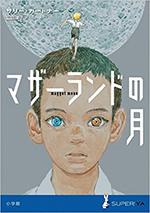女人入眼(永井紗耶子)
 |
|
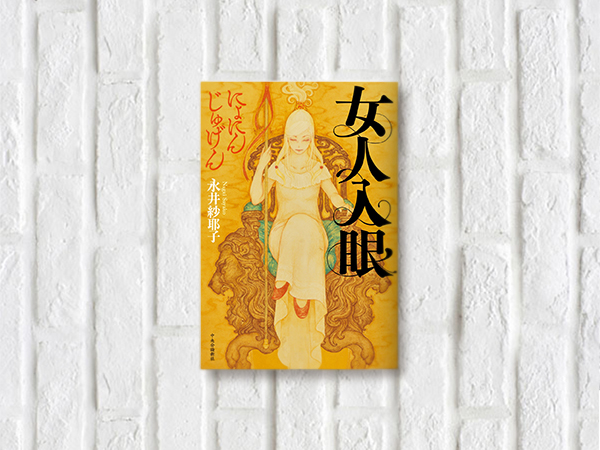 女性たちの政争 女人入眼
永井紗耶子(著) 第167回直木賞候補作 永井紗耶子さんの『女人入眼』を読みました。
私は今年(2022年)の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』を毎週楽しみに見ております。 元々、鎌倉時代のことはあまり詳しくありません。同じく源頼朝と北条政子を主人公とした大河ドラマ『草燃える』は見た記憶はあるけれど細かいことは覚えておりません。 ということで『鎌倉殿の13人』で見るさまざまな人物のエピソードはとても新鮮。 とはいえ、まるで流れ星のように、煌めいたかと思うと消えていく登場人物が多く、切なくなることも多々。特に哀れを感じたのは、木曽義高と大姫の段でした。 木曾義仲の息子義高と、源頼朝と北条政子の娘 大姫は許嫁でした。 実質は人質だった義高ですが、大姫は義高を心から慕い、義高も大姫のことが好きだった。でも、頼朝が木曾義仲を討伐し、息子の義高も生かしてはおけないということで命を奪われました。まだ幼かった大姫ですが、義高への気持ちは強く、心を病んでしまいます。のちに頼朝は大姫を後鳥羽天皇に入内させようとしますが、大姫は若くして亡くなってしまうのでした…… 木曽義高を演じたのが、梨園のプリンス市川染五郎さん。お顔立ちだけではなく、着物の着こなしや時代物の所作が凛々しく美しく、テレビの前の私まで大姫のような気持ちになってしまいました。こんな素敵な運命の人を失うだけでもショックなのに、自分の父親のせいだとなったら、どれほどショックだったでしょうか。 話が長くなりました。 『女人入眼』は、大姫入内にまつわる物語です。 京都の六条邸に仕える女房 衛門こと周子は20歳。
女主人の命により、源頼朝と北条政子の娘 大姫を入内させるために鎌倉へ遣わされた。后にふさわしい素養を身につけさせる、いわばお后教育係だ。帝の寵愛を受け、男子を産むことができればその女性は国母となる可能性が大きい。そうなれば関わった人たちの権力も増すのだから、これはとても大きな仕事と言える。 鎌倉には周子の父 大江広元がいる。広元は元々は下級貴族だったが、このまま京にいても先はないと見切りをつけて頼朝についたことで出世していた。母と自分を捨てた父ではあるが、大姫入内に関しては協力を仰がねばならいだろう。 しかし周子の思惑通りにことは運ばなかった。大姫が心を病んでいることは噂で聞いていたが、実際に会ってみると考えていた以上に深刻だったのだ。お后教育どころか、まともに会話ができない。それ以前に面会もできないこともある。 なんとか大姫の気持ちを知りたいと真剣に向き合ううちに、周子は大姫のことを出世の手段としてではなく、一人の女性として見るようになってきたのだった…… (永井紗耶子さん『女人入眼』の出だしを私なりに紹介しました) この小説は徹底的に女性中心に描かれています。
帝をめぐる女性たちの、誰がお世継ぎを産んで国母となるのか。その人の後ろ盾は誰なのか。 自分自身が后になれなくても、誰を応援し帝に近づけるのか、それを練るのも女性です。男性が戦によって権力争いをしている時に、女性はそういう形で政治に参加しているというわけ。 この小説の主人公である周子がお仕えしているのは丹後局。『鎌倉殿の13人』では鈴木京香さんが演じていました。怖い女性でしたよねぇ。 この小説での丹後局は、碁盤に石を置いていくように人を動かす女性として描かれています。 丹後局は夫に先立たれたばかりの時は無力なただの女性だったのに、今では政に携わる力を持っている理由を周子にこう語っています。 「見聞を広めたからだ。後白河院の傍らにて、人と権力の動きを見聞きし、何れに力があり、何れに財があるのかが分かった。それが即ち力になった」
(永井紗耶子さん『女人入眼』 P48より引用) また、続けてこうも語っています。
「(─前半略─)見聞はさながら船を漕ぐ櫂。それを得てようやく、私は岸を目指す術を知った」
(永井紗耶子さん『女人入眼』 P48より引用) 自分の力で宮廷の複雑な人間関係を泳いで行こうと思えば、知識が必要だということですね。ただ権力者のそばで笑っているだけではダメで、観察眼や分析力を身につけることが大切。これは現代にも通じることだなあと思いました。
周子は自分もいつか丹後局のようになりたいと思い、その最初のステップとして大姫入内を成功させるつもりだったのでした。でも、大姫の苦しみや悲しみに触れて徐々に考え方が変わってきます。自分の出世のために利用するに忍びないほど、大姫の苦しみが大きいことを知ったのです。 大姫の悲しみ苦しみの原因が木曽義高との死別だけではない、という著者の解釈には驚きました。 ネタバレぎりぎりですが、現代で言うところの「毒親」問題とだけ書いておきましょう。 大姫は亡くなり入内できなかったことは知識として知っていても、大姫の最期は心が痛みました。 ただ、物語の最後に登場した周子の姿に慰められました。私がこの小説を読み始めてすぐに「周子がこうなればいいのにな」と思った通りになっていたからです。 私はこれまで、中世の女性がどんなふうに生きていたのか、深く考えたことがありませんでした。 なんとなく、戦も政治も男性に任せて、その陰で生きていたように思っていたのですが、この小説を読むと、この時代にも働く女性がいて、上下関係に苦しみながら勤めを全うしようとしていたのだなと親近感を覚えました。 ちなみにタイトル『女人入眼』は”にょにんじゅげん”と読みます。 「仏は眼が入らねばただの木偶でございます。眼が入って初めて仏となるのです。男たちが戦で彫り上げた国の形に、玉眼を入れるのは、女人であろうと私は思うのですよ。言うなれば、女人入眼でございます」
(永井紗耶子さん『女人入眼』 P17より引用) これは天台座主 慈円の言葉ですが、慈円にこう言わせたのは著者である永井紗耶子さん。
きっと永井さんは、国(物事、と言ってもいいかも)を動かすのは男性だけではない。魂を入れるのは女性なのだ、とおっしゃりたいのではないかしら。 『女人入眼』は、女性中心に描かれたこの小説をよく表したタイトルだと思いました。 女人入眼
永井紗耶子(著) 中央公論新社 建久6(1195)年。京の六条殿に仕える女房・周子は、宮中掌握の一手として、源頼朝と北条政子の娘・大姫を入内させるという命を受けて鎌倉へ入る。気鬱の病を抱え、繊細な心を持つ大姫と、大きな野望を抱き、目的のためには手段を選ばない政子。二人のことを探る周子が辿り着いた、母子の間に横たわる悲しき過去とはー。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook