HOME![]() ■関西出版界に生きる女性たち
■関西出版界に生きる女性たち
![]() 田靡純子さん(株式会社法律文化社 代表取締役社長)
田靡純子さん(株式会社法律文化社 代表取締役社長) ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■関西出版界に生きる女性たち
田靡純子さん(株式会社法律文化社 代表取締役社長)
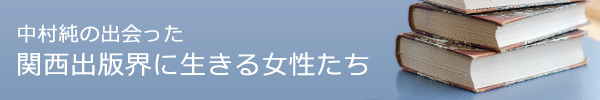

| 田靡 純子さん (たなびき じゅんこ/出版編集者 株式会社法律文化社 代表取締役社長) 兵庫県出身。1977年 同志社女子大学英語英文学科卒 法律文化社入社。編集者として勤務し、2005年に営業部長と兼任の取締役に。2007年代表取締役、2011年より代表取締役社長に就任。 法律文化社:京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町71 http://www.hou-bun.com/ |
| 「学問を市民の生活の中に生かしていきたい。 こんな社会になってほしい」という理想と志とともに。 |
| 出版のお仕事についたきっかけは、どのようなことでしたか。 |
| 私が就職したのは1977年。73年の第一次オイルショックで男性も就職氷河期の時代です。四大卒の女性は公務員か教員しか就職先がない時代で、初めて銀行やジャスコ(現在のイオン)に就職したことがニュースになるような時代でした。 さかのぼること高校1年の頃。私は兵庫県姫路市の出身です。父が村代表として保守系で市会議員に立候補しました。高校生の私は、「票固め、選挙対策」という村のお祭り騒ぎを目の当たりにして、「いったいこれはなんだろう」と思いました。 高校では「政経」、今の「現代社会」で民主主義を学び、憲法は絶対的なものだと思っていました。しかし、垣間見た選挙活動は、「民主的」なものではなかったのです。私は、すぐに「なんで?」と思ってしまうところが昔からあります。高校の時は「はてな」という学級新聞を毎日書いて、ガリ版刷りにして自主的に配り、100号まで発行しました。 私には兄と弟がいました。親は兄と喧嘩すると「妹なんやからやめとき」、弟と喧嘩すると「お姉ちゃんなんやから、女やからやめとき」と。「おかしいやんか」と思いました。そこでも鍛えられて、憲法のいう民主主義がストンと胸に落ちたのです。 大学でも、高校のときの志は変わらず、教員かマスメディア=「社会的に問題意識を広げていく職業」に就きたいと思っていました。大学4年のときに友達に紹介され、法律文化社でアルバイトをするようになったのです。アルバイトとして働いているころ社員欠員があり、やってみないか、と言われました。法律が中心の出版社ですが、私は英文学の専攻。「私は法学部ではないのですが良いのですか」と訊きました。たぶんすぐやめると思われていたのではないかと思います。 幸いなことに1977年当時、すでに女性社員の先輩もいて、男女同一賃金、同一職場、完全週休2日制でした。働き続けるには大変よい会社でした。男女雇用機会均等法施行は1986年。90年代初めでも、女性は一般職就職が大半だったことを考えれば、大変恵まれた会社でした。ただ、入社当時は定年は女性40代半ば、男性55歳。産休は欠勤扱いでした。初任給が安かったので、社長に直談判して「木曜18時からの家庭教師のアルバイトを続けさせてくれ」と言いました。今振り返れば「よくそんなことを言うね」と思います(笑)。 やがて劇団員と駆け落ち同然で結婚、出産。夫の収入が少ないので、「扶養手当を出してほしい」という要求を組合に取り上げてもらうまで3年、会社に認めてもらうのにまた3年。今は女性社員が扶養手当をいただくのも当たり前になっていますが、大黒柱は男性というのが社会通念の時代です。主張するばかりで仕事をしないのはよくないので、仕事には懸命に取り組みました。 |
 |
| 具体的にはどのようなお仕事をされてきましたか。 |
| 弊社の出版物は人文社会科学系で、法律書が半分ほどです。大学テキストが多いのですが、私は法律以外の分野、政治学、社会福祉、社会保障を中心にどの分野も担当し、長いこと編集部で企画、編集や校正の仕事をしてきました。 法律文化社は、大学とともに歩んできた出版社です。進学率も右肩あがりの時代は、法律書に関しては、営業努力をしなくとも一定販路を保っていくことができました。しかし、ほかの分野はそう強くないから、本を作るだけでなく「執筆者にいかに採用してもらうか、より多くの大学でどれだけ採用されるか、考えながら本を作っていく」という課題を持って働いてきました。 やがて1990年代の大学改革で教養部がなくなり、2004年に法科大学院ができて、先生方の配置もガラッと変わりました。大学が変化すれば、出版社も従来のやり方では対応できなくなります。「本の企画を立てながら営業部に回ってくれ」と会社から言われ、営業部長として異動したのが2003年のことです。「マーケティングの感覚がないと本もできなくなる」という危機感もありましたので、何の抵抗もなく異動しました。 |
| どのようにして、今の役職になられましたか。 |
| 2005年に、営業部長と兼任の取締役になりました。私は社内では比較的、仕事に対してはっきりとモノを言う厳しい人間です。出版も厳しい時代ですから、社内を引き締めていくという役割で2007年に代表取締役になり、2011年に代表取締役社長に就任しました。私で7代目社長になります。弊社はここで働いていた人間が役員や社長になっていく会社です。 小さな会社ですから、社長をしながら今も年間何点、と担当を持って編集をしています。自己主張も強く、「生意気」と言われてきた私ですが、反対された結婚、就職、仕事上の主張も、聴いて受け止めてくれる方たちがいました。「認められてきた」からこそ今があります。だから、社長をするにあたって、「人を認める」ということは大事にしていきたいと思っています。 |
| これまでにどんな壁を経験され、どのように乗り越えてこられましたか。 |
 私どもの仕事は、大学の転換期に影響を受けますが、現在がこれまでにない大きな壁にぶつかっています。少子化で学生数も減り、書籍、紙媒体をめぐる環境も変化しました。先日も、大手の出版取次会社、太洋社さんが倒産しました。このことが意味するのは、従来の本の流通システムが通用しなくなり、出版という商売そのものの在り方が変わってきているということです。 私どもの仕事は、大学の転換期に影響を受けますが、現在がこれまでにない大きな壁にぶつかっています。少子化で学生数も減り、書籍、紙媒体をめぐる環境も変化しました。先日も、大手の出版取次会社、太洋社さんが倒産しました。このことが意味するのは、従来の本の流通システムが通用しなくなり、出版という商売そのものの在り方が変わってきているということです。会社の歴史は長いけれど、新しい策を考え、実行することができなければ、厳しい環境にさらされます。今は、想定通りの売り上げ減です。わが社だけにいたら、なかなか世間が見えない。外に出て、起こっていることをしっかり見て、感じ、考えるときです。 個人的にぶつかった壁は、専門書の編集者として自信が持てなかった時期が続いたことです。どんなに勉強しても専門家の先生にかなうわけがない。そんなとき、他社の編集者が「編集者は第一読者。専門知識の問題ではない。著者が考えていることを、わかりやすく読者に伝えることが編集者の仕事ですよ。」と教えてくださったのです。「先生たちは専門用語で話すけれど、編集者は読者との橋渡しだ」と思い、自分の仕事に確信が持てるようになりました。 私は、悩んだときは原点に戻ります。「学問を市民の生活の中に生かしていく」「こんな社会になってほしい」という最初の志に立ち返り、その観点での思いを抱いて編集者として著者にお話に行くようになりました。1996年に『自分からの政治学』(石川捷治 ・平井一臣編)という大学テキストを出しました。40歳の頃、やっと編集者としてこのやり方でよいのだ、と思えた本です。 当時の大学のカリキュラムでは政治学の授業は「政治史」など生活から遠い内容が多く、これでよいのだろうか、という疑問がありました。「自分の身の回りから考えて、政治はこういうものだ」と思えるようなテキストを作りたい、と著者にお話してみました。そのころ、経済学や政治学など専門の学問をいかに教えるかが各学会で議論されており、本書も日本政治学会の大会のシンポジウムで取り上げられ、時宜にかなう企画でもありました。 「選挙は自分の税金を何に使うか」を決めることであり、それが政治の基本。そんなことがわかる政治学のテキストを創ることで、大学の授業、そして社会も変わっていくという経験をしました。「先生、どんな教科書をお使いですか」「学生さんに、どんな力をつけたいと思っていらっしゃるのですか」と、出版を通して大学教育の在り方を一緒に考えていく。本を出すだけでなく、一歩踏み込んだ役割をしていくのが、これからの出版社なのではないかと思っています。 紙媒体が難しい時代ですが、教科書は電子書籍にはあまり向かないと思っています。ページをめくっていくこと、行間を読むこと。そこには、自由な思考の空間が無限に広がっています。本の良さは失われることはありません。 |
| お仕事をされる中で、心にある「想い」はどのようなことですか。 |
 専門的な学問をいかに一般社会人に読んでいただくかということを、自分のテーマにしています。例えば『刑事裁判のいのち』(木谷明著 2013年)という本では、裁判員制度導入にあたって、一般の人に冤罪や裁判のことを知ってほしいという強い思いがあって、木谷先生に一般書のご執筆をお願いしました。 専門的な学問をいかに一般社会人に読んでいただくかということを、自分のテーマにしています。例えば『刑事裁判のいのち』(木谷明著 2013年)という本では、裁判員制度導入にあたって、一般の人に冤罪や裁判のことを知ってほしいという強い思いがあって、木谷先生に一般書のご執筆をお願いしました。自分がどんな本を出したいのか、どんな社会にしたいのか、というロマン、理想、志がないと出版の仕事はできません。「儲かる、売れる本」というだけでは著者と信頼関係を作れません。執筆者と共に語り合う熱い心と誠実さが必要です。しかし一方で、本を売るための冷静な目も必要です。 敗戦後の混乱期、紙の供給も難しい時代に、法律雑誌『法律文化』(月2回発行)を創刊したのが弊社の始まりです。同誌は、法学博士・故吉川大二郎の「民主的平和国家の再建のためには民衆の文化的、殊に法的知識の水準を高めること」との考えのもとに、戦後の民主主義を育んできました。そのような志で70年続いてきた会社を、私の代でつぶさないように大切に、時代とともに歩んでいきたいと決意しています。 |
| 最後に。本を読むということ、関西で出版社を営むということについてどう考えておられますか。 |
| 人間は基本的にひとりです。しかし、本を読み他者のことを思うことによって、自分の世界を広げ、世界をふくらませていくことができます。情報ならそこでストップしますが、本はそこから考えていく「思考メディア」です。本から拡がっていきます。 東京に9割の出版社が集中していますが、京都には、まだ行間のある時間が流れています。「思考する本」を創る環境として適しています。執筆者は全国におられますが、私どもは関西の時間の流れの中で本を創り、発信していきたいと思っています。 |
| ありがとうございました。 |
| 「憲法と民主主義」が、田靡さんの出発とお仕事の原点。日本の多くの出版社が戦後、戦争への反省のもとに、「民主主義と言論の自由」を掲げ産声をあげました。出版不況と言われる厳しい環境の中、出版人としての矜持と原点が、「壁」を乗り越え、未来を切り拓くと確信しました。仕事とご自身の半生を語ってくださった田靡さんは、勁(つよ)く、知的で謙虚、とてもチャーミングな方でした。
(取材:2016年3月・5月/所属・役職名等は取材時のものです)
|
 取材:中村純 取材:中村純編集者・詩人・執筆業・キャリアカウンセラー。 慶応義塾大学文学部卒。1993年から出版社(文化出版局、三省堂)勤務、2006年~2012年まで母校で教員も務める。2012年3月京都転居を折に、フリーランスで人物インタビューや単行本の編集に携わる。女性と仕事、教育もフィールドのひとつ。 著書に、詩集「草の家」「海の家族」(ともに土曜美術社出版販売)。詩集「はだかんぼ」、エッセイ集「いのちの源流―愛し続ける者たちへ」(ともにコールサック社)、インタビュー集「憲法と京都」(週刊通販生活連載、かもがわ出版刊行)。京都新聞コラム「現代のことば」連載中。2005年横浜詩人会賞、詩と思想新人賞受賞。 |
■関西出版界に生きる女性たち 記事一覧
-
「たった一人の会社でも、本という同じステージで勝負ができる」女性と子ども応援を理念に出版社を営む千葉さん
-
「本づくりはおもしろい」茶道を中心に日本文化を伝える京都の出版社「淡交社」の出版編集者、小川さん
-
「編集者は第一読者。わかりやすく読者に伝えることが編集者の仕事」歴史ある出版社7代目社長の田靡さん














