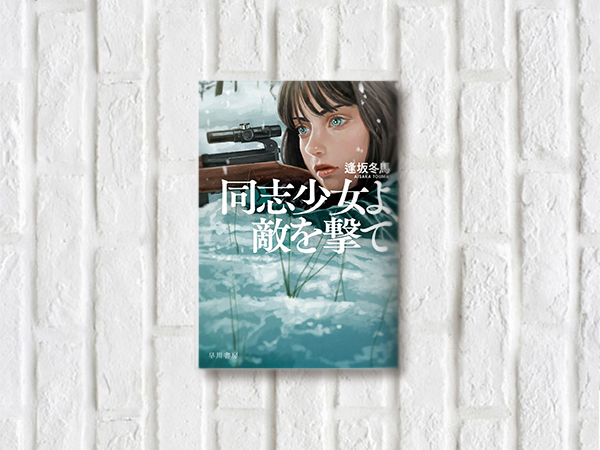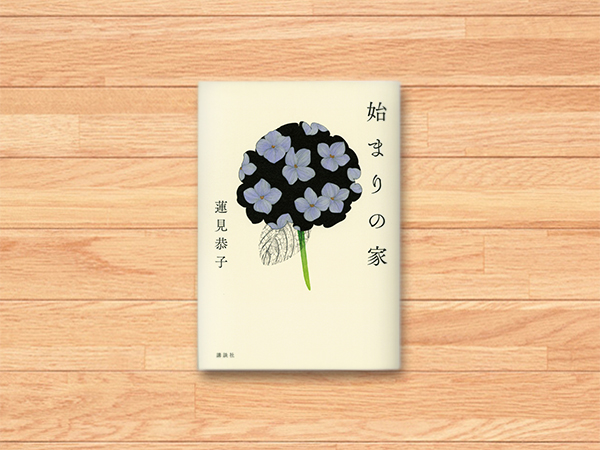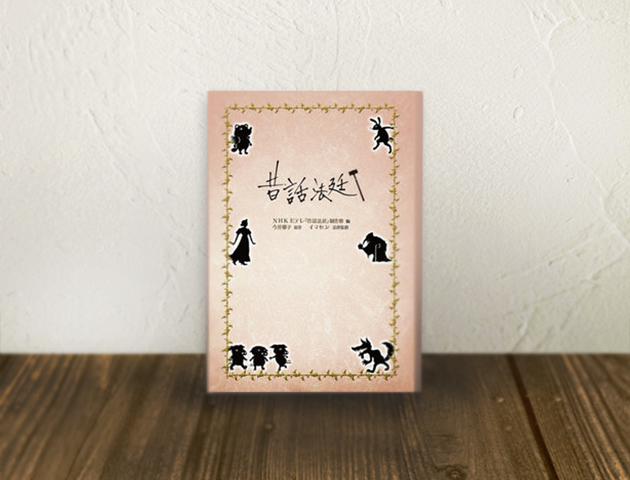マンガ ぼけ日和(矢部太郎)
 |
|
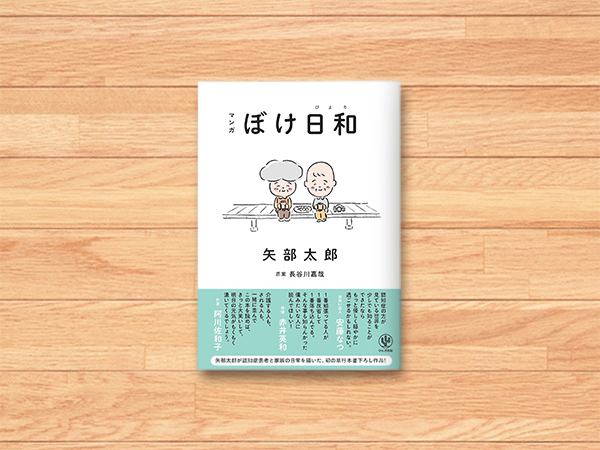 親と子が逆転するのを受け入れる マンガ ぼけ日和
矢部 太郎 長谷川 嘉哉(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFM みのおエフエムの「デイライトタッキー」。
その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。 2025月2月12日放送の番組では、矢部太郎さんの『マンガ ぼけ日和』をご紹介しました。 この作品は、お笑い芸人であり漫画家でもある矢部太郎さんが、認知症専門医である長谷川嘉哉さんの著書『ボケ日和』をもとに、描かれたものです。(長谷川さんの作品は「ボケ日和」、矢部さんの作品は「ぼけ日和」。間違って表記しているわけではありません) 「ぼけ」「ボケ」という言葉に嫌悪感を抱く方がいらっしゃるかもしれません。今は「認知症というんですよ!」と訂正したくなるかも。 でも、この作品の原案者 長谷川嘉哉先生は認知症専門医です。そんなことは言われなくてもわかっておられるはず。あえて「ボケ」という言葉を使われているのには理由があるのではないかと思いました。 「マンガ ぼけ日和」にその理由は書かれていません。私は勝手に「家族が認知症と診断されても焦ったり、悲観的にならないで」「力まず、ぼけーっとしていいんだよ」という意味ではないかと受け止めています。 この本には、認知症のさまざまな局面と、それに対して介護家族はどうすれば良いのかが分かりやすく描かれています。そのアドバイスをしてくれるお医者さんは多分、長谷川医師がモデルなのだと思います。 冒頭に、こんな言葉がありました。 介護する人に余裕がなければ 患者さんを笑顔にすることはできない 介護家族だって 仕事に行っていいし 遊びに行っていいんです 毎日笑っていいんです (矢部太郎さん『マンガ ぼけ日和』 P23より引用)
泣きそうになりました。
認知症に限らず、病気の家族がいるとき、そしてそれが重い症状であればあるほど、介護する側は全ての楽しみを捨てて尽くさなくてはいけないような気がしていました。 2023年に実母と養父を亡くしましたが、二人が同時に入院している時には、頼まれた物を差し入れたり洗濯物を交換するために病院をハシゴするだけで毎日イライラしていました。 当時はラジオのレギュラー番組を週2回持っていたので、要領の悪い私には時間が全く足りなかったのです。そんな中で息抜きや観劇などの楽しみごとを持つことに大きな罪悪感を覚えたことを思い出しました。 だけど介護家族にも仕事があるし、気晴らしだって必要ですよね。 それを「いいんです」と言ってもらえることが、どれほど救いになるか。 また、認知症がどういうものか理解せずに介護すると、「以前はこんなお父さんじゃなかった」「前は穏やかなおばあちゃんだったのに」と、介護家族も傷つき、苛立ち、それが患者さん本人に伝わって悪循環になりかねません。 この本では、患者さんの症状がいろいろ紹介され、その理由や対処法を易しく解説してくれています。 例えば、やたら怒りっぽくなる、大切なものを盗まれたと言い出す、夫が(妻が)浮気しているのではないかと言い出す、幻覚を見る…などなど。 認知症に伴って現れる症状には、その人の人生が現れることが多いのだとか。 お金に苦労した人は「お金を盗られた」妄想が出やすい。そしてたいていの場合、一番お世話になっている人を犯人扱いするそうです。 認知症の人は、いろいろなことがわからなくなっていくことが不安でたまりません。一番頼りにしている人に常に意識が向いていて、嬉しいことも嫌なことも全てその人に結びつけるので、物がなくなったと思ったら「アンタが盗っただろう?!」となるのですって。つまり「アンタが盗った」は「アンタがいないと困る」と同義語だと。 なかなかそんなふうには考えられませんけどね。 でも、何も知らずに犯人扱いされるより、自分は頼られているから犯人にされたのかと思う方が気持ちに余裕がでるかもしれません。 認知症の方には、情報を与えて安心させてあげてくださいという言葉もありました。 お孫さんだったら「おばあちゃん、私、わかる?」と言うのではなく、ちゃんと名前を言ってあげてください、ということです。 「孫の⚪⚪だよ、遊びにきたよ」と言った具合に。 これについては以前、別の本で読んだことがあります。 初期の認知症の時には、頭の中の情報の糸が繋がっていないだけで、ヒントをもらったら「ああ!」と思い出し、安心するのだと。 私の経験上、相手との関係が遠ければ この本に書いていることは比較的簡単にできると思います。 私の親戚に、認知症の方がいました。 親戚の集まりでお会いすると、その方の表情から、私が誰なのか分かりそうで思い出せないのだな、ということが察せられました。 そこで「千波留です。ご無沙汰しています」と自分の名前を添えてご挨拶すると、ホッとしたように、そして嬉しそうに名前を呼んでくださり、その後の会話が続きます。 でも、今度は同じことを何度も何度も言われました。 「千波留ちゃん、車はどこに置いたの?駐車場に停められた?」 これを10分おきくらいに聞かれるのです。 私は何度同じことを言われても「はい。駐車場に停められました」「大丈夫ですよ、ちゃんと駐車場に停められましたよ」と、さも今初めて質問されたかのように、こちらも同じことを返事することができました。全くイライラせずに。「さっき言いましたよ!」なんて言い返す気持ちなどこれぽっちも浮かびませんでした。 それはその方が私にとって遠い存在であり、その日の用事が終わったらさよならできるからです。 もし、これが親だったら?同居している祖父母だったら? イライラせずにいられるかどうか自信はありません。 それは、何度も同じことを聞かされてうんざり、という気分だけではなく、「あのしっかり者のお母さんが、どうしてこうなるのか」といった、やるせないような気持ちから生まれるイライラだったりするのではないでしょうか。 最後に、この本のなかで一番心に沁みた言葉をご紹介します。 認知症になっても笑って過ごせているご家族は しっかりしてよ などと「これまでどおり」を求めるのではなく 「ありのまま」 親と子が 逆転したことを受け入れる それが本当の大人なのかもしれません (矢部太郎さん『マンガ ぼけ日和』 P33より引用)
親と子が逆転する?
やっぱり泣きそうになりました。 でも、それを受け入れてこそ「ぼけ日和」に恵まれるのでしょう。 マンガ ぼけ日和
矢部 太郎 長谷川 嘉哉(著) かんき出版 四季(春・夏・秋・冬)に分けて症状の進行を書いた認知症専門医・長谷川嘉哉の『ボケ日和』を矢部太郎があたたかなまなざしで漫画化!笑って、泣けて、心が軽くなる一冊です。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook