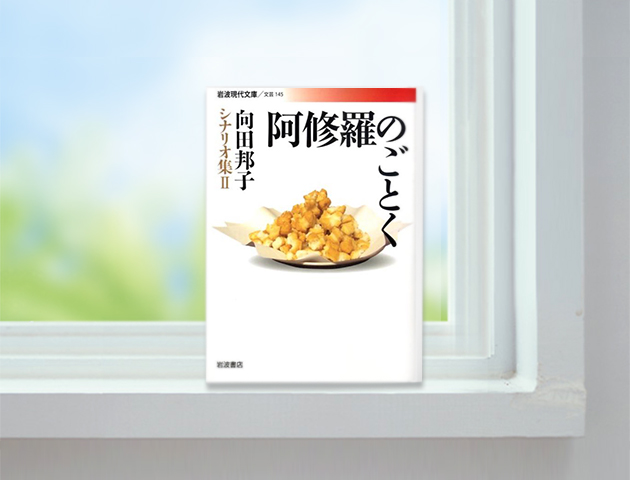銀の猫(朝井まかて)
 |
|
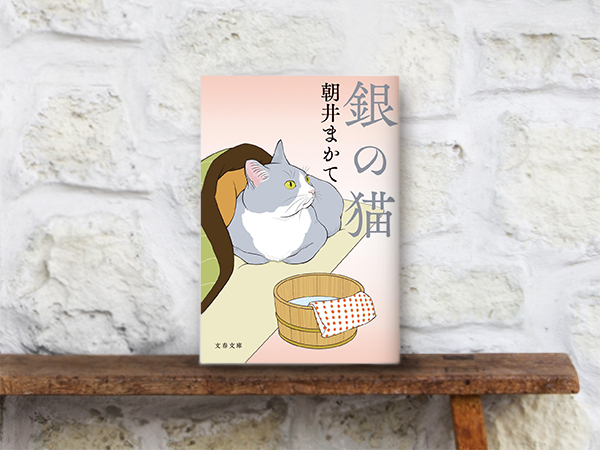 江戸時代にも介護の仕事がありました 銀の猫
朝井まかて(著) 朝井まかてさんの『銀の猫』を読み始めたのは、表紙に描かれた猫が可愛かったから。まさか、それが江戸時代の介護を描いた小説だとは思ってもいませんでした。
嫁ぎ先から追い出されたお咲は、現在母親と二人で長屋暮らし。お咲は「介抱人」としてご老人のお世話をすることで生計を立てている。母親を養っているだけではない、母が作った借金の返済もしているのだ。
介抱人の仕事は楽ではないけれど、ご老人と接すると、人生いろいろ、老後も色々であることがわかり、日々勉強させてもらっていると感じるお咲だった。 お世話をするご老人には理解があるお咲だが、 身勝手に生きてきた上、 自分の作った借金を娘に背負わせて平気な顔をしている自分の母親には寛大になれないでいるのだった。 (朝井まかてさん『銀の猫』の出だしを私なりに紹介しました)
私はまず、江戸時代にも介護の仕事があったことに驚きました。よく考えてみれば、いつの時代にも「生老病死」はあるのだから、江戸時代に介護の仕事があっても不思議はないのかもしれませんが、私は今まで介護を描いた時代小説を読んだことがありませんでした。
そもそも老後の問題を描いた歴史小説ってありましたっけ?私の狭い知識の範囲では、深沢七郎さんの『楢山節考』ぐらいしか思い浮かびません。でもあれは介護ではなく「棄老」のお話ですよね。 主人公のお咲は25歳。金銭問題で嫁ぎ先から追い出されました。お咲が悪いのではありません。お咲の母親がお咲に内緒でたびたび婚家に金を無心しにきていたのです。 その都度金を用立てたのは、お舅さん。人間的によくできたお舅さんは今でいう要介護状態になっており、お咲は心を込めてその介護(小説内では介抱)に努めていました。 もしかしたらそのお礼の意味もあって、お舅さんはお咲の母親にお金を渡していたのかもしれませんね。しかしそれが結構な金額になった時、夫と姑に知られるところとなり、それが原因でお咲は離縁されてしまうのです。ここまで母親が受け取った金額を借金として抱えた状態で。 実はその時夫は浮気をしており、新しい女性との再出発ができる良いきっかけだと思っていたようです。そんな夫に未練はありませんが、お咲が心配なのはお舅さんのこと。 自分がお世話できなくなって、今頃どうしているだろうと思うととても切ないのです。それだけ、人間的に尊敬できるひとであり、家の中で居場所がないような気持ちになっていたお咲に優しくしてくれたお舅さんでした。 お咲は、そのお舅さんからもらった小さな銀の根付けをお守りのように大切にしています。これがタイトルの『銀の猫』というわけです。 お咲は「鳩屋」という口入屋(職業斡旋所)に登録していて、そこからの派遣で介抱(今でいう介護)をしています。ずっと一つの家に勤めるのではなく、数日〜数週間働いて、また別のところに派遣されるというシステム。 お咲はどこに行っても評判がいいので、新しく依頼があった家や、ちょっと気難しい要介護者のところにまずお咲が行き、様子を見て他の人に引き継ぐことが多いのでした。お咲の介抱ぶりが好評なのは、お舅さんに仕えた経験があるおかげかもしれませんね。 『銀の猫』には8つの短編が収められています。それぞれ、別の家庭、別のお年寄りが描かれています。介抱されるご老人は多種多様。子どもたちの心配をよそに好き勝手に振る舞う老人もいれば、ひどく遠慮して自分の意思を表明できないご老人も。 とはいえ、介抱される人たちが皆「哀れ」な「弱い」老人ではありません。皆、体力がなくなっているだけで人生経験は豊富。結構したたかなのです。 以前、介護士さんにお聞きしたことがありますが、仕事である以上「のめり込まないこと」がとても大事なのだそうですね。無条件に親身になってはいけなくて、どこかに一線を引くことが大事なのだと。 お咲もその辺りをよくわきまえていて、あれこれ家の方針に口出しをしたりしません。そんなことをしたら逆にご老人の待遇が悪くなってしまうことがあると経験で学んでいるのです。そのあたり、プロなのだなと感じました。
お咲は己の手を信じていた。この両手でできることを精一杯、尽くすのみだ。
それ以上のことは介抱人の本分を越える。
(朝井まかてさん『銀の猫』 P291より引用)
色々なご老人に対してプロの介抱人として接しているお咲ですが、こと自分の母のことになると感情的になってしまいます。「この人がいなくなったらどんなに楽か」と思うほど。
その反面、そんなことを考える自分をひどい人間だと思ったりもします。この辺り、ひどく身につまされるというか、気持ちが分かりすぎて辛いくらいです。 私自身、赤の他人のご老人にはいくらでも優しくできますが、自分の親のこととなるとイライラすることが多くて…。まぁ、お咲の場合は私とは比べ物にならないくらい、母親に苦労させられているのですが。 そんなお咲を中心に、介抱されるご老人たち、口入屋「鳩屋」の夫婦、介抱人仲間、長屋の隣人などなど、多種多様、個性豊かな人たちが登場します。 また、介抱(介護)については、頑張りすぎて自分が倒れては元も子もない、時には人の手(プロの手)を借りた方が介抱する側される側どちらにとっても良い結果になることや、他人が接することで介抱される側にも新たな刺激が生まれ良い方向に転換することもあるなど、現代に通じることがいっぱい。 ただ、今と違うなぁと思ったのは、江戸時代、介抱する役目は嫁ではなく、跡取り息子本人だったということ。 手伝って欲しいのに、芝居小屋に遊びに行く暇はあっても舅姑の足をさすってあげる暇はないという嫁が増えている…というような愚痴が書かれており、一体いつから介護の仕事は嫁あるいは女性の役目という流れになったのだろうと思いましたよ。 偶然ではあるのですが、最近老後を描いた本を続け様に読んで、今まで以上に自分の老後に思いをはせることが多くなりました。 登場人物の一人がこんなセリフを語っています。
「本当はあたしも誰にも看取られずに、世話をかけずに逝きたいけどね。
獣や草木みたいにさ、野山で行き倒れられたらどんなに安穏だろう。
もっと気楽にさ、そう、気儘におさらばしたいんだよ、あたしは。
(ー中略ー)己の死にようを選べないとは、ほんにままならない」
(朝井まかてさん『銀の猫』 P217-218より引用)
本当にその通りだと思います。自分の死に際、死に様を選べたらどんなにいいか。
だけどそれはできません。逆説的ですが、今この時を一生懸命に生きるしかないんだなと思うのでした。
音声での書評はこちら
【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 銀の猫
朝井まかて(著) 文藝春秋 嫁ぎ先を離縁され、「介抱人」として稼ぐお咲。百人百様のしたたかな年寄りたちに日々、人生の多くを教えられる。一方、妾奉公を繰り返し身勝手に生きてきた自分の母親を許すことが出来ない。そんな時「誰もが楽になれる介抱指南書」作りに協力を求められー長寿の町・江戸に生きる人間を描ききる傑作小説。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook