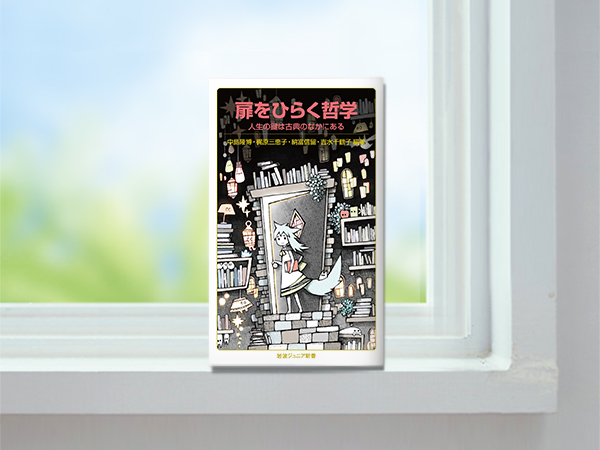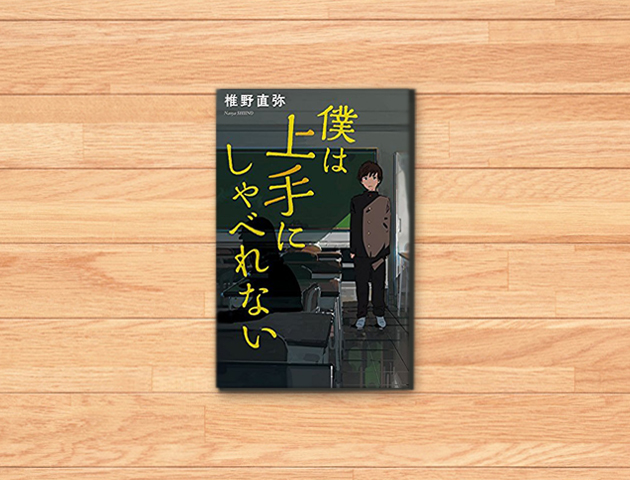火喰鳥(今村翔吾)
 |
|
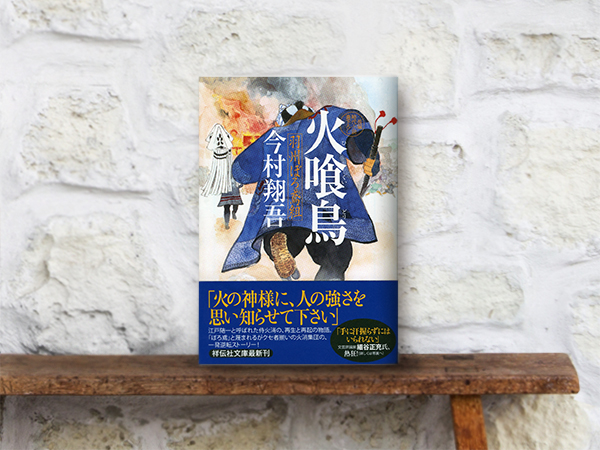 数ページで惹き込まれた 火喰鳥 羽州ぼろ鳶組
今村 翔吾(著) 直木賞作家 今村翔吾さんのデビュー作『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』を読了しました。
「火事と喧嘩は江戸の華」と言われた江戸時代のお話。
しょっちゅう大火事が起こる江戸の街。その火を鎮圧する火消しは江戸の庶民にとってヒーローだった。 かつて、"火喰鳥"と異名を取るほどの腕利きの火消し頭領だった松永源吾。訳あって火消しを引退していた源吾のことを、出羽新庄藩が火消し頭取として召し抱えたいという。 とは言え、日本一貧乏と言われている新庄藩には予算がない。お金をかけずに立て直せと言われたら、まずは人材確保が最優先。火消し装束などにお金を使ってはいられない。 ぼろぼろの火消し装束で火に立ち向かう彼らについたあだ名は「ぼろ鳶」。 松永源吾はぼろ鳶を再興させられるのか?江戸の街を脅かす放火犯を捕まえられるのか?! (今村翔吾さん『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の出だしを私なりに紹介しました)
火事の当事者になったことはありますか?
私は「当事者」は言い過ぎでも、関係者になったことがあります。 私の父はかつて、ダンボール工場を経営しておりました。 ダンボールの原紙を購入し、製函して(箱の形になるよう仕上げて)各企業に納入するのです。 工場の隣に祖父母の家があったこともあり、私は小学生から中学生にかけて、よく工場に出入りしていました。 工場の一角にはダンボールの原紙がおいてあります。 それは私の背よりも大きなロールで、トイレットペーパーの巨大版を想像してください。 ダンボール板の断面を見ていただけばわかりますが、ダンボールは紙と紙の間に、波打つような形に加工した紙を挟んでいます。 工場では、まずそのダンボール板を製造。 出来上がったダンボール板はパレットの上に積み上げられます。 それは巨大な色紙の塔のようで、子どもの背丈より高く積み上げられていました。 絶対に工場で遊んではいけないと言われていたけれど、このダンボールの塔はかくれんぼにもってこいなので、私はいとこたちと度々遊んだものです。 その後、ダンボール板は組み立てれば箱の形になるように折り目をつけたり、裁断をしたりします。 もちろん、注文された箱の大小によって、異なるものが出来上がるのです。 さて、ある夏の日。私は小学校高学年か、中学に入ったばかりだったと思います。 祖母の家に遊びに行っていた私は夜、消防車のサイレンに驚かされました。 火元が近いのかサイレンがどんどん大きく聞こえてくるのです。あれ?隣で止まったよ。 「工場が燃えている!」と、近所に住んでいた叔母が飛び込んできました。 えええええ!! 驚く私。祖母は一瞬腰が抜けたように、階段に座り込み、そこから動かなくなりました。 飛び込んで来た叔母は、すぐに台所に走り、米櫃からお米を出してシャカシャカ研ぎ始めるではありませんか。 え?火事だよ、逃げないの?どうしてお米を炊くの? 訝る私に「燃えてるとこはここから遠い。今のうちにお米炊いて、消防士さんにおにぎり差し入れするんや!」と おば。 そういうものなのか、とびっくりしました。 さてお米が炊き上がったら叔母が私に「はよこっちおいで!おにぎり握るで!!」と命令。 当時の私はほとんど炊事を手伝ったことがなかったので、炊き立ての熱々ご飯を握ることができません。 「あつ!!熱い!」と手の上にご飯を乗せてはパッと放り出す始末。 「もー!!役に立たんやっちゃなぁ!」 叔母は鬼のような速さでおにぎりを量産します。すごいわ。 出来上がったおにぎりを消防士さんに持っていく段になって私は「私も行くぅ〜」。 消火活動をこの目で見るなんて滅多にない体験だと思ったのです。 「アカン!!」 叔母は間髪入れずに却下。私は祖母の近くで火事の続報を待つばかりでした。 まだ鎮火の知らせがない時に、叔母が祖母に 「お母ちゃん、今のうちに大事なものをまとめておこう。今やったら持ち出せるし」と言ったのですが、祖母は 「何も持たんでいい。ご近所に飛び火するかもしれない時に、火元の自分らだけ財産持って逃げるなんてできますかいな!」 と言っていたのが印象的でした。 さて、火は無事に消し止められ、幸いなことに隣接していた祖父母宅も無事で、ご近所にも飛び火しませんでした。 気になるのは火事の原因。当初は、工場で働く従業員さんのタバコの火の不始末ではないかと考えられていました。 先に書いたように、ダンボール工場内は紙だらけなのです。誰かがタバコの火を消し忘れ、それが何かの拍子で紙に燃え移ったのではと誰もが考えました。昭和40年代、咥えタバコで仕事をする人がいた時代です。 ところが消防署の調査で分かった原因は聞いたこともない言葉でした。 「粉塵火災」。 科学的にご説明することは難しいので簡単に言いますと、細かい粒子が空中で浮遊し、お互い同士が摩擦しあったり、電気的な刺激を受けたりすると爆発的に燃え上がるという状態です。 紙を裁断するダンボール工場では、細かい紙のカスのようなものが日々生まれます。 たまたまその日、掃除が行き届かなかったのか、工場内に舞っていたダンボールの裁断屑が発火したということでした。 聞けば、紙だけではなく、小麦粉や砂糖のようなものでも粉塵火災は起こりうるそうです。 以後、工場内の清掃がより一層徹底されたのはいうまでもありません。 残念なことに、この工場ではもう一度、放火に近い事故で火事を起こしました。 そんなことで私は、消防車や消防署員さんたちには普通以上の尊敬の念を持っております。 余談が長くなりましたね。 消防車も、水道もホースもなかった時代、しかも建物は木と紙でできている時代に、どうやって火消しは消火活動を行っていたのか、まずその点でこの小説は興味深かったです。 また、登場人物が皆個性的で楽しい。 ”火喰鳥”とまで讃えられたのに、火消しから引退していた主人公の松永源吾。 計算が早く、理論派で、相手が誰であろうと言うことは言う、妻の深雪。 父親は火消しだったけれど、跡を継ぐ気もなかったやる気のない若者 新之介。 膝を故障して相撲が取れなくなった力士。 異人の血を引き、外見が日本人離れしていることで気後れしている秀才。 それぞれが予算がほとんどない新庄藩の火消し集団を立て直していくのです。 また、火事の原因についての表現も興味深いのです。 映画『バックドラフト』で有名になった、密閉された空間で起こっている火事に、 急に酸素が供給されると爆発的な延焼を起こす現象は「朱土竜」と呼ばれていたそうです。 また、私が経験した粉塵火災も小説の中に出てきます。 火事装束も満足に揃えられない貧乏な火消し集団「ぼろ鳶組」の活躍、松永源吾の克服すべきトラウマ、夫婦の絆、そして江戸の街を燃やし続けようとする放火犯との戦い…… 様々な要素が盛り込まれているため、火事に関心がない方にも面白く読んでいただけると思います。(火事を面白がっているわけではありません) ちなみに「ぼろ鳶組」が所属していた出羽藩新庄は現在の山形県新庄市。 新庄市の皆さんがこの小説を特別なものと感じ、大いに応援していることは言うまでもありません。 このシリーズは11巻までの人気シリーズに成長したのでした。
音声での書評はこちら
【パーソナリティ千波留の読書ダイアリー】 この記事とはちょっと違うことをお話ししています。 (アプリのダウンロードが必要です) 火喰鳥 羽州ぼろ鳶組
今村 翔吾(著) 祥伝社 かつて、江戸随一と呼ばれた武家火消がいた。その名は、松永源吾。別名、「火喰鳥」-。しかし、五年前の火事が原因で、今は妻の深雪と貧乏浪人暮らし。そんな彼の元に出羽新庄藩から突然仕官の誘いが。壊滅した藩の火消組織を再建してほしいという。「ぼろ鳶」と揶揄される火消たちを率い、源吾は昔の輝きを取り戻すことができるのか。興奮必至、迫力の時代小説。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook